- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “歯科全般”のセミナー動画
- 遊離端義歯はこうやってつくる。

遊離端義歯はこうやってつくる。
パーシャルデンチャー設計の基本と遊離端攻略法
- セミナー時間
- 1時間32分
- 講師
- 和田 淳一郎
講義詳細
「鉤歯がすぐにダメになってしまう」「安定が悪く使い物にならない」
遊離端義歯は設計が難しく、上記の理由で抜歯が必要になったり・患者さんに使ってもらえないことが度々あります。
その背景には遊離端義歯ならではの力の加わり方が関与しており、欠損形態から力の働きを考え、鉤歯へのストレスが少なくかつ安定の良い設計を目指さなければなりません。
例えばクラスプを変えてみる、症例によっては二次固定を応用してみるなどが挙げられますが日々の臨床においてここまで考えながら処置を行える先生は限られていると思われます。
このセミナーでは「遊離端義歯の設計」をテーマに、遊離端義歯設計の基本的な知識から王道的な考え方、欠損部の評価法、力の見方、調整法に至るまでを東京科学大学(Science Tokyo) 大学院医歯学総合研究科 生体補綴歯科学分野講師の和田淳一郎先生に解説していただきます。
実際の症例をベースに、背景の読み解き方・トラブルへの対象法についてもお話ししていただきます。
歯を守り・健康を維持する義歯を作りたい先生必見です。
こんな方におすすめ
👉 遊離端義歯製作のコツが知りたい
👉 義歯設計のポイントを学びたい
👉 安定する義歯を作りたい
講師

和田 淳一郎
詳細東京科学大学(Science Tokyo)大学院医歯学総合研究科 生体補綴歯科学分野 講師。
東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業後、同大学歯学研究科部分床義歯補綴学分野入局、博士課程修了。東京医科歯科大学歯学部附属病院診療科回復系診療科 義歯外来医員、同大学大学院医歯学総合研究科医歯学系専攻口腔機能再構築学講座部分床義歯補綴学助教を経て、トゥルク大学歯学部生体材料科学分野 トゥルククリニカルバイオマテリアルズセンター(TCBC)客員研究員。帰国後、現職。
日本補綴歯科学会専門医。日本補綴歯科学会第117回学術大会課題口演コンペティション優秀賞受賞。
著書に「パーシャルデンチャー活用力 ーライフコースに沿った基本から使いこなしまでー」など。著書・講演に「ペリオ×パーシャルデンチャー 支台歯をどう守り,どう活用するのか?」「【保険の有床義歯 臨床&請求 虎の巻】磁性アタッチメント」など多数。
1Dプレミアムに登録するとすべてのセミナー見放題!
月額 11,760円(税込)
作品数
1000本以上
ジャンル
臨床から経営まで
全分野体系的に網羅
受講者数
5000人以上
1Dセミナーの特徴
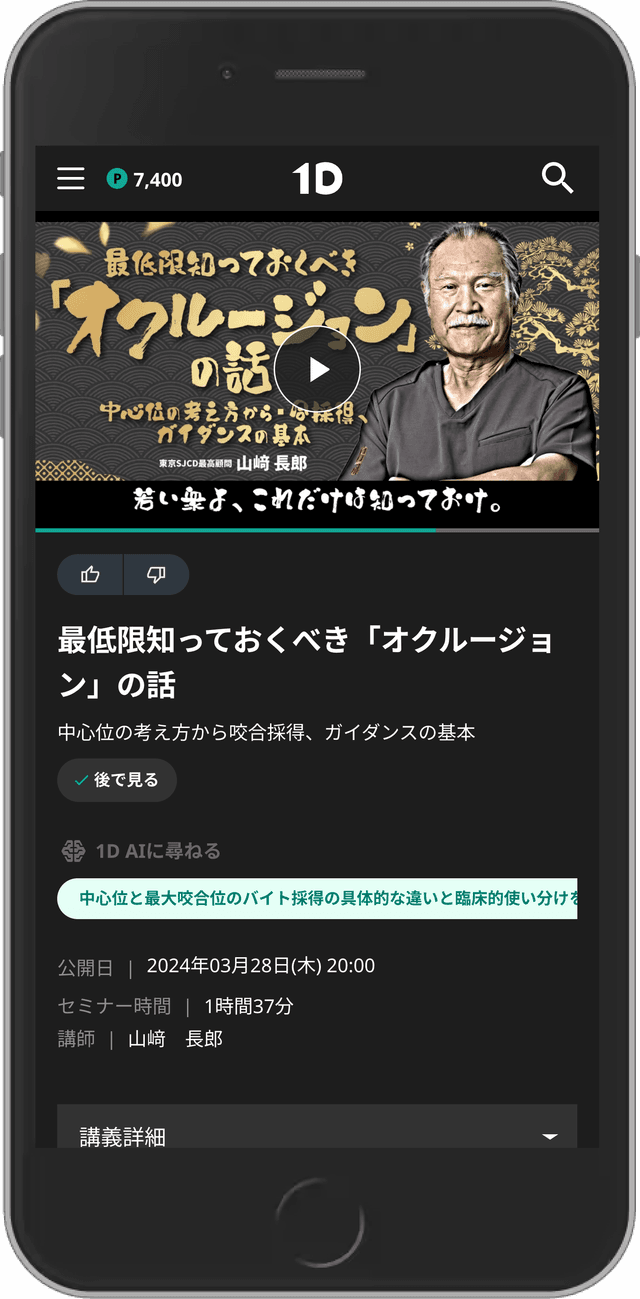
実際の症例を完全解説
倍速再生やスキップ機能で
スキマ時間を活用
活字では伝わりきらない
微細な技術を動画と音声で習得
安心のサービス設計
いつでもどこでも視聴可能
パソコン・スマートフォン・アプリで視聴できます。
1,500時間以上のセミナーを
お得に見放題
お得に見放題
月額11,760円(税込)で見放題です。
月末入会でもOK
更新日は入会日から数えて1ヶ月後です。
いつでも
解約できて安心
解約できて安心
解約手続き後も更新日までは視聴できます。
更に今なら、実践ですぐに使える
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
※毎月新規特典が追加されます。
※特典配布は予告なく終了することがあります。

関連するジャンルで探す
和田 淳一郎 先生のセミナー
新着セミナー
おすすめセミナー
1Dプレミアム会員
11,760
円/月
1Dマスターコースに全て参加可能
1D歯科セミナーに全て参加可能
1Dマスターコース・1D歯科セミナーの全アーカイブ配信を視聴可能
・
簡単に領収書発行が可能。医院の経費にできます。
・
いつでも退会いただけます。
・
各コンテンツの配信には期限があるため早めの入会がおすすめです。
- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “歯科全般”のセミナー動画
- 遊離端義歯はこうやってつくる。























