- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “小児歯科”のセミナー動画
- 子どもの歯ぎしりはやめさせるべきか?

子どもの歯ぎしりはやめさせるべきか?
小児のブラキシズム~基本的知識からその対応まで~
- セミナー時間
- 1時間22分
- 講師
- 宮脇 正一
講義詳細
小児のブラキシズム(子どもの歯ぎしり)は日常臨床においてしばしば観察される現象ですが、その多くは健常者に認められるものであり、どのように考えたら良いのか、経過観察あるいは治療介入が必要なのか等の判断に迷うことも少なくありません。
しかし叢生(がたがたの歯並び)などブラキシズムと関連すると考えられている問題はいくつかあり、適切な説明や対応が求められる機会はとても多いです。
本セミナーでは「小児のブラキシズム」をテーマに、基礎的な知識から発現機序、成長発達との関わりやその対応について、鹿児島大学(歯科矯正学)教授の宮脇正一先生に解説していただきます。
さらに、どのような症例があるのか、治療介入が必要とされるポイントや、その判断基準、介入方法ならびに介入の時期や注意点などについて、実際の症例をもとにお話ししていただきます。
小児のブラキシズムをどう捉えるかについては、臨床家としての姿勢を試される課題でもあります。保護者の不安に適切に応えつつ、成長発達を考慮した診療を行うための実践的ヒントも提供していただきます。
小児歯科や矯正歯科に携わる先生はもちろん、一般の歯科で小児患者を診る先生にとっても有益な内容です。
こんな方におすすめ
👉小児のブラキシズムの捉え方や治療を含む対応法を身に付けたい
👉 現在のブラキシズムの概念や発現機序について知りたい
👉 歯列・咬合への影響や治療中の注意点が知りたい
👉 保護者への説明のポイントを学びたい
講義目次
- ブラキシズムの基本的知識(概念, 種類と定義, 診断基準, 評価法, 頻度・症状・病態, 原因, 関連因子・発現機序[仮説])
- ブラキシズムへの対応(成長期の患者への対応, 青年期以降の患者への対応, 矯正歯科治療中の患者への対応)
- 今後の展望
講師
宮脇 正一
詳細鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 歯科矯正学分野 教授。経歴・資格:1989年大阪大学歯学部卒業後、同大学院修了(博士[歯学])・日本矯正歯科学会認定医・指導医、奈良県立大学口腔外科学講座助手(1997~1999)、岡山大学講師・准教授(~2005)、モントリオール大学客員研究員(2001~2002)、厚生労働省臨床修練指導歯科医、2005年鹿児島大学教授就任後、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科副研究科長(2011~2016)、鹿児島大学歯学部長(2016~2020)、日本矯正歯科学会学会誌(Clinical and Investigative Orthodontics)編集長、日本顎関節学会専門医・指導医、日本口蓋裂学会矯正歯科認定師、日本顎変形症学会認定医、日本歯科専門医機構認定専門医(矯正歯科)等。論文・著書:ブラキシズムに関する原著論文(J Dent Res、Sleep、AJO/DO、J Oral Rehabil等)・総説論文(ブラキシズムに対する最近の考え方ならびに顎関節症との関連とその対応について、北矯歯誌2024等)、著書(ブラキシズム完全読本[医歯薬出版2025、分担執筆]、まるごとわかるブラキシズム[医歯薬出版2022、分担執筆]等)計121編。
1Dプレミアムに登録するとすべてのセミナー見放題!
月額 11,760円(税込)
作品数
1000本以上
ジャンル
臨床から経営まで
全分野体系的に網羅
受講者数
5000人以上
1Dセミナーの特徴
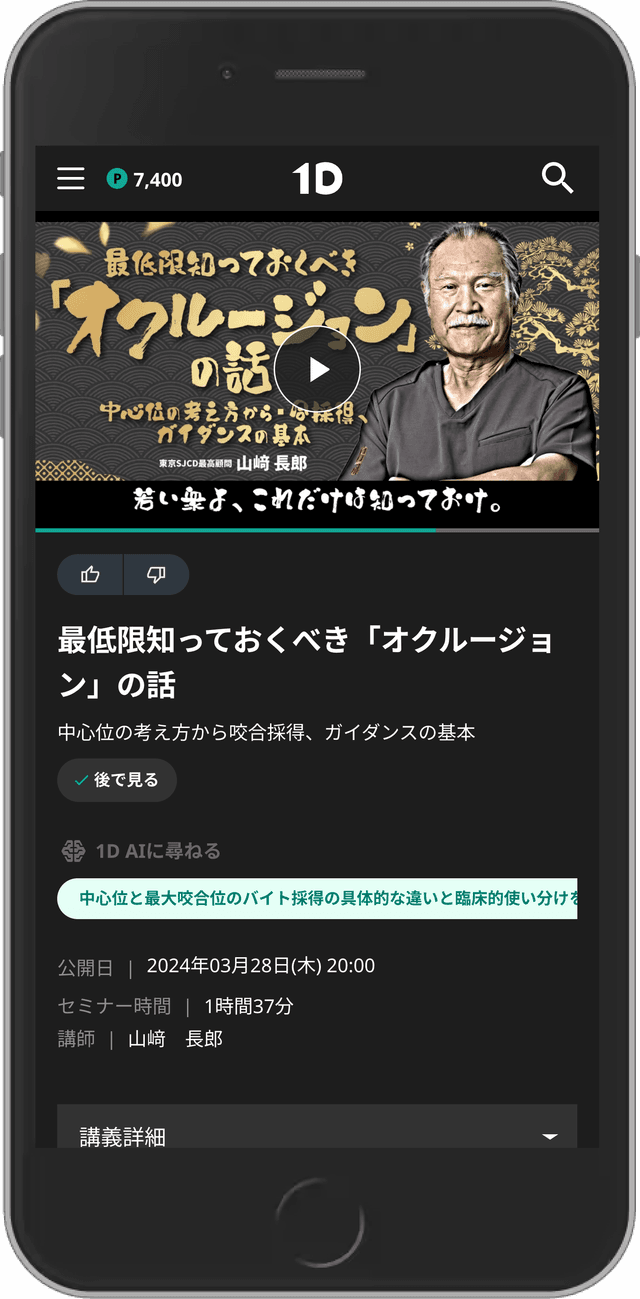
実際の症例を完全解説
倍速再生やスキップ機能で
スキマ時間を活用
活字では伝わりきらない
微細な技術を動画と音声で習得
安心のサービス設計
いつでもどこでも視聴可能
パソコン・スマートフォン・アプリで視聴できます。
1,500時間以上のセミナーを
お得に見放題
お得に見放題
月額11,760円(税込)で見放題です。
月末入会でもOK
更新日は入会日から数えて1ヶ月後です。
いつでも
解約できて安心
解約できて安心
解約手続き後も更新日までは視聴できます。
更に今なら、実践ですぐに使える
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
※毎月新規特典が追加されます。
※特典配布は予告なく終了することがあります。

新着セミナー
おすすめセミナー
1Dプレミアム会員
11,760
円/月
1Dマスターコースに全て参加可能
1D歯科セミナーに全て参加可能
1Dマスターコース・1D歯科セミナーの全アーカイブ配信を視聴可能
・
簡単に領収書発行が可能。医院の経費にできます。
・
いつでも退会いただけます。
・
各コンテンツの配信には期限があるため早めの入会がおすすめです。
- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “小児歯科”のセミナー動画
- 子どもの歯ぎしりはやめさせるべきか?






















