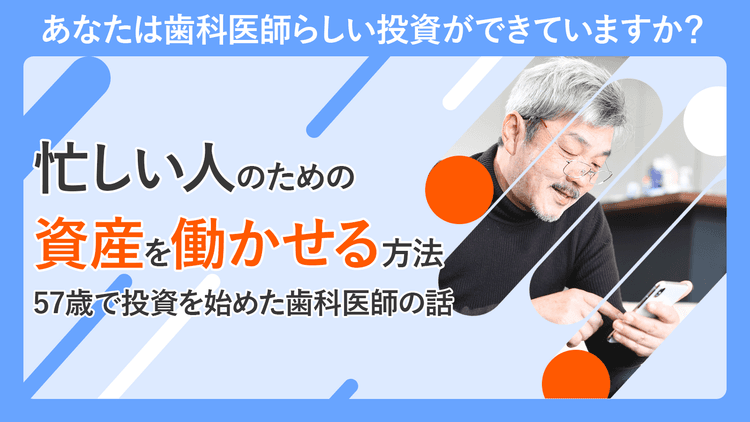歯科用語集
2022年7月1日
う蝕活動性試験
「う蝕活動性試験」とは?歯科用語の解説と症例を紹介
う蝕活動性試験とは?
う蝕活動性試験とは、う蝕のリスク評価である。
歯垢を検体とし、酸産生能を調べるテストにはカリオスタット、KKYテストがあり、エナメル質を検体とし脱灰能を調べるテストにはエナメル質生検法がある。
また、唾液を検体とし、酸産生能を調べるにはスナイダーテスト、ワッチテスト、う蝕原因菌数を調べるRDテスト、緩衝能を調べるにはドライゼンテスト、グルコースクリアランステストがある。
う蝕活動性試験の使用目的(Socransky)
う蝕活動性試験の使用目的としては、下記の通りです。
【臨床現場における使用目的】
- 患者を協力させるための指標として
- リコールの適切な時期を決める一助として
- 高価な装着物を装着するときの指針として
- 予後を推定する一助として
- 矯正バンドを装着するときにう蝕誘発の可能性を探る指針として
【研究現場における使用目的】
【公衆衛生の場における使用目的】
- 保健指導の立案、組み立てのための指標として
関連用語
Tooth Wear (0)
抜髄処置 (0)
掲載情報について
1D(ワンディー)は、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士向けの情報が集まる、日本最大級の専門メディアです。
トップレベルの臨床家・研究者からオンラインで学べる「歯科セミナー」や、臨床・経営・ライフスタイルの最新情報が収集できる「歯科ニュース」など、多彩な歯科医療コンテンツを配信しています。
本サイトは、歯科医療関係者(歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手・歯科学生等)を対象に、歯科医療の臨床・研究・経営等に関する情報を集約したものです。歯科医療関係者以外の一般の方に対する情報提供を目的としたものではないことをご了承ください。
また、本サイトで提供する情報について細心の注意を払っておりますが、内容の正確性・完全性・有用性等に関して保証するものではありません。詳細は利用規約をご覧ください。
CONTACT
CONTACT
CONTACT
CONTACT
SNS
© 2025 1D inc.