- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “訪問・高齢者歯科”のセミナー動画
- 「食べる」を解明する。咀嚼・嚥下障害にならないために。

「食べる」を解明する。咀嚼・嚥下障害にならないために。
プロセスモデルで考える摂食嚥下リハ
- セミナー時間
- 1時間24分
- 講師
- 松尾 浩一郎
講義詳細
咀嚼から嚥下までのプロセス、理解していますか?
古典的な咀嚼嚥下の概念では、嚥下が始まるまで口腔と咽頭は口峡部で遮断されていると考えられていました。
しかし、多くの研究により咀嚼しているときには口峡は開いており、嚥下まで口腔と咽頭はひと続きの空間をなすことが明らかになりました。
今後の超高齢社会において、要介護者人口の増加は目に見えています。
従来の咬合回復だけでなく「より安全に、快適に食生活を送ること」が求められていくでしょう。
このセミナーでは、咀嚼嚥下を古典的な4期連続モデルではなく、4つのステージに分けるプロセスモデルを用いて、顎運動とそれに協調した舌、 舌骨、軟口蓋などについて東京医科歯科大学の松尾教授に解説いただきます。
咀嚼のための口腔機能回復だけが、ゴールではありません。
こんな方におすすめ
👉咀嚼から嚥下までの流れをきちんと理解したい
👉咀嚼に関わる舌、舌骨、軟口蓋などの運動を知りたい
👉摂食嚥下障害への対応法を学びたい
講義目次
- 咀嚼嚥下の古典的概念
- 新たなプロセスモデルについて
- 咀嚼と嚥下の評価
- 摂食嚥下障害への対応
- リハビリテーション
講師

松尾 浩一郎
詳細東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯理工学専攻地域・福祉口腔機能管理学教授。東京医科歯科大学歯学部卒業後、同大学院高齢者歯科学分野 入局、ジョンズホプキンス大学医学部リハビリテーション講座 研究員、ジョンズホプキンス大学医学部リハビリテーション講座 講師、松本歯科大学障害者歯科学講座 准教授、藤田保健衛生大学医学部歯科 教授、藤田医科大学医学部歯科・口腔外科学講座 主任教授を経て現職。日本老年歯科医学会 理事/専門医/指導医/摂食機能療法専門歯科医師、日本障害者歯科学会 理事/認定医、日本静脈経腸栄養学会 学術評議員/認定歯科医、日本摂食嚥下リハビリテーション学会 評議員/認定士、Dysphagia Research Society 理事。
1Dプレミアムに登録するとすべてのセミナー見放題!
月額 11,760円(税込)
作品数
1000本以上
ジャンル
臨床から経営まで
全分野体系的に網羅
受講者数
5000人以上
1Dセミナーの特徴
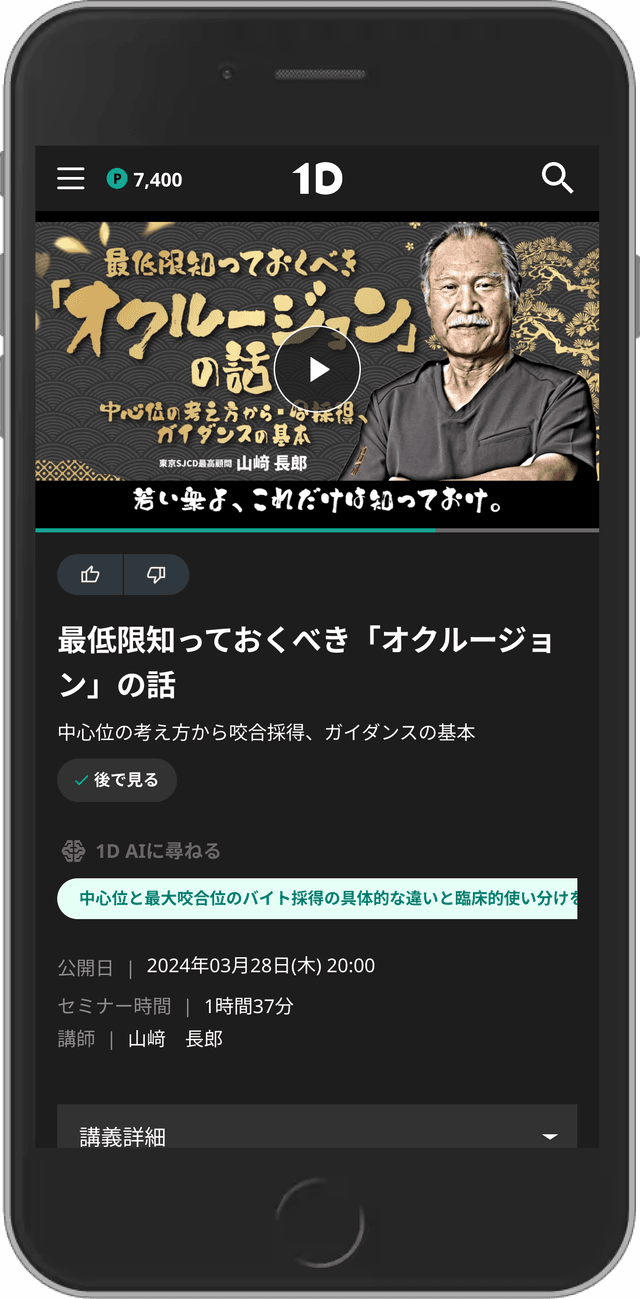
実際の症例を完全解説
倍速再生やスキップ機能で
スキマ時間を活用
活字では伝わりきらない
微細な技術を動画と音声で習得
安心のサービス設計
いつでもどこでも視聴可能
パソコン・スマートフォン・アプリで視聴できます。
1,500時間以上のセミナーを
お得に見放題
お得に見放題
月額11,760円(税込)で見放題です。
月末入会でもOK
更新日は入会日から数えて1ヶ月後です。
いつでも
解約できて安心
解約できて安心
解約手続き後も更新日までは視聴できます。
更に今なら、実践ですぐに使える
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
※毎月新規特典が追加されます。
※特典配布は予告なく終了することがあります。

新着セミナー
おすすめセミナー
1Dプレミアム会員
11,760
円/月
1Dマスターコースに全て参加可能
1D歯科セミナーに全て参加可能
1Dマスターコース・1D歯科セミナーの全アーカイブ配信を視聴可能
・
簡単に領収書発行が可能。医院の経費にできます。
・
いつでも退会いただけます。
・
各コンテンツの配信には期限があるため早めの入会がおすすめです。
- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “訪問・高齢者歯科”のセミナー動画
- 「食べる」を解明する。咀嚼・嚥下障害にならないために。























