- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “訪問・高齢者歯科”のセミナー動画
- 明日から使える「咽頭喀痰吸引」実践

明日から使える「咽頭喀痰吸引」実践
摂食嚥下リハの必要な呼吸器の知識とリスク管理
- セミナー時間
- 1時間46分
- 講師
- 谷口 裕重
講義詳細
摂食嚥下リハビリテーションのリスク管理と聞いて最初に思い浮かぶものはなんですか?
大半の先生は「誤嚥・誤飲予防」や「肺炎予防」が頭に浮かぶのではないでしょうか。
それらの予防も重要ですが、予期せぬことが起きた時は「その時点で生じていることと対処方法」を判断することが求められます。
例えば、口腔管理中やミールラウンド中に多量に誤嚥や窒息した際に、状況や状態を悪化させない対応が必要です。つまり、我々歯科医療者も緊急時の状況把握スキルと対処方法について基本的な呼吸機能・背景にある疾患・誤嚥や窒息時の対応等の適正な知識と技術を備えておく必要があります。
このセミナーでは「咽頭喀痰吸引」をテーマに、呼吸器の解剖などの基礎的な知識から、歯科医師が知っておくべき呼吸器疾患、咽頭喀痰吸引の方法や必要性の判断基準について実践に即した形で 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座摂食嚥下リハビリテーション学・教授 谷口裕重先生に解説していただきます。
訪問診療に力を入れているクリニックは勿論、今後始めたいクリニックにもおすすめです。
明日からの臨床に「咽頭喀痰吸引」を導入するため、気楽に受講してください。
こんな方におすすめ
👉 これから訪問診療を始めたい
👉 咽頭喀痰吸引の手技を身に付けたい
👉 最低限の呼吸器に関する知識を確認したい
講義目次
- なぜ歯科医療者が咽頭喀痰吸引を学ぶ必要があるのか-患者の疾患・障害の複雑化・リスク管理の必要性-
- 咽頭喀痰吸引をするための摂食嚥下機能、呼吸器に関連する解剖・生理学
- 咽頭喀痰吸引の必要性を判断するポイント-頚部聴診法・パルスオキシメーターの使用-
- 咽頭喀痰吸引の実際-口腔・鼻腔・気管からの吸引方法-
- 終わりに
講師

谷口 裕重
詳細朝日大学歯学部口腔病態医療学講座摂食嚥下リハビリテーション学・教授。愛知学院大学歯学部歯学科卒業後、新潟大学医歯学総合研究科口腔生命科学専攻博士課程修了博士(歯学)。藤田保健衛生大学医学部歯科・口腔外科講師、朝日大学大学院歯学研究科准教授・歯学部口腔病態医療学講座障害者歯科学准教授、歯学部口腔病態医療学講座 摂食嚥下リハビリテーション学准教授を経て現職に至る。日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、日本老年歯科医学会認定医、日本老年歯科医学会摂食機能療法専門歯科医師、日本老年歯科医学専門医、日本静脈経腸栄養学会認定歯科医、日本障害者歯科学会認定医、日本嚥下医学会 相談歯科医、日本老年歯科医学会指導医。著書・講演に「はじめて学ぶ歯科衛生士のための咽頭喀痰吸引マニュアル呼吸器のリスク管理と実践」「アセスメントに基づいた摂食嚥下訓練を実施しよう」など多数。
1Dプレミアムに登録するとすべてのセミナー見放題!
月額 11,760円(税込)
作品数
1000本以上
ジャンル
臨床から経営まで
全分野体系的に網羅
受講者数
5000人以上
1Dセミナーの特徴
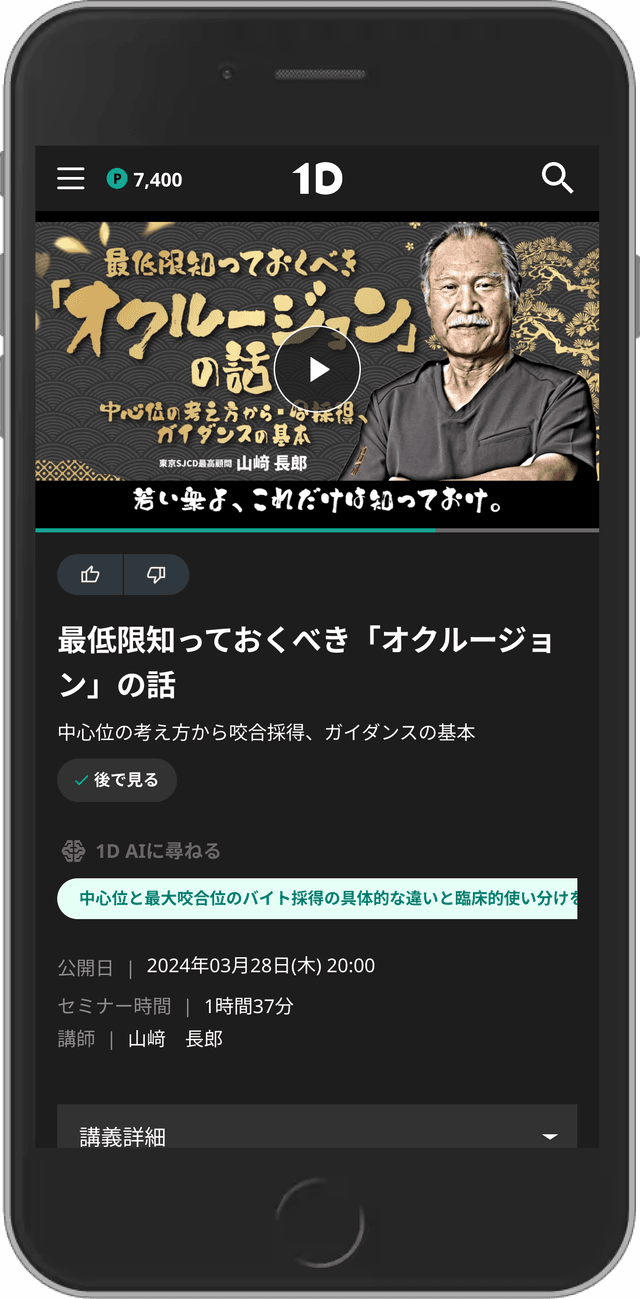
実際の症例を完全解説
倍速再生やスキップ機能で
スキマ時間を活用
活字では伝わりきらない
微細な技術を動画と音声で習得
安心のサービス設計
いつでもどこでも視聴可能
パソコン・スマートフォン・アプリで視聴できます。
1,500時間以上のセミナーを
お得に見放題
お得に見放題
月額11,760円(税込)で見放題です。
月末入会でもOK
更新日は入会日から数えて1ヶ月後です。
いつでも
解約できて安心
解約できて安心
解約手続き後も更新日までは視聴できます。
更に今なら、実践ですぐに使える
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
※毎月新規特典が追加されます。
※特典配布は予告なく終了することがあります。

谷口 裕重 先生のセミナー
新着セミナー
おすすめセミナー
1Dプレミアム会員
11,760
円/月
1Dマスターコースに全て参加可能
1D歯科セミナーに全て参加可能
1Dマスターコース・1D歯科セミナーの全アーカイブ配信を視聴可能
・
簡単に領収書発行が可能。医院の経費にできます。
・
いつでも退会いただけます。
・
各コンテンツの配信には期限があるため早めの入会がおすすめです。
- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “訪問・高齢者歯科”のセミナー動画
- 明日から使える「咽頭喀痰吸引」実践























