- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “口腔外科”のセミナー動画
- GPのための口唇口蓋裂

GPのための口唇口蓋裂
病態・治療の知識と診療所での正しい対応
- セミナー時間
- 1時間25分
- 講師
- 西條 英人
講義詳細
クリニックに口唇口蓋裂の患者さんが来た場合、先生ならどのように対応しますか?
大半の先生が専門の医療機関に紹介すると答えるでしょうし、その答えは間違いではありません。しかし「知識に基づき自院では対応不可と判断したうえでの紹介」と「どうすればいいか分からず取りあえずで行う紹介」とでは天と地程の差があります。
一般的に大学病院のような専門機関で治療するイメージの強い口唇口蓋裂ですが、症例によっては開業医でも対応可能なものもあります。特に治療のひと段落着いた後のメインテナンスは一次医療機関である開業医の役割であり、遭遇頻度が低いからと勉強を怠ることは致命的とも言えるでしょう。
このセミナーでは「開業医が知っておくべき口唇口蓋裂」をテーマに、一次医療機関として口唇口蓋裂患者が来院した際に対応するための知識、対応の可否を判断するための目、具体的どのような処置を行うのか、定期メインテナンスでの注意事項、患者及び保護者の心に寄り添うことの重要性について 東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・運動機能医学講座准教授 西條英人先生に解説していただきます。
「口唇口蓋裂の患者さんも普通の子と同じように診て大丈夫なんだ!」これまでの考え方がひっくり返るセミナーです。
こんな方におすすめ
👉 開業医に必要な口唇口蓋裂の話が聞きたい
👉 口唇口蓋裂患者が来院した際の対応を学びたい
👉 一次医療機関として様々な患者さんに対応出来るようになりたい
講義目次
- 口唇口蓋裂とは
- 必要な診査・診断
- 開業医で対応可能な症例と具体的な内容
- 定期メインテナンスでのポイント
- 心に寄り添うことの重要性
講師
西條 英人
詳細東京大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・運動機能医学講座准教授。東京大学医学部附属病院口唇口蓋裂センターセンター長、宮崎大学医学部顎顔面口腔外科学講座臨床教授。博士(医学)(埼玉医科大学)。日本口腔外科学会専門医・指導医、日本口腔科学会認定医、日本顎顔面インプラント学会指導医、日本有病者歯科医療学会専門医・指導医、日本小児口腔外科学会指導医、日本先進インプラント医療学会専門医・指導医、日本再生医療学会認定医、ICD制度協議会インフェクションコントロールドクター、バイオインテグレーション学会指導医、日本口蓋裂学会認定師。著書・講演に「口蓋裂患者における口蓋裂幅と言語成績の検討~音響特性評価による新規診断値の設定~」「口唇裂の胎児治療を目指した帯状再生組織によるマウス胎仔口唇欠損の修復と融合の検証」など多数。
1Dプレミアムに登録するとすべてのセミナー見放題!
月額 11,760円(税込)
作品数
1000本以上
ジャンル
臨床から経営まで
全分野体系的に網羅
受講者数
5000人以上
1Dセミナーの特徴
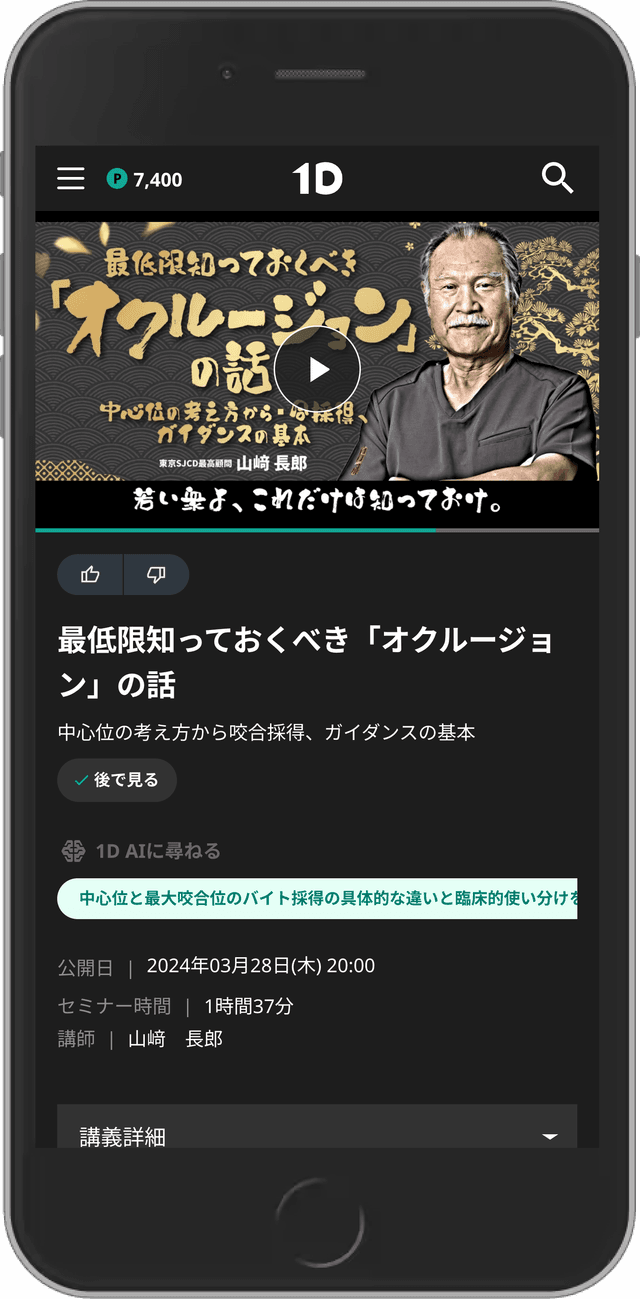
実際の症例を完全解説
倍速再生やスキップ機能で
スキマ時間を活用
活字では伝わりきらない
微細な技術を動画と音声で習得
安心のサービス設計
いつでもどこでも視聴可能
パソコン・スマートフォン・アプリで視聴できます。
1,500時間以上のセミナーを
お得に見放題
お得に見放題
月額11,760円(税込)で見放題です。
月末入会でもOK
更新日は入会日から数えて1ヶ月後です。
いつでも
解約できて安心
解約できて安心
解約手続き後も更新日までは視聴できます。
更に今なら、実践ですぐに使える
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
※毎月新規特典が追加されます。
※特典配布は予告なく終了することがあります。

西條 英人 先生のセミナー
新着セミナー
おすすめセミナー
1Dプレミアム会員
11,760
円/月
1Dマスターコースに全て参加可能
1D歯科セミナーに全て参加可能
1Dマスターコース・1D歯科セミナーの全アーカイブ配信を視聴可能
・
簡単に領収書発行が可能。医院の経費にできます。
・
いつでも退会いただけます。
・
各コンテンツの配信には期限があるため早めの入会がおすすめです。
- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “口腔外科”のセミナー動画
- GPのための口唇口蓋裂
























