- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “咬合・補綴”のセミナー動画
- 生活歯の支台歯形成

生活歯の支台歯形成
露髄を防ぎクリアランスを確保する形成テクニック
- セミナー時間
- 1時間32分
- 講師
- 三浦 宏之
講義詳細
「これ以上削ったら露髄かな?」「術後に疼痛が起きたらどうしよう」
生活歯の形成では脱離や破折以外にも、歯髄が生きているからこその注意が必要になります。
小さいう蝕であれば問題はありませんが、歯質の欠損が大きい症例や生活歯でFMCを選択した場合など実は恐る恐るになっている方は意外と多いように感じられます。
またCAD/CAMといった新しい材料や装置が取り入れられたことで、形成のポイントが分からなくなってしまっている方も少なくないと思われます。
このセミナーでは「生活歯の支台歯形成」をテーマに、基本的知識から道具の選択、露髄を防ぎながらクリアランスを適切に確保する形成法、手技における注意点に至るまでを東京医科歯科大学名誉教授の三浦宏之先生に解説していただきます。
材料・咬合ごとの勘所についてもお話ししていただくため、保険から自費に渡る様々な症例役立つ知識が得られます。
生活歯でも怖くない。
日常臨床のレベルが変わるセミナーです。
こんな方におすすめ
👉 生活歯の安全な支台歯形成を身に付けたい
👉 露髄や術後疼痛を防ぎたい
👉 支台歯形成のスキルアップがしたい
講義目次
- 生活歯の形成とは
- 失活歯との違い
- 最低限抑えるポイント
- 材料ごとの違い
- 症例ごとの違い
講師
三浦 宏之
詳細東京医科歯科大学名誉教授。 東京医科歯科大学歯学部補綴学第2講座専攻生・医員・助手・教授、同大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野教授、東北大学歯学部非常勤講師、徳島大学歯学部 非常勤講師、東京工業大学非常勤講師、東京医科歯科大学歯学部附属歯科技工士学校長、九州大学非常勤講師を歴任。日本補綴歯科学会専門医・指導医。著書・講演に「臨床咬合学辞典」「目で見るクラウン・ブリッジ-トータルにとらえる歯のかたち」など多数。
1Dプレミアムに登録するとすべてのセミナー見放題!
月額 11,760円(税込)
作品数
1000本以上
ジャンル
臨床から経営まで
全分野体系的に網羅
受講者数
5000人以上
1Dセミナーの特徴
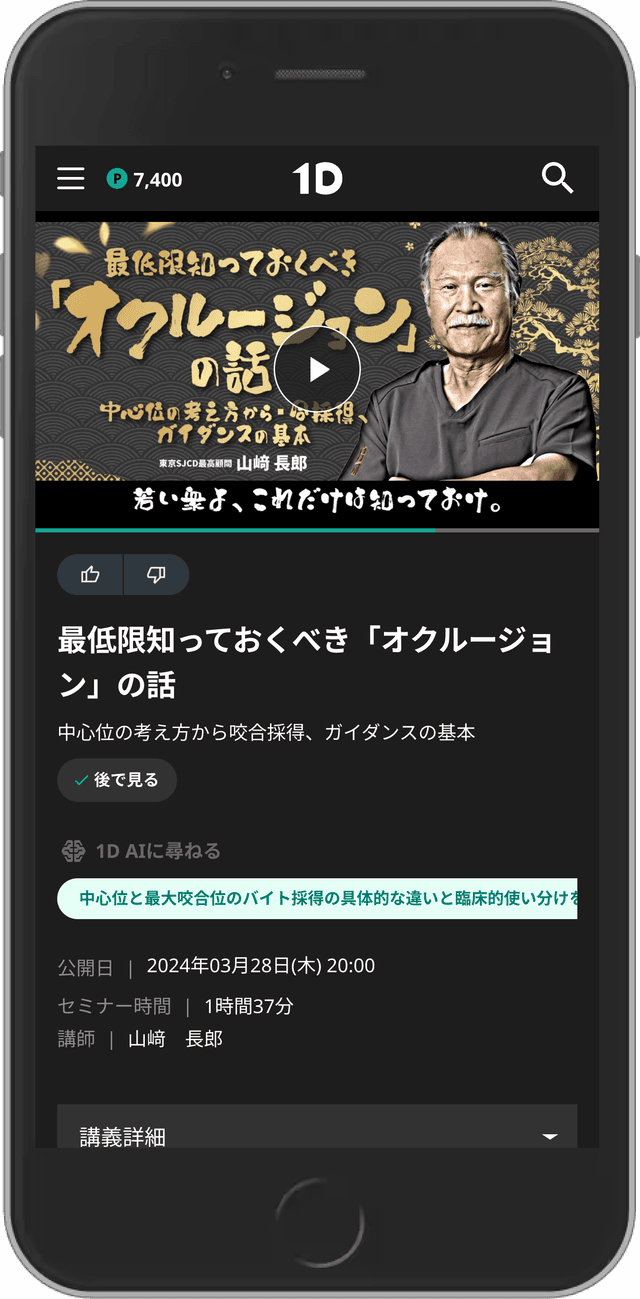
実際の症例を完全解説
倍速再生やスキップ機能で
スキマ時間を活用
活字では伝わりきらない
微細な技術を動画と音声で習得
安心のサービス設計
いつでもどこでも視聴可能
パソコン・スマートフォン・アプリで視聴できます。
1,500時間以上のセミナーを
お得に見放題
お得に見放題
月額11,760円(税込)で見放題です。
月末入会でもOK
更新日は入会日から数えて1ヶ月後です。
いつでも
解約できて安心
解約できて安心
解約手続き後も更新日までは視聴できます。
更に今なら、実践ですぐに使える
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
※毎月新規特典が追加されます。
※特典配布は予告なく終了することがあります。

新着セミナー
おすすめセミナー
1Dプレミアム会員
11,760
円/月
1Dマスターコースに全て参加可能
1D歯科セミナーに全て参加可能
1Dマスターコース・1D歯科セミナーの全アーカイブ配信を視聴可能
・
簡単に領収書発行が可能。医院の経費にできます。
・
いつでも退会いただけます。
・
各コンテンツの配信には期限があるため早めの入会がおすすめです。
- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “咬合・補綴”のセミナー動画
- 生活歯の支台歯形成























