- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “咬合・補綴”のセミナー動画
- ピタッと入るブリッジの「時短形成」テクニック

ピタッと入るブリッジの「時短形成」テクニック
基本形態から平行性確保のポイント、テーパーが過剰にならないコツを伝授
- セミナー時間
- 1時間28分
- 講師
- 川西 範繁
講義詳細
ブリッジ形成は通常の形成におけるポイントに加え平行性への配慮も求められることから、他の形成より時間を要してしまう・苦手意識のある先生が多いと感じております。
特に卒後すぐの先生の中には「1歯のクラウン形成も大変なのに、ブリッジなんて無理無理」と感じている方もいることでしょう。
しかし「削り始める位置を決める」「平行性の基準を明らかにする」「目で見えるようにする」などのポイントをおさえることで、形成の時間を劇的に短く出来るかもしてません。
このセミナーでは「ブリッジ形成の時間短縮」を目標に、ブリッジ形成の基本からミラーテクニック、バーの選び方、平行性の基準の定め方、テーパー付与のコツに至るまでを 神奈川歯科大学歯科補綴学講座クラウンブリッジ補綴学分野講師/補綴科クラウンブリッジ診療部門診療部科長 川西範繁先生に解説していただきます。
長期予後のためのポイントについてもお話ししていただくため、速いだけに終わらない確実な技術も身につきます。
「ブリッジ形成は時間がかかっても仕方がない」
その常識、覆しましょう!
こんな方におすすめ
👉 ブリッジ形成について学びたい
👉 失敗しない形成のコツが知りたい
👉 時短のポイントを身に付けたい
講義目次
- ブリッジ形成の基本
- 平行性の確保のコツ
- 理想的なテーパー付与とは
- 見える、ミラーテクニック
- ブリッジを長持ちさせるには
講師

川西 範繁
詳細神奈川歯科大学歯科補綴学講座クラウンブリッジ補綴学分野講師/補綴科クラウンブリッジ診療部門診療部科長。神奈川歯科大学歯学部卒業後、同大学歯学研究科咀嚼機能制御補綴学分野に入局。神奈川歯科大学大学院 歯学研究科口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野助教、同大学附属病院デジタル歯科診療科 (副診療科長)、歯科補綴学講座クラウンブリッジ補綴学分野助教・講師を経て現職に至る。一般社団法人日本デジタル歯科学会にて学術奨励賞を受賞。著書・講演に「すれ違い咬合に対して金属床を用いて咀嚼機能改善を図った一症例 」「CAD/CAM技術を応用した歯冠補綴治療の実践 」など多数。
1Dプレミアムに登録するとすべてのセミナー見放題!
月額 11,760円(税込)
作品数
1000本以上
ジャンル
臨床から経営まで
全分野体系的に網羅
受講者数
5000人以上
1Dセミナーの特徴
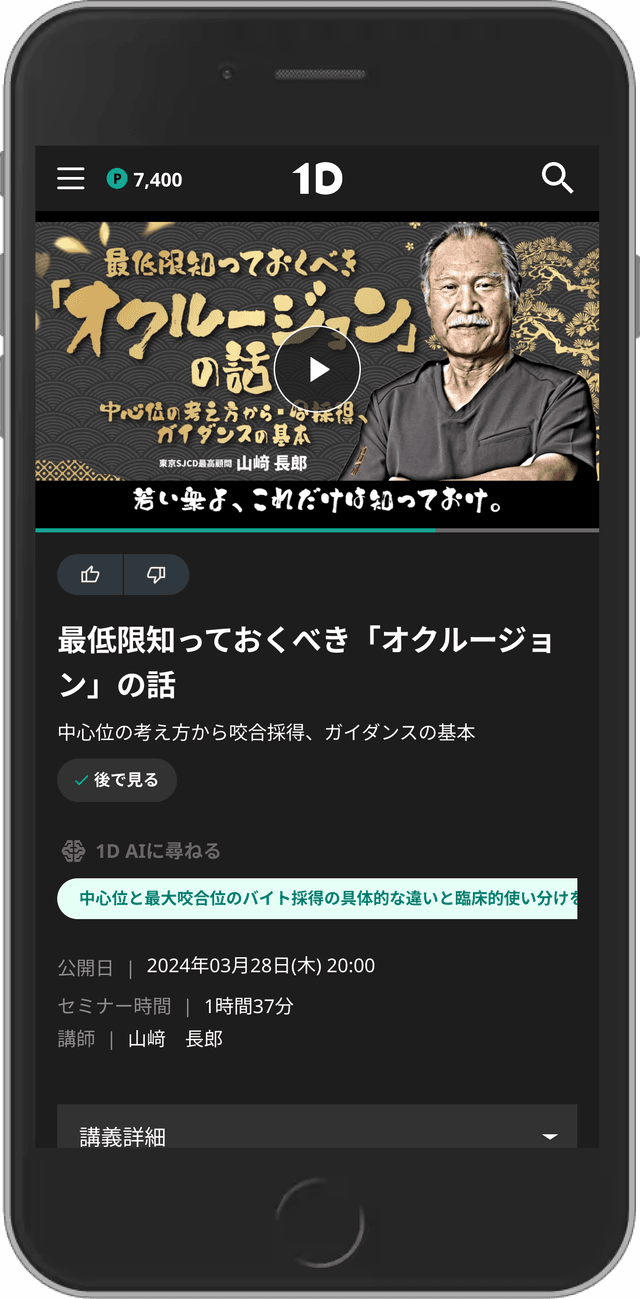
実際の症例を完全解説
倍速再生やスキップ機能で
スキマ時間を活用
活字では伝わりきらない
微細な技術を動画と音声で習得
安心のサービス設計
いつでもどこでも視聴可能
パソコン・スマートフォン・アプリで視聴できます。
1,500時間以上のセミナーを
お得に見放題
お得に見放題
月額11,760円(税込)で見放題です。
月末入会でもOK
更新日は入会日から数えて1ヶ月後です。
いつでも
解約できて安心
解約できて安心
解約手続き後も更新日までは視聴できます。
更に今なら、実践ですぐに使える
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
「患者説明キット」や「自費率向上マニュアル」等
総額100万円以上の臨床支援ツールをダウンロードし放題
※毎月新規特典が追加されます。
※特典配布は予告なく終了することがあります。

川西 範繁 先生のセミナー
新着セミナー
おすすめセミナー
1Dプレミアム会員
11,760
円/月
1Dマスターコースに全て参加可能
1D歯科セミナーに全て参加可能
1Dマスターコース・1D歯科セミナーの全アーカイブ配信を視聴可能
・
簡単に領収書発行が可能。医院の経費にできます。
・
いつでも退会いただけます。
・
各コンテンツの配信には期限があるため早めの入会がおすすめです。
- 歯科オンラインセミナー・動画配信は1D
- “咬合・補綴”のセミナー動画
- ピタッと入るブリッジの「時短形成」テクニック























