- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 歯周保護材
- ビー・エス・エーサクライの歯肉保護材、レジーナマルチの多用途と使い分けについて徹底レビュー
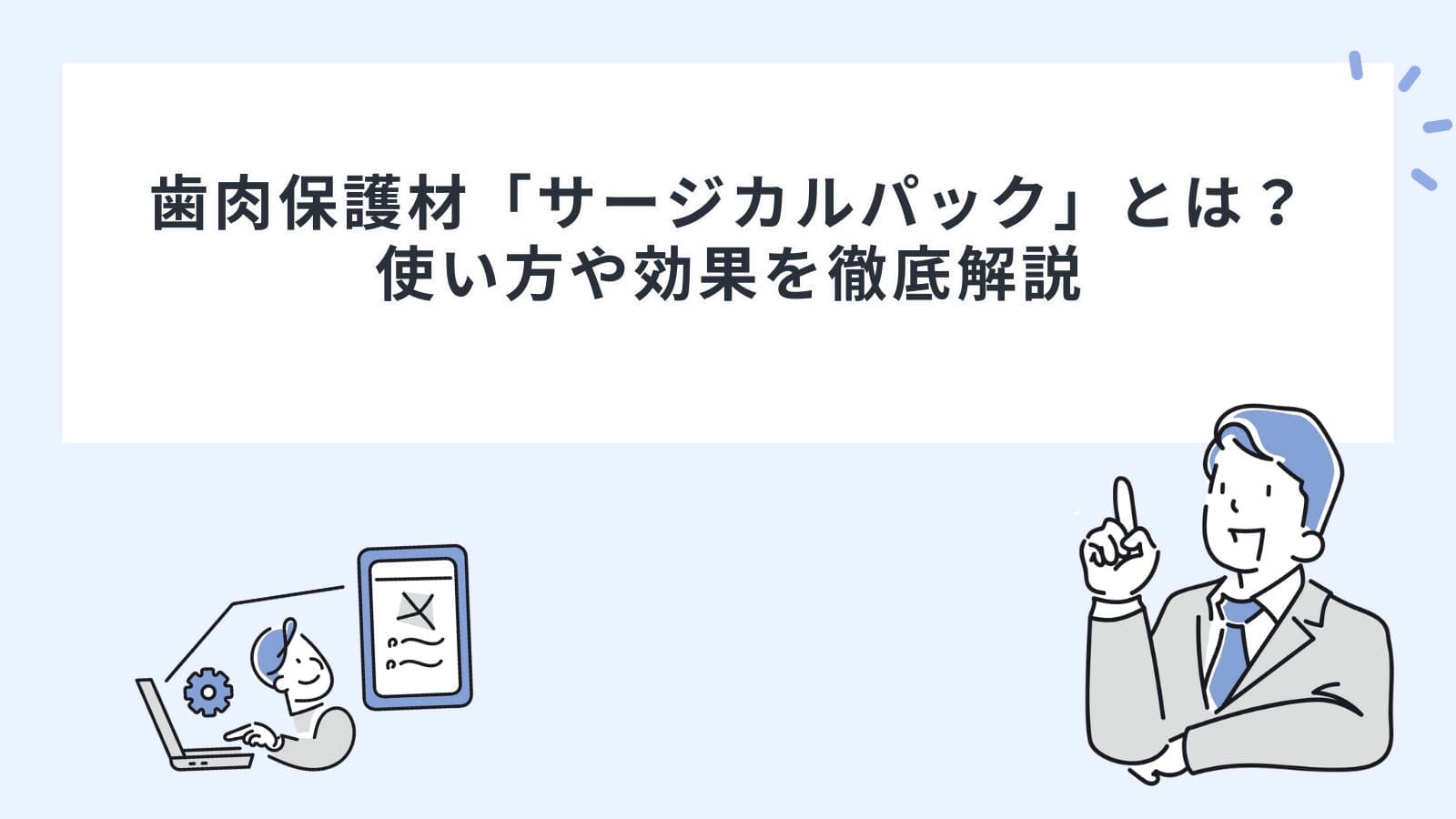
ビー・エス・エーサクライの歯肉保護材、レジーナマルチの多用途と使い分けについて徹底レビュー
歯科臨床では、「もう少し簡便に歯肉を守れないか」と感じる瞬間が多々ある。例えばオフィスホワイトニングで高濃度の漂白剤を使う際、歯肉をしっかり覆えず患者に痛みを与えてしまった経験はないだろうか。またラバーダムを省略した充填処置で唾液に悩まされ、接着不良によるやり直しに時間を費やしたこともあるかもしれない。こうした現場の悩みに応えるべく開発されたのが、ビー・エス・エーサクライの歯肉保護材「レジーナマルチ」である。本記事では、この多用途レジンの使い分けについて臨床と経営の両面から徹底レビューする。診療効率の向上から患者満足度アップまで、経験豊富な歯科医師の視点で本製品の価値を紐解いていく。
レジーナマルチとは何か
レジーナマルチは、ビー・エス・エーサクライ社が提供する光重合型歯肉保護用レジンである。正式な販売名は「レジーナマルチ」で、一般医療機器として届出された歯科用材料である。用途は名前の通り多岐にわたり、オフィスホワイトニング時の歯肉マスキング、模型上でのカスタムトレー用スペーサー作製、さらには石膏模型のブロックアウトまで一本でこなす多目的レジンである。1ケースに2g入りシリンジが5本と先端チップ25本が含まれており、医院向け価格はおよそ4,200円(税別)となっている。製造国は韓国で、高品質ながらコストパフォーマンスに優れる点も特徴の一つである。使い捨てチップを装着したシリンジから直接塗布し、歯科用光照射器で硬化させて使用する。短時間で弾性のある保護膜を形成でき、施術後は簡単に一塊で剥がせるため患者への負担も少ない。以下では、その具体的な性能と活用法を詳しく見ていく。
主要スペック
レジーナマルチの主要スペックとしてまず挙げられるのは、その粘性と流動性のバランスである。適度な粘度がありながら流れ落ちないレベルのフロー特性を持ち、狙った位置に思い通りに塗布しやすい設計になっている。これは歯頸部や乳頭部といった細かな歯肉領域にも薄く均一に広げられることを意味し、マージン際まで確実に覆えることにつながる。またφ0.7mmの極細ディスポーザブルチップが付属し、ピンポイントでレジンを置けるため歯間部や複雑な模型面でも作業性が高い。
次に光重合特性であるが、一般的なLED光重合器で約10秒の照射により硬化が完了するスピード硬化型である。硬化後のレジンは弾力を有するゴム状の固まりとなり、処置中は歯肉にしっかり付着してずれにくく、終了後には一体となって一括除去が可能な適度な強度を備える。歯面への付着も強すぎないため、エナメル質を傷つけずに剥がせる点も臨床的に安心である。色調は鮮やかなブルー系で、術野での視認性が高く取り残しの防止に役立つ。これは光重合型歯肉保護材全般に重要な点で、淡色の歯肉とのコントラストが明瞭なおかげで塗布範囲や厚みを術者が直感的に把握できる。
レジンの生体適合性も見逃せない。短時間口腔内に留置して使用する材料であり、製品自体は唾液や漂白ジェルに対して化学的に安定で溶出もしないよう設計されている。実際、術後に歯肉へ薬剤が漏れず保護できることはもちろん、レジン自体が軟組織に刺激を与えにくい処方となっている。硬化時の発熱も少量塗布であればごく僅かで、患者が不快を訴えるケースはほとんどない。スペック上は未滅菌製品だが、術者の操作次第で無菌的に扱うことができ、後述のように同一シリンジを複数患者に使い回すことも可能である。
最後に包装単位と保存性であるが、2gシリンジ×5本という構成は、多用途に使える製品だけに必要な分だけ開封し無駄なく使い切れるメリットがある。各シリンジはライトガードの施された不透明プラスチック製で、開封前の有効期限は通常2年以上と十分に長い。直射日光を避け室温で保管すれば品質は安定しており、少量ずつの使用でも性能劣化なく使い続けられる。仮に余ってもモデル上のブロックアウト等で消費できるため、在庫が死蔵される心配も少ないだろう。
互換性と運用方法
あらゆるホワイトニングシステムとの相性が良い点は、レジーナマルチの大きな利点である。特定のメーカーの漂白剤専用品ではなく汎用の歯肉保護レジンであるため、現在クリニックで採用しているオフィスホワイトニング材が何であれ、その前処置として問題なく併用できる。例えば過酸化水素製剤を用いる国内外の主要ホワイトニングシステム(TiON、オパールエッセンス等)のプロトコルに組み込んでも全く支障がない。強いて注意するとすれば、ホワイトニング用の光照射装置を併用する際の順序である。一般にホワイトニングではまず歯肉保護材を光重合で硬化させ、その後に漂白ジェル塗布→ホワイトニングライト照射という流れになるが、使用する光重合器の波長とホワイトニングライトの波長が近い場合、照射順によってはレジンが硬化不良を起こすリスクがある。対策として、レジン硬化はホワイトニングライト照射前に必ず専用の光重合器で確実に行うことが大切である。各種LED照射器に対応した設計ではあるが、念のためパワーが十分な器機(できれば1,000mW/cm²以上の出力)で硬化させることで万全を期したい。
運用面では、現在の診療フローに無理なく組み込める柔軟性が評価できる。ホワイトニング時は開口器や口唇リトラクターで歯肉を露出させ乾燥させた状態で、本材をシリンジから直接歯肉に圧出・塗布する。その際、歯頸部エナメル質にも0.5mm程度重ねて盛り上げ、歯肉側へも高さ2〜3mmほど立ち上げるように連続して覆うと良い。こうすることでエナメル質との境界にしっかりシールが形成され、漂白剤が隙間から漏れ込む心配がなくなる。塗布直後は粘性により形が保持されるので、所定の範囲を覆い終えたら速やかに光照射器で硬化する。特別なラッピングや薬液処理は不要で、その場で口腔内にレジンの弾性マスクが出来上がる手軽さが売りだ。術後は探針やピンセットで端をめくれば簡単に剥離でき、歯肉からの剥がし残りも起こりにくい。硬化物は一体化しているので、小片が散らばるようなこともなく安全に回収できる。万一一部が歯間部に残っても目視で確認でき、超音波スケーラー等で除去しやすい。
カスタムトレー用スペーサーとして使う場合の互換性も良好である。石膏模型上では、通常シリコンやワックスで行っていたブロックアウト作業をレジンで代替できる。石膏面にも適度に付着するが硬化後に工具で簡単に剥がせるため、トレーの真空成型後はレジンを外して模型を元の状態に戻せる。また模型上に塗布する際にも流れ落ちず薄く広げられるため、必要最小限の厚みで薬剤保持用スペースを作ることができる。市販のシート(マウスピース材料)との相性も問題なく、レジン表面は硬化後滑沢になるのでシートが貼り付いてしまうこともない。つまりどのメーカーのマウスピース素材でもスペーサーとして機能し、トレー内面に均一な薬剤室を設けることが可能である。
さらに技工用途の互換性にも触れておくと、石膏模型の表面修正材・埋め立て材としても有効である。咬合圧で割れやすいアンダーカット部分の埋め立てや、気泡欠損部の補填にレジーナマルチを用いれば、即座に硬い補修箇所が得られる。技工用レジンや即時硬化パテとは異なり、光照射までは硬化が始まらないため、細部まで練り込んでから硬化位置でしっかり固められる点が作業性を高める。硬化後もバーで削ったり調整が可能で、不要になれば工具で簡単にそぎ落とせるため模型を損ねない。これは院内で簡易なプロビジョナル(仮義歯やガイド)の作製を行う際にも便利で、院内ラボワークの小回りが利くようになる。
感染対策の観点では、本製品はディスポーザブルチップを介して塗布するため衛生的に使用できる。1本のシリンジを複数患者に跨いで使う際には、必ず新しい先端チップに交換し、シリンジ先端からの逆流が起きないよう慎重に扱う必要がある。幸い本材は粘性があるため逆流しにくく、通常の使い方で内容物がシリンジ内で汚染されるリスクは低い。それでも院内感染リスクをゼロにするには一患者一シリンジが理想ではあるが、コスト面から現実的には1本のシリンジを複数回に分けて使い切る運用が可能である。保管の際には直射光を避け、キャップで遮光するだけでよい。専用の保管ケースや冷蔵設備も不要で、診療チェア脇のユーティリティワゴンに常備しておくことで必要なとき即座に取り出せる機動性も備えている。
経営インパクト
レジーナマルチ導入による経営面の影響を考えると、そのコストパフォーマンスの高さがまず挙げられる。1ケース(シリンジ5本入り)の価格がおよそ4千円台であり、ホワイトニング症例なら1症例あたり数百円程度の材料費増加に留まる計算である。例えば、1患者の全顎ホワイトニングでシリンジ半分(約1g強)を使用したと仮定するとコストは800円程度となる。一般にオフィスホワイトニングの自費診療費は数万円規模であり、その中で800円はごくわずかな割合である。一方、この800円の投資によって歯肉の安全が確保され施術クオリティが向上する効果は計り知れない。患者の痛みやトラブルを防ぎ、満足度が上がればリピート利用や口コミ紹介につながる可能性も高まる。クレーム対応や治療やり直しに費やす時間とコストを考えれば、事前に保護材を使ってリスク低減を図る方が経営的にも賢明である。
加えて、本製品は多用途ゆえの費用対効果を発揮する。ホワイトニングのみに使える材料を在庫すると、その施術件数が少ない医院では賞味期限内に使い切れず無駄になるリスクがある。しかしレジーナマルチであれば、仮にホワイトニング需要が小さくても、日常の保険診療や模型作業に転用できるため在庫ロスが生じにくい。例えば、レジン充填の際にラバーダムを張る余裕がないケースで代わりに本材を歯肉縁に適用すれば簡易防湿が図れ、接着不良による将来的な再治療率の低下にもつながる。再治療が減れば無償やり直しの機会損失が減り、長期的には医院の利益率向上となる。また、チェアタイム短縮の効果も見逃せない。通常ラバーダム防湿には装着・撤去に数分を要するが、レジンによる局所防湿なら1分程度で塗布硬化が完了する。仮に3分の時短が叶えば、1日20症例で約1時間の診療枠創出に相当する。浮いた時間に追加の処置や患者対応ができれば、人件費当たりの生産性が上がり、売上増加や患者回転率向上という経営メリットに直結する。
ROI(投資対効果)の観点では、本製品は初期投資も運用コストも低いため即効性の高い投資と言える。高額機器のように何年もかけて費用回収を計画する必要はなく、購入後すぐの数症例で十分元が取れる。例えばホワイトニングを新たに導入する際、患者への事前説明で「歯肉保護材で安全に配慮して行います」と付け加えることで安心感を提供でき、自費率アップにも貢献するだろう。実際、歯肉保護の有無で患者の体感痛が変われば、その評判が次の患者獲得につながる。医院の差別化ポイントとして「しっかり歯肉を保護して行う丁寧なホワイトニング」を掲げられれば、価格競争ではなく付加価値競争で優位に立てる。レジーナマルチ導入コストは微々たるものだが、それにより安全性と品質をアピールできるマーケティング効果すら期待できるのである。
さらに、本材はスタッフの技能活用にも貢献する。ホワイトニング業務を歯科衛生士に任せる医院も多いが、歯肉保護材の使用により術中トラブルリスクが減れば、比較的経験の浅いスタッフでも安心して施術を任せやすくなる。これは院長自身の時間を他の収益施策に振り向けられることを意味し、組織的な収益最大化に寄与する。つまり、レジーナマルチは単なる材料ではなく、院内リソース配分の効率化を促すツールでもある。低コストで多機能という特徴をフル活用すれば、投資対効果は数字以上に大きく現れるだろう。
臨床成功へのコツと院内体制
レジーナマルチを効果的に使いこなすには、いくつかの臨床上のコツと運用上の工夫を押さえておきたい。まず臨床テクニックとして重要なのは、的確な塗布方法である。ホワイトニング時に歯肉を覆う際は、乾燥させた清潔な歯肉に少量ずつレジンを出して広げていく。一度に厚塗りしようとせず、薄く均等に層を重ねるイメージで行うと良い。特に歯間乳頭部は薬剤が漏れやすい隙間となるため、チップ先端で押し込むようにして連続したバリアを形成するのがポイントだ。適切な厚みはおおむね2mm程度だが、心配な部位には硬化後にもう一層追加塗布することも可能である。また、歯面側へ0.5〜1mm重ねるように盛ることでエッジ部分のシール性が高まる。逆に歯面を覆いすぎないよう注意も必要だ。漂白ジェルが触れるべきエナメル質までレジンで覆ってしまうと、その部分だけ漂白効果が減弱する恐れがあるためである。したがって歯肉側へは十分、歯側へは最小限というバランスを取りながら塗布範囲を調整するとよい。
光重合の際には、一気に広範囲を硬化させようとせず数ブロックに分けて順次照射する方が確実である。特に高出力ライトを用いる場合、樹脂の発熱が集中しすぎると患者が熱感を訴えることがある。上顎右半分、左半分、下顎右、下顎左と4セグメントほどに分け、各10秒ずつ照射するようなイメージで行えば、熱の分散とムラなく硬化が両立できる。術者は光ガイドを歯肉から適度に離し、直射する角度に注意することで照射漏れを防ぐ。硬化が不十分だと処置中に一部剥がれたり薬剤が浸みる原因となるため、照射時間はメーカー推奨より長め(例:15秒)に設定するなど慎重すぎるくらいが丁度良い。
剥離時のポイントとしては、焦らず一方向へゆっくり剥がすことである。硬化物は弾性があるため急激に引っ張るとちぎれてしまう可能性がある。片端から少しずつ浮かせ、指または鉗子でフィルムを巻き取るようにすると、大きな一塊として除去できる。仮に細片が残った場合でも、染色液で確認する必要はなく目視で青色の欠片が判別できる。残留物は探針やスケーラーで軽く触れれば外れるため、患者に違和感を残さないよう最終確認は怠らないようにする。
院内体制の面では、スタッフ教育と役割分担を工夫したい。レジーナマルチの操作自体はシリンジで塗布しライトを当てるだけとシンプルであり、歯科衛生士や助手でも適切にトレーニングすれば十分施術可能である。実際、ホワイトニング前処置としての歯肉保護はDH業務として行われることが多く、本材を使えば誰でも均一な結果を得やすい。そこで院内で事前に練習を行うことを推奨する。模型や不要義歯などにレジンを塗って硬化・剥離する練習を積むと、適切な厚みや広げ方の勘所が掴める。研修時にはあえて薄く塗りすぎて破れるケース、厚塗りしすぎて余剰が出るケースなどを試してもらい、失敗例から学ぶと効果的である。
また材料の配置場所も重要だ。忙しい診療中にさっと取り出せるよう、ホワイトニングセットと一緒にトレーに載せておく、あるいはCR充填セットに1本忍ばせておくなど、用途ごとの配置を決めておくと無駄がない。「あのとき保護材が手元になかったために歯肉を傷つけてしまった」という事態を防ぐには、術式の標準プロトコルに組み込んでしまうのが一番である。例えばホワイトニングのセットアップ手順書に「歯肉保護レジン塗布」と明記し、スタッフが忘れず準備できるようにする。また、レジン充填のトラブルシューティングフローにも「必要に応じ歯肉保護材で防湿」といった選択肢を加えて共有しておくと、新人スタッフでも現場判断がしやすくなる。
患者説明の場面では、本材の使用意図を簡潔に伝えることで患者の安心感を高めることができる。施術前に「これから歯ぐきを保護する専用のレジンを塗ります。ゴム状に固まってカバーするので薬剤が歯ぐきに付いてもしみません」とひと言添えるだけで、患者は「しっかり対策してくれる」という印象を持つものだ。青い樹脂を塗られると驚く患者もいるため、「青いマスキング材で歯ぐきを覆っています」と鏡で見せながら説明するのも良いだろう。処置後には「歯ぐきに異常がないか確認しますね」とレジンを剥がしながら声掛けし、細心の注意を払っている姿勢を示すことも信頼構築につながる。レジーナマルチは単に歯肉を守るだけでなく、そうしたホスピタリティ演出の道具としても活用できる。
適応症と適さないケースとは?このレジンが活きる場面とは
レジーナマルチの適応症としては、大きく三つのカテゴリーに分けられる。第一にオフィスホワイトニングである。これは本材が最も威力を発揮する場面で、高濃度過酸化物による軟組織の化学的損傷を確実に防ぐために必須と言える。特に歯肉縁まで漂白ジェルを塗布するような症例や、知覚過敏リスクを減らす目的でも、歯頸部の歯肉と象牙質露出部を覆っておくと安心感が違う。第二にコンポジットレジン修復などの通常診療である。ラバーダムを装着しづらい小規模なケースや、歯肉縁下に及ぶ窩洞で唾液や出血を一時的に遮断したい場合に有用だ。完全な防湿効果こそ期待できないが、歯肉からの浸出液や出血点をレジンで押さえ込むことで、応急的に術野を乾燥状態に保てる。例えばクラスV(歯頸部う蝕)の充填時、わずかな唾液でボンディング不良が起こる懸念がある場合に歯肉縁をレジンでシールすれば、その間に接着操作を完了できるだろう。第三に簡易な技工・補綴作業である。カスタムトレーやプロビジョナル作製時の模型修正、矯正用アライナー作製時のモデルスペーサー、あるいは仮義歯調整時のアンダーカットブロックアウトなど、細かな模型上の作業に適している。即時硬化型のレジンとしてペンライト的に使えるため、技工士が不在でも院内でちょっとした補正が完結するのは医院にとってメリットである。
一方、適さないケースも認識しておきたい。まず長時間の使用や長期留置には向かない。レジーナマルチはあくまで処置中の一時保護材であり、外科処置後の歯肉包帯(ペリオドレッシング)のように数日間付けっぱなしにする用途には使えない。硬化後は弾力があるとはいえ強い咀嚼圧には耐えず、誤って噛めば剥がれてしまう。また唾液中で長期間置くことは想定されておらず、清掃不能な状態で放置すると細菌の温床となりかねない。そのため手術創や抜歯窩の保護には適用せず、あくまで処置中から直後に撤去する前提で使うことが重要だ。
次に重度の歯肉炎や出血が止まらない部位では効果を発揮しにくい。歯肉が腫脹出血している場合、表面に乾燥状態を作るのが困難でレジンがきちんと付着しない恐れがある。無理に押さえつけて硬化しても、内部から出る出血や浸出液でふやけて剥離してしまう可能性がある。したがって炎症部位の防湿にはラバーダムか圧排操作など別の手段を講じ、本材は健康な歯肉に対して使用するのが原則となる。また術前の歯面清掃でペリクルや汚れを落としておくことも密着向上に役立つ。
また口腔内全体の防湿が必要なケースには適しない。根管治療や接着修復のように一本の歯を完全に乾燥隔離するには、やはり従来型のラバーダムシート&クランプが不可欠である。レジーナマルチは歯肉を覆うことはできても舌や頬粘膜までは制御できないため、広範囲の隔離には向かない。よって、ラバーダムの代替は部分的にしか担えないと理解しておく必要がある。唾液量の多い患者や、下顎舌側の操作など唾液の流入が避けられない状況では、本材のみで防湿を完結させるのは難しい。必要に応じて吸唾器やロールワッテ併用でフォローすることになる。言い換えれば、レジーナマルチは「歯肉保護」には適するが、「全面的な防湿」には限界があるということである。
代替アプローチとしては、他社製の類似歯肉保護材を使う選択肢もある。Ultradent社のオパールダムのように緑色や白色の競合製品や、Orasealのように非光重合タイプで湿潤下使用可能なシーラントも市販されている。これらはいずれも一長一短で、例えばOrasealはラバーダム縁のシーリングに優れるが強度が低く単独でマスキングには不向きだったりする。その点レジーナマルチは強度と操作性のバランスが良く汎用性が高いことがメリットである。他の方法としてラバーダムシートを切って歯肉に貼り付ける応用法や、ワセリン塗布のみで凌ぐケースもあるが、安全確実さでは光重合レジンの方が上である。特にホワイトニング時の歯肉保護はガーゼや綿片では不十分であり、薬機法上も薬剤メーカーが樹脂カバーの使用を推奨している。したがって代替手段が「現実的にある状況」は限られており、多くの場合でレジーナマルチを用いることが最善策となるだろう。
クリニックのタイプ別検討ポイント
最後に、クリニックの方針や診療スタイル別にレジーナマルチ導入の向き不向きを考察する。読者自身の医院像に照らし合わせて参考にしていただきたい。
1.保険診療中心で効率重視の医院の場合
日々多数の患者を短時間で回すスタイルの先生にとって、本材は小さな時間短縮と失敗防止策として役立つ。例えば、保険のCR充填でラバーダムを省く場面でも歯肉への樹脂塗布で唾液汚染をある程度防げれば、やり直しのリスクが減り結果的に効率が上がる。費用面では1症例あたり数十円〜数百円の材料費アップだが、再治療一回分が防げれば十分元が取れる計算である。ホワイトニング施術自体は保険範囲外だが、最近は安価なオフィスホワイトニングを集患サービスとして提供する医院もある。その際にも本材を使えば短時間で安全に処置できるため、忙しい診療スケジュールを圧迫しない。施術トラブルによるタイムロスも防げるので、効率重視の医院ほど導入メリットが潜在的に大きいと言える。ただし、極端に材料費削減に注力する医院では「そもそも歯肉保護にコストを割きたくない」という考えもあるかもしれない。しかし、そうしたミス防止投資を惜しんで生じたトラブル対応こそ非効率の元凶である。ゆえに効率経営を標榜するほど、レジーナマルチのような失敗予防の小道具を活用する価値は高い。
2.自費診療メインで高付加価値を追求する医院の場合
審美歯科や予防歯科に注力し、患者満足度を第一に考える医院では、レジーナマルチは患者サービス向上のキーアイテムとなる。オフィスホワイトニングはもちろん、ホームブリーチ用トレー作製やダイレクトボンディング修復など、自費メニュー全般で品質を底上げしてくれる。例えばホワイトニングでは歯肉保護の丁寧さがそのまま患者の快適さに直結する。処置中に痛みがないこと、処置後に歯肉が健康なままであることは患者の感動につながり、「またお願いしたい」というリピート意欲を生む。高付加価値路線の医院では、そうしたきめ細やかな配慮こそがブランドイメージになるため、本材の導入は極めて相性が良い。また自費診療は治療費に余裕がある分、材料コストの増加許容度も高い。数百円のコストで数万円の治療品質が守れるなら、迷う理由はないだろう。加えて、院内ラボやチェアサイドでの細かな補綴調整を自身で行うドクターにも有用だ。インプラントのサージカルガイドを自作する際の樹脂ブロックアウトや、仮歯調整時のアンダーカット充填など、小技が効くシーンでアイデア次第で活躍する。患者への説明でも「この青い保護材で歯ぐきを完全にカバーしていますので安心してください」とアピールでき、ホスピタリティを見える化できる点も自費中心医院にとって大きな武器となる。
3.口腔外科・インプラント中心の医院の場合
外科処置やインプラントオペを主体とする医院では、一見ホワイトニング用の本材は縁が薄いように思える。しかし、意外なところでニーズが潜在していることもある。例えばインプラント埋入後の即時プロビジョナルを院内で作製する際、模型上でレジーナマルチを使えば軟組織部の形態付与や圧排模型の作成が容易になる。また外科中に隣接歯や補綴物を削合する場面で、その部位を保護コーティングする用途も考えられる。歯肉や補綴物を傷つけたくない部分にあらかじめ光重合レジンを塗ってバリアを作っておけば、術後に剥がすだけで保護が完了する。口腔外科系の処置では切削粉や洗浄液が飛び散るが、大切な部位に樹脂カバーをしておけばクリーニングが格段に楽になるだろう。ただし、こうした応用はあくまで補助的なものであり、必ずしも日常的に登場するとは限らない。ホワイトニングや審美治療をほとんど扱わない外科特化型の医院では、本材の出番が少ないかもしれない。その場合、無理に導入する必要はないが、「将来的にホワイトニングもメニューに追加するかもしれない」「スタッフが活用できそう」と感じるなら少量から試してみる価値はある。外科治療で鍛えられた先生方は新素材の応用にも長けているので、レジーナマルチを独自の使い方で活かす可能性もある。
以上のように、医院の志向性によって本材の有用性は多少変わるものの、基本的には汎用性が高くどのタイプの医院でもメリットを引き出せる製品と言えよう。「自院ではあまり使わないかも」と思われる先生も、一度導入すれば想像以上に様々なシーンで活躍するかもしれない。
よくある質問(FAQ)
Q1: 硬化させたレジンはどのくらいの時間、口腔内に置いておいて大丈夫ですか?
A1: 基本的には処置が終わるまでの短時間(30〜60分程度)であれば問題なく口腔内に留置できます。レジーナマルチは長時間の装着を想定した材料ではありませんが、1時間程度であれば軟組織に刺激を与えたり劣化したりする心配はありません。処置終了後は速やかに剥がし、患者の口腔内に残さないようにしてください。硬化物自体は生体親和性が高く、万一小片を誤飲しても消化管で害を及ぼすものではありませんが、大きな片が喉に留まらないよう十分注意して除去することが大切です。
Q2: シリンジ1本を複数の患者で使い回すことは可能でしょうか?衛生面が心配です。
A2: シリンジ本体内のレジンは直接患者に触れることがないため、先端チップを交換すれば複数患者に使用することは技術的には可能です。実際、多くの医院で1本のシリンジを数症例に分けて使っています。ただし、絶対に逆流や二次汚染が起きないよう、使用後は先端を拭き取ってから新しいディスポーザブルチップを装着する、保管時に清潔なキャップで塞ぐなどの配慮をしてください。院内感染対策を最優先するなら患者ごとに新品を使うのが理想ではありますが、コストとのバランスを考えて運用されると良いでしょう。なお一度硬化してシリンジ先端に付着したレジンは、新しいチップに交換すれば除去できます。凝固したレジンがノズル先端に残ると押し出しに支障が出るため、チップ交換時に固まりがないか確認してください。
Q3: 他社の歯肉保護レジンとの違いや優位性は何ですか?
A3: 市場には複数の歯肉保護材が存在しますが、レジーナマルチの大きな特徴は多用途性と操作性のバランスにあります。他社製品ではホワイトニング専用で模型には使えないものや、逆に模型用スペーサーには適合するが口腔内では扱いづらいものもあります。レジーナマルチは適度な粘度で口腔内でも模型上でも扱いやすく、しかも硬化後の強度と弾性が両立している点が優れています。例えばUltradent社のオパールダムは色の選択肢がありますがホワイトニング用途が主であり、Spident社のファインダムは価格面でメリットがありますが内容量が少なめです。それに対し本材は1本で多目的に使える設計のため、医院内の様々なシーンで出番が作れます。また日本国内で入手しやすく、サポートや追加購入もしやすい点も安心材料でしょう。要するにレジーナマルチは「これがあればひと通り困らない」という万能選手的なポジションに位置付けられます。ただし用途や好みによっては他製品の方が適する場合もあるため、既存製品をお持ちの場合は性能を比較検討してみることをお勧めします。
Q4: 硬化不良や剥がれが起こることはありますか?その際の対処法は?
A4: 適切に光照射すれば通常硬化不良は起こりませんが、もしレジンが部分的にベタついたり剥がれてきた場合はいくつか原因が考えられます。第一に照射不足です。ライトの出力低下や照射時間不足で硬化が甘いと、粘着残留物が歯肉に付着してしまいます。その場合、追加で光を当てて完全硬化させるか、一度剥がしてから新たに塗布し直すといった対処を行います。第二に歯肉面の湿潤です。塗布前に十分乾燥していなかったり、唾液や出血が染み出していた場所では密着力が落ちます。そうなると硬化後に端からリフトして浮いてきてしまうことがあります。この場合も一度除去し、可能なら圧排や吸引で乾燥状態を作ってから塗り直します。第三に厚み不足があります。極端に薄く塗り広げすぎると強度が出ず、硬化しても途中で裂けたり破損しやすくなります。剥がれが起きた箇所には少し厚めに盛って補強することが有効です。いずれにせよ、トラブルが起きてもすぐに修正できるのが光重合レジンの利点です。硬化時間を延長する、再塗布するといった臨機応変な対応でリカバリーできるので、落ち着いて対処してください。事前に失敗原因を把握しておけば未然に防げることも多いため、最初のうちは小範囲でテスト硬化して状態を確認するのも良いでしょう。
Q5: レジーナマルチを導入する上で、法規制上の注意点はありますか?
A5: レジーナマルチ自体は一般医療機器に分類される製品であり、医療機関で使用することに特段の制限はありません。薬機法上も医師・歯科医師の裁量で自由に使用できる範囲の材料です。ただし患者向けの宣伝において、「完全に安全」「絶対にしみない」といった効果の断定や優良誤認につながる表現は避ける必要があります。例えばホームページでホワイトニングを紹介する際、「歯肉保護材を使用して安全に処置します」程度の記述は問題ありませんが、「当院の材料で歯ぐきが100%守られます」のような誇張は医療広告ガイドラインに抵触する可能性があります。また製品名を前面に出して宣伝すること自体は禁じられていませんが、一般の方には材料名だけでは伝わりにくいため、「歯ぐきを守る特殊なカバーを使用しています」といった分かりやすい言い換えをすると良いでしょう。院内で使用する分には薬事上の届出や記録義務も通常の歯科材料と同様ですので、特別な手続きは不要です。あとは開封後の保管や使い回しなどで院内感染に注意する程度で、法規制というより標準的な院内ルールの範囲です。要するに、レジーナマルチは通常の歯科材料と同じ感覚で導入できる製品ですので、その点で心配は要りません。もし不明点があれば販売元に問い合わせれば丁寧にサポートしてもらえますし、導入のハードルは高くないと言えるでしょう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 歯周保護材
- ビー・エス・エーサクライの歯肉保護材、レジーナマルチの多用途と使い分けについて徹底レビュー