- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 歯周保護材
- 歯肉保護材「サージカルパック」とは?使い方や効果を徹底解説
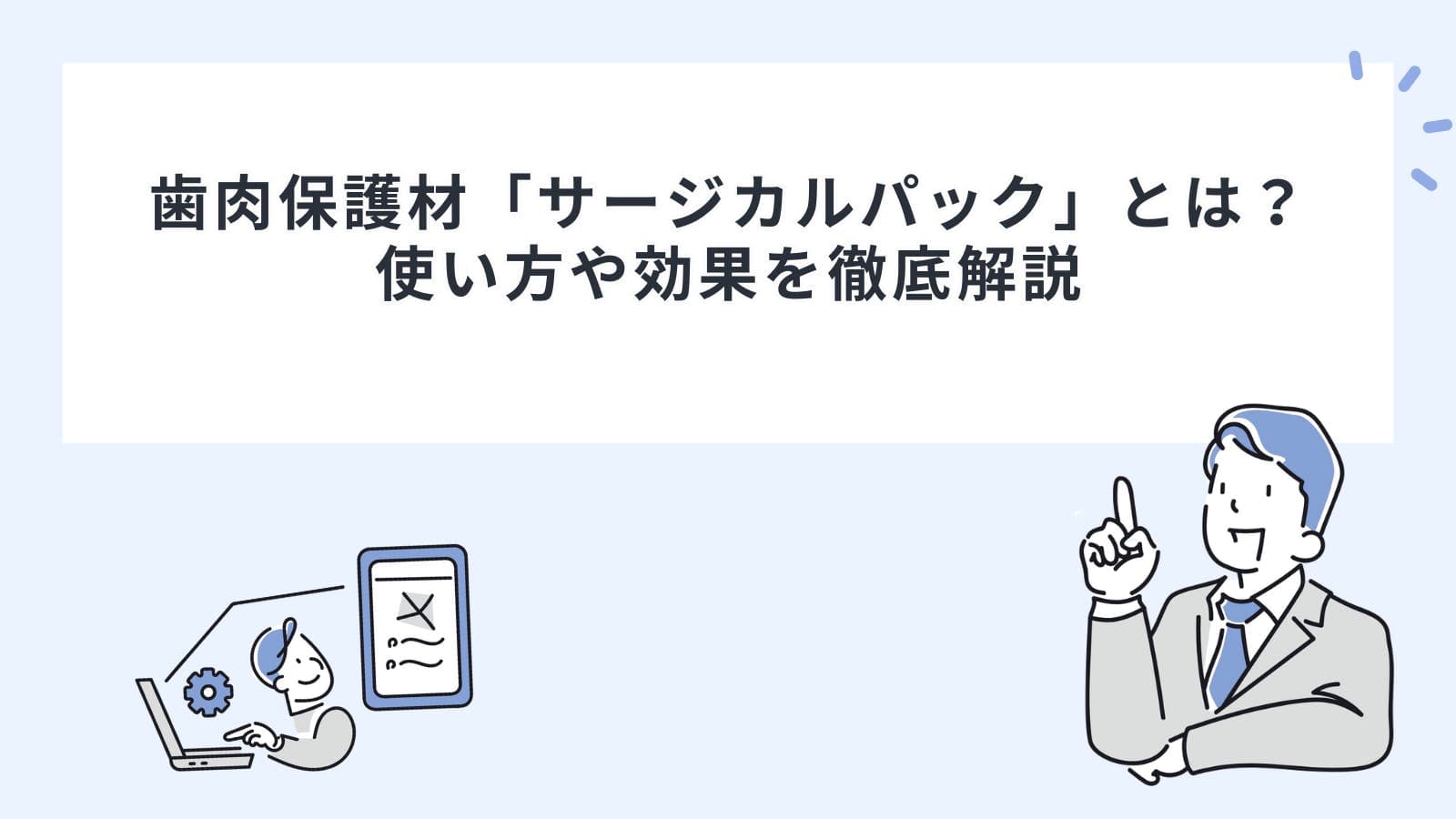
歯肉保護材「サージカルパック」とは?使い方や効果を徹底解説
歯周外科の処置後、患者から「手術部位がヒリヒリして痛む」「食事のたびに傷口が怖い」といった不安の声を受けた経験はないだろうか。たとえばフラップ手術直後に歯肉が露出した状態で帰宅させたところ、翌日に出血と疼痛を訴えられ、急患対応に追われたというケースは臨床現場で珍しくない。サージカルパック(歯周包帯)は、こうした術後の創部を保護し、疼痛や出血を和らげるために用いられる歯科用材料である。本稿では、サージカルパックの臨床的な価値と医院経営への影響を熟練歯科医師の視点から掘り下げ、使い方や効果、導入のポイントを解説する。
読者の先生方がそれぞれの診療スタイルでこの材料を最大限に活用し、患者満足度の向上と投資対効果(ROI)の最大化を図れるよう、経験に基づくヒントを提示したい。
サージカルパックの概要(歯科用歯肉保護材とは)
サージカルパックとは、歯周外科手術後の創傷部を保護するための歯肉保護材である。正式名称は「サージカルパック口腔用」といい、日本標準商品分類では「歯科用繃帯剤」に分類される。一般的には「歯周パック」や「歯肉の包帯」とも呼ばれ、軟膏状あるいはパテ状の材料で術後の傷口を覆って固定する。
対象となる術式は、歯肉切除術・歯肉剥離掻爬術(フラップ手術)・歯周組織再生療法など歯周領域の外科処置全般である。抜歯後に歯槽骨が露出するようなケースや遊離歯肉移植術のドナー部位の保護にも応用されることがある。適応範囲として、術後の創面被覆とそれに伴う疼痛軽減・止血・感染予防が挙げられる。ただし、縫合によって完全に一次治癒が見込める症例では必須ではなく、症例に応じて使用の是非を判断する。また薬機法上の区分としては管理医療機器もしくは医薬品に位置付けられ、歯科医院でのみ使用・提供可能な材料である。
サージカルパック口腔用(昭和薬品化工製)を例にとると、1セットに散剤60gと液剤15mLが含まれる粉液混合型である。使用時に適量を練り合わせて用いるタイプで、歯科用酸化亜鉛ユージノールセメントの一種に分類できる。この製品は2012年に承認され、現在も広く流通している。なお同種製品として、粉液を混ぜるタイプのほかにペースト2剤を練和する非ユージノール系タイプ(例:コーパック)や、光重合で硬化させるタイプ(例:Barricaid〈輸入品〉)などが存在する。いずれも目的は手術部位の保護であるが、成分や扱いが異なるため詳細は後述する。
主要な特徴とスペック
サージカルパックの基本構成は、粉末基剤と液剤を混合して硬化させるタイプが代表的である。粉末の主成分は酸化亜鉛、液剤はユージノール(チョウジ油)であり、混合後に化学反応で硬化する。酸化亜鉛ユージノール系パック材は、歯科用仮封材などと同様に硬化時間と可働時間が設定されており、練和開始からおよそ数分で操作可能な粘度になり、約15分程度で一次硬化する性質がある。製品によって異なるが、一般に操作時間(ワーキングタイム)は5〜10分程度であり、術者はその間に成形と貼付を完了させる必要がある。
この酸化亜鉛ユージノール系の特徴として、硬化後は適度に硬く脆性を帯びることが挙げられる。硬化物はガム硬度程度で、咀嚼圧にはある程度耐えるが、強い力が集中すると割れる可能性がある。そこで、製剤によっては脱脂綿繊維が混入されており(昭和薬品の製品では短繊維を配合)、硬化後の靭性を高めてヒビ割れを防止している。実際、粉液混合型のサージカルパックは、適切に混練すれば術後1週間程度は一塊で残存する強度を持つ。ただし、硬化後は表面がやや粗造でプラークが付着しやすいため、長期間の放置は望ましくない。
一方、非ユージノール系の歯周パック材も臨床で広く用いられている。その代表例が「コーパック」(ヨシダ製)で、こちらはユージノールを含まず2種類のペーストを等量混和するタイプである。非ユージノール系のメリットは、ユージノールアレルギーの患者にも使用可能な点と、硬化後に弾性があり割れにくい点である。ペーストタイプは混練操作が容易で均一に練りやすく、粉飛びもないため扱いやすい。コーパックは硬化後のひび割れが起きにくく、創面をしっかり覆ったまま保持される。色調もピンク色(歯肉色)とされ、審美的にも目立ちにくい工夫がなされている。操作時間は通常の「レギュラー」タイプで10分前後、早期硬化する「ハード&ファースト」タイプでは5分程度と、術式に合わせて選択可能である。
なお、近年では光重合型パック材(例:Barricaid)も一部で使用されている。これはレジン系のジェルを術後創面に塗布し、光照射により即時に硬化させるものである。光重合型は硬化時間を術者がコントロールでき、必要な場所に少量だけ適用することができるため、審美領域で部分的に保護したい場合に有用と報告されている。しかし、光重合型は輸入材料であり国内承認はされていないため一般には手に入りにくい。国内の標準的な選択肢としては、酸化亜鉛ユージノール系(粉液混合型)と非ユージノール系(ペースト混和型)の2種類を理解しておけば十分である。
各種サージカルパックが臨床アウトカムに与える影響として、特筆すべきは術後疼痛の軽減効果である。ユージノール系では材料自体に鎮痛・消炎作用が期待できる。具体的には、液剤成分のチョウジ油(ユージノール)には局所麻酔様作用と鎮痛効果があり、さらに亜鉛成分には収れん作用や穏やかな殺菌作用があるとされている。そのため、ユージノール系パック材は創部を物理的に覆うだけでなく、化学的作用で疼痛を和らげ炎症を抑える働きも見込まれる。一方、非ユージノール系は化学的鎮痛作用はないものの、物理的バリアによって外部刺激から創面を遮断し、患者が舌や指で触れてしまうことを防ぐことで結果的に疼痛緩和につながる。いずれのタイプでも術後出血の抑制には有効であり、創口を安定させることで血餅の保持や肉芽形成を助ける役割がある。
スペック面で歯科医師が注目すべきポイントは、操作性と安定性である。粉液混合型は練和比や環境温度により硬化時間が変動しうるため、初心者には「練るタイミングが難しい」「手に張り付いてしまう」といった課題がある。一方、ペースト混和型は比較的予測通りに硬化し、混ぜムラも少ないため扱いやすさで勝る。硬化後の除去に関しては、ユージノール系はやや脆いため外す際に割れて細片が残ることがあり、非ユージノール系は弾性が強く一塊で外れやすい傾向がある。それぞれの特徴が臨床での扱いやすさと患者の快適さにどう影響するかを踏まえ、自院で採用する製品を選定するとよい。
サージカルパックの使用方法と取り扱い
実際の使い方は、製品の種類ごとに若干異なるが、基本的な流れは共通している。ここでは酸化亜鉛ユージノール系パック材の操作手順と、運用上のポイントを説明する。
標準的な貼付手順
手術終了直前、創面からの出血が落ち着き始めた段階で練和を開始する。粉と液をおおよそ4〜5:1の割合で練板上に取り出し、金属スパチュラで約1分間混ぜ合わせる。最初は粉気が残るが、徐々に泥状のパテになってスパチュラから塊で持ち上げられる粘度になれば練和完了である。練和物を手に取る際には、グローブにくっつきにくくするため手袋を水で湿らせるかワセリンを薄く塗るとよい。指先と手掌で直径5mm程度の棒状に整形し、処置した部位の長さに合わせて適切な長さにする。
最初に頬側(唇側)の歯肉に沿わせて棒状パック材を置き、軽く指で圧接する。同様に舌側(口蓋側)にも成形物を置いて圧接する。次に隣接部で2つのパック材を連結させる。ヘラ状の器具(外科用フラットプラガー等)で歯間部に圧接し、頬舌間でしっかり咬み合うように一体化させる。このとき、パック材を歯頸部よりやや根尖側に押し込むように圧接すると、包帯材が歯面に締まり脱離しにくくなる。創面全体が完全に覆われたことを確認し、最後に口唇や舌を動かしてもらいながら余剰な部分を除去する。余計なはみ出しは、会話や咀嚼の妨げになるだけでなく、硬化後の緩み・脱落の原因となるため、この段階で取り除いておくことが重要である。
貼付後、おおよそ5〜10分で初期硬化が始まる。約15分経過した時点で指で触れても動揺しないことを確認し、ここで処置終了となる。患者には「しばらく舌で触らないように」「30分程度は飲食を控えてほしい」旨を伝える。ユージノール系の場合、貼付直後はチョウジ油特有の香味を強く感じることがあるため、「しばらくクローブ(丁子)の味がしますが心配いりません」と説明しておくと患者は安心する。
運用上の注意点
術後の指導として、サージカルパック装着中は硬い食物や刺激物(香辛料、熱すぎる飲食物)は可能な限り避けるよう伝える。装着部位は歯磨きせず清潔綿球などで軽く拭く程度にとどめ、それ以外の歯は通常通り清掃するよう指導する。パック材は通常1週間ほど装着し、抜糸時または術後7日目に合わせて除去する。場合によっては3〜4日で外すこともあるが、歯周組織の安定のため1週間はそのままにしておくことが多い。装着中に出血や脱落、破損が生じた場合は、早めに来院してもらい、一度除去と洗浄を行った上で再装着する対応を取る。稀にパック材が外れてしまっても、創面がすでに上皮化を始めて落ち着いていれば再装着せず経過観察とすることもある。この判断は術後経過日数と創部の安定度によるが、不安があれば新しいパックを貼り直す方が安全である。
取り外しは、スケーラーやピンセットで縁に引っ掛け、塊ごと剥がすように行う。非ユージノール系では比較的容易に一塊で外れるが、ユージノール系では欠けながら取れることが多いため、遺残物が歯間やポケット内に残らないよう丁寧に除去する。除去後、患部を洗浄・清拭し、歯周組織の治癒状態を確認する。必要であればこの時点で再度パック材を貼付し直し、さらなる1週間経過を待つ場合もある(例:広範囲の歯周再生術で治癒に時間を要する場合など)。
院内での取り扱いとして、サージカルパックは常温保存可能だが、粉剤は吸湿しやすく液剤は揮発性があるため、開封後はフタをしっかり閉めて保管する。長期間放置すると液剤が劣化し硬化不良の原因となることがあるので、定期的に在庫を確認し、適切に使い切るようにする。粉液型の場合、必要量だけ小分けできるため無駄が少ないが、使用頻度が低い医院では有効期限内に使い切れないリスクもある。そのような場合は、歯科商店を通じて小分包タイプや少量セットを入手するか、あるいはペーストタイプ(最小構成が比較的小容量)を検討すると良い。また、スタッフへの教育も重要である。術者が処置に集中している間にアシスタントが練和を行えるよう訓練しておけば、チェアタイムの短縮につながる。パック材の練和・貼付は歯科医師自身が行う必要があるが、補助的な準備をスタッフが担当することで効率よく運用できる。
他資材との併用については、特殊なケースを除きサージカルパック単独で十分である。例えば、遊離歯肉移植術(FGG)のドナー部(口蓋)では出血防止に圧迫副子としてテンポラリーデンチャーやシリコンシートを併用することがあり、その上からパック材で固定するケースもある。また、外科用錫箔と組み合わせて覆う方法も文献的には紹介されている。しかし一般臨床では、パック材のみで創面保護と圧迫固定の機能を兼ねられるため、通常は単独使用で十分な効果を得られる。
医院経営へのインパクト
サージカルパック導入の判断には、経営的な視点も欠かせない。まず材料コストであるが、サージカルパック口腔用(粉液タイプ)の薬価は約1gあたり70円前後である。1症例の術後処置に用いる量は散剤換算で2〜3g程度が目安で、材料費にすると200円程度に収まる計算になる(液剤分も含めても数十円程度の加算である)。一方、非ユージノール系のペーストタイプも1箱あたり数千円で数十回分の処置が可能であり、1回の使用あたり数百円以下といった低コストである。したがって材料そのものの費用負担はごく軽微と言える。
直接的な診療報酬との関係では、歯周外科処置における創傷被覆は診療報酬点数上は個別に算定されず、手術料に包含されている。そのためパック材を使用しても保険請求額は変わらないのが実情である。自費診療であれば、手術処置費用に組み込む形になるが、先述のとおり微々たるコストであり患者への請求額に大きな影響は及ぼさない。一見すると収益に直結しない付加対応のようにも思えるが、経営的には長期的な投資対効果の観点で評価すべきである。
まず患者満足度の向上という無形の効果がある。術後の疼痛軽減や快適性の確保は、患者からの信頼獲得につながり、リピート来院や紹介増加という形で医院の収益に貢献する可能性が高い。小さな不満が患者離れを招くことを考えれば、数百円のコストで満足度を高める意義は大きい。また、サージカルパックを使用することで術後の緊急対応が減少すれば、医院全体のオペレーション効率は向上する。例えばパック非使用で帰した患者が夜間に痛みや出血で電話をかけてきたり、予定外の来院を求めてきたりすると、担当医はその対応に追われることになる。これは見えない人件費コストであり、他の予約診療にも影響を及ぼすリスクがある。パック材によってこれらのアフターケアコストを予防できれば、トータルでの収益性は向上すると考えられる。
さらに、チェアタイム短縮効果も見逃せない。術後にパック材で創面を安定させておけば、次回の再来時に傷が保護された状態なので、抜糸や清掃処置がスムーズに行える。仮にパックを使用せず、術後に血餅脱落や感染が起きていた場合、治癒遅延により追加の処置やアポイントが必要になり、結果的にチェアタイムが余計に割かれてしまう。パック材の利用は適切な治癒環境を提供することで再処置のリスクを下げ、無駄な時間とコストを省く一助となる。
耐用年数や保守費という観点では、サージカルパックは消耗品であり機器のような減価償却は発生しない。強いて言えば在庫管理が必要なくらいで、導入の初期投資ハードルは極めて低い。1セット購入しても数千円程度であるため、小規模な医院でも資金繰りに負担をかけずトライアルできる。仮に使いこなせなかった場合のロスも小さいが、逆に少し工夫すれば非常に高いリターンを生みうる素材と言える。
ROIを考える上では、「患者一人あたり数百円の投資で信頼を維持し、再来院による数万円の治療収入を守る」という図式になる。とりわけ高額な自費の歯周再建治療などでは、術後管理の充実がそのまま患者評価に直結するため、パック材のような細部への配慮が将来的な症例紹介や追加治療の受注につながっていく。また、歯周外科に苦手意識を持つ一般開業医がパック材を併用することで術後管理の安心感が得られれば、積極的に歯周外科治療を提供できるようになるという波及効果も期待できる。それにより医院の診療メニュー拡充や自費率向上が図れれば、経営全体としてもプラスに働くだろう。
総じて、サージカルパックの経営的インパクトは「縁の下の力持ち」としての価値である。直接的に利益を生むツールではないものの、患者満足・時間管理・再治療削減といった間接的な面で医院の発展を支える存在と言える。そのためには単に材料を購入するだけでなく、スタッフ教育や患者説明を含めた運用設計をきちんと行い、真のROI向上につなげることが肝要である。
上手に使いこなすためのポイント
新たにサージカルパックを導入する際、もしくは今以上に有効活用するには、いくつか臨床上のコツがある。ここでは、20年以上の臨床経験に基づき得られた「使いこなしのポイント」を共有する。
1. 十分な止血と乾燥が成功の鍵
パック材は血液や唾液に触れると付着しづらくなる。貼付前に創面を滅菌ガーゼで圧迫し、可能な限り出血を止めておくことが大切である。完全に乾燥させる必要はないが、表面が半乾きになる程度まで待ってから練和を始めると良い。タイミングとしては、縫合や圧迫により出血が減少してきた段階で練和を開始すると、貼付時にちょうど良い状態になる。焦って早く練りすぎると、パックを置く頃にまだ出血が続いていて定着不良になることがある。反対に遅すぎると練和物が硬化し始めて貼付に苦労する。術式の進行と硬化時間を逆算し、最適なタイミングを図ることが肝心である。
2. 適量を見極め、薄すぎず厚すぎず
初心者によくある失敗は、パック材を薄く伸ばしすぎてしまうことだ。材料が不足すると創面が露出したり、硬化後にエッジが鋭利になって痛みの原因となったりする。一方で、盛りすぎも禁物である。分厚いパックは重量で剥がれやすく、また舌や頬に干渉して患者に不快感を与える。適切な厚みは歯肉面からおよそ3〜5mm程度で、歯面とほぼフラットになるくらいが望ましい。必要に応じて余剰分はカットし、形態修正を行う。コツとして、練和した材料は欲張って全部使い切ろうとせず、あえて一部を廃棄する余裕を持つくらいでちょうど良い量になる。製品コストが低いからこそできる贅沢だが、安全確実な被覆のためには必要な判断である。
3. 固定効果を高める工夫
サージカルパックは単なる覆いではなく、歯肉弁の位置維持にも寄与する。特にフラップ手術では、パック材を正しく圧接することで縫合糸では補いきれない広範な面圧を加え、歯肉弁の浮き上がりを抑制できる。具体的には、歯間部でしっかり押し込むこと、さらに創面よりわずかに根尖側に配置することがポイントである。瘢痕治癒を期待する歯肉切除術では創面と同高さで十分だが、再付着を期待するフラップ手術ではパックを少し根尖側にずらして貼付し、歯冠方向へ圧をかけるよう意識すると良い。こうすることで包帯自体が歯肉弁の添圧板のように働き、初期治癒を安定させる。逆に、この固定効果を狙わない場面—例えば単純な歯冠長延長術で縫合が不要なケース—では、無理にパック材を使わず創面露出のまま経過を見た方が早期に上皮化する場合もある。術式の目的に応じて、パック材を力学的にどう活用するかを考えることが大切である。
4. 患者説明と心理ケア
初めてサージカルパックを見る患者は、その見た目に驚くことがある。白色やピンク色のガムのような物体が歯肉に貼り付いているため、不安に思うのは当然だ。そこで、貼付後に手鏡で状態を見せながら丁寧に説明すると安心感を与えられる。「これは傷口を保護する包帯です。このまま一週間ほど置いておきます」と伝え、さらに「取れる頃には傷もかなり治っています」と術後の見通しを示すと患者は前向きになれる。また、「もし途中で外れてしまっても慌てずにご連絡ください」と付け加えることで、患者は万一の時にもパニックになりにくい。実際、パック材が予定より早く脱離してしまっても、創面が安定していれば大事には至らないケースが多い。しかし患者はそれを判断できないため、不測の事態では必ず相談するよう伝えておくことが肝要である。術後の不安を取り除くことも歯科医の重要な仕事であり、パック材は患者との信頼関係を築くコミュニケーションツールとも捉えられる。
5. 継続的な院内トレーニング
使い慣れるまでは、どうしても練和に時間がかかったり、貼付に手間取ったりする。しかし回数を重ねれば、ほとんど無意識に調整できるようになる。院内で1〜2回、模型や豚顎を使ったデモンストレーション練習を行うのも良い方法だ。スタッフとともに練和から貼付・除去まで一通りシミュレーションしておけば、本番の手術で慌てずに済む。特に歯科衛生士や助手にも材料の硬化特性を体感させておくことで、術中のサポートが的確になる。ベテランの歯科医師であっても、新しい種類のパック材(例えばユージノール系から非ユージノール系に切り替えた場合)を導入した際は、クセの違いを事前に掴んでおくべきである。材料の粘性変化や硬化速度、匂いの強さなどを把握しておくことで、自信を持って臨床に臨むことができる。
以上のポイントを押さえておけば、サージカルパックは決して難しい材料ではない。むしろ一度コツを掴めば手放せない頼れる存在になる。臨床の引き出しの中にこのような道具があること自体が術者の安心感につながり、結果として歯周外科治療全体の質向上につながるだろう。
適したケースと適さないケース
サージカルパックは万能ではない。適応症とそうでない場合をきちんと見極め、材料特性に応じた使い分けをすることが重要である。
典型的に適しているのは、広範囲の歯周外科処置で創面が露出するケースである。フラップ手術後に歯肉を縫合しても、一部は二次治癒になる創傷が残ることが多い。そうした部分をパック材でカバーすれば、外力や細菌から保護され安定した治癒環境が得られる。また、遊離歯肉移植術(FGG)のドナー部(口蓋側)や結合組織移植術の受容部においても、パック材で圧迫止血と保護を行うと疼痛が軽減し治癒が早まる傾向にある。歯周組織再生療法(エムドゲイン等併用下でのフラップ手術)でも、縫合部位の安定を図る目的で使用されることが多い。特に垂直性欠損に対する再生手術では、再生材料を入れたエリアを包帯で静止させておくことが理にかなっている。
出血傾向が高い患者(抗凝固薬内服など)の抜歯創や外科処置部にも、サージカルパックは有用だ。適応外ではあるが、ドライソケットの予防目的で抜歯窩に詰めて覆ったり、骨が露出した抜歯創に貼付して保護したりするケースも臨床的には見られる。止血剤だけでは不安な場合にパック材を上から押さえて固定するといった応用的使用である。ただし、この用途ではパック材自体に治療効果を期待するのではなく、あくまで機械的な保護と圧迫を提供する補助手段と捉えるべきである。
一方、適さないケースもある。まず小規模な歯肉切除や切開のみで済むケースでは、創傷がごく小さく縫合不要な場合も多い。この程度の傷であれば、パック材を貼るメリットよりデメリットの方が大きくなる可能性がある。例えば、1歯だけの歯冠長延長術(ガミースマイル修正など)で切除創が歯肉縁に限局するような場合、敢えてパック材を貼ると逆にその存在感が患者に煩わしさを与える恐れがある。また、パック材を維持するにはある程度の広がりと支えとなる隣接歯が必要である。単独遊離歯(周囲に支えがない歯)や歯列の末端部など、固定源が限られる部位では装着が難しく、無理につけてもすぐ脱落してしまうことが多い。そのような場合は、あらかじめ患者に「包帯は使用しませんが問題ありません」と説明し、術後はこまめなうがいと清潔保持で対応する方が良い結果となる。
ユージノールアレルギーや樹脂アレルギーの既往がある患者も注意が必要だ。ユージノール系パックは約4%の頻度で粘膜刺激による潰瘍などの副作用報告がある。以前、仮封材や根管充填材でアレルギー症状を起こした患者には、非ユージノール系を選択することで回避できる。万が一、装着後に強い刺激感や粘膜のただれが見られた場合は、すぐに除去して洗浄し、必要ならステロイド軟膏塗布などの処置を施す。アレルギーの疑いがあれば今後のためにパッチテストで確認しておくことも有用である。
また、感染コントロールの観点でも考慮が要る。術前に十分なプラークコントロールがなされず、手術部位に慢性的な感染リスクが残るような状況でパック材を被せると、その下で細菌が繁殖してしまう危険がある。理想的には手術の前段階で口腔衛生指導やスケーリングを済ませておき、清潔域で外科処置を行うのが前提だが、緊急性のある場合など準備不足で手術に至るケースもゼロではない。そのような場合、術後にパック材で密閉してしまうことが最善かは検討を要する。場合によっては創面を開放し、術後数日で消毒に通ってもらう方が安全なこともある。術後管理のリソース(通院頻度や患者の協力度)も考慮して、必ずしも全症例に一律でパック材を使用すべきとは言えない。
以上をまとめると、サージカルパックは広範で複雑な手術ほど有効性が高く、局所的で小さい処置ほど必要性が低い傾向がある。また患者の体質や口腔環境によっても適不適があるため、メリット・デメリットを天秤にかけて判断することが望ましい。適材適所で使い分けることで、パック材は真価を発揮するのである。
診療方針別・導入検討のポイント
歯科医師それぞれの診療方針やクリニックの特徴によって、サージカルパック導入の意義や活用法は異なってくる。ここでは、いくつかのタイプ別に導入判断の指針を述べる。
1. 保険診療中心で効率重視の医院の場合
保険診療主体の一般歯科では、歯周外科自体の頻度がそれほど高くないこともある。また診療報酬上パック材使用で加点があるわけではないため、コスト意識から敬遠する声も聞かれる。しかし、効率重視の医院こそパック材の導入メリットは大きい。なぜなら、限られた時間内に多くの患者を回すためには想定外のトラブルを極力減らす必要があるからだ。術後の痛みや出血で予定外の来院が発生すると、その日は他の予約にしわ寄せが及び、オペレーション全体の効率が落ちる。サージカルパックで患者の術後トラブルを抑えられれば、スケジュール通りに診療を進めやすくなる。
もちろん、短時間で貼付するためのトレーニングは必要だが、一度習熟すればパック材の貼付自体は5分程度の追加処置にすぎない。例えば歯周外科1ケース(手術時間60分)の中に組み込んでも所要時間は1割未満増えるだけである。それで得られる安心には十分見合う。保険診療中心の先生にありがちな「時間との戦い」において、サージカルパックは小さな時間投資で大きな安心を買う道具と言える。また「うちの医院では歯周外科もきちんと術後ケアしている」という姿勢は、患者やスタッフにも好印象を与え、医院全体の信頼感向上につながる。効率と品質の両立を目指すなら、一度採用を検討して損はない素材である。
2. 自費診療中心で高付加価値メニューを提供する医院の場合
インプラントや歯周再生治療など自費診療を中心とする医院では、患者満足度の追求が何より重要である。高額な治療費に見合う価値を提供するため、術後経過の快適さにも最大限配慮すべきだ。こうした医院では、サージカルパックの導入はもはや「してもしなくてもいいオプション」ではなく、標準ケアの一部として組み込む発想が望ましい。実際、多くの先進的な歯周専門医やインプラント専門医院では、術式説明の段階から「手術後は保護材で傷口を覆います」と患者に伝え、安心感を持って臨んでもらっている。これは言わばホスピタリティの表現でもあり、細部への気配りとして患者に伝わる。
経営的には、自費治療のフィーには術後管理費用も含まれているため、サージカルパックにかかるコストは十分織り込まれているはずだ。むしろ、その数百円を惜しんで患者の不興を買っては本末転倒である。また、自費診療を選ぶ患者層はインターネットなどで情報収集していることが多く、「他院では術後にパックをしてくれたのに、こちらでは何もない」といった比較をされる可能性もある。高付加価値を掲げる医院ほど最新で最良のケアを提供する必要があり、その意味でパック材を用いた丁寧な術後処置は欠かせないだろう。さらに、審美領域の手術では透明やピンクのパック材を駆使して目立たないよう工夫するなど、より高度なサービスも可能だ。患者のQOLを重視する自費中心のクリニックでは、サージカルパックを単なる材料ではなくサービスツールと捉え、有効に活用してほしい。
3. 歯周病専門・口腔外科・インプラント外科を主体とする医院の場合
高度な歯周外科やインプラント手術を日常的に行う専門性の高い医院では、術後管理もまた高度な水準が求められる。ただし、この層の医院では術者のスキルが高く、術式次第でパック材の必要性を判断しているケースが多い。例えば、インプラント埋入手術では基本的にフラップを完全閉鎖するため、パック材は不要である。一方、結合組織移植やエステティックゾーンの歯周形成術では効果的なので使用するといった具合に、症例ごとに合理的な選択をしている。
こうした専門医院では既にサージカルパック自体は導入済みであることが多いが、そのアップデートについて検討してみる価値がある。古くからユージノール系しか使っていない場合、非ユージノール系に切り替えることで患者の快適性が上がるかもしれない。また、従来手練れの歯科医師ほど「パック無しでも問題なく治せる」という自負もあるが、それでも敢えて使うことでさらなるリスク低減が図れる場面もある。専門医院に来る重度の歯周病患者は全周的なフラップ手術が必要になることもあり、大量のパック材を要するケースもある。そんなとき、作業効率を上げるためにペーストタイプを導入したり、自動練和器(あるいは最近ではカートリッジ式の自動ミキシングガン)を活用したりするのも良い工夫だ。
一方で、症例選択を誤ると逆効果にもなりうる点に注意したい。例えば、複雑な骨移植を伴う手術ではパック材の圧で移植骨が動くリスクも考えられるため、そうした場合は使用しないほうが無難なこともある。また術者が複数いる大きな病院・クリニックでは、パック材使用の有無が術者の判断でばらつくとスタッフが混乱する可能性がある。院内プロトコルとして「この術式では必ず使用」「この場合は不要」などルールを定め、チームで共有しておくと良い。専門性の高い医院だからこそ、材料に関する知見もアップデートし続け、最善手を選び取る姿勢が求められる。サージカルパックは古典的材料ではあるが、いまだ進化を遂げている分野でもあり、専門家ほど柔軟に取り入れてほしい。
以上のように、医院のタイプによってサージカルパック導入の意味合いは変わる。しかし共通して言えるのは、患者本位の医療という観点ではいずれのタイプでもプラスに働くということだ。必要性の大小はあれど、「患者にとって良いこと」であれば採用を検討する価値がある。各院の経営戦略や診療哲学に照らして、本材料をどう位置づけるか考えてみていただきたい。
よくある質問(FAQ)
Q. サージカルパックは必ず使用しなければならないのか?
A. すべての歯周外科症例に必須というわけではない。創面が小さく一次治癒が見込める場合や、術後の管理が容易なケースでは使用しないこともある。ただし広範囲の手術や疼痛・出血のリスクが高いケースでは、患者負担軽減のため使用が推奨される。術式と患者状況に応じて判断すべきである。
Q. パック材をしたままにすると、傷の治りが遅くなることはないか?
A. 適切に使用すれば、治癒が遅延することは通常ない。パック材は創面を物理的に保護し、二次感染や機械的刺激を防ぐため、結果的に正常な治癒を促進する。ただし長期間(2週間以上)放置した場合、下にプラークがたまり治癒を妨げる可能性があるため、通常は1週間程度で除去することが大切である。
Q. サージカルパックが途中で取れてしまった場合、どうすればよいか?
A. まず患者に慌てないよう説明しておくことが重要である。取れた場合は可能なら速やかに医院で状態を確認する。創面が安定していれば再装着せず様子を見る場合もあるが、出血や痛みがある場合は洗浄後に新しいパックを貼り直す。いずれにせよ抜糸予定日より前に外れた場合は一度受診してもらうのが安全である。
Q. ユージノール系と非ユージノール系はどちらを選ぶべきか?
A. 一長一短であり、医院の方針や患者の体質によって使い分けるのが望ましい。ユージノール系は鎮痛効果や止血効果が期待できる反面、稀に刺激性がある。非ユージノール系は刺激が少なく扱いやすいが、化学的鎮痛作用はない。アレルギーリスクのある患者には非ユージノール系を選ぶなど、症例に応じて適切なタイプを選択すると良い。
Q. 保険診療でもサージカルパックの費用を患者に請求できるか?
A. サージカルパック自体は診療報酬上、歯周外科処置に包含されており、単独での算定項目はない。そのため保険診療内では患者から追加費用を徴収することはできない。しかし材料費は低廉であり、使用によって術後管理が円滑になるメリットを考えれば、費用対効果は十分に高いと考えられる。自費診療では当然治療費に含めて問題ない範囲のコストである。医院側の負担としてごくわずかであるため、保険・自費を問わず必要と判断したケースでは積極的に使用すると良いだろう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 歯周保護材
- 歯肉保護材「サージカルパック」とは?使い方や効果を徹底解説