- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 歯周保護材
- ジーシー昭和薬品の歯肉保護材、サージカルパック口腔用について使い方と臨床のコツを徹底レビュー
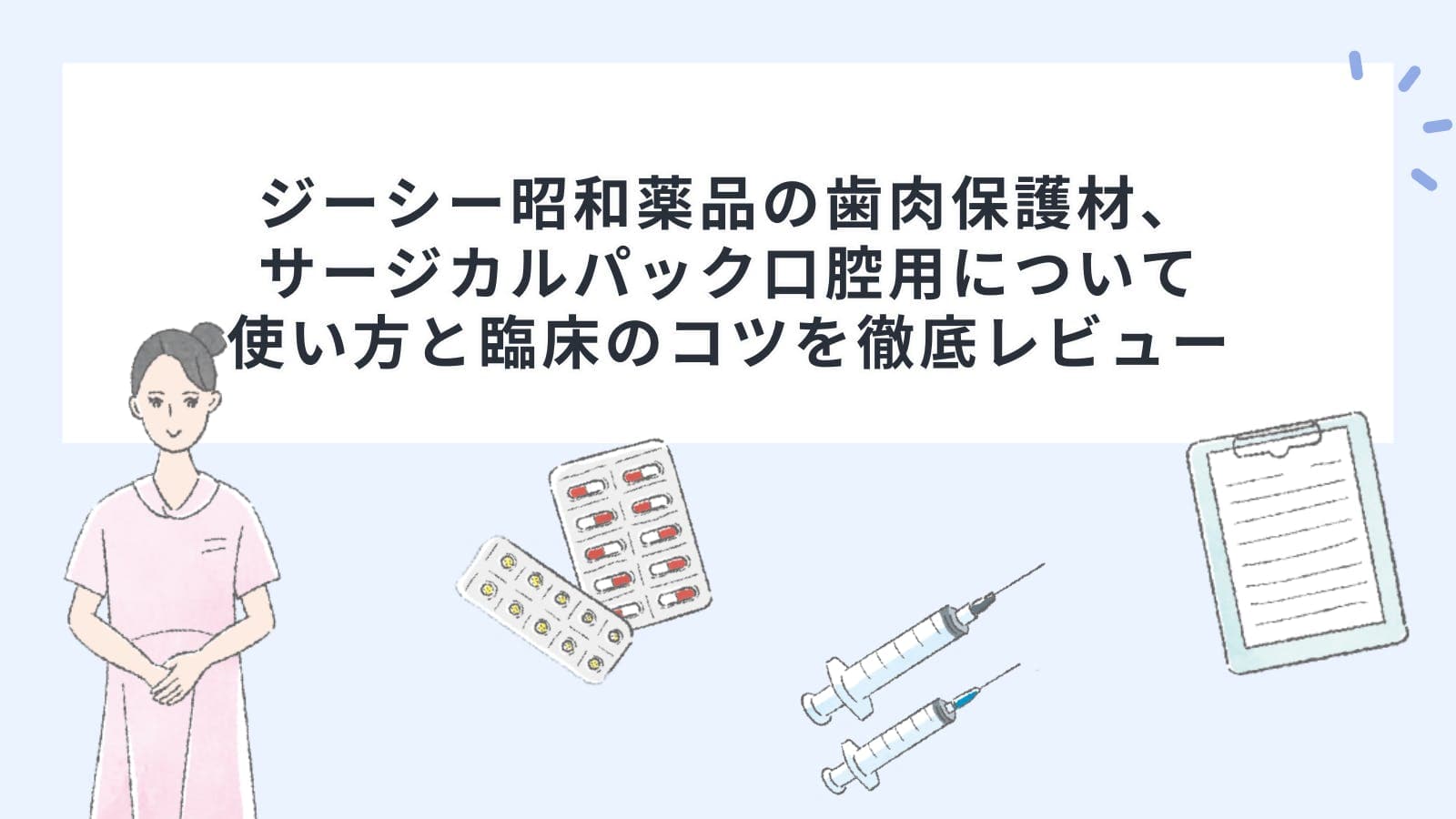
ジーシー昭和薬品の歯肉保護材、サージカルパック口腔用について使い方と臨床のコツを徹底レビュー
歯周外科処置の術後管理に悩んだ経験はないだろうか。たとえばフラップ手術後に創部が露出したままだと、患者の痛みや出血が続かないか心配になる。しかし、一方で保護用のパックを貼付してもすぐに外れてしまい、「手間の割に意味があったのか」と疑問に感じたことがあるかもしれない。実際、術後の歯肉保護材の使用は臨床現場で判断が分かれるポイントである。
若手の頃、せっかく装着したパックが患者の帰宅前に脱落して冷や汗をかいた――そんな失敗談を持つ歯科医師も少なくないだろう。しかし適切に使いこなせば、歯肉保護材は術後管理の心強い味方となり得る。本稿では、ジーシー昭和薬品の『サージカルパック口腔用』に焦点を当て、その使い方と臨床のコツを徹底レビューする。製品の客観的なデータから臨床現場での有用性、さらに医院経営への影響まで、多角的に分析し、読者が自信をもって本製品の導入判断ができるようサポートしたい。
サージカルパック口腔用の概要
『サージカルパック口腔用』は、ジーシー昭和薬品が提供する歯肉保護材(歯科用繃帯剤)である。粉剤と液剤の2剤からなり、使用時に練り合わせて患部に貼付するタイプの歯科用包帯材だ。主成分は酸化亜鉛とチョウジ油(クローブオイル)であり、いわゆる酸化亜鉛ユージノール系のパック材に分類される。歯周外科処置後の創面を覆い保護する目的で使用され、適応となる処置は歯肉切除術、歯周フラップ手術、歯肉移植術後のドナー部位保護など多岐にわたる。
本製品は歴史的にも実績のある処方で、1980年代から歯科臨床で用いられてきた伝統的な歯科材料である(発売開始は1988年)。歯科領域ではこの種の材料を俗に「歯肉包帯」や「コーパック」と呼ぶことがあるが、『サージカルパック口腔用』はまさにその国産ジェネリック製剤と言える。なお、薬機法上は「処方箋医薬品」に指定されており、歯科医師が管理下で使用する医薬品扱いの材料である(一般の市販はされていない)。内容量は粉末60gと液15mLのセットで提供されており、1症例あたりわずかな量の使用で済む。
主なスペックと臨床的な意味
『サージカルパック口腔用』の組成には、臨床性能を高める工夫が凝らされている。粉剤の有効成分である酸化亜鉛は、組織タンパクと結合して不溶性の被膜を形成し、創部を保護するとともに収れん・消炎作用を発揮する性質がある。液剤のチョウジ油に含まれるユージノールは、局所麻酔作用によって術後の疼痛を和らげる効果が期待できる。つまり本剤は、物理的バリアだけでなく化学的作用でも創面の安静確保に寄与する素材である。
さらに添加物として、粉剤中には短繊維状の脱脂綿(コットンファイバー)が含まれ、ロジン(松ヤニ)や高分子系の増粘剤も配合されている。これらにより硬化後のパックは適度な強度と弾性を備え、簡単には割れず一塊で除去しやすい性状になっている。また歯面への付着力も良好で、術中にしっかりと患部へ留まってくれる。硬化後は白色〜淡黄白色のパテ状物質となり、柔軟性を保ちつつ所定の形を維持する。術後1週間程度は脱落せず安定して留置できるよう設計されており、その後は比較的容易に除去可能な硬さに留まるのも特長だ。
混和操作の指標として、粉:液をおおむね4〜5:1の比率で練り、約1分間の練和で粘土状のペーストが得られるようになっている。操作時間は数分程度で、口腔内に適用後およそ10〜15分ほどで初期硬化し始める。硬化中も完全に石のように硬くなるわけではなく、適度な弾力を残すため、咀嚼時に過度な不快感を与えず、除去時にも割れ散ることなく一括して取り外せる。このようなスペックは、古典的な酸化亜鉛ユージノールセメントに改良を加え、臨床現場で扱いやすく患者に優しい性質を実現したものである。
適切な使用方法と運用上の注意点
混和から貼付までの手順
使用時には、まず術後の創面の出血をきちんと止血し、乾燥状態を確保することが重要である。止血・乾燥の目処が立った段階で、付属の粉剤と液剤を練板上に適量取り出し練和を開始する。適量とは明確な匙量はないが、目安として粉4に対し液1程度の割合である。約1分間、ヘラでしっかり練り込むと、泥状から指で練れる固さのパテ状に変化する。この練和ペーストをヘラですくい取り、手のひらに移して指で直径5mm前後の棒状(ロープ状)に転がし伸ばす。通常、貼付部位の長さに合わせた棒状パックを2本用意し(頬側用と舌側用。上顎口蓋側の場合も同様)、まず唇側・頬側の患部に沿って置き、外側から軽く圧接する。続いて反対側(舌側・口蓋側)にも同様に配置し、両側のパック材が歯間部で連結するようにする。歯間部ではヘベラや平坦な器具でパック材を軽く押し込むと、顎側と舌(口蓋)側のパックがかみ合い、しっかり固定される。
貼付後は、パックが創面を十分覆っていることを確認する。余剰な部分があれば、この時点で除去または整形しておく。特に歯間部からはみ出した飛び出しや、唇側・舌側で過剰に広がった部分は除去することが望ましい。余剰が多いと硬化後に緩みや脱落の原因となるだけでなく、会話や咀嚼の際に邪魔になったり、粘膜を圧迫して褥瘡性潰瘍を起こすリスクもある。適切な大きさと滑らかな形態に整えることが、トラブル防止の大きなポイントである。
パック材は装着後、徐々に硬化が進む。およそ15分経過した時点で、もう一度パックが安定して付着しているか、出血がパック下に滲んできていないかを確認する。この確認を怠ると、止血不良で内部に血が溜まりパックが浮き上がる場合や、患者が帰宅後に脱落するケースにつながるので注意したい。術者またはスタッフは、この間に患者の頬や舌を軽く動かしてみて、パックが不必要に動揺しないか、痛みを訴えないかもチェックする。問題なければ、そのまま硬化を待って術後の注意説明に移る。
院内運用上の工夫
本製品は特別な機器を要さず、手作業で調製・適用できる材料である。練和には使い捨ての練板紙やガラス板、ステンレススパチュラがあれば十分だ。混和操作自体は歯科衛生士や助手に委譲可能であり、術者が縫合や止血を行っている間にスタッフがパックを練り始めることで、タイムロスなく施術を進めることもできる。スタッフに任せる場合は、事前に十分なトレーニングを行い、適切な粘度や形状を習得してもらうことが重要である。慣れないうちは、実患者で使う前に少量を試し練りして感触を掴むとよいだろう。
液剤にはユージノールを含むため、揮発を防ぐためにも使用後はボトルをしっかり密栓し、直射日光を避けて室温保存する必要がある。長期間放置すると液の揮発や酸化で劣化する可能性があるため、保管環境と期限管理には留意したい(本剤の有効期限は未開封で約3年である)。粉剤も吸湿すると塊になる恐れがあるため、使用後はすぐ蓋を閉める習慣をつけたい。なお、万一粉や練った材料が術者の手指や患者の皮膚・衣服についた場合、放置すると付着物が固着してしまう。皮膚に付いた場合はベンジン(またはアルコール)で素早く拭き取り、その後石鹸と温水で洗い流せば落とせる。衣服に付着した際も早めに有機溶媒で処置しないとシミになることがあるので注意する。
他材料との互換性
本剤は基本的に単独で使用する材料だが、状況に応じた応用も見られる。例えば、抜歯後のドライソケット処置で抗生剤粉末(ミノサイクリン系の歯周薬など)を患部に塗布し、本剤で覆封することで疼痛緩和と感染予防に役立てるといった活用報告がある。また、粘膜移植術(MGS)の際には移植片上に錫箔(ティンホイル)を当て、その上から本剤を貼付することでパック材が直接移植創面に貼り付かないよう工夫する術者もいる。このように症例に応じて他の創傷被覆材や薬剤と併用することも可能であり、本剤の柔軟な運用が臨床上許容されている。
一方で、ユージノール含有製剤特有の注意点として、レジン系材料との相性が挙げられる。ユージノールは未重合レジンを劣化させる作用があるため、パック装着中や除去直後に近接部でコンポジットレジン修復や接着処置を行う場合は注意したい。実際にはパック除去後に十分に清掃すれば大きな問題には至らないが、例えば短期間で仮歯の装着・調整を繰り返すようなケースでは、ユージノールの影響で一時的に接着が弱まる可能性があることを念頭に置いておく。
医院経営にもたらす影響
歯科材料を導入する際には、その費用対効果も無視できない。『サージカルパック口腔用』の場合、材料コストはごくわずかである。1セット(60g/15mL)あたりの価格は市販ベースでおよそ5千円前後だが、1症例に使用する量は数グラム程度にとどまる。実際、本剤は薬価基準に収載されており、1グラムあたり66.6円という設定になっている。仮に1症例で粉液合わせて5g使用したとしても、薬価換算で約333円である。しかも保険診療の場合、この分の薬剤料は診療報酬として請求可能なため、医院側の実質的な負担にはならない。自費診療で用いる場合でも数百円程度の材料費にすぎず、高額な機器投資とは異なり初期投資のハードルは極めて低い。
むしろ注目すべきは、本剤の使用が間接的にもたらす経営メリットである。術後の経過が安定し、患者の苦痛やトラブルが減れば、不要な緊急対応や追加処置に割く時間が節約できる。忙しい保険中心のクリニックであれば、術後出血の電話対応や再来院対応に追われる事態はスケジュールの乱れを招きかねない。パックをする一手間がそうしたリスクを低減し、結果的に全体の診療効率維持につながると考えれば、コスト以上の価値があると言えるだろう。
患者満足度への影響も見逃せないポイントだ。術後にしっかり創部を保護してもらえることは、患者にとって「丁寧な処置を受けた」という安心感につながる。例えば自費の歯周形成術などでは、術後に痛みが少なく快適に過ごせれば、治療そのものの評価が高まり紹介やリピートに結びつくかもしれない。患者からの信頼獲得は長期的に見て医院の繁栄に資するものであり、本剤のような小さな配慮が積み重なってブランド力向上につながる可能性がある。
ROI(投資対効果)の観点で考えても、本剤の導入は「ほぼノーリスクで潜在的な利益を得られる施策」である。材料費は微々たるもの、保管も容易、さらに使わなければそのまま保管しておけばよい(腐敗するものではなく比較的長期保存可能)。にもかかわらず、いざというときに使用すれば術後合併症の軽減や患者満足度向上といったリターンが見込める。仮に本剤の使用でひとりの患者の術後不満を解消でき、その患者が離反せず将来の来院につながれば、それだけで投資回収は十分と言えるだろう。
上手に使いこなすためのポイント
『サージカルパック口腔用』を真価発揮させるには、いくつかのコツと注意点を押さえておく必要がある。まず初期導入時の注意として、材料の取扱いに慣れるまでは練和量を少なめに調整し、適切な粘度を体験してみることだ。練和直後はペースト状だが、手でこねているうちに徐々に硬化が進むため、練りすぎないように注意する。1分ほど練ったらすぐに成形・貼付の段階に移るのが良い。悠長にしていると指で転がす段階で固くなりすぎ、歯面に馴染まなくなる恐れがある。
術式上のコツとしては、前述の通り止血と乾燥がキーポイントである。しっかり止血したつもりでも、パック貼付後ににじむ程度の出血が起こることはある。そのため、ある程度ガーゼ圧迫で止血ができたら、完全に出血が止まるのを待つのではなく、パック練和を開始しつつ、貼付の直前までガーゼで圧迫止血を続けると効率的だ。そしてガーゼを外した直後にすかさずパックを当てて圧接する。このタイミング管理によって、せっかく付けたパックが血液で浮いて外れる事態を防げる。
貼付時は指である程度形作ってから口腔内に運ぶわけだが、指サックや手袋にパック材がべたついて扱いづらい場合がある。その際は指先にワセリンを少量塗布したり、手袋ごとアルコールで湿らせたりすると、材が付きにくく作業しやすくなる。特に細いロープ状にした材を歯間に押し込む際に指に引っ付いてしまうと厄介なので、工具と指先のどちらかは滑沢にしておくと良いだろう。
患者への術後指導も、使いこなしの一環と言える。パックを貼ったまま患者が帰宅した後、適切に過ごしてもらわなければ効果が半減する。まず、装着したパックは通常次の来院日(5〜7日後)まで外さない旨を伝える。自分で触ったり外そうとしないよう釘を刺すことが大事だ。食事は極度に熱いもの・硬いものは当日避け、できれば反対側で咀嚼してもらう。歯磨きも当日は創部を避け、翌日以降もパックを外そうと無理にブラッシングしないように説明する。その代わりとして、クロルヘキシジンなどの含嗽剤でうがいをするよう指示すれば、プラークコントロールの助けになる。パック装着中は創部が覆われているとはいえ、周囲はプラークが蓄積しやすいため、できる範囲で口腔清掃を促すことも重要である。
トラブルへの対処についても触れておこう。万一パックが術後早期に脱落してしまった場合、慌てずに創部の状態を確認する。術後2〜3日以上経過していれば、そのまま無包装でも問題ないことが多い。患者に電話で状況を聞き、痛みや出血が顕著でなければ様子を見る判断もあり得る。逆に装着翌日など極めて早期に外れた場合や、患者が強い不安を訴える場合は、再度新しいパックを貼り直すことを検討する。ただし再装着には再び十分な止血と乾燥が必要であり、場合によっては局所麻酔下で創面を洗浄し直すこともある。無理にその場しのぎで付けても二次感染や延長出血のリスクがあるため、状況に応じて慎重に判断したい。
除去の際は、硬化後も完全硬化型セメントほど硬くはないため、周囲の歯や歯肉を傷つけないようヘベラやスケーラーで縁からそっと剥離していけば、比較的一塊で取れてくるはずだ。無理に引っ張らず、複数箇所から徐々に浮かすようにすると患者の不快感も少ない。歯間部にわずかに残った破片は探針などで除去し、念のため洗浄消毒して処置完了となる。患者には「取った後しばらくは歯肉が柔らかく敏感になっています」と説明し、優しいブラッシング指導を行うと親切である。
適応症例と適さないケース
『サージカルパック口腔用』が真に威力を発揮するのは、広範囲に及ぶ歯周外科処置後のケースである。典型的なのは歯肉切除術後の広い創面保護だ。例えばガミースマイル改善目的の歯肉整形(ガムラインの整形)では、上顎前歯部の歯肉を切除した後に本剤でしっかり創面を覆えば、患者の術後疼痛は格段に軽減される。また、フラップ手術(歯周ポケット掻爬術・歯肉剥離掻爬術)後に縫合した部位へ貼付しておけば、頬舌側からの刺激や食物残渣の侵入を防ぎ、縫合部位の安定が期待できる。他にも、遊離歯肉移植術のドナーサイト(口蓋側の採取創面)の保護には古くから歯科用パック材が用いられており、本剤もその目的に適している。このように、広い創傷面が露出している場合や二次治癒を促進したい場合に、本剤の使用価値は高い。
一方で、適さない状況も把握しておく必要がある。まず、創面がごく小さい場合だ。たとえば歯間乳頭部のみの切除や数ミリ程度の小さな切開創では、パックを貼る操作自体が難しく、仮に貼れても大きさが勝って異物感ばかり増してしまう。こうしたケースでは、きちんと縫合していればパックなしでも治癒に大差ないことも多く、無理に使用する必要はない。また、固定源がないケースも問題となる。例えば無歯顎の顎堤骨整形を行った場合、歯が無いためパック材を安定させるアンカーが得られない。歯間部に引っ掛けられないとパックは剥がれやすく、頬粘膜と粘膜面に挟み込む方法もあるが、広範囲では保持が難しい。このような場合は、パックの代わりに義歯や樹脂製の外科用ステントで傷口を覆う方法が現実的である。
素材特性による制限もある。ユージノールへのアレルギーが疑われる患者には本剤の使用は避けるべきだ。実際のアレルギー頻度は極めて低いものの、過去にクローブの香料で皮膚炎を起こした人などは注意が必要である。貼付後に異常な痛みや粘膜のただれ(発赤・潰瘍)が生じた場合は、すみやかにパックを除去し適切な処置に切り替える。副作用としてごくまれにパック接触部位の潰瘍形成が報告されており、患者ごとの反応を観察する姿勢も求められる。
なお、昨今の歯周治療ではパック非使用の流儀も増えている。たとえばエムドゲインなどを用いた歯周組織再生療法では、術後にパックをしないことも多い。これは再生を期待する繊細な創面に圧力をかけたくないという考えや、術後の清掃性を重視する見解によるものである。逆に、従来型の歯肉切除(瘢痕治癒を期待する処置)では、パックによる圧迫が血餅の安定や肉芽増殖の抑制に寄与するという古典的知見もあり、術式の目的によって賛否が分かれるのだ。要するに、本剤の使用適否はケースバイケースであり、創面の大きさ、縫合の有無、患者の状態、術者の治療方針などを総合して判断すべきである。
歯科医師タイプ別
保険診療が中心で効率を重視する歯科医師の場合
保険診療主体で毎日多くの患者をさばいている先生にとって、治療効率は最優先事項だろう。追加の処置に時間を割くことには慎重になるかもしれない。パック装着も、一見「手間が増えるだけでは」と捉えがちだ。しかし、忙しい医院ほど術後トラブルによる想定外の時間ロスは致命的になり得る。本剤を使用することで、術後の出血や疼痛クレームによる急患対応が減れば、結果的に診療スケジュールが乱れず効率維持につながる。先述の通り、本剤の材料費は保険点数で算定でき、医院側のコスト負担はほぼゼロに近い。つまり「少しの手間でリスク低減」という観点で、効率重視派の歯科医師にも導入のメリットは十分ある。
もちろん、闇雲に全ての処置で使う必要はない。あくまで必要な症例に的確に使うことが重要だ。例えば、通常の単純抜歯や小手術ではパックなしでも何ら問題なく治癒することが多い。そのような場面では使わず、逆に「これは出血や痛みが強そうだ」「術後のフォローが大事だ」と判断したケースに絞って投入する。メリハリの効いた運用をすることで、忙しい診療の中でも効率と丁寧さを両立できるだろう。
自費診療で高付加価値を目指す歯科医師の場合
インプラントや歯周形成外科、審美治療など自費中心のクリニックでは、治療結果のクオリティと同様に患者体験価値が重視される。術後経過の快適さやケアの手厚さは、患者満足度を左右する重要な要素だ。高額な治療であればあるほど、些細な術後の不快感も患者の評価に響く可能性がある。そこで、本剤のような歯肉保護材を適切に活用することは、サービス品質を高める有効な手段となる。
例えば、歯周形成術を受けた患者に対し「手術後、患部を保護する特殊なパックを装着しています。傷口を守り、痛みを和らげるための処置です。」と説明すれば、患者は自分が丁寧にケアされていると感じるだろう。実際に痛みが少なければなおさら満足度は高まる。こうした「一手間かけたケア」は、他院との差別化にもつながり、自費治療の付加価値として十分にアピールできるポイントだ。
費用面を考えても、自費診療の収益から見ればパックの材料費はごく微々たるものであり、惜しまず使う方が得策である。ただし審美志向の患者の中には、口の中に白いパック材が見えることに抵抗を示す人も稀にいる。そのような場合は、透明で目立たない光重合型の歯肉保護材(レジン系ドレッシング材)を選択することもできるだろう。しかし、それらは鎮痛成分を持たないため、本剤のようなクローブ由来成分による「じんわり効く安心感」は得られない。審美と機能のバランスを考慮しつつ、患者のタイプに応じて使い分けるのも一つの戦略である。
総じて、高付加価値診療を目指す歯科医師にとって本剤の導入は、患者へのホスピタリティを形にする手段と言える。細部まで行き届いた術後ケアは必ず患者の心に残り、医院のファンづくりにつながるだろう。
口腔外科・インプラント中心の歯科医師の場合
親知らずの抜歯やインプラント埋入など口腔外科処置がメインのクリニックでは、歯周手術ほど本剤の出番は多くないかもしれない。実際、インプラント手術では基本的に切開創を縫合して一次治癒を図るため、術後にパックを貼る習慣はあまりない。しかし、外科中心の現場でも本剤を備えておく意義はある。
一つは、予期せぬ術後トラブルへの対応だ。例えば抜歯後のドライソケット(乾燥症候群)は、患者に強い痛みを与え長引くことがあるが、対症療法としてユージノールを含むペーストで患部を覆う処置は古くから有効とされている。本剤と抗生剤の組み合わせで疼痛が劇的に和らぐケースも報告されており、口腔外科領域の救急処置ツールとして活用できる可能性がある。また、インプラント治療に付随する軟組織の処置(歯肉整形や増殖処置)を行う際にも、パック材による保護が役立つ場面が考えられる。
外科処置中心の歯科医師にとって、本剤は「頻繁には使わないが無いと困るかもしれない道具」の一つである。コスト負担や保管スペースをほとんど気にせず備蓄できるので、いざという時のためにストックしておいて損はないだろう。特に開業医で口腔外科も幅広くこなしているような場合、患者を他院に紹介せず自院で処置完結するための引き出しを増やすという意味でも、本剤の存在は安心材料となる。
よくある質問(FAQ)
Q. パックを使用すると治癒は速くなるのか?
A. 直接的に傷の治りが「速くなる」ことを保証するエビデンスは必ずしも明確ではない。ただし、本剤によって創面が安定し外力や汚染から保護されることで、正常な治癒過程が妨げられずに済む効果は期待できる。要は、何もしない場合に比べて有利な環境を整える役割であり、それが結果的に順調な治癒につながると考えられる。特に術後早期の血餅安定や疼痛軽減による炎症ストレス低減は、間接的に治癒促進に寄与すると言えるだろう。
Q. どのくらいの期間、パックを装着しておくべきか?
A. 一般的には術後5〜7日程度を目安に装着する。1週間前後で創面の初期治癒が進み、パックなしでも外力に耐えられる状態になるためである。術後1週間のチェック時にパックと抜糸を同時に行うことが多い。それ以上長く留置するとパック周囲にプラークがたまり歯肉炎を起こす可能性があるため、遅くとも10日ほどで除去するのが望ましい。万一、予定前に外れてしまった場合の対応については本文中で述べた通りで、状況次第では再装着せず経過観察とすることもある。
Q. 患者がパックの味や違和感を嫌がることはないか?
A. クローブ(丁子)由来の薬剤特有の香りと味があるため、敏感な患者は「スースーする」「薬っぽい味がする」と感じることがある。また、口の中に固形物が貼り付く違和感は多少なりとも生じる。しかし、多くの患者は術後の痛みや出血が抑えられる恩恵のほうを強く感じるため、パック自体への苦情はあまり多くない印象である。装着前に「少し薬の味がしますがすぐ慣れます」「しっかり傷を守るために付けます」と説明し理解を得ておけば、大抵の患者は受け入れてくれる。どうしても香りが苦手という患者には、無香料の非ユージノール系パック材を検討してもよいだろう。
Q. ユージノールアレルギーが心配だが大丈夫か?
A. ユージノールによるアレルギー反応(接触性皮膚炎や粘膜炎)は頻度としては非常に低い。しかしゼロではないため、過去に香辛料や樹脂にアレルギーがあった患者では慎重になるに越したことはない。初めて本剤を適用した後は、患者には強い痛みやヒリヒリした感じがないか様子をよく聞くようにすると安心だ。万一、貼付部位が腫れたりただれが生じた場合は、すぐにパックを除去し適切な処置(洗浄や抗炎症処置等)に切り替える。幸い重篤な症状に至るケースは稀で、本剤自体にも抗炎症作用があるため多くの患者には問題なく使用できる。
Q. 保険診療でパックの費用を算定できるのか?
A. できる。本剤は歯科用医薬品として薬価が設定されており、使用したグラム数に応じて診療報酬明細書に算定可能である。算定方法の詳細は厚労省の点数表に準拠するが、処置時に使用した薬剤として計上する形になる。具体的には1gあたり66.6円で計算されるため、例えば5g使用すれば約333円が加算される計算だ。ただし保険請求上は実際の使用量に基づくため、カルテには使用薬剤名と使用量を記載しておく必要がある。いずれにせよ材料費が保険でカバーされる点は、保険診療下で導入しやすい利点である。なお、自費診療の場合は材料費込みで治療費を設定することになるが、先述の通りコスト自体僅少なので大きな負担にはならないだろう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 歯周保護材
- ジーシー昭和薬品の歯肉保護材、サージカルパック口腔用について使い方と臨床のコツを徹底レビュー