- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 歯周保護材
- 歯周保護材「バリケード」とは?光重合型パック材の使い方と特徴
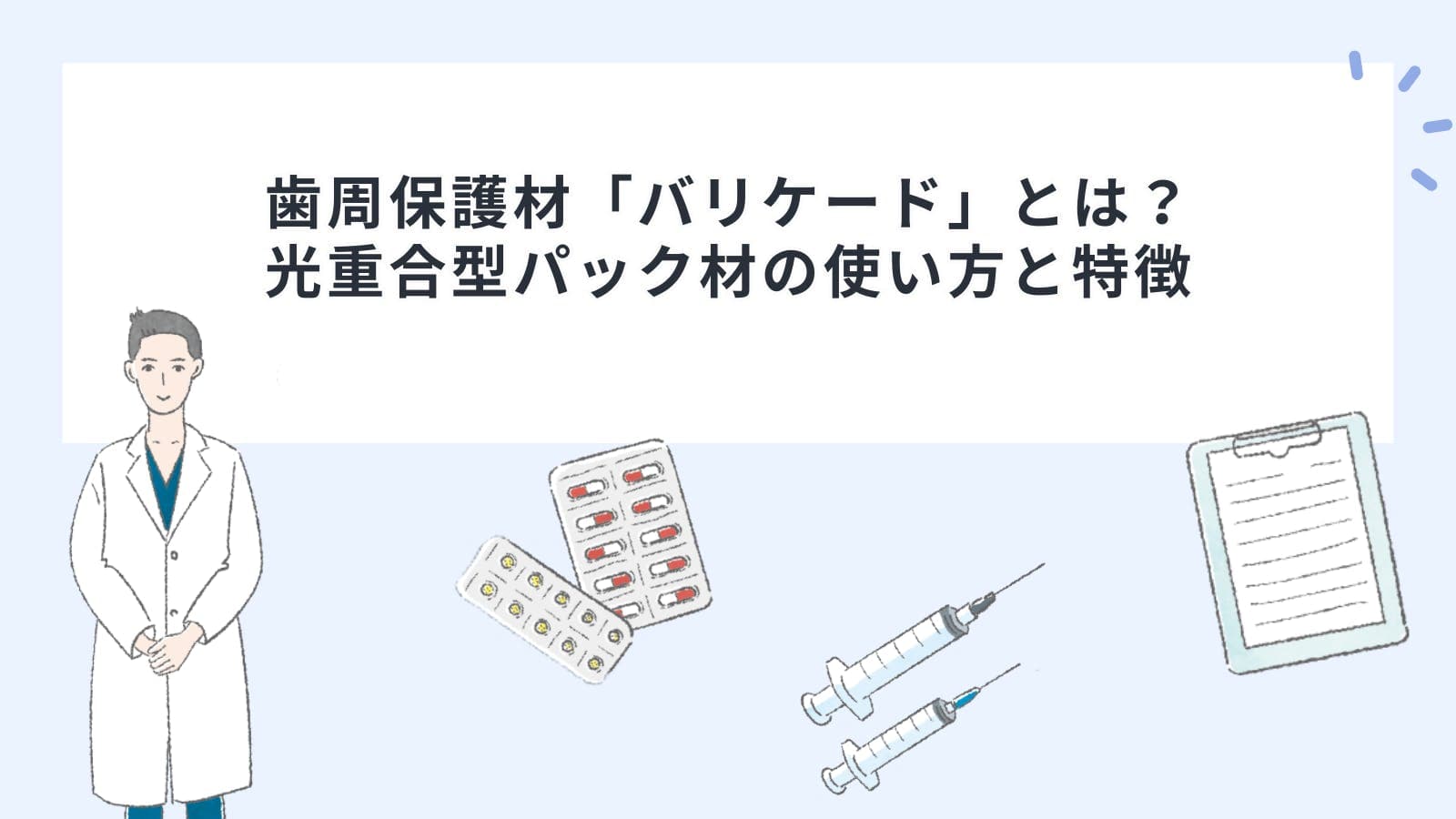
歯周保護材「バリケード」とは?光重合型パック材の使い方と特徴
例えば、前歯部での歯周外科後、創部を保護するためのパック材をどうするか悩んだ経験はないだろうか。従来の歯周パック(コーパック)は創面保護には有用だが、使用には煩わしさが伴う。ペーストを練和する手間、口腔内で目立つ見た目、独特の臭気や味が患者に敬遠されることもある。術後に慎重に形態を整えたつもりでも、一部が剥がれてしまったり、患者が違和感を訴えたりした苦い経験を持つ臨床家も多いであろう。とりわけ審美領域の手術では、パック材が審美性を損なうことを懸念して、あえて使用を見送ったケースもあるかもしれない。
こうしたジレンマに応えるべく登場したのが、光重合型の歯周保護材「バリケード(Barricaid)」である。可視光で硬化する樹脂製ドレッシング材で、術後創面を目立たず確実に覆う新しい選択肢として注目されている。本稿ではバリケードの特徴と使い方を掘り下げ、臨床現場および医院経営の両面からその導入価値を検証する。読者の先生方が自身の診療スタイルに照らし、この製品の導入が術後管理や患者満足度向上、さらには投資対効果(ROI)にどう寄与し得るかを判断する一助となれば幸いである。
製品の概要
バリケード(Barricaid)は、歯周外科処置後の創面保護に用いる光重合型の歯科用ドレッシング材である。米国デンツプライシロナ社(旧デンツプライ・コーク)によって製造され、歯科用シリンジに充填された単一コンポーネントの樹脂ペーストとして提供されている。可視光照射によって硬化し、歯肉や歯槽骨の術後創面を薄い弾性のカバーで覆うことができる。淡いピンク色に着色された半透明の材質で、装着しても口腔内で目立ちにくく審美性を損ないにくい点が特徴である。シリンジ1本あたり内容量4gで、通常4本入りのパッケージで流通している。
本製品の想定適応は、歯周外科(フラップ手術や歯肉切除術、遊離歯肉移植後など)における創部の保護や、抜歯後の創部保護などである。従来の歯肉パック材と同様、創面を外力や感染から遮断し、初期治癒を安定化させる目的で用いるが、バリケード自体には薬効成分は含まれず、あくまで物理的保護膜として機能する。薬機法上は歯科用の歯周保護材(歯肉包帯剤)に分類される医療機器であり、適法に流通している。なお、本製品はメタクリレート系樹脂を主成分とするため、重度の樹脂アレルギー既往を持つ患者には使用できない。
主要スペックと臨床での意味
バリケードはレジン(樹脂)ベースの歯周包帯剤であり、その化学組成と物性が臨床上の使いやすさに直結している。主成分はウレタンジメタクリレート系の光重合レジンで、石英粉末やシリカなどの微細フィラーが含有されている。これにより硬化後も適度な強度と弾性を持ち、術後の咬合圧や口腔内の力に対して脆性の破折を起こしにくい。硬化後の質感は硬すぎないゴム様のフィルムで、歯肉に密着して創面を覆うが、指で押すとわずかに弾力を感じる程度の柔軟性も有する。従来のペースト系パック材に比べ、硬化後にひび割れたり崩れたりしにくいのは、このレジン特有の物性によるものである。
光重合条件も本製品の重要なスペックである。バリケードはカンフォキノン(CQ)系光重合開始剤を含み、波長約470nmの可視光に反応する。一般的な歯科用LED照射器(光強度500mW/cm^2以上)を用い、パックした部位の頬側・舌側それぞれから約10秒ずつ光を当てれば、完全に硬化する。例えば4〜5歯分の範囲をカバーした場合、片側合計40秒程度の照射で硬化が完了する計算であり、術後処置の時短につながる。硬化時間を術者が任意にコントロールできるため、練和材のように操作時間に追われることがなく、十分に形態を整えてから確実にセットできるのも臨床上大きな利点である。
色調および外観もスペック上の特徴である。硬化前後とも薄いピンク色の半透明で、歯肉に馴染むため審美領域でも目立ちにくい。患者から見ても「創傷を覆う包帯」がほとんど認識されないため、心理的抵抗感が少ない。また半透明であることで、装着後も創部の状態(出血の有無や腫脹)をある程度観察できるメリットもある。従来のコーパックでは厚生な不透明物で創面を完全に隠してしまうが、バリケードは保護しつつも術後経過のモニタリングを妨げにくい点で有用である。この特性は臨床上の安心感にもつながる。
バリケードの使い方と運用上のポイント
バリケードの使用方法は、基本的に従来の歯肉パック材と同様に「創部をパテ状の材料で覆い、隣在歯に機械的に固定する」という手順である。ただし、本製品はあらかじめシリンジに入った1剤式のペーストであり、開封後すぐに使用可能である点が異なる。練和の必要がないため、操作時間に追われることなく落ち着いて処置できるが、一方で光に反応して硬化を始める性質上、取り扱い時には周囲光による露光に注意が必要である。長時間放置すると未照射でも徐々に粘性が増してくる可能性があるため、2分以上使用を中断する場合はペーストを遮光下に置くといった配慮が望ましい。
ペーストの適用は直接法と間接法の2通りが推奨されている。直接法では、シリンジ先端を用いてそのまま術野の歯頸部〜歯肉辺縁部に沿ってペーストを押し出し塗布する。アタッチメントチップを外し、まず少量をシリンジ外で押し出して目詰まりがないことを確認してから口腔内に適用すると良い。吐出圧は強く押しすぎず、ゆっくり一定圧で絞り出すのがコツである。直接法は操作がシンプルだが、患者ごとにシリンジを使い切り廃棄する必要がある(交叉感染防止のため)。高価な材料であることを考慮すると、可能な限り1本のシリンジを複数患者に使用したいところであり、そのために採られるのが間接法である。
間接法では、まず清潔な紙皿やパレット上にあらかじめワセリンなど潤滑剤を薄く塗布しておく。その上にシリンジから必要量(目安として0.5〜1g程度)を押し出し、すぐにシリンジ先端を元のキャップで密閉する。空気や光への露出を最小限にするため、この作業は手早く行う。取り出したペーストは潤滑した指先またはプラスチック製のへらなどでリボン状に丸め、創部を覆うように貼り付けていく。ペーストはグローブに非常に付着しやすいため、操作する指先はあらかじめ患者の唾液や水で湿らせるか、無害なジェルで潤滑しておく必要がある。これはコーパック操作時と同様の要領で、指にまとわりつかずスムーズに成形するための重要なポイントである。
実際の適用においては、まず頬側(または舌側)の歯肉面にペーストを置き、指や器具で歯頸部に押し付けながら辺縁を整える。隣在歯の近心・遠心の歯間部に少し押し込むように延ばし、細いブリッジを架けるように連続させていくことで、硬化後に機械的ロックがかかり脱離しにくくなる。ただし過度に深く歯間部へ流し込む必要はなく、表面的な把持で充分である。片側が所定の範囲を覆えたら、その面をライトで硬化させる。一連の操作は、片側(頬側または舌側)ずつ完全に硬化させてから反対側に移るのが望ましい。前述の通り4歯分程度なら40秒ほど連続照射すれば完全硬化する。その後、反対側(舌側または頬側)にも同様にペーストを貼着し、硬化させて創面をサンドイッチ状に被覆する。硬化後は必要に応じて咬合干渉をチェックし、高すぎる部分があればロータリー器具でトリミングすることもできる。
運用上留意すべき点として、硬化後に素材が強固に固着しすぎないよう、除去のしやすさも考慮して適用することが挙げられる。バリケード自体は歯面や組織に接着するわけではなく、あくまで機械的に嵌合しているにすぎない。しかし歯間部で太くつなげすぎたり、深いアンダーカットに食い込むように固めてしまうと、除去時に分割が必要になる場合がある。術後1週間程度で除去する際には、頬側と舌側それぞれのパックを歯間部ではさみ等で切離し、必要に応じて縫合糸も切ってから、そっと摘んで剥離すれば痛みなく除去できる。あらかじめ適度な厚み・大きさにとどめておけば、大抵は一塊となって容易に除去可能である。なお、ユージノール系材料(酸化亜鉛ユージノールなど)や過酸化水素製剤は本レジンの重合を妨害し軟化させる恐れがあるため、術後処置で併用しないほうがよい。これは従来の非ユージノール系コーパックと同様である。
シリンジに残ったペーストは、直射日光を避け室温(10〜24℃)で保管すれば長期間品質を維持できる。使用後は必ず付属の遮光キャップで先端を密閉し、エタノール等で外表面を清拭消毒した上で保管する。未使用分の使用期限管理は通常のレジン材料と同様で、表示の有効期限内に使い切る必要がある。
医院経営に与える影響
新たな材料導入に際しては、そのコストが医院経営に及ぼす影響も考慮しなければならない。バリケードの場合、最も直接的なコストは材料費である。国内での販売価格は4g入りシリンジ4本セットでおよそ3万円台半ばと高価であり、1本あたり約7,000〜8,000円となる計算である。1症例(例えば4〜5歯分のフラップ手術)に使用するペースト量は概算で0.5〜1g程度であることから、材料費は1回の手術あたり1,500〜2,000円前後となる。この数字は、従来のコーパック材のコスト(1症例あたり数十〜数百円程度)と比較して数倍以上に及ぶ。単純計算では、バリケードを使うことで症例毎に数百円〜千数百円の追加コスト負担が発生することになる。
しかし、バリケードの経済的価値は単に材料費の比較だけでは測れない。まず、オペ後の処置時間短縮による効率化効果がある。光重合により即時硬化するため、練和や待ち時間が不要で、術後のチェアタイムを削減できる。例えば、従来法でパック調整・硬化に費やしていた時間が約5分短縮できたと仮定しよう。月に10件の歯周外科症例がある医院であれば、1ヶ月で50分、年間では約10時間の診療時間を新たに創出できる計算になる。この時間を他の診療や追加の患者対応に充てられれば、収益機会の拡大につながる。人件費的にも、歯科医師・スタッフの5分間のコストを考えれば、その分の節約が材料費の上乗せ分を相殺し得る。
さらに、バリケードの使用によって患者満足度が向上すれば、長期的な経営メリットも期待できる。術後の痛みや見た目に対する患者の不安を軽減できれば、その医院への信頼感やリピート意向が高まる可能性がある。実際、光重合型パック材は味や臭いがほとんど無く快適であるため、多くの患者が従来のパックより好ましいと感じるという報告もある。患者が快適に術後を過ごせればクレームや緊急来院のリスクも減り、医院側の余計な負担軽減にもつながる。特に自費診療で高度な歯周形成術やインプラント周囲の軟組織移植などを提供する場合、術後のフォローがスムーズで患者満足が高ければ、高額治療の価値提供として大きな意味を持つ。口コミや紹介で新たな患者獲得につながる可能性も考えれば、バリケードの費用はマーケティング投資とも捉えられる。
要は、バリケード導入によるROI(投資対効果)は、目先の材料費増加だけで判断すべきではないということである。短期的にはコストアップだが、それを上回る効率化と患者ロイヤリティ向上による長期的リターンが見込める。医院の診療内容や重視する価値にもよるが、戦略的に活用すれば“支出を伴うサービス向上”が最終的に“収益向上”に転化し得る好循環を生み出すだろう。
上手に使いこなすためのポイント
バリケードの利点を最大限に引き出すには、いくつかのコツや留意点を押さえておく必要がある。まず導入初期には、実際に操作して樹脂の扱い感覚に慣れることが大切である。コーパックに比べて粘着性が高く、初めは指や器具に付きやすいため、あらかじめ少量を模型や不要歯牙で試し、どの程度の力加減で広がるか、どれくらいの厚みが適当かを感触として掴んでおくと良い。またスタッフにも基本的な取り扱い手順を共有し、術者が縫合している間にシリンジ準備やペーストのディスペンス(間接法の場合)ができるよう役割分担しておけば、手術の流れがスムーズになる。
術式上のポイントとしては、術野の環境と材料の操作性が挙げられる。パックを適用する前に、創部からの出血は可能な限り止血し、歯面・歯肉をガーゼ等で乾燥させておくことが重要である。唾液や血液で濡れた状態だとペーストが滑って十分に付着・適応しない恐れがある。素材自体に接着力はないため、機械的に保持させるには清潔乾燥な面への圧接が効果的である。次に、ペーストの操作中は指先や器具を必ず潤滑しておくこと。ワセリンを塗ったグローブや湿らせたガーゼを用いて表面を整えると、ベタつかず滑らかに成形できる。特に辺縁部は薄く広げすぎると強度が落ちるので、適度な厚み(約2mm)を保ちつつ、周囲組織との段差が小さくなるよう形態修正すると良い。最終仕上げに湿らせたガーゼを軽く当てて表面をなでると、余分なペーストが除去され均一な膜厚になるため、その後の硬化が確実かつ綺麗に行える。
光重合のタイミングと順序も重要なテクニックである。前述の通り、一側のパックを完全に硬化させてから反対側に移るのが基本である。硬化途中で動かすと変形の原因になるため、片側ずつ確実に固定する。また硬化前に咬合干渉のチェックを忘れずに行うこと。材料が軟らかいうちは咬んでみて違和感がないか患者に確認し、高さがありそうな部分はこの段階で取り除いておく。硬化後は調整可能とはいえ、術後の患者の顎運動で余分な部分が欠けると予期せぬ尖端が残ったりする可能性もあるため、あらかじめ噛み合わせに干渉しない滑らかな形に整えておくほうが安全である。
院内体制の面では、バリケードを使用する手術の際に必要な物品(シリンジ、パレット、ワセリン、照射器など)をあらかじめトレイにセットし、術者とアシスタントがいつでも使えるよう準備しておくと良い。特に照射器は充分に充電・性能確認されたものを用い、所定の照射時間を守ることで確実な硬化を保証する。硬化不良は術後のトラブルにつながるため、光量が不安な古い照射器しかない場合は、事前にランプの交換や点検を行っておくべきである。また複数本のシリンジを併用する際は、どの患者にどのロットを使用したかを管理し、万一リコール等があった場合に追跡できるよう、他の歯科材料同様ロット番号の記録も推奨される。
患者への声かけ・説明の工夫も、製品を有効活用する上で見逃せないポイントである。術後の説明では、創部に透明な保護剤を塗布してあり「硬いかさぶた」のように傷口を守る役割を果たすこと、そして1週間後に歯科医院で除去する予定であることを伝えておく。そうすることで患者の不安が和らぎ、安心感を与えられる。実際に装着物が見えづらいため説明なしでは気付かない患者もいるが、術後に触ったり舌でいじったりしないよう注意を促しておくことは重要である。味や臭いがしないためその点の煩わしい説明は不要だが、違和感が強い場合でも無理に剥がそうとせず早めに受診・相談するよう指示しておくことで、万が一外れかけても自己判断で取ってしまうリスクを減らせる。患者とのコミュニケーションを適切に行い、バリケードの存在意義と取り扱いを理解してもらうことで、術後1週間の経過を双方にとって快適かつ安全に過ごすことができる。
適応する症例と適さないケース
バリケードは、術後保護材として幅広い歯周処置に応用できるが、特にその真価を発揮するのは審美性と利便性が求められるケースである。たとえば前歯部のフラップ手術や歯肉整形術の後に、従来のコーパックでは見た目が気になるような場合、バリケードであれば患者に悟られないほど自然にカバーできる。また、手術侵襲が比較的小さく、縫合だけでは不安だが術後パックで安定化させたい、といったケースにも向いている。具体的には、歯周ポケット剥離掻爬術後の歯肉辺縁の保護、APF(付着歯肉形成術)後の創面保護、インプラント周囲の軟組織増大手術後の歯肉保護などで有用である。抜歯後の保護にも応用可能で、隣接歯が残る部位であれば抜歯窩を覆って血餅保持に使うこともできる。総じて「術後に軟組織の安静を図りたいが、見た目や快適さにも配慮したい」状況で、本製品のメリットが最大限に生かされる。
一方で、バリケードが適さない・有効でない場面も存在する。まず患者要因として、レジンアレルギーが疑われる症例には絶対に使用できない(添付文書上の禁忌事項である)。また、術後にパックを長期間維持できないような口腔清掃状態不良の患者では、仮に装着しても早期脱離や下にプラークが停滞するリスクが高く、かえって炎症を助長しかねない。そうした場合は、術後の清潔維持指導を徹底するか、そもそもパック材の使用自体を再考すべきである。創部の状況に関しては、広範囲で隣接する歯のない無歯顎部位では物理的に固定が困難なため、バリケードの適用は難しい。例えば、全顎的に歯周手術を行った後の広い無歯顎領域や、義歯装着部位などでは、義歯床や特注の外科用ステントで圧迫保護する方が現実的であり、樹脂パック材の出番は基本的にない。また、遊離歯肉移植(FGG)のドナー部位(口蓋側粘膜)など、歯の支えがなく出血面だけが広がる創傷では、本製品は保持しようがないため使用対象外となる。
さらに、術式の要求によってはバリケードが不得手なケースもある。移植片の圧迫固定など、創部に強い圧迫力・支持力を与える必要がある場合、バリケードの薄い弾性シートでは十分な固定力を期待できない。例えば歯肉移植術の受容部位で移植片を押さえつけておきたい場合は、糸での縫着や従来型パック材の厚みを利用した圧迫の方が効果的である。同様に、術後に大量の排膿や滲出液をドレインさせる必要がある症例(重度の感染病変を伴う場合など)では、むやみに創面を密閉せず、ガーゼドレナージなどオープンな処置が優先される。その際もバリケードの出番はない。総じて、バリケードは「通常は歯周パックを使用することが望ましいが、その欠点を補いたいケース」で使う価値が高い。一方、「もともとパックが不要なケース」や「パックでは代用できない要件があるケース」に無理に当てはめるものではない。症例ごとの状況を見極め、バリケードの得意とする場面で選択することが肝要である。
医院タイプ別
保険診療中心で効率重視の歯科医院
保険診療主体で多数の患者をさばくスタイルの医院にとって、新規材料導入は費用対効果がシビアに問われる。バリケードの材料費は決して安くはないため、日常的に歯周外科症例が少ない場合、フルパックを購入しても使い切れずコスト高になる懸念がある。そのため、このタイプの医院ではバリケードを全症例に常用するより、選択的に使用する戦略が現実的である。例えば、前歯部の難しいケースや患者から審美面の要望が強い症例など、ここぞという場面だけにバリケードを投入し、それ以外は従来のコーパックや縫合だけで対応する、といった使い分けである。院長や担当医がバリケードの利点(迅速さ・快適さ)を十分理解し、コストをかけるに値するケースかどうかを見極める判断力が求められる。効率重視の医院では、1件あたり数分の短縮も積み重なれば診療枠増加につながるため、もし月間の歯周手術件数がそこそこあるなら、トータルではプラスになる可能性も高い。一方、症例数自体が少ないのに義務的に導入すると、在庫コストばかりかさんで宝の持ち腐れになる恐れがある。従って、このタイプの医院では、自院の症例ボリュームと患者ニーズを勘案し、「ここぞ」という場面に絞って部分導入するのが賢明であろう。
高付加価値の自費診療を志向する歯科医院
自費率が高く、患者に最高のクオリティと快適さを提供することを重視している医院では、バリケード導入のメリットは大きい。このタイプの医院では、治療費に材料コストを十分反映できるため、1症例あたり数千円の追加費用は大きな負担とならない。それよりも、患者満足度やクリニックの評価向上というリターンの方が価値を持つ。実際、審美歯科や高度歯周治療を掲げる医院では、術後のフォローまで含めたトータルなケア品質が問われる。バリケードを使用すれば、「当院では術後に目立たない特殊ドレッシング材で傷口を保護します」とアピールでき、競合差別化のポイントにもなり得る。患者にとっても「細部まで配慮が行き届いた先進的な治療」という印象を抱きやすく、信頼醸成につながる。こうした医院では、むしろ従来型のコーパックを使って術後に不快感や審美的ストレスを患者に与えること自体がブランド価値を損ねかねない。したがって、症例の大小を問わず標準術後プロトコルとしてバリケードを採用するくらいの姿勢があってもよいだろう。コスト面も、一連の自費治療費に上乗せするかたちで容易に吸収できるため、投資回収の心配も少ない。総合的に見て、高付加価値路線の医院にとってバリケードは「患者満足への投資」として積極導入すべきアイテムと言える。
口腔外科・インプラント中心の歯科医院
親知らずの抜歯やインプラント手術など外科処置をメインに行う医院では、歯周外科専門医院とはまた事情が異なる。多くの口腔外科系処置では、術後は基本的に縫合閉鎖が可能であり、必ずしも歯肉パック材を要しない場合が多い。インプラント埋入や骨造成後はフラップをしっかり縫い合わせて終えるため、バリケードで覆う場面はほとんどないだろう。従って、このタイプの医院ではバリケードの優先度は高くない。ただし、すべての処置が縫合閉鎖で済むわけではなく、時に歯周組織へのアプローチや、インプラント周囲炎の外科的処置、あるいは骨造成後に一部縫合が難しい部位の保護など、歯周パックが欲しくなる場面も出てくる。そのようなスポット的なニーズに備え、1パックをストックしておく価値はあるかもしれない。とりわけ、インプラント周囲の軟組織再生や審美領域での抜歯即時埋入後に一時的に傷口を覆いたい場合など、バリケードが役立つシーンは限定的ながら考えられる。導入する場合も、頻繁には使わないことが予想されるため、在庫の使用期限管理に注意し、適切に保管する必要がある。まとめると、外科中心の医院ではバリケードは必須のツールではないが、「あると安心」な補助材料と言える。主力業務ではないがゆえに導入を見送るのも一策だが、もし取り入れるなら限定的な用途で上手に活用し、使い忘れによる在庫死蔵だけは避けたい。
よくある質問(FAQ)
Q. バリケードと従来の歯肉パック剤(コーパック)との違いは何か?
最大の違いは、バリケードが光重合型の単一樹脂であり、練和不要で即時硬化する点である。従来のコーパック(非ユージノール系パック材)は二剤を混合して用い、硬化に数分〜十数分を要するが、バリケードは光を当てるまで硬化せず自由に操作でき、照射後は数十秒で完全に固まる。また、バリケードはピンク色半透明で審美的にも目立ちにくく、味や臭いもないため、患者の快適性が高い。一方で材料費はバリケードの方が高価であり、操作時に指先への付着対策が必要などの取り扱い上の違いもある。総じて、バリケードは操作性・審美性で優れる反面、コスト面では従来材より負担が大きいと言える。
Q. 術後、バリケードはどれくらいの期間装着しておくのか?
基本的には術後1週間程度である。通常、抜糸や経過観察のため術後7日ほどで来院してもらい、その際にパックも一緒に除去する流れになる。傷口が安定していれば1週間で外して問題ない。それ以上長く放置すると、パック周囲にプラークが溜まり始めるため好ましくない。万一、予定より早く外れてしまった場合は、創部が安定していれば再装着せず経過を見ることもあるが、術後すぐに脱離した場合は清潔を保つため付け直すことを検討する。いずれにせよ、次回予約日まで確実に維持されるよう計画するのが望ましい。
Q. バリケードの除去は難しいか?除去時に痛みはある?
正しく装着されていれば、除去はさほど難しくない。頬側と舌側のパックを歯間部でカットし、ピンセットで摘めば一塊でスルッと剥がれることが多い。硬化樹脂ではあるが柔軟性があるため、除去時に歯や歯肉を傷つける心配もない。痛みも通常はほとんど伴わず、抜糸と似た程度かそれ以下である。ただし、歯間部に深く入り込みすぎていると引っかかる場合があるため、その際は無理に剥がそうとせず、小さなハサミで樹脂を切り分けてから除去すれば痛みは防げる。また縫合糸に樹脂が絡んでいることもあるが、その場合も糸ごと切断してから外せば問題ない。
Q. バリケード使用時に注意すべき点や禁忌事項は?
いくつか重要な注意点がある。まず患者のアレルギーに留意すること。メタクリレート系レジンに対する重篤なアレルギーがある患者には絶対に使用しない。また、操作の際は周囲の照明光で硬化が始まらないように注意し、必要以上に明るい光源の下で放置しない。指や器具への付着を防ぐために潤滑剤(ワセリンなど)を使うことも必須である。さらに、他の材料との相性として、ユージノール含有の材料や過酸化水素水とは併用しない。これらは樹脂の重合を阻害・軟化させる恐れがあるためである。禁忌事項としては上述のアレルギー以外に特段の制限はないが、製品の添付文書に記載された使用方法と保管条件は厳守する必要がある。
Q. コストに見合う効果は本当にあるのか?
ケースによるが、適切な症例に使えば十分に見合う効果があると考えられる。確かに材料単価は高いものの、術後処置の時間短縮や患者満足度の向上といったメリットが得られる。患者からすれば不快な臭いや見た目のストレスがなくなるため治療満足度が上がり、医院への信頼にもつながる。そうしたポジティブな評価はリコール来院や紹介増にも寄与し、長期的には経済的リターンをもたらす可能性が高い。逆に言えば、費用を惜しんで患者に不快な思いをさせてしまっては本末転倒である。医院の方針と患者層に照らし、バリケードの価値が発揮できる場面では積極的に活用することで、結果的に費用を上回る効果が得られるだろう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 歯周保護材
- 歯周保護材「バリケード」とは?光重合型パック材の使い方と特徴