- 歯科機材の比較なら1Dモール
- パノラマ
- 歯科のパノラマレントゲンおすすめ15選を徹底比較!比較のポイントから各製品の特長、値段などを解説!
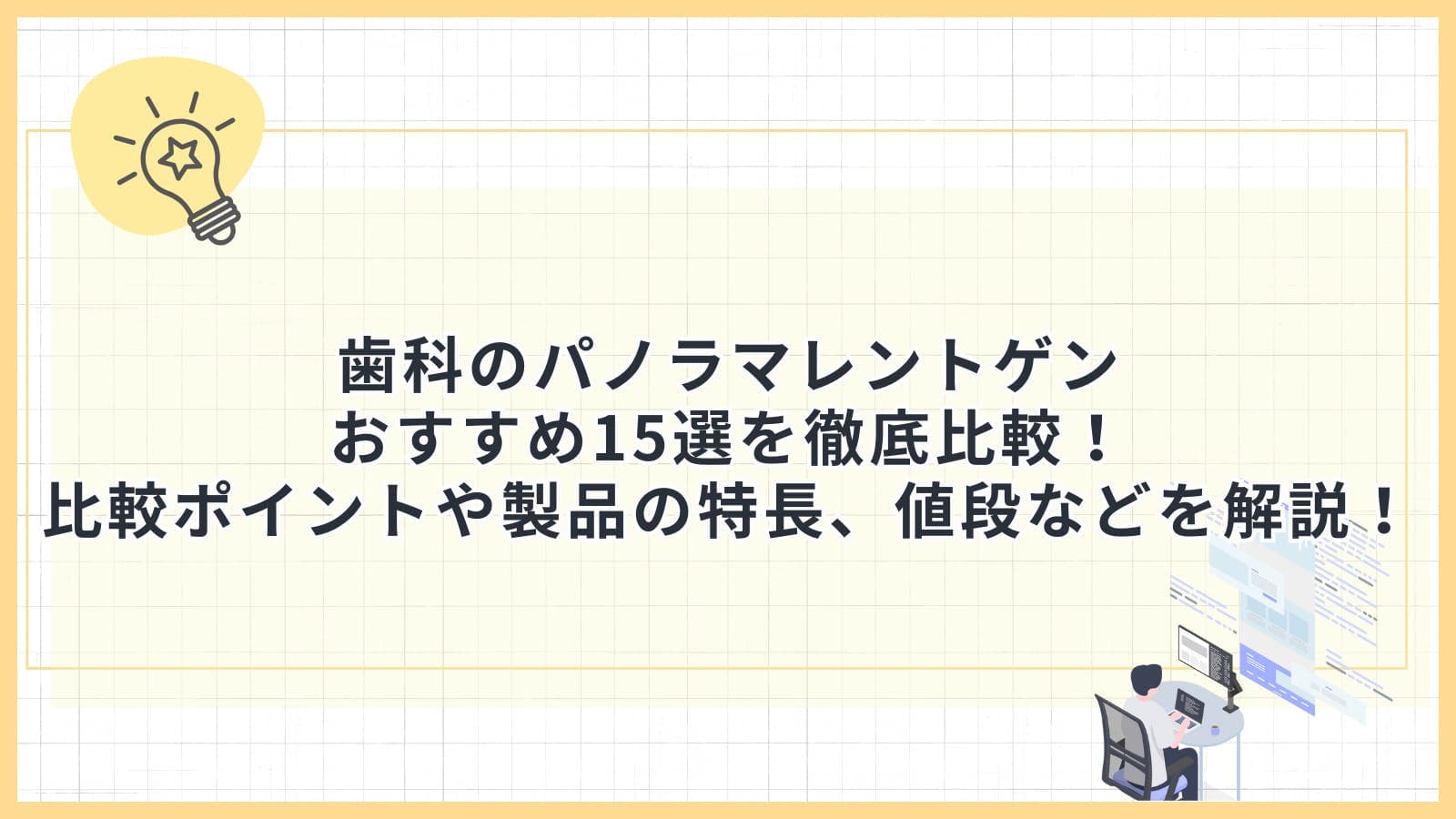
歯科のパノラマレントゲンおすすめ15選を徹底比較!比較のポイントから各製品の特長、値段などを解説!
歯科診療でパノラマレントゲン撮影を行った際、「前歯部がぼやけて写ってしまい、もう一度撮り直した」という経験はないだろうか。あるいは、新規開業や機器更新にあたり「高額なパノラマ装置、どれを選べば投資に見合うのか」と頭を悩ませている先生も多いはずである。パノラマX線装置は口腔内全体を一度に写せる基本検査であり、う蝕から埋伏智歯、顎骨病変に至るまで診断の要となる半面、導入コストや維持費も無視できない。
本記事では、パノラマ装置選びの臨床的ヒントと経営的戦略を提供する。画質や操作性など診断精度に直結するポイントはもちろん、「1枚あたりのコスト」「チェアタイム短縮による収益改善」まで踏み込み、先生方が最適な1台を選び抜く手助けをしたい。最後まで読み進めれば、各種製品の特徴と選び方の基準が明確になり、投資対効果(ROI)を最大化する戦略が見えてくるであろう。
目次
主要なパノラマレントゲン比較早見表
以下に、代表的な歯科用パノラマX線装置の主要スペックと経営指標を一覧表で示す。撮影可能な範囲(パノラマのみかセファロ付加可能か)、画像技術上の特徴、おおよその価格帯、撮影スピードといった項目を比較した。クリニックの規模や診療内容に応じた選択の参考にしていただきたい。
| 製品名(メーカー) | 撮影機能 | 特徴的な技術・強み | 参考価格帯(万円) | パノラマ撮影時間(秒) |
|---|---|---|---|---|
| Orthophos E(デンツプライシロナ) | パノラマ(セファロオプション有) | 高品質CsIセンサー採用、デジタル移行に最適 | 約400〜600万円 | 約14秒(標準モード) |
| Orthophos S(デンツプライシロナ) | パノラマ+セファロ(3Dアップグレード可) | 2D/3Dハイブリッド対応、豊富な撮影プログラム | 約600〜800万円 | 約14秒(標準2D) |
| Planmeca ProOne(プランメカ) | パノラマのみ | 壁付け可能な省スペース設計、操作パネル直感的 | 約400〜500万円 | 約10秒 |
| Planmeca ProMax 2D(プランメカ) | パノラマ(セファロ可、3D可) | 将来拡張性が高くCT化可能、画像解析ソフト充実 | 約600〜800万円 | 約10秒 |
| Veraview IC5 HD(モリタ) | パノラマのみ | 国内メーカーの安定品質、前歯部高精細モード搭載 | 約500万円前後 | 約8秒(高速モード) |
| SOLIO XD(朝日レントゲン) | パノラマのみ | フォーカス合成技術(断層合成)でブレ補正 | 約500〜600万円 | 約7〜9秒 |
| PaX-i(VATECH) | パノラマ+セファロ | CMOSデュアルセンサーで低コスト実現 | 約300〜500万円 | 約10秒 |
| PaX-i Insight(VATECH) | パノラマ+セファロ | マルチレイヤー撮影(焦点深度拡大)対応 | 約400〜600万円 | 約10秒 |
| CS 8100SC(ケアストリーム) | パノラマ+セファロ | 3秒高速セファロ撮影、自動トレース機能 | 約700〜800万円 | 約10秒 |
| Trophypan Smart(YOSHIDA) | パノラマのみ | Tomosharp画像処理で鮮明化、汎用デジタル機 | 約400〜500万円※ | 約10秒 |
| Panoura A1(YOSHIDA) | パノラマのみ | シンプル操作と最新CMOSで高画質・低価格 | 約300〜400万円 | 情報公開なし※ |
| OP 2D(KaVo/デジス) | パノラマのみ | Orthopantomograph伝統の信頼性、高コントラスト | 約500万円前後 | 約9秒 |
| VistaPano S(デュールデンタル) | パノラマのみ | S-Pan多重画像合成で自動鮮明化、7秒高速撮影 | 約400〜600万円 | 約7秒 |
| X-Mind prime(アクトエオン) | パノラマ+(3D/セファロ選択) | 軽量コンパクトで壁掛け可能、将来CT拡張可 | 約400〜700万円 | 約12秒 |
| I-Max(Owandy) | パノラマ(3D/セファロオプション) | 世界最軽量級(壁掛け型)、コストパフォーマンス高 | 約300〜500万円 | 約10秒 |
※価格は機種構成や販売時期により変動する目安である。またTrophypan SmartおよびPanoura A1の価格・撮影時間は公表情報が少ないため推定値を含む。
一覧表から分かるように、基本的なデジタルパノラマ装置は300〜600万円前後に集中しており、セファロ撮影機能や特殊技術を備えた上位機は600〜800万円程度となる。低価格帯でもCMOSセンサーや画像処理技術の進歩により画質は飛躍的に向上しており、エントリーモデルでも日常診療には十分耐えうる。一方、高価格帯の装置は経営視点では大きな投資だが、高速撮影によるチェアタイム短縮や新規自費診療(矯正やインプラント)の導入といった収益拡大の機会をもたらす可能性がある。続いて、製品選定にあたって着目すべき比較ポイントを解説し、その後に各製品の詳細レビューを行う。
パノラマ装置の比較ポイント(臨床性能と経営効率)
パノラマレントゲンを比較検討する際、臨床面と経営面の両軸から評価することが重要である。ここでは主要な比較項目として、「画質と診断精度」「操作性とワークフロー効率」「経済性(コストとROI)」の3点を取り上げ、それぞれが臨床結果と医院収益にどう影響するかを考察する。
画質と診断精度の比較
画像の鮮明さと解像度は、虫歯の進行度評価や歯周組織の状態把握、埋伏歯・病変の検出に直結する。近年のデジタルパノラマ装置はほとんどが高感度なCMOSセンサーを採用し、従来のCCDやフィルムに比べ解像度とコントラストが向上している。また、各社が独自の画像処理技術を搭載している点も見逃せない。例えばVATECH PaX-i Insightのマルチレイヤー撮影では、一度の回転で複数の焦点平面の画像を取得・合成し、前後方向の焦点ボケを大幅に軽減している。これにより、患者の位置ずれで前歯部が不鮮明になる問題が起きにくく、再撮影リスクの低減につながる。朝日レントゲンのSOLIO XDも「焦点合成」技術を用い、取得した断層データから全領域にピントが合った画像を再構築できる。同様に、Carestream系統(YOSHIDAのTrophypanシリーズなど)の装置が備えるTomosharpテクノロジーでは、撮影後にアルゴリズムでピントの合った層を強調し、常に鮮明なパノラマ像を得る工夫がなされている。
さらに画質モードの柔軟さも診断精度を左右する。多くの装置は成人用・小児用のモードや、低被ばくで撮影するエコモードを備える。デュールデンタル VistaPano SではS-Pan技術による鮮鋭化に加え、撮影所要時間7秒という高速撮影が可能で、動きボケを抑えつつ高精細画像を提供する。モリタ Veraview IC5 HDは「ハイスピードモード」で約8秒の撮影を実現しつつ、高解像度モードも選択でき、状況に応じて画質と速度を切り替えられる。画像の階調表現(ダイナミックレンジ)も重要で、骨密度の違いや微細な病変を描出するには14〜16ビットのセンサー出力が理想的である。各メーカーともその点を強化しており、例えばVATECHやSironaの機種は14ビット以上の階調で骨梁の描出性を高めている。
これら画質の違いは診断の確実性に影響するだけでなく、患者説明の説得力にもつながる。鮮明なX線写真を用いて「この陰影がう蝕です」と示せば患者の理解も得やすく、治療受諾にも良い影響を与える。経営面では、診断精度向上により見逃しや誤診を防ぎ、再治療コストやクレームリスクを減らす効果が期待できる。特にインプラントや歯周治療など精密な診断が必要な分野では、高画質パノラマが術前評価の信頼性を高め、不要なトラブルを未然に防ぐ投資と言える。
操作性とワークフロー効率の比較
装置の使いやすさと撮影ワークフローの効率は、患者1人あたりの所要時間=チェアタイムに直結する。例えば患者の立ち位置・固定のしやすさは重要なポイントだ。従来、あご台とハンドルを備えた設計が主流であったが、近年は正面対面式の配置を採用する機種(Sirona OrthophosやYOSHIDAトロフィーパンなど)が増えている。対面式では術者が患者の顔正面で直接位置づけを確認でき、短時間で正確なポジショニングが可能である。YOSHIDAのTrophypan Excelではデザイン面で「肩が当たりにくい構造」を追求し、体格の大きい患者でもスムーズにポジショニングできる。こうした設計上の工夫が誤差による撮り直し防止と撮影時間短縮につながる。
撮影プロセスのスピード自体も効率に大きく影響する。表のとおり、一周の撮影時間は概ね7〜15秒程度であるが、高速撮影モードを持つ機種では動きぼけが減るためリテイク(再撮影)の頻度が低下するメリットがある。特に嘔吐反射が強い患者や小児では、撮影時間が長引くほど不動を維持するのが難しくなるため、高速撮影は患者負担軽減にも直結する。ケアストリームのCS 8100SCはセファロ撮影を含め非常に高速(セファロ最短3秒)で、患者がじっと止まっていられるか不安なケースでも安心だ。短時間撮影による被ばく低減効果もあり、安全管理の観点からも好ましい。
ユーザーインターフェースとソフトウェア連携も診療効率を左右するポイントだ。近年のデジタルパノラマは多くがタッチパネル式の操作画面を搭載し、撮影部位の選択や患者情報入力が直感的に行える。例えばAir Techniques(デュール)のProVecta S-Panは7インチのカラータッチディスプレイでモード選択も一目瞭然である。また、患者ごとに適切なX線量を自動設定する機能を持つ装置(VATECH PaX-iの年齢・性別自動設定機能など)は、撮影条件ミスを防ぐとともに撮影準備を迅速化する。撮影後の画像転送も見逃せない。デジタルデータ連携がスムーズであれば、撮って数秒でチェアサイドのモニターに画像が表示でき、すぐに患者説明に入れる。Ciモールで紹介されているPaX-iの例ではタブレットと連携し、撮影直後にその場で患者と画像を見ながらカウンセリングを行えるとされている。これは患者待ち時間の短縮だけでなく、タイムリーな説明で患者の疑問や不安を即座に解消しやすく、満足度向上に寄与する。
メンテナンス性もワークフローには重要だ。例えばパノラマ・セファロ兼用機では、従来は1つのセンサーを付け替えて兼用するタイプがあったが、最近はセンサーを2基搭載し付け替え不要な機種(VATECHやSironaの一部モデル)が主流である。センサーの抜き差し作業がないため物理的損傷リスクが減り、故障やダウンタイムの回避につながる。年間保守契約料は機種により異なるが、相場は約20万円前後【参考:業界情報】であり、これは決して安くない。しかし、日々の安定稼働と万一の迅速な修理対応による診療中断リスクの低減を考えれば、計画的メンテナンスへの投資も長期的な経営効率アップといえる。操作性・ワークフローが優れた装置はスタッフ教育の手間も軽減する。操作が複雑な機械だと新人スタッフへのトレーニングに時間を取られ、エラーも起きやすいが、簡便なUIやオート機能が充実した機種なら誰でも短時間で使いこなせるため、人為ミスが減り院内全体の生産性が向上する。
経済性(コストパフォーマンスとROI)の比較
歯科用パノラマ装置は高額な設備投資であるから、経営的視点でその費用対効果を吟味する必要がある。まず初期導入コストだが、上記一覧の参考価格帯にある通りデジタルパノラマのみで約300〜600万円、セファロ付加や高機能タイプで600〜800万円程度が目安となる(為替や時期により変動)。例えばYOSHIDA Panoura A1やVATECH PaX-iといったエントリーモデルは400万円前後から導入可能で、レントゲン設備としては比較的手が届きやすい水準である。一方、Dentsply SironaやCarestreamなどグローバル大手メーカーのフラッグシップ機、およびCT併用可能なハイブリッド機は800万円近くに達することもあり、開業医にとって慎重な判断が求められる。初期費用だけでなく、法定耐用年数(通常5〜6年)を踏まえた減価償却や、年間の保守契約費・部品交換費も計算に入れる必要がある。
しかし重要なのは、単なる支出ではなく投資として回収できるかという視点である。ROI(投資対効果)を考えるとき、まず診療報酬や自費収入への貢献が挙げられる。パノラマ撮影は保険点数にして約1000〜2000点(1枚あたりの算定)であり、日常的に撮影する検査としては大きな収入源ではないものの、診断精度向上による追加治療の発見という間接的な貢献が大きい。例えばパノラマで埋伏智歯の存在や歯周骨欠損が確認できれば、必要な抜歯や歯周治療を提案でき、その分の治療収入が生まれる。インプラントや矯正治療を提供している医院では、高性能なパノラマ画像が患者への説明ツールとなり、治療受諾率向上=自費収入増加につながるケースも多い。最新機種を導入し「当院では画像診断にも力を入れています」という姿勢を示すこと自体が、患者の安心感や医院のブランディング向上に資する。
次にコスト削減効果も見逃せない。フィルム式からデジタル式に移行すれば、薬液やフィルム代といったランニングコストがほぼゼロになる。近年はほとんどの医院がデジタル化済みだが、もし未だフィルム現像を行っているならデジタルパノラマへの更新は維持費削減の即効性ある施策となる。また、デジタルデータ管理によりフィルム保管スペースも不要となり、物理的書庫スペースを有効活用できるという効用もある。チェアタイムの短縮も経営効果に直結する。撮影準備から画像確認までの一連の流れが効率化すれば、1日に対応できる患者数が増やせる可能性がある。例えば高速現像が不要なデジタルでは、撮影から画像表示まで数十秒〜1分程度で完了するため、その分だけ診療サイクルが早まる。1日あたり数人でも多く診察できれば、年間では相当の増患効果となる。
また、装置の耐久性と故障リスクも長期的なROIに影響するポイントだ。初期費用が安くても故障が多ければ修理費や代替機レンタル費がかさみ、患者対応の遅延による機会損失も発生する。国内メーカー(モリタや朝日など)は全国的なサービス網と迅速なパーツ供給が期待でき、故障時のダウンタイム短縮という意味で安心感がある。海外メーカーでも信頼性の高いブランド(SironaやPlanmecaなど)は装置寿命が長く、結果的に長期で見れば安定運用によるコスト削減につながる。中古市場やリース契約も経営戦略上検討されるが、薬機法上の管理や保証の問題もあるため慎重に見極めたい。新品導入時にはメーカーの保証内容(多くは1〜2年のフルパーツ保証)やアップグレードオプション(後からセファロ増設やCTユニット追加が可能か)も確認しよう。将来的に医院の診療内容拡大を見据えるなら、多少初期費用が上がっても拡張性のあるモデルを選ぶことで、買い換え無しに対応でき結果的な投資節約となる場合もある。
以上のように、パノラマ装置の比較検討では単純な価格の安い高いではなく、その装置が生み出す価値を多角的に評価することが重要である。では具体的に各製品ごとに、どのような特徴や強み・弱みがあり、どんな医院にマッチするのかを見ていこう。
おすすめ歯科用パノラマレントゲンの製品別レビュー
以下に、主要なパノラマX線装置を個別に取り上げ、臨床性能と経営インパクトの双方からレビューする。それぞれの製品がどのような強み・弱みを持ち、どのような診療スタイルの先生に適しているかを具体的に描写する。読者自身の医院像と照らし合わせながら、自分にフィットする一台を見極めていただきたい。
Orthophos E(デンツプライシロナ)デジタル移行に最適なエントリーモデル
Orthophos Eは世界的メーカーであるデンツプライシロナの2Dパノラマ装置で、デジタルレントゲンへのスムーズな移行をテーマに設計された基本モデルである。従来機から評価の高い信頼性と画質は継承しつつ、操作系統をシンプルにまとめ、初めてデジタルパノラマを導入する医院でも戸惑いなく使えるよう配慮されている。CsI(セシウムヨウ化物)蛍光体を用いた高感度センサーにより、低被ばくでも鮮明な画像が得られる点が臨床的メリットだ。撮影プログラムは標準のパノラマに加え、小児モードや一部野外顎を除いた撮影など一通り備えており、日常診療のあらゆる場面をカバーする。
経営面では、高品質ながら価格が比較的抑えられたシロナ製品として魅力的である。上位機種に比べ付加機能を絞っている分、導入コストを低減しており、先述の価格帯で言えば中堅クラス(およそ500万円前後)に位置する。オプションでセファロアームを追加可能なため、将来的に矯正診断を院内で完結したい場合にも対応できる柔軟性がある。一方で3D(CT)へのアップグレードは非対応なので、ゆくゆくCT導入を視野に入れる医院では、初めから上位モデルや他社のハイブリッド機を検討したほうが良いだろう。Orthophos Eは「まずはデジタル化で業務効率を上げたいが、過剰な機能はいらない」という開業医にマッチする。シロナのブランド力は患者への訴求力もあり、待合室等で「最新デジタルレントゲン導入」をアピールすることで信頼感向上にもつながるだろう。堅実な性能と国際メーカーのサービス体制によって、長期にわたり安心して使える入門機として評価できる。
Orthophos S(デンツプライシロナ)将来を見据えたハイエンド2D/3Dハイブリッド
Orthophos Sはシロナの提供する上位モデルで、2Dパノラマ撮影に加えて3D(CBCT)モジュールへの拡張性を備えたハイブリッドX線装置である。現在は2Dパノラマ・セファロ装置として導入し、必要に応じて後日CTユニットを追加できる柔軟な構造が特長だ。画質面ではシロナ独自の高解像イメージングと自動位置補正機能が充実しており、多少の顎位ズレがあってもアルゴリズムが補正してクリアな画像を提供する。撮影プログラムも豊富で、標準・小児・断層厚み変更・咬翼状(バイトウィング)撮影・TMJ専用など多彩なモードを搭載し、あらゆる臨床ニーズに1台で応える。またオプションのAi機能により撮影画像から自動で所見をマーキングするような最新技術も組み込まれている(国によって仕様は異なる)。
経営的には、Orthophos Sは高額投資であるが将来的なROIを描きやすい装置である。というのも、この機器を導入することで新たな自費診療(CTを用いた高度診断や精密インプラント治療)への道が拓けるからである。初期導入時点では2Dパノラマ運用に留め、患者数やニーズの高まりに合わせて3Dユニットを追加すれば、一台買い増すより低コストでCT導入が実現する。矯正や口腔外科に注力するクリニックであればセファロ撮影も含めフル機能を一元管理でき、紹介先への依頼を減らして院内完結率を上げる戦略が取れる。患者にとっても「他院に行かずこの場でCTまで撮れる」という利便性は大きな付加価値であり、医院の総合力アピールとなろう。ただし注意点として、フルスペックを活かすにはスタッフの習熟や診断知識のアップデートも必要で、宝の持ち腐れとしない運用努力が求められる。また価格帯は最高クラス(700〜800万円台)であり、分割払い・リース契約など資金計画も綿密に立てたい。Orthophos Sは、「現在は一般歯科中心だが将来は高度医療にも展開したい」という成長志向の医院にとって、長期的パートナーとなりうるハイエンド機である。
Planmeca ProOne(プランメカ)省スペースと手頃な高性能の両立
Planmeca ProOneはフィンランドのプランメカ社によるコンパクト設計のパノラマX線装置である。壁付け可能なユニークなデザインが特長で、診療室の一角や限られたスペースにも無理なく設置できる省スペース性を誇る。操作パネルはタッチスクリーン式で、アイコン表示によりモード選択も直感的に行える。プランメカの画像処理アルゴリズムにより、高コントラストでシャープな画像が得られる点も評価ポイントだ。特に歯槽骨の境界や歯根膜スペースなど細部の描出に優れており、一般的な虫歯・歯周病の診断からインプラント埋入前の大まかな評価まで、毎日の診療をしっかり支えてくれる。ProOneはパノラマ専用機でセファロ追加やCT拡張には対応しないものの、そのシンプルさゆえ可動部が少なく故障が少ないとの声もある。機械的信頼性の高さは、機器トラブルで診療を止めてしまうリスクを減らす意味で経営上ありがたい特長である。
価格面では中価格帯(約400〜500万円)に位置し、欧州製品としては比較的手頃と言える。省スペースはすなわち省コストでもあり、新規開業時にレントゲン室を広く取れない場合でもProOneなら既存スペースに後付けしやすい利点がある。壁掛け設置によりユニット増設が不要なケースでは、専用室の工事費用も抑えられる可能性があるだろう。ただし将来的に「やはりセファロも欲しい」となった場合には買い替えが必要になるため、導入前に診療方針との整合を検討しておくべきだ。総じてProOneは「限られた空間と予算で、でも画質と信頼性は妥協したくない」という先生に適した一台である。ヨーロッパの洗練されたデザインは患者への訴求力もあり、機能美を感じさせる機器として医院の雰囲気づくりにも一役買うだろう。
Planmeca ProMax 2D(プランメカ)アップグレード自在なプレミアムパノラマ
Planmeca ProMax 2Dはプランメカ社のフラッグシップ級パノラマ装置で、多彩な拡張オプションを特徴とするプレミアムモデルである。基本構成では高性能デジタルパノラマだが、必要に応じてセファロアームの追加や3D CBCTモジュールへのアップグレードが可能で、まさに“One for All”のコンセプトを体現している。画像性能は極めて高く、プランメカ独自のADR(自動露出補正)や動体検知機能により、患者個々に最適化されたX線出力でブレや過不足のない画像を得ることができる。さらに、専用ソフトウェアであるRomexisは画像解析機能が充実しており、インプラントシミュレーションや神経管の自動マーキングなど、診断からプレゼンまでワンストップで対応する強力なツールだ。これら高度な機能は、一歩進んだ臨床応用(高度な外科処置や矯正分析など)を支える武器となる。
経営面では、その拡張性の高さゆえに初期投資額も高めではあるが、Orthophos Sと同様に段階的に設備投資を回収できるモデルでもある。まずパノラマ診断で収益基盤を固め、患者ニーズや症例数に合わせて後からCT機能を付加し新たな収入源を得る、といった戦略が可能だ。ProMaxシリーズは耐用年数内での機能拡張を見込んで堅牢に作られており、製品寿命が長いことでも知られる。長く使えるということは買い替え頻度が減り、結果としてライフサイクルコストが抑えられる利点となる。価格帯は上位機ゆえ600〜800万円以上と高額だが、一台で将来のCT需要まで賄えると考えれば合理的との評価もできる。導入にあたっては、例えば「5年以内にインプラント症例を年○件増やす」「CT撮影を年間○件行う」といった具体的な目標を設定し、それにより何年で投資回収できるかシミュレーションしておくと良い。Planmeca ProMax 2Dは「先を見据え、常に最新技術を取り込みながら医院を成長させたい」という経営者マインドを持つ先生にフィットするだろう。高度機能を使いこなすことで得られる患者からの信頼と、医院のハイテクなイメージは、投資以上のリターンをもたらす可能性が高い。
Veraview IC5 HD(モリタ)国内信頼ブランドのスタンダードデジタル
Veraview IC5 HDは国内大手のモリタ製作所が提供するデジタルパノラマX線装置で、「国産機ならではの堅実さ」が光る一台である。一般的名称である「管理医療機器 デジタル式パノラマX線診断装置」のとおり、奇をてらった機能よりも基本性能の充実に重点を置いている。具体的には、公称焦点0.5mmのX線管球と60〜70kV可変の出力により、安定して高精細な画質を提供する。撮影モードは標準パノラマのほか小児用・咬翼相当・顎関節4分割など基本を網羅。撮影時間は約8〜10秒で、通常モードと高解像度モードを切替可能だ。前歯部など見たい部分に応じて画質優先かスピード優先かを選べる点は実用的である。操作系はシンプルで日本語表示にも対応しており、機械操作に不慣れなスタッフでも直感的に扱える親切設計と言える。国内生産による品質管理の徹底と、きめ細かなサポート体制もモリタブランドの強みで、故障時の迅速なメンテ対応やパーツ供給に安心感がある。
価格は中価格帯(約500万円程度)で、海外プレミアム機ほど高額ではないが、格安モデルほどの安さでもない。これは国産ゆえの部品調達コストや品質維持コストを反映しているが、その分長期間の安定稼働による価値が期待できる。筆者の周囲でも「10年以上トラブルなく稼働しているIC5シリーズ」をよく耳にする。機器停止による診療機会損失や患者への迷惑を最小限にしたいと考えるなら、安定した国産機は選択肢として有力だ。セファロ撮影が必要な場合は上位モデルや他製品を検討することになるが、保険診療中心でパノラマが撮れれば十分という歯科にはIC5 HDはオーバースペックにならない適切な性能だろう。「派手さはいらない、壊れずちゃんと撮れればそれで良い」という堅実志向の院長先生にフィットする。患者から見ても、日本の老舗メーカー機器が鎮座していることは安心材料となりうる。まさに縁の下の力持ちとして、日々の診療を地味にしかし確実に支えてくれる存在である。
SOLIO XD(朝日レントゲン)先進画像処理でフォーカスミスを軽減
SOLIO XDは京都に本社を構える朝日レントゲン工業のデジタルパノラマX線装置で、画像処理技術の先進性が際立つモデルである。朝日レントゲンは日本で初めて歯科用パノラマ装置を国産開発したパイオニアであり、本機にも長年のノウハウが詰め込まれている。最大の特徴は新開発の「AFパノラマ(Asahi Fine Panorama)」と呼ばれる画像処理で、「ノイズ除去」「シャープ化」「焦点合成(フォーカススタッキング)」の3機能を組み合わせることで撮影画像を自動補正する。これにより、どの部位でも輪郭が明瞭なパノラマ写真が得られる点が大きな強みだ。患者の歯列形状によっては通常一枚の断層像では全域にピントを合わせるのが難しいが、SOLIO XDでは断層幅30mmのデータから複数層を合成するトモシンセシス技術でそれを克服している。臨床的には、根尖部が不鮮明だったり上顎洞底が写らなかったりといった再撮影要因が減るため、一発で欲しい情報が揃う診断効率の良さが光る。また焦点調整だけでなくノイズリダクションも効いているため、金属修復物によるアーチファクト影響も軽減されている。標準の画質が非常に良好なので、撮影後の画像調整に手間取ることも少ない。
経営的視点では、SOLIO XDは国内メーカー品質と最新技術の両方を享受できる点がメリットだ。価格帯は中〜やや高め(500〜600万円程度)と推定されるが、撮り直し減少による患者あたり作業時間の短縮や、明瞭な画像による治療説明効率アップなど、見えにくい形でROIに貢献するだろう。特に複雑な根管治療や歯周外科のケースで事前診断が的確にできれば、追加処置やアポイント変更といった無駄を省ける。朝日レントゲンは国内各地にショールームやサービス拠点を持ち、導入前のデモから導入後のフォローまで手厚いサポートを行っている。これは大規模メーカーに引けを取らない強みで、操作習熟やトラブル時にも安心だ。SOLIO XDは「最新テクノロジーで診断精度を極限まで高めたい」と願う先生にとって魅力的な選択肢となる。反面、セファロやCTは搭載しないので用途はパノラマ診断に限定されるが、その領域ではトップクラスの性能を発揮する。高度な画像に価値を見出し、患者に“精密検査のできる歯科医院”としてアピールしたい場合にも有効だ。
PaX-i(VATECH)低被ばく・低コストで世界導入のベーシック機
PaX-i(パックスアイ)は韓国VATECH社のデジタルパノラマ装置で、全世界90カ国以上で導入されているグローバルヒットモデルである。コストパフォーマンスに優れた基本性能が最大の特徴で、CMOSセンサーによる高画質デジタル撮影を、競合他社と比べて驚くほど抑えた価格帯で提供している。画質面では、直交撮影モード(Orthogonal Mode)がユニークだ。通常パノラマはX線が斜めに当たるため重なりがちの隣接歯も、直角入射モードを選ぶことで歯間の重なりを減らした鮮明画像が得られる。術者がバイトウィング撮影をしたい場合に近い情報をパノラマ1枚で補完でき、う蝕診断の助けとなるだろう。また小児向けモードではX線露出範囲を縮小し被ばく線量を抑える配慮もなされている。実際、VATECHは低線量技術に力を入れており、同社CTでは最大85%線量低減と謳うモデルもあるほどである。PaX-i自体も一般的なパノラマより被ばく低減が意識されており、患者にも説明しやすい。セファロ付モデルでは2つのセンサーを搭載するため、センサー付け替えの手間や故障リスクがないのもポイントだ。
経営的にPaX-iが魅力的なのは、何と言っても導入ハードルの低さである。Ciモールで「驚きの低価格」と紹介されているように、他社では考えにくい価格帯(300万円台〜)でデジタルパノラマを入手できる場合もある。開業時の初期投資を極力抑えたい場合や、古いアナログ機からの置き換えで予算が限られている場合には、有力な選択肢となるだろう。安価だからといって画像が粗悪では困るが、PaX-iは世界中のユーザー数が品質を証明しているとも言え、実際筆者も何院かで症例画像を見た限り、普段使いには十分クリアな画質である。メーカーのVATECHは日本国内でも直販体制を整えており、韓国メーカーながらサポート面も強化されてきている。ただ、ユーザー数が急増している分、導入クリニック同士の情報交換(例えばSNSグループ等)は盛んだが、メーカーサポートの手が足りないケースがないかは注視したいところだ。PaX-iは「費用を抑えてデジタルパノラマ導入したい、でも画質も妥協できない」という医院にフィットする。保険診療が中心でROI回収に時間をかけられない場合でも、この装置なら数年内のペイを十分見込めるだろう。コスト意識の高い経営において心強い味方となる一台である。
PaX-i Insight(VATECH)多層画像で死角を無くす次世代パノラマ
PaX-i Insightは前述のPaX-iをベースに、“Insight(洞察)”の名が示す通りより深い情報量を提供する次世代パノラマ装置である。最大の特徴はマルチレイヤーパノラマ撮影機能で、撮影時に焦点深度の異なる複数のパノラマ画像を取得し、それらを統合して1枚の鮮明な画像を作り出す。この技術により、通常は一点にしか合わない焦点が前後広範囲に及ぶため、例えば多少患者の前後位置がずれても全歯列にピントが合った画像が得られる。特に上顎前歯部や下顎前歯部で起こりがちな焦点ボケを大幅に軽減でき、根尖の確認漏れや病変の見逃しリスクを下げてくれる。Insight画像では複数の断層データを保存しているため、撮影後に特定部位の画像のみ再構成して精査することも可能で、半端なCBCT並みとは言わないまでも、2D装置でありながら擬似的な立体情報を読み取れる点が画期的だ。例えば歯根の湾曲や重複、埋伏歯の位置関係なども、異なるレイヤーの画像を見ることで把握しやすくなる。VATECHはこの機能を「Insight Pan」と称し、より正確な診断と治療計画に役立つとアピールしている。
経営面でPaX-i Insightを考えると、基本構造はPaX-iと同じであるためコストは比較的抑えめで、概ね400〜600万円程度と見られる。標準のパノラマモードも搭載しており用途に応じて使い分け可能なので、症例によっては通常の一層画像でさっと撮影し、難症例では多層でじっくり撮影するといった柔軟な運用ができる。多層撮影ゆえデータ量は増えるが、そこはコンピュータの進歩で処理時間も許容範囲に収まっている。ROIの観点では、Insightの導入によりCTを導入しなくても得られる情報が増えるという点が興味深い。もちろん真の3DではないのでCTの代替はできないが、「本来CTを撮影依頼していたようなケースの一部がパノラマで補える」可能性がある。これは患者に追加被ばくや高額なCT費用を負担させずに済む利点となり、患者満足度向上や信頼関係構築に資するだろう。さらに、多層画像のおかげで診断精度が上がり、見逃していた治療すべき箇所を発見できれば、それはそのまま治療件数・売上増につながる。PaX-i Insightは「CTほどではないが、より深い診断情報を得たい」というニーズに応える中間解として価値が高い。特に根管治療や埋伏歯抜歯などで事前情報を少しでも多く得たい先生や、CT導入は予算的に難しいが診断精度は妥協したくないという医院にとって、投資する価値のある一台と言える。
CS 8100SC(ケアストリーム)矯正に威力発揮の高速パノラマ・セファロ
CS 8100SCはアメリカのケアストリーム・デンタル(旧コダック)のデジタルパノラマ+セファロ装置で、圧倒的な撮影スピードと先進のソフトウェア機能を兼ね備えている。まず特筆すべきはセファロ撮影の速さで、18×24cmの頭部X線写真をわずか3秒でスキャンできる世界最速クラスの性能である。通常、セファロは長い露光時間が必要で患者動揺が問題になるが、この装置では一瞬で撮影が完了するためブレのない側貌規格写真がほぼ確実に得られる。矯正治療を手掛ける歯科医院ではセファロ分析の精度が治療計画の要だが、CS 8100SCなら患者の協力度に左右されず常にクリアな画像を提供し、安定した治療結果に貢献するだろう。パノラマ撮影自体も約10秒程度と高速であり、Tomosharp技術により位置ズレ補正や組織別フィルター(骨用・歯用など)の適用も可能である。さらに注目なのが自動セファロトレース機能で、撮影した側貌頭部X線画像から主要なアナトムポイントをAIが自動検出し、わずか10秒程度で分析用のトレース図を作図してくれる。従来30分近くかかっていた分析作業が一瞬で終わるわけで、これは矯正専門医のみならず一般歯科で矯正を扱う先生にとっても劇的な省力化となる。このようにCS 8100SCは矯正歯科領域における革命的ツールとも言える存在だ。
経営面では、先端機能ゆえの高額さ(700〜800万円台)は避けて通れないものの、それを補って余りある効果が期待できる。まず矯正診断を外部のレントゲンセンターや他院に委託していた場合、本機を導入することで院内完結による収益化が図れる。撮影料だけでなく分析作業時間も短縮されるため、同じ時間でより多くの患者対応や他の診療に充てることができる。さらに高速撮影は患者体験を向上させ、小児患者の撮影嫌い克服や保護者の安心感につながる。経営視点では「矯正に強い歯科医院」としてのブランド確立にも寄与し、周囲から矯正患者が紹介されて増患する可能性もあるだろう。一方で、この装置は明確に矯正・外科向け機能に振った構成のため、もし「うちは矯正はやらない」という医院であれば宝の持ち腐れとなる。セファロ不要であれば、同シリーズのパノラマ専用機CS 8100や他の安価なモデルで十分である。したがってCS 8100SCは「矯正や外科に本格参入し、専門医院並みの体制を整えたい」という医院にこそ適している。設備投資額は大きいが、それによって新たな自費治療分野を開拓できると考えればROIの見通しは立てやすい。実際、同機導入後に矯正治療件数を飛躍的に伸ばした開業医の例も報告されている。ハイスペック機を活かしきるだけの情熱と展望があるなら、強力な武器となってくれるだろう。
Trophypan Smart(YOSHIDA)汎用デジタル機に鮮鋭化技術をプラス
Trophypan SmartはYOSHIDA(吉田製作所)が扱うデジタルパノラマ装置で、必要十分な機能に画質向上技術を加えたバランスの良いモデルである。YOSHIDAは国内ディーラーとして海外の優れた装置を取り入れつつ、日本の歯科医院のニーズに合わせたローカライズを行っている。本機もフランスのTrophy社(現ケアストリーム傘下)の技術を基にしており、Tomosharpテクノロジーを搭載している点が特徴だ。Tomosharpにより位置ズレを補償し、エッジの効いた鮮明な画像が得られることは前述の通りだが、Trophypan Smartでは更に画像フィルターを任意に選択できる。たとえば骨構造を強調するフィルターを適用すれば微細な骨梁や骨欠損が見やすくなり、象牙質・エナメル質を強調するフィルターなら齲蝕の陰影が浮き上がる。診たい組織に応じてリアルタイムに画像調整できるのは、アナログ時代にはなかったデジタルならではの利点である。基本性能としては標準的なデジタルパノラマで、成人・小児・断層幅変更・TMJ撮影と一通り揃っており、大きな不足はない。なお「Smart」の名が付くが、これは特定のAI機能等を指すものではなく、総合的にスマートな使い勝手という意味合いである。実際シンプルなUIでスタッフにも好評な機種だ。
価格帯は中堅(推定400〜500万円前後)で、YOSHIDAが幅広い歯科医院に導入を進めていることもあり比較的入手しやすい印象だ。YOSHIDAの営業網・サポート網を通じて導入時のトレーニングやメンテナンスも受けやすく、初めてのデジタル化でも安心感がある。セファロやCTが必要になった場合は上位機種(Trophypan系列のExcel 3Dなど)への入替を検討する形になるが、裏を返せばパノラマ専用機に徹することで構造がシンプルになり、扱いやすさと故障の少なさにつながっている。Trophypan Smartは「まずは基本のデジタルパノラマを導入し、日常診療の質を上げたい」と考える医院に向いている。例えば保険診療主体のクリニックで、従来フィルムレントゲンだったところを本機に置き換えれば、チェアサイドですぐ画像を見せて患者説明を充実させられるし、保険請求上もパノラマ算定の機会を逃さず行えるようになる。またYOSHIDAブランドは歯科業界で長年の信頼があり、部品交換や将来の買い替え時にも下取り等で融通が利きやすい点も経営上メリットと言える。尖った機能はないかもしれないが、まさにオールラウンドプレーヤーとして医院の日々の診療に溶け込み、堅実に働いてくれる一台である。
Panoura A1-2D(YOSHIDA)シンプル操作と最新技術を両立した新鋭モデル
Panoura A1-2DはYOSHIDAが近年リリースしたデジタルパノラマ装置で、「高画質はそのままに価格を抑えた次世代機」とうたわれている。販売終了となったXeraSmartシリーズの後継的位置づけであり、より洗練されたデザインと操作性で登場した。特筆すべきは新開発の高解像度CMOSセンサーを搭載しながら、コストパフォーマンスに優れる価格設定がなされている点だ。YOSHIDAは公式に価格を公開していないものの、「導入しやすい2Dレントゲン」としていることから、国産品としては驚くほどの低価格帯を実現した可能性が高い。画像品質はXeraSmart譲りのシャープさを持ち、さらに断層可変テクノロジーによって撮影後でも任意の部位に再フォーカスし鮮明化できるという。これは撮影後にソフトウェア上でフォーカス位置をずらし再構築する技術で、多少の位置ズレならリカバリーできるためリテイクを防ぐ効果がある。またパノラマ画像から必要部位をデンタル(口内法)サイズに切り出し保存する機能も備え、保険算定上はパノラマかデンタルかを選択できる柔軟性を持つ(同一部位で両方算定は不可だが)。これは撮影1回で二通りの用途をカバーするユニークな機能で、患者負担軽減と診療報酬上の効率化双方にメリットがある。
Panoura A1は経営面でも新規開業や機器更新時の心強い味方となり得る。おそらく300万円台〜400万円程度で導入可能と推測され、他社新鋭機では考えにくいリーズナブルさだ。低価格機ながらYOSHIDAの販売網で提供されるため、保証やアフターサービスも抜かりない。シンプル操作はスタッフ教育コストを下げ、誰でも短時間で扱えることで院内オペレーションの均一化に寄与する。Panoura A1は「最新機種を手頃な価格で」という欲張りな条件を実現した製品であり、とりわけ開業まもない若手歯科医師に適しているだろう。初期投資を抑えつつ最新技術を積極活用して差別化を図りたい先生にはうってつけだ。ただしセファロやCT拡張はできないため、分院展開や専門分野拡充の段階では上位機へのステップアップも視野に入れる必要がある。それでもまずはこのPanoura A1で医院のデジタル診断基盤を固め、収益を伸ばしながら将来の投資に備えるという賢い戦略が取れる点で価値ある一台と言える。
OP 2D(KaVo/DEXIS)元祖オルソパンの血統を継ぐ信頼機
ORTHOPANTOMOGRAPH™ OP 2DはKaVo(カボ)社が展開するデジタルパノラマ装置で、その名のとおり世界初のパノラマ装置「オルソパントモグラフ」の伝統を受け継ぐモデルである。フィンランドのインストゥルメンタリウム社で培われた技術が礎にあり、現在はKaVo(およびデジス)ブランドとしてグローバルに販売されている。OP 2Dの美点は何と言っても画質の安定感と機械的信頼性である。焦点0.5mmのX線管と高品位センサーにより、コントラストが高くメリハリの利いた画像が得られる。軟組織と硬組織の境界が明瞭で、例えば上顎洞の粘膜肥厚や骨の菲薄化なども捉えやすい。撮影モードも基本をしっかり押さえ、標準/小児/顎関節/TMJ開閉口/前歯部高精細など臨床で欲しいプログラムが揃う。特に前歯部高精細モードでは断層幅を薄くし、切歯部の重なりやボケを低減する工夫がなされている。車いす対応設計もされており、装置自体の上下可動範囲が広く、全ての患者にやさしいユニバーサルデザインだ。
OP 2Dの価格は中堅クラス(500万前後)で、欧米のプレミアムブランド機としては比較的手に届きやすい部類だ。これには近年の市場競争でKaVo/DEXIS陣営が価格戦略を見直した背景もある。機械の耐久性が高く長く使えるため、一度購入すれば少なくとも法定耐用年数(6年)以上は大きな追加投資なく働いてくれる。ランニングコストは、デジタルゆえ消耗品はほぼ無いが、念のため数年ごとの予防保守点検をしておけば10年選手も夢ではない。ROIの観点では、派手な新機能で直接収益を生むタイプではないが、トラブルフリーで診療を止めないことが最大の貢献と言える。まさに黒子的存在で、知らず知らず医院経営を支えてくれるだろう。OP 2Dは「実績のあるブランドで安心したい」「奇をてらうよりオーソドックスな方が良い」という院長に適した製品だ。もし将来CTが必要になった場合は上位のOP 3Dなどに買い替える道があるが、2Dパノラマ単体としての完成度は非常に高く、導入後の満足度も高い傾向にある。患者説明時にも「これは世界で最初にパノラマを作ったメーカーの最新機種ですよ」といったエピソードを交えれば、話のタネになり信頼感もアップするかもしれない。
VistaPano S(デュール/エアテクニック)革新的S-Pan技術で簡単シャープ画像
VistaPano Sはドイツのデュールデンタル(Dürr Dental)社が開発したデジタルパノラマ装置で、米国ではAir Techniques社からProVecta S-Panとして提供されているモデルである。最大のセールスポイントはその名にあるS-Panテクノロジーで、撮影された数百層もの断層画像データから、各部位で最も鮮明な像を自動抽出・合成するという高度な画像処理を行う。これにより、術者が意識せずとも常に鮮明なパノラマ写真が得られるというわけだ。例えば患者の顎位が完全には合っていなくても、S-Panアルゴリズムが複数断層の中から最適ピントの部分を継ぎ合わせるため、結果として全歯列にピントが合ったような画像になる。これはデュールが長年培ってきた画像処理技術の賜物で、ユーザーからは「とにかく写りがシャープ」「誰が撮っても安定した画像品質」と評判が良い。撮影自体も7秒程度と高速で、8インチの操作タッチパネルからワンタッチでモード選択ができるなど、使い勝手の良さにも定評がある。オプションのCephモデルでは4秒程度のセファロ撮影も可能で、ヨーロッパを中心に矯正歯科からも支持を集めている。
経営面でVistaPano Sがもたらすメリットは、画像品質の平準化による効率アップである。どのスタッフが撮影しても一定以上の鮮明さが保証されるため、撮り直しが激減する。撮り直しは被ばくの増加や患者の不信感にもつながるため、ゼロに近づける意義は大きい。また説明用の画像編集もほぼ不要で、撮って出しの画像をすぐ患者に見せられるので説明時間により多く充てられるだろう。価格は中程度(400〜600万円)で、本機の高度な自動処理を考えれば費用対効果は高い。ドイツ製品らしく造りがしっかりしており、メカの耐用性にも定評がある。デュール/エアテクニックは日本でも販売代理店経由でサポートが受けられるが、国内シェアはまだ大手ほどではないため、サービス拠点の場所など事前に確認しておくと安心かもしれない。VistaPano Sは「画質調整や失敗撮影に悩まされたくない」「誰が操作しても一定品質にしたい」という医院に特に向いている。複数ドクター・スタッフが交替で撮影するような大型診療所や、分院展開で均一な診療クオリティを目指す法人などには、強力な“画質の自動番人”となってくれるだろう。
X-Mind prime(アクトエオン)小型軽量で必要十分、CT拡張も可能
X-Mind primeはフランスのアクトエオン(Acteon)社が開発したパノラマX線装置で、壁付け型としては世界最軽量級というユニークな特徴を持つ。2Dパノラマ専用モデルと、3D CBCT対応モデル(X-Mind prime 3D)があり、2Dモデルでも後から3Dモジュールを追加可能な設計となっている。重量はわずか約66kg程度で、標準的な歯科用ユニットの背面やユーティリティスペースに省スペースで設置できるのが魅力だ。工事も比較的簡易で済むことから、小規模な診療所や移転・増設の多いチェーン歯科で採用例が増えている。画質面では最新のCMOSセンサーと適応型フィルターによって、コンパクトでも高画質を実現している。ヨーロッパの独立系ユーザーレビューでは「サイズから想像するよりずっとクリアな画像」と評価されており、基本的な診断には全く問題ないクオリティといえる。さらにActeonは歯科用超音波やカメラでも知られる企業で、X線装置にもそのノウハウを活かしエコな被ばく制御や直感的なソフトUIを実装している。
経営面では、X-Mind primeは初期費用と設置コストの低さが際立つ。壁掛けゆえ床工事が不要になるケースもあり、クリニック改装時にも導入しやすい。価格も2Dモデルなら400万円台と手頃で、スタートはパノラマで将来的にCTを…というOrthophos SやProMaxに近い戦略を、より低予算で実現できる。もっとも、FOV(撮影視野)は小型ゆえCTにしても8×8cm程度と限定的なので、本格的な広範囲CTが欲しい場合には物足りない可能性はある。その分、無駄を省いて価格に反映していると言えるだろう。X-Mind primeは「省スペースクリニックや訪問歯科で使いたい」「将来的に機能追加できる柔軟な機械が欲しい」ニーズに応える。特にユニット増設が難しい医院でも壁に取り付け可能な利点は大きく、レントゲン専用室を確保できないような都会のテナント診療所でも導入しやすい。CTモジュールを載せてもコンパクトさは健在なので、インプラントガイド作製用に小さなCTが欲しいといった場合にも好適だ。Acteonは日本でも知名度が上がりつつあり、サポート体制も年々整備されてきている。X-Mind primeは、必要な機能を必要なときにという合理的発想で作られた装置であり、設備投資を段階的に進めたい医院の良き相棒となるだろう。
I-Max(Owandy)ゼロフロアスペースを実現した壁掛けパノラマ
I-MaxはフランスのOwandy社製のデジタルパノラマX線装置で、「世界で一番軽いパノラマ」というキャッチコピーを持つ製品である。その最大の特徴は、まるで口腔内X線のように壁に直接設置するワイヤーマウント式で、床面積を一切占有しない点にある。重量も60kg台と非常に軽く、一般的な壁に補強を施せば取り付けが可能だ。これは特に、小規模クリニックやスペース効率が重要な都市部診療所で威力を発揮する。実際、「レントゲン室を用意できなかったがI-Maxなら診療室の片隅に付けられた」という導入例が欧州で報告されている。画質は最新のCMOSセンサーにより、標準的なデジタルパノラマと遜色ない。壁掛けで多少揺れが心配な向きもあるが、撮影時はしっかりと固定アームが支え、安全性に配慮されている。Owandyはソフトウェアインテグレーションにも力を入れており、クリニックの既存電子カルテや画像管理ソフトとの連携も柔軟だ。クラウド経由でどの端末からでも画像参照できるシステムなど、IT面で先進的な試みをしているメーカーでもある。
I-Maxの経営上のメリットは、導入コストの低減と省スペースによる診療効率向上である。床に据え置きタイプではないので、レントゲン専用チェアやスペースを用意しなくても患者を座らせて撮影できる。つまり、本来ユニット1台分使うところを壁だけで済むため、空いた床面積を他の用途(ユニット増設や器材配置)に充てられる。これは坪数あたり家賃の高い都市部では経済効果が大きい。また、I-Max自体の価格も低〜中価格帯(300〜500万円)とリーズナブルで、壁掛け設置工事を含めても全体コストはかなり抑えられる印象だ。デメリットとしては、日本国内でのシェアが高くないため情報や実績が少なく、サポートは代理店経由になる点がある。しかしOwandyは世界的には30年以上の歴史あるブランドで信頼性も確立されている。I-Maxは「物理的制約をクリアしてレントゲンを導入したい」場面において力を発揮する。例えば開業医でなくとも、大学病院の分室や検診センターなど限られた一角に仮設的にX線を置きたい場合などにも有用だろう。工夫次第で空間を生み出し、なおかつデジタル化の恩恵を享受できる点で、非常にニッチだが刺さる医院には刺さる一台である。
よくある質問(FAQ)
Q1. デジタルパノラマとフィルムパノラマではそんなに差がありますか?
A1. はい、画質・効率ともに大きな差がある。デジタルは解像度が高く画像調整も自在なため診断精度が上がる。また現像不要で撮影後すぐ表示できるため患者待ち時間が減り、フィルム代や廃液処理コストもゼロになる。被ばく量もデジタルの方が低減できる傾向がある。総合的に見て現在新規導入するならデジタル一択である。
Q2. パノラマレントゲンだけで歯の根や細部まで診断できますか?
A2. パノラマは広範囲を一度に写せるが、細部解像度は口内法X線(デンタル)の方が上である。そのため根管の細かな形態や微小な根尖病変、初期の歯槽骨吸収などはデンタル撮影やCTが必要な場合も多い。ただし最近のパノラマ装置は焦点合成や高解像モードでかなり細部まで写るようになってきており、適切に使えば補助診断には大いに役立つ。
Q3. セファロ付の装置を導入すべきか迷っています。矯正専門ではないのですが…
A3. 一般開業医で日常的に矯正治療や外科的診断をしないのであれば、無理にセファロ付を選ぶ必要はない。セファロ付きは価格が100〜300万円上乗せとなり、保険算定も限られるためROIが低くなる。ただ今後矯正歯科との連携や自院矯正を拡大したい意向があるなら初めからセファロ対応機を選んでおくと追加投資なく始められる。現在の診療内容と将来計画で判断すると良い。
Q4. 中古のパノラマ装置を検討中ですが注意点は?
A4. 中古品は初期費用を抑えられるメリットがある反面、耐用年数や保守の問題がある。X線装置は特定管理医療機器なので譲渡時の手続きやメーカーのサポート継続可否を確認する必要がある。またデジタル機器の場合、古いとパソコンやソフトが現行OSに対応しない恐れもある。中古購入時は信頼できる中古業者から買い、できればメーカー点検済みの商品を選ぶ。総合的には、よほど予算が厳しい場合を除き新品導入をおすすめしたい。
Q5. パノラマ装置の耐用年数はどのくらい?買い替えのサインはありますか?
A5. 法定耐用年数は5〜6年だが、実際には10年前後使っている医院も多い。買い替え時期のサインとしては、画像センサーの劣化による画質低下や、頻発する故障・修理対応が挙げられる。またソフトウェアのサポート切れや新OS非対応で運用に支障が出るケースも増えてくる。画質が明らかに他院より劣る、修理費が嵩む、と感じたら買い替え検討のタイミングと言える。技術進歩も早い分野なので、最新機種への更新で得られるメリット(被ばく低減や診断能向上)も踏まえて判断すると良い。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- パノラマ
- 歯科のパノラマレントゲンおすすめ15選を徹底比較!比較のポイントから各製品の特長、値段などを解説!