- 歯科機材の比較なら1Dモール
- パノラマ
- 歯科のパノラマレントゲン「オルソパントモ」とは?分かること・被ばく量・CTとの違い
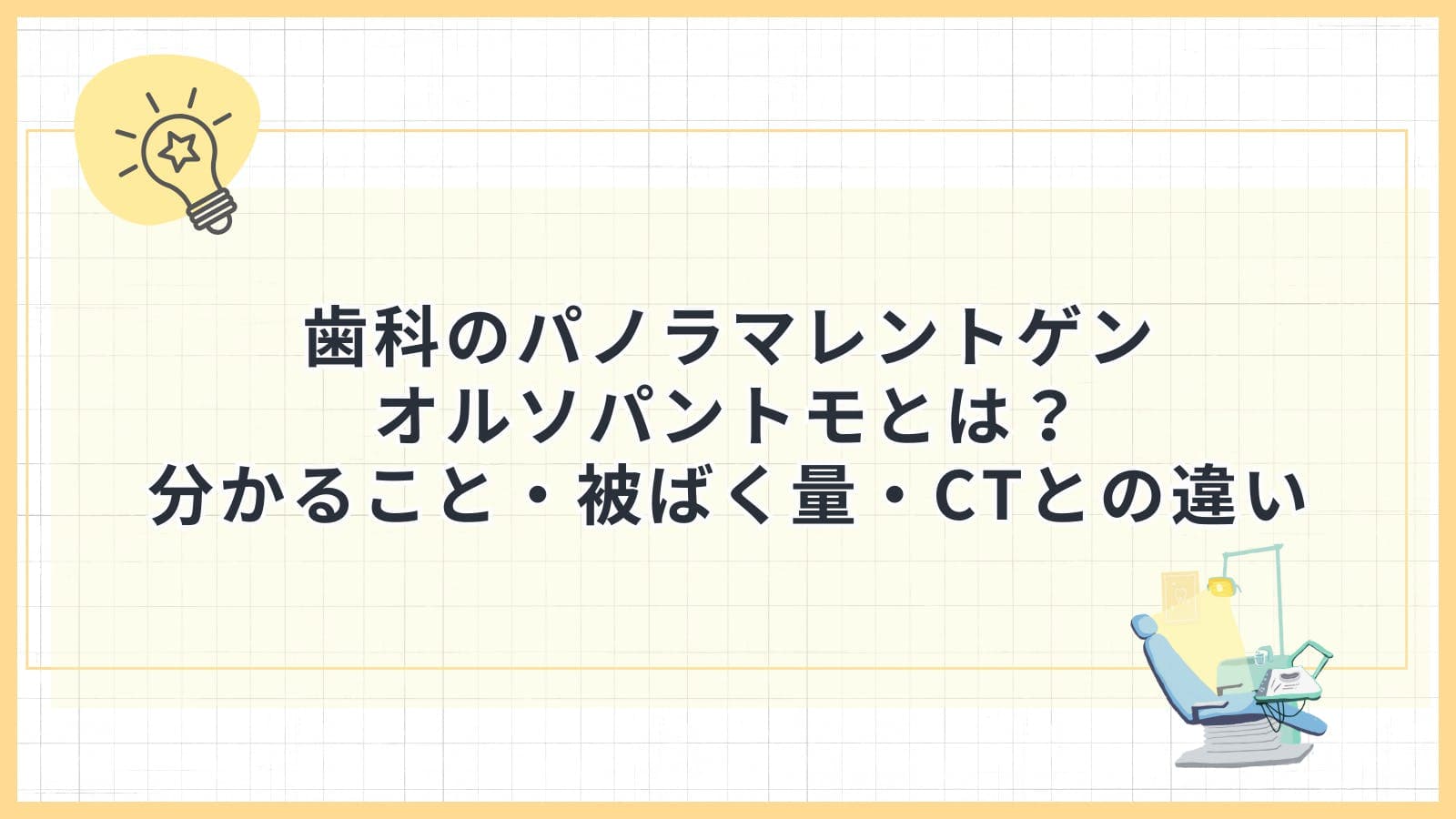
歯科のパノラマレントゲン「オルソパントモ」とは?分かること・被ばく量・CTとの違い
日々の臨床で、埋伏智歯の抜歯時にパノラマレントゲンだけでは下顎管との位置関係が読み切れず、判断に迷った経験はないだろうか。あるいは、インプラント埋入直前になって骨の幅が足りないのではと不安になり、冷や汗をかいたことがあるかもしれない。
パノラマレントゲン(オルソパントモとも呼ばれる)は歯科診療に欠かせない基本装置であり、上下顎全体の状態を一枚の画像で迅速に把握できる。う蝕や歯周病の診断から埋伏智歯の位置確認、顎骨の嚢胞・腫瘍の発見まで広く活用され、被ばく線量も比較的少なく安全性が高い。しかし2次元画像であるがゆえに、骨の正確な厚みや神経・血管の立体的位置関係など重要な情報は写し出せない。
その限界を補うのが歯科用CT(コーンビームCT)である。3次元画像によってインプラントの術前シミュレーションや難症例の診断が飛躍的に精密化し、より安全な治療計画が可能となった。一方で、歯科用CTの導入には数千万円規模の投資が必要で、限られた予算や診療スペースの中で「本当に必要だろうか」「導入して採算は合うだろうか」と悩む開業医も少なくない。
本記事では、歯科臨床と医院経営の両面からパノラマレントゲンと歯科用CTを徹底比較し、それぞれの強みと弱みが診療成績や収益に与える影響を分析する。さらに、機器選定の判断基準や投資回収の考え方についても考察し、読者が自身の診療スタイルに最適な選択を下せるようサポートする。パノラマとCTの使い分けに悩む先生にとって、本記事が臨床的ヒントと経営戦略の両面で指針となり、投資対効果(ROI)最大化の一助となれば幸いである。
パノラマレントゲンと歯科用CTの違いについて比較表
まず、パノラマレントゲン(パノラマ)と歯科用CT(CT)の主な違いを一覧表で確認しよう。臨床的な性能に加え、コストや時間効率といった経営面の指標も含めて整理する。
| 比較項目 | パノラマレントゲン | 歯科用CT |
|---|---|---|
| 画像の次元 | 2次元(平面)画像 | 3次元(立体)画像 |
| 撮影視野 | 上下顎全体を一度に撮影 | 顎骨・歯を立体的に撮影(部位により撮影範囲を選択可能) |
| 確認できる情報 | 歯・歯根、顎骨の大まかな構造と病変の有無 | 歯・顎骨の詳細構造(骨の厚み、神経や血管の位置関係など) |
| 主な用途 | う蝕・歯周病の診断、埋伏智歯(親知らず)の位置確認、顎骨病変のスクリーニング | インプラント計画、難抜歯の事前診断、根管治療の難症例評価、顎関節・嚢胞の精密診断 |
| 放射線被ばく量 | 約0.03 mSv(非常に低い) | 約0.1 mSv(パノラマ比で高いが医科CTより低い) |
| 機器の価格帯 | 約300万〜600万円 | 約800万〜1,500万円以上 |
| 保険算定(診療報酬) | 1回あたり約1,000〜2,000点(※約4,000〜8,000円) | 条件下で算定可:1回約3,000〜5,000点(※約12,000〜20,000円) |
| 患者負担額(3割負担) | 約1,200円程度 | 約3,500円程度(保険適用条件時) |
| 撮影所要時間 | 約10〜15秒/回 | 約10〜20秒/回 |
| 操作・画像解析 | 操作は簡便。得られる画像もシンプルで解釈しやすい | 画像データ量が多く、専用ソフトによる解析に時間と知識が必要 |
| 患者への説明容易性 | 平面写真のため患者には状況をイメージしづらい場合がある | 立体画像により患者自身も直感的に状態を理解しやすい |
| 経営面のメリット | 導入コストが低く、日常診療で常用(全患者にルーチン撮影可能) | 高度診療(インプラント等)による自費収入増や差別化に寄与 |
※注: 被ばく量は代表的な設定時の値であり、機種や撮影条件により変動する。また保険点数は2025年時点の概算で、適用条件によって算定可否が異なる。
パノラマレントゲンとCTの違いとは?
画像から得られる情報量と診断精度の差
パノラマレントゲンは2次元の平面画像で歯列全体を把握できるが、得られる情報は大まかな概形に留まる。歯や歯根の位置関係、顎骨の輪郭、う蝕の広がりなどは把握できるものの、骨の厚みや神経の正確な走行位置までは読み取れない。例えば下顎管と親知らずの位置関係はパノラマでは重なって見えることが多く、術者の経験と勘に頼らざるを得ない局面もある。
一方、歯科用CTは3次元画像により情報量が飛躍的に増加する。断層画像から骨の高さ・幅、神経管や副鼻腔との位置関係、歯根の形態や内部構造(根管形態、破折線など)まで詳細に観察可能である【※】。これにより診断精度が向上し、見落としや誤診のリスクが減少する。臨床的には、CT画像があることでインプラント埋入位置の微調整や骨造成の要否判断が正確に行え、難治性の根管治療でも追加の根管や病変を発見しやすくなる。結果として再治療の発生や術中合併症を減らせるため、患者満足度の向上と長期的な医院の信頼獲得につながる。
診断精度の差は医院経営にも影響する。精密な診断に基づく治療は成功率が高く、治療保証コストやクレーム対応に追われるリスクを低減する。また、CTを駆使した高度診断を提供すれば、「しっかり診てもらえる歯科医院」という評判が立ち、紹介やリピートにも結びつくだろう。ただし、CT画像の読影には専門知識と時間を要する。装置を導入したからといって活用しきれなければ宝の持ち腐れである。十分なトレーニングを積み、読影力を身につけてこそ、CTの高精度診断が真に医院の強みとなる。
※医科用CTと比べると歯科用CTは軟組織の描出には適さないが、歯・骨など硬組織の高解像度画像が得られるよう最適化されている。
放射線被ばく量と安全性
放射線による被ばくは患者にとって不安材料になりやすいポイントであり、安全性の観点から無視できない。パノラマレントゲン1回の被ばく線量は概ね0.03ミリシーベルト程度とされ、歯科の画像診断の中でも極めて低い部類である。これは自然に浴びる放射線(日本の年間自然被ばくは約1.5ミリシーベルト)のごく一部で、患者への負担はごくわずかである。
歯科用CTの被ばく線量は1回あたり約0.1ミリシーベルト前後と、パノラマよりは高いものの、それでも医科用CTスキャン(頭部で数ミリシーベルト級)に比べれば桁違いに低線量に抑えられている。コーンビームCTは照射範囲が限局され、必要最小限の線量で済む設計だからである。したがって適切な用途で限定的に使用する限り、歯科用CTも安全性は高いと言える。実際、現在の歯科用CTは低被ばくモードの搭載やパルス照射制御など技術改良が進み、小児や妊婦への配慮が必要な場合でも必要最低限の線量で撮影可能である。
安全性という観点では、放射線量だけでなく診断・治療の安全性も見逃せない。パノラマのみで手探りに治療を行うより、CTで解剖学的構造を把握しておく方が圧倒的に安全な処置が可能である。例えばインプラント埋入や埋伏歯抜歯では、CTで神経管や骨の状態を確認することで、偶発症(神経損傷や穿孔)のリスクを最小限に抑えられる。これは患者の安全だけでなく、術者にとってのリスク管理という意味でも大きなメリットだ。一方で、CT撮影は必要性がある場合に限り行うというのが原則である。不要なケースまで漫然とCTを撮影すれば、わずかとはいえ被ばく量を積み重ね患者の不信を招く可能性がある。被ばくリスクと診断メリットを天秤にかけ、適切な使い分けをすることが肝要である。
医院経営の視点でも、安全性は信用に直結する重要事項である。低被ばくであること、そして安全確実な治療に繋がることを患者に丁寧に説明できれば、最新設備への投資は医院の信頼ブランドを高める資産となるだろう。
導入コストとランニングコストの比較
歯科用レントゲン機器は高額な設備投資となるため、導入コストと維持費もしっかり把握しておく必要がある。パノラマレントゲンの新規導入費用はメーカーやモデルにもよるが、おおよそ300万〜600万円程度が相場である。これに対し、歯科用CTはスペックによって幅が大きいが、800万〜1500万円以上とパノラマの2〜3倍以上の初期投資を見込む必要がある。さらに、セファロ(矯正用頭部X線)撮影機能を追加する場合はパノラマ装置にプラス100〜300万円ほどの追加費用が発生することが一般的だ。
初期費用以外にもランニングコストを考慮しなければならない。パノラマ・CTいずれもデジタル機器である以上、撮影用センサーやX線管球の寿命、定期点検が必要となる。年間の保守契約料は各社概ね20万円前後で、数年に一度は部品交換やソフトウェアのアップデート費用もかかる。また、防護工事など設置環境への投資も無視できない。特にCTは本体重量が重く(200kg前後になる機種もある)床補強が必要な場合や、従来のレントゲン室に収まらずレイアウト変更を伴う場合がある。そのため導入時には本体価格だけでなく、工事費や付帯設備費も含めた総費用を算出しておくことが重要だ。
両者のコスト差は明確だが、近年はパノラマとCTの複合機も登場している。1台でパノラマ撮影とCT撮影の両方に対応できるモデルで、スペース効率に優れる反面、価格も中間的(パノラマ単体より高額だがCT単体よりは安い)な設定になっている。将来的にCT導入を視野に入れているなら、まずパノラマ・CT兼用機を導入し、徐々にCT活用を増やすという戦略も考えられる。
最後に資金調達面では、購入かリースかという選択肢もある。購入の場合は高額だが資産計上でき、減価償却による節税効果も得られる。リースの場合、初期負担を軽減できる反面、長期的には総支払い額が割高になることも多い。自治体によっては開業時の設備投資に対する補助金制度もあるため、情報収集と計画的な資金繰りが大切である。
投資対効果と収益への寄与
次に、導入した機器がどれだけ収益に貢献するか、投資対効果の視点で比較する。パノラマレントゲンは保険診療の基本検査として頻用され、1回撮影ごとに診療報酬(約1,000〜2,000点)が算定できる。患者の自己負担はわずかで拒否感も少なく、初診患者には必ずパノラマ撮影を行うという医院も多いだろう。つまりパノラマは日常診療の中でコンスタントに収益を生み出す設備であり、その投資回収期間は比較的短い。購入費500万円の機器でも、保険算定を積み重ねれば数年で元を取ることは十分可能である。
一方、歯科用CTは適用症例が限られるため直接の収益機会は少なめだ。保険適用できるケース(埋伏歯の診断や顎関節症の評価など)は限られ、多くのインプラントや自費診療でのCT撮影は診療報酬上は算定できない。ただし、自費診療の場合はCT撮影料を患者に負担いただく(例えば1回1万円〜2万円の撮影料を自費治療費に上乗せする)ことが一般的で、その分が収入となる。またCTがあることで高額な自費治療(インプラント、再生療法、矯正治療など)を安心して提供できるようになるため、間接的な収益拡大効果は大きい。例えば、これまでインプラント症例を他院に紹介していた医院が自院でCTを導入すれば、術前診断から埋入手術まで一貫して行えるようになり、新たな収益源を獲得できる。
ROIの観点では、年間どれだけCTを活用できるかがカギとなる。仮にCT装置導入に1,000万円かかったとしても、年間に数十件のインプラントや難症例治療を成立させ、その売上増で5年程度で投資回収できれば理想的だろう。具体的には、インプラント1本が約30万円の利益を生むとして年間20本増やせれば600万円、CT撮影料収入も含めれば5年弱で回収計算になる。一方、症例数が少ないにもかかわらずCTを導入すると、減価償却費や維持費の負担が大きく、ROIが低下する。このため、CT導入の判断は自院の症例ボリュームと今後の展開を見据えて行う必要がある。 現状インプラントを年数件しか行っていない場合は、まずは必要時に撮影センターや大学病院に患者を紹介し対応する方法も現実的である。しかし高度診療を自院の柱に据えていきたい方にとって、CTは安全性と信頼性を担保しつつ収益拡大を図るための欠かせない投資といえる。
また、ROIには数値化しにくい要素としてマーケティング効果もある。最新のCTを導入しホームページや院内掲示でアピールすれば、患者に安心感を与え、新規来院の動機になることもある。「インプラントならCTのある医院で」と考える患者心理を捉えれば、装置自体が集患ツールとなり得るわけだ。反面、宝の持ち腐れになれば単なる経費でしかないので、導入後は積極的に活用し、自費診療メニューを拡充するなど設備投資を収益化する工夫が求められる。
診療ワークフロー・時間効率への影響
設備導入は診療フローにも変化をもたらす。パノラマレントゲンは撮影自体が短時間(10秒程度)で終わり、撮影後すぐに画像が得られるため、診察中のフローを妨げない。歯科衛生士や助手でも操作習得が容易で、患者をレントゲン室に誘導してサッと撮影し、戻ってくるまで数分と経たない。その意味でチェアタイムへの影響はごくわずかである。撮影画像の解釈も歯科医師にとって日常診療の一部であり、特段の時間追加は発生しない。
歯科用CTの場合、撮影自体の所要時間はパノラマと大差ないものの、その前後の工程や診断に要する時間が増加する傾向がある。まず撮影前には、金属アーチファクトを減らすために義歯や金属製の仮歯を外す、患者の頭部をしっかり固定する、といった準備が必要だ。撮影後も、得られた多数の断層画像から所見を読み取るために、歯科医師がパソコン上で数分〜十数分かけて解析を行うケースが多い。特に初めてのCT導入直後はソフトウェアの扱いに慣れず、診療全体のスピードが落ちる可能性がある。
しかし、適切にワークフローに組み込めばCTはむしろ時間短縮につながる場面もある。 例えば、これまでパノラマとデンタルX線を何枚も組み合わせて確認していた複雑な症例が、CT1回の撮影で必要情報をすべて網羅できれば、トータルの撮影回数は減る。外部の医療機関にCT撮影を依頼して結果を待っていたような場合には、院内で即日撮影・診断できることで治療開始までのリードタイムを大幅に短縮できる。患者にとっても紹介先へ足を運ぶ手間が省け、当日のうちに詳しい説明を受けられるメリットがある。
院内コミュニケーションの観点でも、CT画像は有用である。スタッフ間で情報共有しやすく(たとえばデジタルモニターに3D画像を表示しながら症例検討できる)、術者のイメージを他のスタッフが理解しやすい。これによりチーム医療の精度が上がり、処置の段取りやアシストが円滑になる効果も期待できる。
もちろん、CT導入後のワークフロー構築にはスタッフ教育と役割分担の見直しが不可欠だ。撮影自体は従来のレントゲンと似ていても、その後のデータ処理やファイリング、患者への説明資料作成など、新たに発生する業務もある。これらを効率的に運用するために、画像管理ソフトと電子カルテの連携を図ったり、CT画像の所見入力テンプレートを用意したりといった工夫も求められるだろう。
総じて、パノラマは迅速さと手軽さで日常診療の流れを支え、CTは一部の高度診療で時間をかけた精密診断を可能にするツールと言える。両者を適材適所で使い分け、診療効率と品質のバランスを取ることが重要である。
代表的な歯科用パノラマ・CT装置の特徴比較
現在、日本国内では多くのメーカーからパノラマレントゲンおよび歯科用CT装置が販売されている。ここでは、その中から代表的な製品をいくつか取り上げ、それぞれの特徴をレビューする。各製品のスペック上の強みと弱み、そしてどのような診療スタイルの歯科医師に適しているかを解説する。
Veraview X800(モリタ) / 高精細撮影を実現するオールインワンCT
国内メーカーであるモリタのVeraview X800は、パノラマ・CT・セファロ撮影を1台でこなすオールインワンのフラッグシップ機である。最大直径17cmの広範囲撮影から最小径3cmの局所高精細撮影(エンドモード)まで多彩なFOV(撮影範囲)を選択でき、インプラントから精密根管治療まであらゆる用途に対応可能だ。画質は日本トップクラスと評され、微細な骨梁や根尖病変も鮮明に描出する。これは解像度の高いフラットパネルディテクタや0.125mmボクセル相当の撮影モードなど最新技術によるもので、肉眼では捉えられないレベルの情報を提供してくれる。
Veraview X800はユーザビリティにも優れている。撮影時の自動位置合わせ機能や、車椅子対応の昇降構造など、臨床現場の細かなニーズに配慮した設計だ。さらに撮影後の画像処理も高速で、モリタ独自の画像ソフトウェアによりインプラントプランニングや神経管の自動表示などがスムーズに行える。デジタル印象やCAD/CAM機器との互換性も確保されており、他社システムとのデータ連携も良好である。
弱みとしては、装置価格がおよそ1,000万円前後〜1,500万円と非常に高額な点が挙げられる。また機能が豊富な分、操作メニューも多岐にわたり、すべてを使いこなすにはそれなりの習熟が必要だ。エンドモードなど特殊撮影を活用するには撮影条件の微調整知識も求められる。
この製品は「質にこだわる歯科医院」に最適である。インプラントはもちろん、マイクロスコープ併用の精密歯内療法や再生治療など、ハイエンドな診療を提供する際に真価を発揮する。予算に十分な余裕があり、国内最高水準の画像診断能力を武器に診療の付加価値を高めたいと考える開業医にとって、Veraview X800は頼もしいパートナーとなるだろう。
Axeos(デンツプライシロナ) / 大視野と先進機能を備えたフラッグシップCT
デンツプライシロナ社のAxeosは、ドイツ発の最上位クラス歯科用CTであり、その特徴は広い撮影視野と高画質にある。最大で顎顔面全体をカバーする大径FOVに対応し、埋伏歯の位置把握から顎変形症の術前評価、さらには気道や副鼻腔の観察まで1回の撮影で包括的に行える。画質も極めてシャープで、同社独自の画像処理技術により低被ばくモードでも骨の細部構造まで鮮明に捉えることができる。撮影モードは標準と高精細が選択可能で、用途に応じて解像度と線量のバランスを調節できる。
Axeosは患者にも配慮したデザインを採用している。頭部固定用のライトガイドや安定した顎台に加え、開放感のある構造で閉塞感や恐怖心を和らげる工夫がなされている。座位のまま短時間で撮影が完了し、高齢者や車椅子の患者でも負担が少ない。また、オプションでセファロ撮影ユニットを搭載可能で、矯正歯科領域の分析にも対応できる拡張性がある。
この機種の弱点としては、本体が大型であるため設置スペースの確保が課題となる点が挙げられる。重量も重く、床への固定や耐荷重のチェックが必要だ。価格帯はVeraview X800と同様に1,000万〜1,500万円以上と高額であり、資金計画をしっかり立てる必要がある。また輸入機器であるため、操作ソフトや表示が英語ベースになっている部分があり、慣れるまで戸惑うスタッフもいるかもしれない。
Axeosは「包括的な高度歯科医療」を掲げる医院にマッチする。インプラントと矯正治療の双方を手がけたり、口腔外科手術から顎関節症治療まで幅広く対応するクリニックにとって、広範囲かつ高精度の画像診断能力は大きな武器となるだろう。シロナ社のCAD/CAM(CERECシステム)やガイデッドサージェリーシステムとのデータ連携もスムーズで、デジタルワークフローを統合的に運用したい先生にも適した一台である。
Planmeca ProMax 3D(プランメカ) / 柔軟な撮影範囲と拡張性を持つ汎用型CT
フィンランドに本社を置くプランメカ社のPlanmeca ProMax 3Dシリーズは、柔軟な撮影オプションと将来的な拡張性が魅力のデジタルX線装置である。複数のモデルが用意されており、「Max」「Mid」「Plus」「S」など撮影範囲や機能の異なる構成からクリニックのニーズに合わせて選択できる。例えば、小規模の撮影範囲に特化したモデルで導入し、後にユニットを追加してフルスペック化するといった段階的アップグレードにも対応可能である。
ProMax 3Dは画像品質にも定評がある。独自のUltra Low Dose™撮影モードでは、被ばく線量を大幅に低減しながらも必要な診断情報を維持できる。また金属アーチファクト低減技術や、自動露出補正機能により、インプラント周囲や修復物がある症例でもクリアな画像を提供する。標準ではパノラマとCTに対応し、必要に応じて後からセファロ撮影ユニットを追加することで矯正用頭部X線にも対応可能だ。こうしたモジュール式の設計は、将来診療内容が広がった際にも機器を買い換えず機能追加できる点で経済的メリットがある。
ユーザーインターフェースは分かりやすく、日本国内ではKaVo経由で販売・サポートが行われているため、導入時のトレーニングやトラブル対応も安心だ。価格帯はモデルにより幅があるが、おおむね中〜高価格帯で、最高スペックのものは他社フラッグシップ機と同等クラスになる。低価格モデルであればCTとしては比較的手が届きやすい。
この製品は「段階的に設備充実を図りたい医院」に向いている。現在は小規模なインプラントや難症例が時折ある程度だが、将来的に自費治療を増やしていきたい、といった計画を持つ先生には、必要十分な性能を確保しつつ投資を抑えられる柔軟な選択肢となるだろう。また、海外製ながら国内代理店の手厚いサポートが受けられるため、初めてCTを導入する開業医にとってもハードルが低い。
注意点として、モジュール追加による拡張は後から可能とはいえ、その際には追加費用が発生する。初期にどこまでの機能が必要か、将来の構想と予算バランスを考え、過不足ない構成を選ぶことが重要である。
FineCube(ヨシダ) / コンパクトながら高精細な国産CT
ヨシダ製作所のFineCube(ファインキューブ)は、省スペース設計と高画質を両立した国産の歯科用CT装置である。名前のとおりキューブ状のコンパクトな本体が特徴で、レントゲン室の限られた空間にも無理なく設置できる。焦点スポット径0.2mmという高性能X線管球を搭載し、ボクセルサイズも小さく設定可能なため、骨細部や根尖の描出能力が高い。埋伏歯の位置関係や微小な根管の判断など、モリタやシロナの最上位機に比肩する解像度との評価もある。
FineCubeはパノラマ撮影機能も標準搭載しており、2D/3Dを用途に応じて切り替えて使用できるオールインワンタイプだ。操作インターフェースは日本語表示で直感的に扱いやすく、初めてCTを扱うスタッフでも短期間で習熟できるよう工夫されている。メーカーであるヨシダは全国にサービス網を持ち、導入時の講習から保守点検までサポートが手厚い点も心強い。
価格はCTとしては中程度(700万〜1,000万円前後)で、国内メーカー品としてコストパフォーマンスは良好と言える。国産ゆえ部品調達や修理対応も迅速で、万一のトラブル時にも診療への影響を最小限に抑えやすい。実際、ヨシダ製レントゲンは国内シェアも高く、多くの歯科医院で採用されている実績が品質の裏付けとなっている。
欠点を挙げるとすれば、撮影できる範囲(FOV)が直径8cm程度と限定されることである。上下顎を一度に撮影するには範囲外になる場合があり、その際は上下別々にスキャンする必要がある。また、高精細ゆえに撮影データ容量が大きく、保存用PCには十分なストレージと性能が求められる。
FineCubeは「小規模空間でのCT導入」を検討する医院や「初期コストを抑えつつ自費診療にも挑戦したい」開業医に適した一台だ。現在は保険診療中心でも、将来的にインプラントや難症例の治療を取り入れていきたいと考えるのであれば、無理のない投資額でCTのメリットを享受できるだろう。
AZ‐シリーズ/Solio XZII(朝日レントゲン) / 老舗メーカーによる高速撮影CT
朝日レントゲン工業は日本の歯科用X線装置メーカーの草分けであり、そのAZシリーズ(現行はSolio XZII)は信頼性の高い歯科用CTとして広く知られている。最新モデルのSolio XZIIでは新型フラットパネルセンサーの採用により画像の鮮明度が向上し、360度フルスキャン時でも撮影時間12秒(180度スキャンなら6秒)という短時間で高精細な3D画像を取得できる。撮影スピードが速いことは被写体ブレの軽減につながり、動きやすい患者(小児や高齢者)でもクリアな画像を得やすい。
朝日レントゲンのCTは、独自のCTポジションシステムによる頭部支持や、撮影後の画像処理アルゴリズムによるノイズ低減など、長年の開発蓄積が随所に活かされている。パノラマやセファロ撮影にも対応する一体型であり、同社製の過去のパノラマ装置から置き換える場合も操作感に違和感が少ない。国内大学や病院でも多数導入実績があり、その実証された耐久性と安定したアフターサポートは老舗メーカーならではの強みだ。
価格帯は上位機種ゆえに1,000万円近くと高めだが、その分、長期使用に耐える堅牢なつくりと、ソフトウェアの無償アップデート提供など運用面のメリットも大きい。全国をカバーするサービス拠点網により、定期メンテナンスだけでなく急な故障対応時にも比較的短時間で技術者が駆けつけてくれる体制が整っているのも安心材料である。
この製品は「信頼性重視で設備投資したい医院」に適する。特に、既に朝日製のパノラマを使用していて勝手が分かっている場合や、矯正歯科や口腔外科領域で高画質な3D診断を日常的に行いたい場合に威力を発揮するだろう。また、撮影スピードが速いため、1日に多数の撮影をこなす必要がある大規模医院や大学病院附属施設などにも向いている。
留意点として、他メーカーに比べ撮影後の画像表示インターフェースがやや専門的で、細かな調整項目が多いとの指摘もある。必要に応じて活用する機能を取捨選択し、スタッフ間でプロトコルを整備することで、機能の豊富さをかえって効率に繋げるよう工夫したい。
よくある質問(FAQ)
Q. オルソパントモとは何ですか?
A. オルソパントモ(オルソパントモグラフ)は、歯科用パノラマX線撮影装置のことである。もともとはパノラマレントゲン装置の商品名(Orthopantomograph)だが、現在では一般名称のように使われており、「パントモ」と略されることもある。要するにパノラマレントゲンと同義と考えて差し支えない。
Q. 歯科用CTは保険適用になりますか?
A. 限られたケースで保険適用が可能である。具体的には、「埋伏智歯(親知らず)の抜歯に関連した診断」「顎関節症の評価」「顎骨嚢胞・腫瘍の診断」「顎裂の評価」など、通常のレントゲンでは診断困難でCT撮影が真に必要と認められる場合に限り保険算定が認められている。それ以外(例えばインプラント治療や自費の矯正診断目的など)は保険適用外で、患者に自費負担してもらう形になる。保険適用となる条件下では、1回のCT撮影でおおよそ3,000〜5,000点(3割負担で約3,000〜5,000円程度)の診療報酬が算定できるが、適用範囲外の場合は算定できない点に注意が必要である。
Q. 医科用CTと歯科用CTの違いは何でしょうか?
A. 一般の医科用CTはファンビーム方式で身体の断層画像を撮影する大型装置であり、歯科用CT(コーンビームCT)は歯科領域に特化したコーンビーム方式の中型装置である。医科用CTは全身の軟組織や臓器まで写し出せ、高いコントラスト分解能を持つ反面、被ばく線量が高く装置も非常に大きい。一方、歯科用CTは撮影範囲を頭頸部(顎顔面)に限定し、歯や骨など硬組織の描出に最適化されている。解像度は歯科用CTの方が細かく、例えば歯のひびや根管の形態まで捉えられるが、筋肉や神経といった軟組織の識別能力は医科用CTに劣る。また歯科用CTは装置がコンパクトで、患者が座った姿勢のまま短時間で撮影できるなど、歯科診療所で扱いやすい設計になっている。総じて、歯や顎の評価には歯科用CTで十分であり、歯科医院で医科用CTが必要になるケースは特殊な病変の診断を除き多くない。
Q. インプラントを行うのにCTは必須ですか?
A. 法律上「必須」と定められているわけではないが、現代の標準的なインプラント治療においてCTによる事前診査は事実上不可欠である。パノラマレントゲンだけでも経験豊富な術者であれば対応可能な場合もあるが、顎骨の厚みや神経・血管の位置を正確に把握せず手術を行うことはリスクが大きい。CT撮影を行えば、インプラントの埋入位置・角度をシミュレーションでき、安全マージンを確保した治療計画を立案できる。結果として神経麻痺や上顎洞穿孔などの重大な偶発症を回避でき、患者にとっても術者にとっても安心材料となる。近年ではガイデッドサージェリー(サージカルガイドを用いた手術)も普及しているが、これもCTデータがなければ作成できない。以上のことから、インプラント治療を安全かつ確実に行うためには実質的にCTは必須と言ってよいだろう。どうしても院内にCTが無い場合は、提携先で撮影してもらうなど代替策を講じて万全の準備を整えることが望ましい。
Q. レントゲン機器は中古品やリースで導入しても大丈夫でしょうか?
A. 中古品やリースの活用も一つの選択肢であるが、それぞれメリット・デメリットがある。中古品の購入では初期費用を大幅に抑えられる反面、機器の劣化や保証の問題に注意が必要だ。特にCTは精密機器であり、旧世代の装置だと画像品質が最新機種に比べ見劣りすることもある。中古を検討する際は、信頼できる業者を通じて整備状況を確認し、メーカーの保守対応が受けられるか(既にサポート終了していないか)をチェックすることが重要だ。
一方、リース契約での導入は、初期投資を平準化できる利点がある。開業直後で資金に余裕がない場合でも月額リース料で最新機種を導入できるため、資金繰りの面では魅力的だ。ただし、リース期間の総支払額は本体価格の合計より高くつくのが一般的であり、中途解約ができない契約も多い。またリース会社によっては保守サービス込みのプランや代替機の無償提供など独自のメリットを付与している場合もあるため、内容をよく比較検討するとよい。
中古・リースいずれにせよ、耐用年数と今後のサポートを視野に入れて判断すべきである。レントゲン機器の法定耐用年数はおよそ5〜7年だが、実際には10年以上使用するケースも多い。将来的な買い替えサイクルも見据え、自院にとって最も負担の少ない調達方法を選んでいただきたい。なお、国や自治体の設備投資支援策(補助金・減税制度など)は新品購入のみ対象となる場合が多い点にも留意が必要である。中古やリースを含め、総合的に判断して適切な導入方法を検討しよう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- パノラマ
- 歯科のパノラマレントゲン「オルソパントモ」とは?分かること・被ばく量・CTとの違い