- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う「テンポラリーストッピング」とは?使い方や特徴・用途を分かりやすく解説
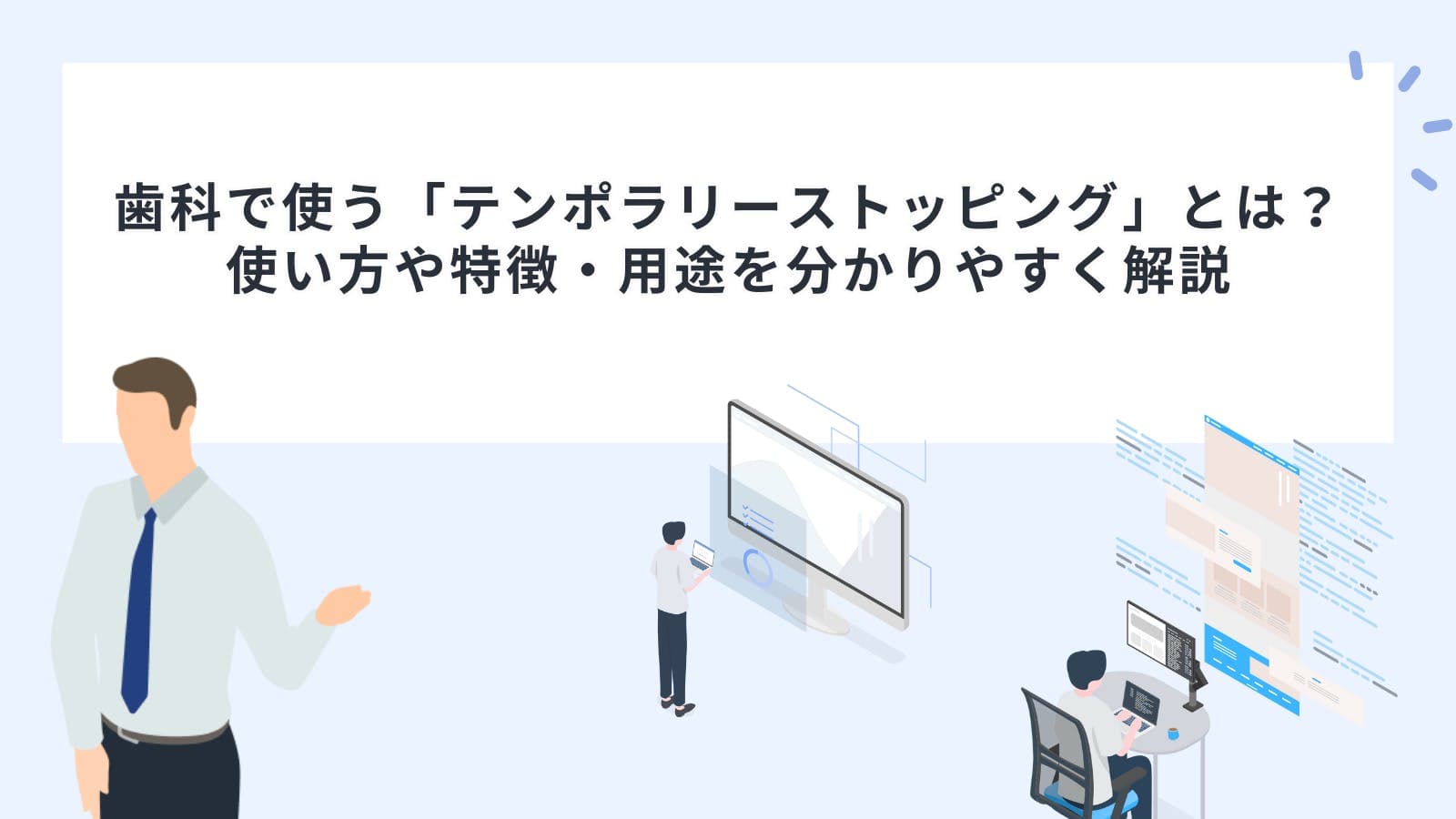
歯科で使う「テンポラリーストッピング」とは?使い方や特徴・用途を分かりやすく解説
歯内療法やう蝕の処置を進める中で、一時的な仮詰めが思わぬ落とし穴になる経験はないだろうか。根管治療で薬剤を貼薬した歯に仮封した材料が次回来院前に脱離し、再感染リスクに冷や汗をかいた――そんな場面を経験した歯科医師も少なくない。一見地味な仮封材であるが、その選択と使いこなし次第で治療経過や患者満足度、さらには医院の効率に大きな差が生まれる。
本稿では、日常的に使用される仮封材「テンポラリーストッピング」に焦点を当て、その臨床的な価値と医院経営への影響を検証する。臨床現場で培われてきた知見をもとに、使い方のコツや他材料との比較、導入判断のポイントを考察する。そうした情報により、読者が自身の診療スタイルに最適な製品を選択し、投資対効果を最大化できるよう指針を提示する。
テンポラリーストッピングとは?
テンポラリーストッピングとは、歯科治療において一時的な封鎖(仮封)を目的に使用される暫間修復材料である。むし歯の除去後や根管治療の途中で、次回の処置まで患歯を密閉し、唾液や細菌の侵入を防ぐために用いられる。一般的名称は「歯科用テンポラリーストッピング」で、管理医療機器として承認された製品である(クラスII)。歯科現場では単に「ストッピング」や「仮封材」とも呼ばれ、古くから日常診療に欠かせない存在となっている。
本製品は棒状の固形材料で、天然ゴム由来のガッタパーチャを主成分に、酸化亜鉛やワックス(パラフィン、蜜ろう等)を配合している。使用時には専用の器具や加熱した器具で材料を軟化させ、軟らかくなったところを窩洞や根管のアクセス洞に詰めて封鎖する。冷却後はゴム状に硬化して仮の蓋となり、次回来院時に除去して本復材料の充填や補綴処置に移行する。短期の仮封に適しており、数日から1〜2週間程度の暫間修復に広く用いられる。
テンポラリーストッピングは、複数のメーカー(松風、GC、東洋化学など)から発売されており、通常はホワイト・ピンク・イエローの3色展開で供給される。色調の選択により、複数歯への貼薬時に薬剤の識別や審美面への配慮が可能である。経済的な価格設定と使いやすさから、保険診療から自費診療まで幅広い診療形態で利用されている。
テンポラリーストッピングの特徴と臨床性能
テンポラリーストッピングの最大の役割は、患歯を外界から密閉するシーリング性能である。適切に窩洞に圧接されたストッピングは、唾液や細菌の侵入を抑え、処置間隔中の二次感染リスクを低減する。ただし本材自体は化学硬化型ではなく、硬化時にわずかな収縮が生じる可能性がある。そのため、完全な気密性を得るには術者の技術が重要であり、窩洞内を乾燥させ確実に充填することで高い封鎖効果を発揮する。短期間(数日〜1週間程度)の使用であれば、適切に装着したストッピングは十分な密閉性を維持できる。
機械的特性としては、硬化後も弾性を有するゴム状の硬さである点が特徴である。他の仮封材料と比べると圧縮強度や耐摩耗性は高くないが、その柔軟性ゆえに咬合圧に対して適度に緩衝作用を示す。窩洞形態によく適合して固着し、外力で割れたり崩れたりしにくいため、適切な厚みが確保されていれば日常的な咀嚼には耐えうる。また、不溶性の成分で構成されており、唾液中で長期間放置しても材料自体が溶解・流失しにくい。このため、予定より来院が遅れた場合でも仮封が失われてしまうリスクは比較的低い。ただし長期間(2週間以上)の放置や、窩洞形態が浅い場合には、咀嚼や清掃時の動揺で脱離する可能性があるため注意が必要である。
操作性の面でも優れた特徴を持つ。本材は常温で固形だが、50〜60℃程度に加熱すると軟化し可塑性を示す。器具に付着しにくい処方のため、指や器具にベタつかず扱いやすい。練和や化学反応を必要とせず、火や電熱器で数秒温めるだけで使用可能になるため、準備時間が短くチェアタイムの短縮に寄与する。窩洞内で素早く硬化(冷却)するので待ち時間もなく、仮封後すぐ次の処置に移行できるのも利点である。一方で火炎による加熱操作を伴うため、扱いに不慣れな場合は器具による軟組織の熱傷などに注意が必要である。
除去の容易さも臨床上の利点である。ストッピングは硬化後も完全硬質にはならず、一塊として除去できる。次回来院時にはエキスカベーターやピンセットで摘み取るように取り除ける。特に根管治療で仮封した場合、内部の綿栓や薬剤を汚染することなく、短時間でアクセス窩を再オープンできる。この撤去の容易さは再処置の迅速化につながり、患者の負担軽減と院内の回転率向上に寄与する。
なお、本材は歯髄診断の温度診にも利用される。小片にちぎったストッピングを炎で加熱し、発煙するほど熱した状態で歯面に接触させることで、歯髄の温度刺激に対する反応を見ることが可能である(いわゆる「スモークドストッピング法」)。冷刺激だけでなく温刺激の診査にも応用できる点で便利であり、歯髄の生活反応や炎症の程度を評価する手段として古くから活用されている。温度診に用いる際は、加熱しすぎた材料が軟組織に触れないよう細心の注意が必要である。
テンポラリーストッピングの使用方法と運用上のポイント
基本的な使用手順
テンポラリーストッピングによる仮封は、適切な手順と衛生管理のもとで行う必要がある。まず、仮封する部位(窩洞や根管のアクセス開口)を十分乾燥させ、唾液や湿気を除去する。次に、本材を必要量だけ清潔な器具で切り取り、専用のストッピングキャリア(または金属製スパチュラ等)にセットする。器具の先端をアルコールランプやバーナーの炎で数秒間あぶり、ストッピングを軟化させる。軟らかくなった材料を窩洞内に素早く押し入れ、平坦または僅かな窪みになるよう形態を整える。適度に圧接して気泡や隙間が入らないように注意しながら、噛み合わせの干渉が出ない高さに調整する。材料は数秒で冷却・硬化するため、成形後すぐに口腔内で安定した仮封蓋となる。
器具と衛生管理
ストッピング操作には、専用器具である「ストッピングキャリア」を用いると効率的である。キャリアは黄銅製の充填器具で、内部に材料を詰めて加熱し、先端から押し出して窩洞に充填できる構造になっている。使用前には必ずオートクレーブ滅菌し、使用中も唾液などで汚染しないよう注意する。キャリアがない場合でも、金属製のヘラや探針を代用し、その先端に付けた材料を加熱して運搬することも可能である。いずれの場合も、過度の加熱は避ける。20秒以上の連続加熱は材料の性質を損ない、歯髄や歯周組織に熱損傷を与える恐れがある。十分に軟化する温度になったら直ちに火から遠ざけ、器具を口腔内に導入する際は熱した金属が粘膜に触れないよう細心の注意を払う。また、軟化した材料は流動性があるため、一度に過量を運ばず徐々に充填し、軽い圧力で押し広げるように充填すると確実に適合させやすい。
ストッピング材料そのものは無菌ではないため、感染対策として取り扱いに工夫が必要である。大容量のブロックから直接患者に使用するのではなく、清潔なシート上に一回使用分を切り出して用いるとよい。万一余剰が出ても他患者には再利用せず廃棄する。材料の保管容器内に汚染が及ばないよう、器具やグローブで直接触れないことも大切である。
単一仮封と二重仮封
テンポラリーストッピング単体でも短期の密閉には有効だが、症例によっては他材との併用で仮封の信頼性を高めることができる。例えば、根管治療で次回までの間隔が長く開く場合や、唾液汚染を極力防ぎたい場合には、ストッピングと硬化型セメントを組み合わせた二重仮封が用いられることがある。具体的には、貼薬した根管の上に小さな綿球(綿栓)を置き、その上層をストッピングで緊密に封鎖する。ストッピングが冷却硬化した後、その更に上から酸化亜鉛ユージノールセメント(例: インターミディエートレストアラティブ材料)やグラスアイオノマーセメントを覆罩する。内層のストッピングが緊密性を担保し、外層のセメントが硬度と耐久性を付与することで、長期に安定した気密仮封が得られる。この二重仮封法により、根管内薬剤の漏出防止や咬耗への耐久性が向上し、特に数週間に及ぶ仮封期間が必要な場合に有効である。ただし、次回の処置時には二重の材料を順に除去する手間がかかる点に留意が必要であり、仮封期間が短い場合や頻回に通院できる患者では、単一仮封で十分なケースも多い。
仮封除去後の処置
本材を除去する際は、前述のように比較的容易に一塊で取り除くことができる。しかし窩壁に一部が付着して残留することもあるため、エアブローやエキスカベーターで細片を除去し、必要に応じてアルコール綿で拭擦して清掃する。特にコンポジットレジン修復や接着性レジンセメントによる最終修復を行う場合、仮封材の蝋分や酸化亜鉛の残留が接着強度に影響する可能性がある。テンポラリーストッピングはユージノールを含まず樹脂硬化阻害のリスクは低いものの、物理的な残渣はしっかり除去することが重要である。この点、IRMなどユージノール系仮封材に比べて、ストッピングは接着阻害成分を残さない利点があり、コンポジット修復との親和性が高いといえる。最終充填に先立ち、仮封除去後の窩洞を十分洗浄・乾燥し、必要であればエッチングやプライミングを行って接着面を整えることで、最終修復物の適合と長期予後を確実なものにできる。
テンポラリーストッピングの医院経営インパクト
コスト面から見ると、テンポラリーストッピングは極めて負担の小さい材料である。500g入り1函の価格は約10000円前後(市価、2025年現在)で、1症例あたり数十円程度と試算できる。1度購入すれば多数の症例に使い回せるため、材料費としての負担感はほとんどない。例えば、仮封を要する症例が月に50件あったとしても、本材の消費コストは月数百円規模に過ぎず、医院全体の経費に占める割合は微々たるものである。このため、コスト削減を目的に仮封材の質を落とすことは得策ではなく、むしろ治療の質や効率を優先して最適な材料を選ぶことが望ましい。
一方、時間と業務効率の観点では、本材の活用による恩恵が大きい。化学反応を要するセメント系仮封材と異なり、ストッピングは即時に硬化し次工程へ進めるため、各処置で数分の時短が可能となる。例えば、従来ZOE系セメントで仮封していた場面をストッピングに切り替えると、練和・硬化待ちの時間(通常1〜2分以上)を削減できる。1症例あたり数分でも、1日あたり多数の仮封処置があれば合計時間は無視できない長さとなる。蓄積された時間を他の処置や患者対応に充てることで、ユニット稼働効率が向上し、ひいては収益性の改善につながる可能性がある。
さらに、予期せぬトラブル対応の削減も経営面では重要である。仮封が不十分で処置間隔中に脱離・破損すると、患者から急患連絡が入り、予定外の対応に追われることになる。急患対応は他の予約診療の合間を縫って行う必要があり、スタッフの負担増やスケジュール遅延を招く。加えて、保険診療内での仮封処置や応急処置は収益面で大きなプラスにならないことが多く、いわば「持ち出し」の労力となりかねない。質の高い仮封材を用い適切に封鎖しておくことで、こうしたトラブルの発生率を下げ、無償の再処置や緊急対応に費やすリソースを削減できる。特に根管治療や保存修復では、仮封が失敗すると治療全体のやり直し(感染再発による再治療)につながるリスクもあり、患者との信頼関係にも悪影響を及ぼしかねない。ストッピングを用いて確実に仮封しておくことは、最終的に治療成功率を高め、再治療の抑制による長期的な経営安定にも寄与するといえる。
患者満足度の面でも、適切な仮封は医院の評価向上につながる。仮封が安定していれば処置間の痛みや違和感が少なく、患者は安心して次回まで過ごすことができる。逆に仮封脱離による疼痛や食片の侵入が起これば、患者の不満や不安が高まり、治療への信頼低下を招く恐れがある。丁寧な仮封とトラブルの無い経過は、患者に「しっかりした治療を受けている」という安心感を与え、リピート受診や紹介にもつながりやすい。わずかなコストの材料で患者体験を向上できる点は、費用対効果の高い取り組みといえるだろう。
以上のように、テンポラリーストッピングは低コストでありながら、院内の時間効率改善、無駄な再処置の削減、患者満足度向上といった多面的な経営メリットをもたらす。仮封材は脇役的存在ではあるが、その選択ひとつで最終的なROI(投資対効果)に影響を及ぼし得ることを念頭に置くべきである。
テンポラリーストッピングを使いこなすポイント
導入初期の注意点
テンポラリーストッピングを初めて使用する際には、器具の扱いと加熱操作に習熟することが重要である。臨床に投入する前に、模型や抜去歯で実際に軟化・充填する練習を行うとよい。加熱温度の目安や硬化までのタイミング、適切な充填量の感覚をスタッフ全員で共有しておくことで、本番の患者でスムーズに扱えるようになる。また、院内でアルコールランプやバーナーを使用する環境がない場合は、小型のガスバーナーや電気加熱器具を準備する必要がある。火気を扱う以上、消火器の設置や火の取り扱いに関するスタッフ教育も行い、安全対策を徹底しておく。器具の滅菌・洗浄手順についても事前に確認し、使い回しによる院内感染を招かないよう、使用後は毎回確実に滅菌処理をするルールを周知しておくことが大切である。
患者への声かけと説明
仮封後の患者には、仮封材が一時的なものである旨と注意事項をしっかり伝える必要がある。「今日は仮の蓋をしていますので、次回来院まで強い力を加えないようにしてください」といった声かけを習慣づけるとよい。具体的には、硬い食品(ナッツ、氷、硬いせんべい等)や粘着性の高い食品(ガム、餅、キャラメル等)は仮封が外れる原因となるため避けるよう指示する。また、神経のある歯を仮封している場合は、「熱い飲み物や冷たい風がしみる可能性がありますが、一時的な症状です」と説明し、必要以上の不安を与えないよう配慮する。デンタルフロスの使用についても、「仮封が取れないよう、フロスは横から引き抜くようにしましょう」とアドバイスするとよい。さらに、「もし仮詰めが取れてしまったら放置せず、ご連絡ください」と伝えておけば、患者は異変時に自己判断で放置せず早期に対処できる。
よくある失敗と対策
仮封材の扱いに不慣れなうちは、いくつかの典型的なミスが起こりやすい。例えば、窩洞が湿ったまま充填してしまい、接着力が弱くなって脱離しやすくなるケースがある。これは、防湿と乾燥が不十分だったことが原因であり、ラバーダムやロールワッテで確実に乾燥環境を確保することで防げる。また、材料を過剰に軟化させすぎると、逆に流動性が高まり操作しにくくなる。軟化のしすぎは避け、粘土状になる程度で火から下ろすよう心がけたい。充填後に咬合調整を怠ることも失敗につながる。高い仮封は患歯に余計な負荷をかけ、痛みや歯の破折リスクを高めるため、軽く咬合紙でチェックし必要に応じて除去・再充填や形態修正を行うべきである。さらに、除去時に窩洞内に一部残存させてしまうミスも散見される。特に深い窩洞では取り残しがないよう、目視と探針で丁寧に確認することが重要である。これらの失敗は、事前の注意と確認で防止可能であり、経験を重ねることで次第にスムーズに仮封処置を行えるようになる。
以上のポイントを踏まえて運用すれば、テンポラリーストッピングのメリットを最大限に引き出し、患者にもスタッフにも安心・安全な仮封処置を実現できるであろう。
適応症と適さないケース
テンポラリーストッピングは多くの場面で有用だが、万能ではない。症例が特に適している場合と、使用を控えるべき場合を整理する。
適応しやすい症例
次回までの間隔が数日〜1週間程度と短いケースでは、ストッピング単独で問題なく密閉を維持できる。例えば、う蝕除去後に軟化象牙質の経過観察を行うケースや、インレー形成後に次回まで仮封しておく場合など、短期の暫間封鎖に適する。
次に、根管治療中の仮封では、根管貼薬後のアクセス洞封鎖に広く用いられる。綿栓との組み合わせで容易に撤去でき、治療再開時に素早く根管に再到達できる利点がある。週1回程度の通院ペースで根管治療を行う一般的なケースでは、十分な気密性と利便性を発揮する。
また、接着修復を予定している症例では、ユージノールフリーのストッピングを使用することで仮封残渣による接着阻害のリスクを低減できる。そのため、接着操作への悪影響を最小限に抑えたい症例に向いている。
さらに、歯髄診断を目的とした経過観察症例でも、深いう蝕で直接覆髄を避け、一時的に封鎖して歯髄の反応を観察するような場合にも有用である。ストッピング自体には鎮静作用がないため、術後の自発痛や温度痛が残るか否かを純粋に評価しやすい。一方、ユージノールを含む仮封材では鎮痛効果により痛みが一時的に緩和され、歯髄の状態を正確に判断しにくくなることがある。
使用を避けた方がよい症例
まず、天然ゴムアレルギーの患者では、テンポラリーストッピングに含まれるガッタパーチャがアレルギー反応を引き起こす危険がある。過去にゴム製品でアレルギー症状を呈した患者には、本材の使用は禁止であり、樹脂系やグラスアイオノマー系など代替の仮封方法を選択すべきである。また、術者やアシスタントがゴムアレルギーを持つ場合も、加熱時に発生する揮発物に触れる可能性があるため使用は避けるべきである。
次に、仮封期間が2週間を超える長期に及ぶ場合や、歯冠部の大部分が失われている場合では、ストッピングのみでは強度・密閉性の維持に不安が残る。このようなケースでは、二重仮封やレジン仮封材、プロビジョナルクラウンなど、より耐久性の高い方法が適している。特に大きな欠損では機械的な保持形態が乏しく脱離しやすいため、接着性の一時充填材や補綴的アプローチを検討すべきである。
また、歯冠部の審美が重要な部位では、本材の色(白・ピンク・黄)や質感が目立つ場合がある。短期間であれば白色を選ぶことで目立ちにくくできるが、強い審美要求がある症例では、あえてコンポジットレジンや審美仮着用セメントで仮封しておく方が患者満足度は高い。
最後に、歯髄の鎮静を優先したい場合には、補綴前の支台歯や深い窩洞で歯髄炎症の沈静化を図りたい症例では、酸化亜鉛ユージノール系の仮封材(例えばIRM)の方が適している。ユージノールの鎮痛作用により症状緩和が期待できるためである。ストッピングにはそのような薬理作用がないため、疼痛管理が主目的の場合には第一選択とはならない。
以上のように、症例の状況や患者要因に応じてテンポラリーストッピングの適否を判断することが重要である。他の仮封材や暫間補綴法とも比較検討し、それぞれの長所短所を踏まえた上で最適な手段を選択することが、臨床成績と患者満足の向上につながる。
読者タイプ別の導入判断ガイド
保険診療メインで効率重視の医院
日々多くの患者を回し、スピードとコスト管理を重視する保険診療中心の歯科医院では、テンポラリーストッピングは極めて相性の良い材料である。仮封処置の時間短縮効果は積み重ねると診療効率の向上に直結し、低コストゆえ材料費の心配もほとんど不要である。保険診療では根管治療やう蝕充填の症例数が多く発生するが、本材を用いることで毎回の仮封を迅速かつ安定して行える。特に週1回ペースで通院する患者が多い状況では、単一仮封でも十分対応可能なため、無駄に複雑な手法を取らずストッピングで簡便に封鎖することが合理的である。ただし、短期間であっても仮封不良によるトラブルが起きれば再診の手間が増えて効率低下につながるため、上記で述べた注意点を守り、確実な封鎖を心がけることが重要である。適切に活用すれば、保険診療の忙しい現場において良質な治療と業務効率の両立に寄与してくれる存在といえる。
自費診療メインで高付加価値志向の医院
精密な治療や患者サービスを重視する自費診療中心のクリニックでも、テンポラリーストッピングは上手く使えば有用なツールとなる。材料コストは僅少であり、高額な自費治療全体の中では無視できるため、費用面で導入をためらう必要はない。むしろ、本材のユージノールを含まない特性は、セラミック修復や高度な接着治療を提供する医院において大きなメリットとなる。仮封材残留によるボンド阻害の懸念が少なく、せっかくの高品質な最終補綴物の接着強度を損なうリスクを減らせるからである。また、患者への細やかな配慮として、前歯部には目立ちにくいホワイト色を選択したり、必要に応じてレジン仮封材と使い分けたりする柔軟な対応も考えられる。自費治療では患者一人あたりに十分な時間を確保できる分、仮封処置にも丁寧に取り組めるため、ストッピングの物性を最大限に活かして高い密閉性を実現できるだろう。ただし、美観や患者快適性が特に重要なケースでは、ストッピングに固執せず他材を用いる判断も必要である。総じて、自費中心の医院においても本材は適所で使えば診療クオリティと患者満足度の維持に貢献し、投資対効果の高いアイテムとなり得る。
外科・インプラント中心の医院
口腔外科処置やインプラント治療を主軸とする医院では、仮封材の出番は日常的には多くないかもしれない。それでも、緊急のう蝕処置や抜歯後の隣在歯のケア、他院からの根管治療依頼など、不意に仮封が必要になる場面はゼロではない。そうした際に備えて、テンポラリーストッピングを常備しておく意義は十分にある。滅菌済みの綿栓と本材があれば、急性症状で来院した患者にも迅速に応急処置が可能であり、大きな設備投資なしに幅広いニーズに応えられる。特に専門特化型の医院では患者の来院間隔が空く傾向があるため、ストッピング使用時も必要に応じて二重仮封を併用するなど、仮封期間の長期化に耐えうる工夫をしておくと安心である。一方で、使用頻度が低いと材料の劣化や管理がおろそかになりがちなので、在庫の使用期限や保管状態には注意が必要である。総じて、外科・インプラント系のクリニックではテンポラリーストッピングが主役になる場面は限られるが、いざという時に適切に使いこなせれば、専門外の処置にも的確に対応できる強みとなる。必要最低限の導入コストで診療の幅を広げる保険として、本材を活用するとよいだろう。
よくある質問(FAQ)
仮封は何日くらいもちますか?
適切に装着されたテンポラリーストッピングは、通常数日から1週間程度は問題なく機能します。メーカー想定では1週間程度の短期間使用が目安とされています。ただし、患者の咬合力や欠損の大きさによって個体差があります。2週間以上にわたる場合には封鎖力が低下したり脱離するリスクが高まるため、必要に応じて追加措置(二重仮封やより強固な材料への置換)を検討すべきです。定期通院の範囲内(次回予約まで)で使う限り、大きな問題は生じにくいでしょう。
天然ゴムアレルギーの患者には使えますか?
いいえ、使用できない。テンポラリーストッピングには天然ガッタパーチャ(天然ゴム)が含まれるため、ラテックスアレルギーの患者に使用すると重篤なアレルギー反応を引き起こす恐れがある。過去にゴム製品でアレルギー症状が出た患者には、本材の使用は禁止であり、樹脂系仮封材やグラスアイオノマーセメントなど代替の仮封方法を選択すべきである。また、術者やアシスタントがゴムアレルギーを持つ場合も、加熱時に発生する揮発物に触れる可能性があるため使用は避けるべきである。
歯髄への影響や鎮静効果はありますか?
テンポラリーストッピング自体に歯髄を鎮静する薬理効果はない。本材はユージノール(鎮痛作用のあるクローブ油)を含まず、中性で生体親和性の高い材料である。そのため、仮封によって歯髄炎症が治まるような直接的な治療効果は期待できないが、刺激が少ない分、歯髄に余計な負担をかけない利点がある。一方で、疼痛緩和を目的とする場合には、鎮痛効果のある酸化亜鉛ユージノールセメント(IRMなど)の使用が適している。症例の状況に応じて使い分けるとよい。
他の仮封材(キャビトンやIRM)との違いは何ですか?
水硬性仮封材の代表であるキャビトン(キャビトンファスト等)との比較では、テンポラリーストッピングは加熱軟化型である点が異なる。キャビトンは唾液中で自己硬化し微膨張するため、器具不要で手早く封鎖でき密閉性も良好だが、硬化後に脆く割れやすい欠点がある。また長期間放置すると水分で徐々に溶解して隙漏れが生じることがある。ストッピングは熱で軟化させる手間があるものの、硬化後はゴム弾性を保ち割れにくく、水に溶けないため長めの間隔でも形状を維持する。次に、IRMに代表される酸化亜鉛ユージノール系セメントとの比較では、ストッピングは混和や硬化待ち時間が不要で操作が迅速、さらにユージノールによるレジン接着阻害がない長所がある。IRMは硬化後の強度に優れ歯髄鎮静効果も期待できるが、混ぜる手間と硬化時間がかかり、また硬化後の除去にもやや労力を要する。総じて、ストッピングは短期間の素早い仮封に最適であり、キャビトンは極短期間の簡便な封鎖向き、IRMは強度と鎮静が必要な場合に向くといった使い分けができる。
材料の保存方法や使用期限はありますか?
テンポラリーストッピングは直射日光や高温多湿を避け、室温(おおよそ0〜30℃)で保管する。夏場は極端な高温(例えば車内など)に置くと軟化変形する恐れがあるため注意が必要である。適切に保管すれば長期間品質を維持できるが、パッケージに表示された使用期限(一般に製造後数年程度)を目安に、新しいものと入れ替えるのが望ましい。古い材料は表面が硬化して軟化しにくくなる場合がある。そのような場合は無理に使わず、新しい製品を開封することが推奨される。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う「テンポラリーストッピング」とは?使い方や特徴・用途を分かりやすく解説