- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う「ハイシール」とは?使い方や特徴を分かりやすく解説
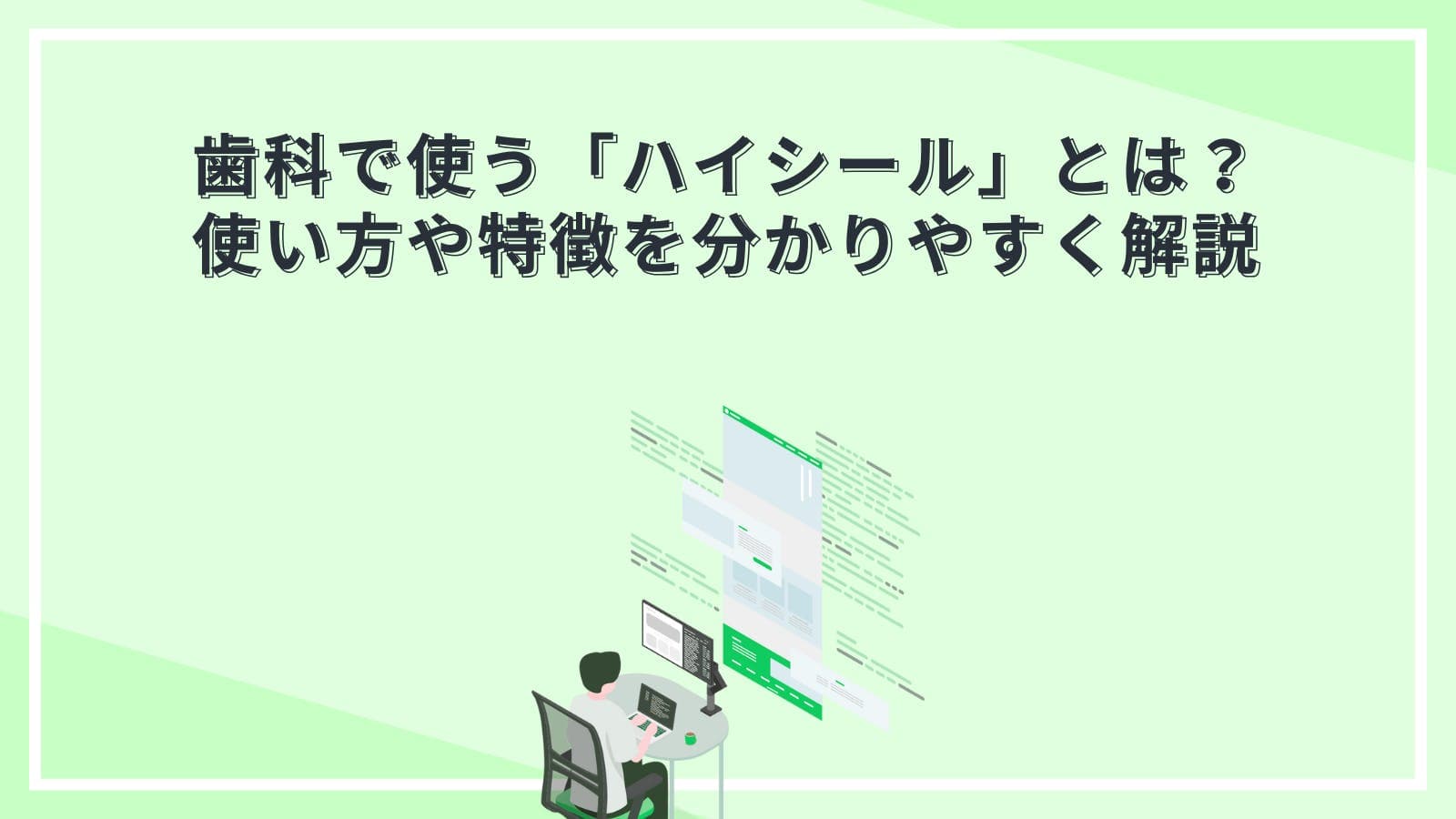
歯科で使う「ハイシール」とは?使い方や特徴を分かりやすく解説
う蝕の除去や根管治療の合間に施す仮封処置は、地味ながら治療全体の成功を陰で支えている。仮封が甘ければ、治療と治療の間に細菌が侵入して感染を再燃させたり、患者が痛みや不快感を訴えて来院するといったトラブルにつながる。忙しい臨床現場では「仮封が外れて患者から連絡が来てしまった」という経験を持つ歯科医師も少なくないだろう。例えば、根管治療で貼薬した後の歯に詰めた仮封が、次の来院前に剥がれてしまい、再び消毒からやり直し…という事態は避けたいところである。
一方で、仮封材にはさまざまな種類があり、それぞれ操作性や封鎖性、撤去のしやすさに特徴がある。素材選びや使いこなしに迷うことも多く、「患者に長く噛まないよう説明したのに、結局すぐ外れてしまった」「安価な材料を使ったら撤去は簡単だが密封が甘く、治療期間が延びた」といったジレンマに直面することもあるだろう。本稿では、歯科用仮封材として広く用いられる松風の「ハイシール」に焦点を当て、その特徴や使い方を臨床的・経営的視点の両面から解説する。仮封材選択のポイントとハイシール導入によるメリットを探り、読者が自身の診療スタイルに最適な仮封材を選択する一助となる情報を提供する。
歯科用仮封材「ハイシール」(松風)の概要
ハイシール(正式表記「ハイ-シール」)は、株式会社松風が製造販売する水硬性タイプの歯科用仮封材である。医療機器認証番号は20100BZZ00549000で、管理医療機器(クラスⅡ)に分類される。適応は歯の仮封、すなわちう蝕処置後や根管治療中の歯などを一時的に封鎖する目的に用いる材料である。包装形態は30g入りのジャー(色調はユニバーサルの1色のみ)で、ペースト状の材料があらかじめ練和済みの状態で入っている。歯科医師が必要量を直接窩洞へ詰めるだけで使用でき、粉液を混合する手間を省けるワンコンポーネント製品である。
ハイシールは水分で硬化する仮封材として位置付けられる。その名の通り、唾液などの水分と反応して硬化が進む「水硬性セメント系」の材料で、古くから用いられる石膏系仮封材(例えばキャビトンなど)と同じカテゴリに属する。ただし、従来の石膏系仮封材に比べ、ハイシールは樹脂系の結合材を配合している点が特徴である。松風独自の「HY材」(タンニン酸とフッ化物を組み合わせた成分)も含まれており、これにより封鎖性や使い勝手の向上が図られている。すなわち、ハイシールは単なる石膏粉ではなくレジンを含むことで適度な粘性と弾性を持ち、操作性と封鎖性能を両立した仮封材と言える。
ハイシールの主要スペックと臨床的意義
ハイシールの組成と硬化メカニズムを紐解くと、臨床での挙動が理解しやすくなる。主成分は硬質石膏(硫酸カルシウム)で、これが唾液中の水分を吸収して水和反応を起こし、二水石膏の結晶形成とともに硬化する仕組みである。材料が窩洞内で徐々に硬化する際、石膏の膨張により隙間を埋めるように自己緊密化する。この微小な膨張が辺縁封鎖に寄与し、仮封材として高い封鎖性を発揮するポイントである。
加えて、樹脂系結合材(ポリ塩化ビニル-酢酸ビニル共重合体など)が配合されていることで、ハイシールのペーストは適度な粘り気と自己凝集性を示す。これにより窩洞内への充填操作が滑らかになり、充填器に程よく付着しつつも、押し込めば腔壁に沿って広がるような扱いやすさがある。硬化前のペーストは指で捏ねた餅状の柔らかさを持ち、圧接すると細かな形態にもフィットする。一方で硬化後は完全に固まるわけではなく、わずかに弾性を残した硬さとなる。この硬化後の適度な軟硬性が、患者の咬合圧に耐える強度と、撤去時に容易に除去できる易削性のバランスを取っている。
ハイシールには松風独自のHY材(タンニン酸を主体とする成分)が含有されている。タンニン酸は収斂性を持ち、象牙質表面のタンパク質を適度に凝固させて細菌の侵入を抑える効果が期待できるほか、フッ化物との組み合わせによりう蝕抑制効果も付与されている。これは、同社のポリカルボキシレート系セメントなどにも伝統的に用いられてきた添加技術であり、仮封期間中の歯牙を守る工夫といえる。ただし、ハイシール自体に直接的な殺菌作用や歯質強化効果を謳うものではなく、あくまで補助的な性質である。
物理的なスペックとして注目すべきは徐硬化性である。ハイシールは充填後、唾液と接触した表面からゆっくりと硬化が進行する。そのため作業時間に余裕があり、充填後に表面を平滑に整える猶予がある点は臨床上利点である。メーカーは「徐硬化性なので表面滑沢性に優れる」と説明しているが、これは硬化がゆっくりで自己流動的に表面が馴染むため、シリンジタイプの速硬化レジン仮封材に比べ粗造な面ができにくいことを意味する。滑沢な表面は患者の舌による違和感を軽減し、仮封が外れにくくなる効果も期待できる。
一方、硬化に約1時間程度を要する点には注意が必要である。表面硬化自体は充填後すぐに唾液で始まるが、咬合圧に十分耐える強度に達するまで約60分はかかる。そのため、ハイシールを詰めた後は患者に最低1時間は咬まないよう指示することが大切である。この初期硬化に要する時間は、臨床上のワークフローや患者指導に影響するスペックであり、特に小児や要介護者など協力が難しい患者の場合には留意すべき点である。後述するように、必要に応じてより即時硬化型の材料を選択するといった工夫も選択肢となる。
ハイシールの使用方法と取り扱い上の留意点
基本的な使用方法はシンプルである。まず窩洞内を十分に洗浄した後、水分を拭き取らず湿潤な状態にしておく。乾燥しきった状態では硬化反応の水源が不足するため、必ず歯面が適度に濡れていることを確認する。次に、ハイシールの容器から必要量(ケースにもよるが米粒大から小豆大程度)をスパチュラや充填用の器具で採取し、そのまま窩洞へ詰め入れる。ペースト状なので隙間なく押し固めやすく、器具で圧接しながら辺縁隆起など形態に沿って成形する。余剰な部分があれば器具先端で除去し、必要に応じて濡らした綿球で表面を軽く擦ると、さらに平滑に仕上がる。
充填操作後は、唾液中の水分によって徐々に表層から硬化が始まる。患者には「これから1時間ほどはできるだけその歯で咬まないでください」と説明し、念のため硬い食品や粘着性の食品(ガム、キャラメル、もち等)は避けるよう伝えておく。特に根管治療中の歯など大きく削ってあるケースでは、仮封が外れると深刻な問題につながるため、患者が理解しやすい言葉で注意喚起することが重要である。仮封充填後すぐに帰宅する患者には、受付で再度声掛けする、メモを渡すなどのフォローも有用である。
他材との併用や互換性については、一般的な範囲で問題ない。例えば、根管治療では薬剤を充填した後に綿塞をし、その上をハイシールで封鎖する二重の仮封を行うことが多い。この綿は後でハイシールごとまとめて除去する際の目印とクッションになり、ハイシールの性能に影響は及ぼさない。また、ハイシール自体には接着性がないため、象牙質接着システムなどとの化学的相性を気にする必要もない。酸化亜鉛ユージノール系の仮封材と異なり樹脂系材料に影響を及ぼす成分(例えばユージノール)は含まれていないため、仮封除去後すぐにレジン系の接着処置やレジンセメントによる合着を行っても硬化阻害などの支障はない。ただし、ハイシールはあくまで窩洞や根管孔を一時的に塞ぐ材料であり、テンポラリークラウンの装着には仮着用セメントを使用すべきである。ハイシールをクラウンの仮着に流用すると、硬化膨張によりクラウンが浮いたり、逆に歯頚部に侵入して除去が困難になったりする恐れがあるため注意したい。
取り扱い上でもう一つ留意点は容器管理である。ハイシールは空気中の湿気でも硬化が進む可能性があるため、使用後はすみやかに容器のフタをしっかり閉める必要がある。長時間開放したままだと、容器内のペーストが乾燥・硬化して使い物にならなくなる。保管は高温多湿を避け、室温(15~25℃)で行う。直射日光や極端な低温高温環境も品質劣化の原因となる。使用期限も容器に記載されているので、在庫管理上は定期的に期限を確認し、古いものから使うようにする。1本30g入りとはいえ、一度に使う量はごくわずかであり、開業医であれば1パックで数十~百症例以上は賄えることになる。開封後長期間経過してペーストが硬く感じられる場合は、思い切って新品に取り換える方が安全である。幸い定価でも数千円以下の比較的安価な製品であり、品質を犠牲にしてまで使い切るメリットはない。
除去の手順も確認しておこう。ハイシールで仮封した歯に再度アクセスする際は、基本的にエキスカベーターやスプーン形成器具を仮封と歯の隙間にあてがい、テコの原理で持ち上げるようにすると塊状にポロリと剥がせる。樹脂を含むおかげで砕け散りにくく、一塊で除去しやすい点は術者にとってありがたい。完全に硬化した後も石膏系材料特有の脆さが若干残っているため、力を入れすぎなくとも容易に破断させられる。大部分は器具で除去できるが、ごく一部歯面に付着が残ることがある。その際は無理にスクレイパーで削り取ろうとせず、アルコール綿球で歯面を擦れば残渣が軟化して簡単に拭い去れる。これはハイシールがアルコールに可溶の成分を含むためで、仕上げにアルコールで清拭しておけば接着や印象への影響もなく安心である。
ハイシール導入による経営面の影響
仮封材の選択は一見すると臨床上の品質のみを左右するように思えるが、実は医院経営にも少なからず影響を与える。ハイシール導入によるコストパフォーマンスとROI(投資対効果)を多角的に考察してみよう。
まず直接的なコスト面では、ハイシールの価格はおおむね1,000~2,000円前後/30gとされる。1症例あたりの使用量はケースにより異なるが、仮に0.3g用いたとすれば1症例あたり数十円の材料費に相当する。これは伝統的なストッピング(加熱して詰めるゴム質の仮封材)の数円以下という超低コストと比べれば割高に映るかもしれない。しかし、歯科診療全体の中で数十円の差は経営上ほとんど誤差の範囲である。一方、この僅かなコスト増によって得られるリターンは大きい。
例えば、仮封が外れて患者が予定外の来院をすると、緊急対応の時間確保に追われ他の患者の予約変更を迫られることもある。特に保険診療中心の医院では1コマの収益は限定的であり、余計なトラブル対応はそのまま機会損失につながる。また、仮封の不備で治療が振り出しに戻れば、その分の処置は医院側のサービス(いわゆる無償対応)になりかねない。数十円を惜しんだ結果、何倍もの時間的・金銭的ロスが発生するリスクを考えれば、初めから信頼性の高い材料を使うことの経済的合理性は明らかである。
ハイシールのようなワンステップ系仮封材は、粉液練和型や加熱型の材料に比べチェアタイムの短縮にも寄与する。練板紙の上で粉と液を計量・練和するといったステップが不要なため、仮封に費やす時間は数十秒から1分程度短縮できるだろう。一見わずかな時間だが、1日あたり複数のケースで積み重なれば無視できない。忙しい診療時間内で「数十秒のゆとり」を生み出せることは、追加アポイントを一枠作れる可能性や、患者説明にもうひと息時間を割ける余裕につながる。人件費換算しても、スタッフや術者の1分は決して軽くないコストであり、その節約効果は材料費の差額以上の価値を生む。
さらに、患者満足度と信頼という無形の価値も見逃せない。仮封がしっかり機能すれば、患者は治療の合間も快適に過ごせる。逆に仮封の不具合で痛みや不便を感じれば、医院への信頼は損なわれかねない。自費診療で高額な治療を提供しているような医院であればなおさら、小さなトラブルでも患者の心証に響く。質の高い仮封材を使い丁寧に処置することは、患者からの「見えない評価点」を積み上げることにつながり、ひいては増患やリピートという形で経営に跳ね返ってくる。
以上より、ハイシールの導入は、低コストで高い効果を上げられる投資と位置付けられる。精密な根管治療や補綴治療の土台を支える仮封クオリティの向上は、再治療率の低下、トラブル対応の減少による生産性向上、患者からの信頼醸成という形で医院経営に貢献するだろう。特に近年は口コミやSNSで患者の声が広がる時代であり、「治療中も特に不自由なく過ごせた」「仮詰めが取れて困るようなことはなかった」といった些細な感想が、新たな患者を呼び込む要因になるかもしれない。
ハイシールを効果的に使いこなすポイント
ハイシールの性能を最大限に引き出すには、単に製品を導入するだけでなく臨床での工夫やチーム内での共有が重要である。以下に、現場で培われた使いこなしのポイントを紹介する。
初期硬化の待ち時間を考慮した段取りを組むこと。ハイシールは充填してから咬合に耐え得るまで少し時間がかかるため、可能であれば患者をチェアサイドで数分間休ませ、その間にカルテ記入や次回予約の調整を行うとよい。完全硬化には1時間要するが、数分経てば表面硬化は始まり触れても大きく形が崩れない状態になる。例えば仮封後すぐにうがいをさせると表層が洗い流される恐れがあるが, 数分待てば軽く水を含んでゆすぐ程度は問題なくなる。術後の注意事項を説明する時間を設けることで、患者も落ち着いて話を聞け、一石二鳥である。
患者教育の徹底も使いこなしの一環である。仮封材の性能を活かすも殺すも、患者が適切に取り扱ってくれるかにかかっている。特に術後の飲食指導は繰り返し強調することが肝心だ。経験上、単に「硬いものは避けて下さい」では具体性に欠け、患者は軽く捉えがちである。「左下の仮詰めが入っている歯では、今日はなるべく何も噛まないようにしてください。ガムやお餅は絶対にやめてください」といった具体的で断定的な言い回しが有効である。また、食事以外でも無意識に舌や指で触れてしまう患者もいるため、「気になっても触らないように」と付言しておくと良い。こうした念押しにより、多くの場合トラブルは未然に防げる。
スタッフ間の情報共有も欠かせない。仮封材をハイシールに切り替えた場合、歯科衛生士や助手にもその扱い方や注意点を周知しておく必要がある。例えば、アシスタントが先に窩洞を乾綿子で乾燥させてしまう癖があると、ハイシールの硬化が遅れ密着も不十分になる恐れがある。そうした細かな点も含めて、「この材料は湿らせて使う」「蓋をすぐ閉める」といった取扱プロトコルを共有しておく。院内マニュアルに仮封材別の使用法を追記したり、ミーティングで注意喚起したりするとよいだろう。
ハイシールを使いこなす上で、敢えて他の仮封材との使い分けも視野に入れることがプロの判断である。例えば、どうしても患者が術後すぐに咬んでしまう可能性が高い(小児、認知症患者など)場合、初期硬化が速い他製品(例えばGC社「キャビトン ファスト」等)を選択する柔軟性も必要だ。また仮封期間が長期間に及ぶ場合、咬耗や溶解に強い仮封法(必要に応じてグラスアイオノマーセメントで蓋をする等)を検討することもあるだろう。ハイシールはあくまで用途限定の仮封材であり、万能ではない。適材適所の選択眼を持った上でハイシールの利点を活かすことが、結果的に診療の質を底上げする。
最後に、トラブル時の対応策も念頭に置いておきたい。万が一、患者が「仮詰めが取れた」と連絡してきた場合でも、ハイシールであれば比較的対処は容易である。患者には取れたものを無理に戻そうとしないよう伝え、可能であれば破片を持参してもらう。ハイシールは無色に近い材料なので、誤飲してしまってもレントゲンに写らず発見困難だが、基本的に石膏由来成分で体内で反応することはなく経過観察で自然排出される。ただし根管充填中であれば早めに来院してもらい、再消毒と仮封し直しが必要である。こうした緊急対応マニュアルを用意しておくことで、仮封材への不安も少なくなる。
ハイシールが適している症例・適さない症例
ハイシールの特性を踏まえ、どのようなケースに適応し、逆に使用を避けた方がよいかを整理する。
適応症例としては、基本的に短期間の仮封が必要な全ての症例が挙げられる。具体的には、根管治療の各ステップ間での歯冠封鎖、インレー・アンレーの形成後から次回来院までの一時的な窩洞封鎖、う蝕除去後に最終的な修復物装着まで時間を置く場合の封鎖などである。これらの場面では、ハイシールの高い辺縁封鎖性と取り扱いの容易さが存分に活きる。特に根管治療では、唾液による感染再発を防ぐため密閉性の高い仮封材が望ましいが、ハイシールは膨張硬化による隙間の少なさから根管治療の標準的仮封材として十分信頼に足る。また、象牙質を多く露出した窩洞でもタンニン酸含有により刺激が緩和される可能性があり、仮封期間中の歯髄保護にも適すると考えられる。
適さないケースとしては、まず長期間の仮封が必要な症例が挙げられる。ハイシールは時間経過とともに唾液で徐々に溶解・摩耗していくため、数か月単位で放置すればさすがに封鎖力は低下する。患者が何らかの事情で来院できず、仮封状態が長引くことが予想される場合は、グラスアイオノマーセメントやレジン仮填封などより長期安定型の材料に切り替える方が安全である。
また、極端に大きな欠損や咬合力が強くかかる部位も注意が必要だ。大臼歯部で咬頭が失われるほど削合しているケースでは、単なる窩洞封鎖では咬合圧に耐えきれず仮封材が割れたり沈下したりしやすい。このような場合には、あらかじめ咬合を落としておく、あるいは小さめの暫間クラウンを装着してしまう方法が現実的である。同様に、ブラキシズムなど強い咬耗力が想定される患者では、ハイシール単独では不安が残る。仮封期間が短くても、必要に応じて咬合圧を逃がす工夫や補強が求められる。
幼児や嚥下障害のある患者では、ハイシール使用自体は禁忌ではないが、誤飲・誤嚥のリスクを考慮すべきである。硬化前のペーストは粘着性が高いが、完全硬化前に外れてしまうと比較的脆い塊となり得るため、小児が飲み込んでしまう可能性がある。基本的に生体に有害な成分ではなく自然に排出されるが、気管に入れば危険である。そうしたリスクが高い症例では、即時硬化型の光重合仮封材など、一瞬で固定できる別材を検討した方が安全な場合もある。
さらに既知のアレルギーにも配慮する。ハイシールの禁忌事項として、成分に対し過敏症の既往がある患者・術者への使用禁止が明記されている。レジン系材料全般にアレルギーを持つ患者は稀だが存在するため、既往問診で注意が必要だ。その場合は、樹脂を含まない他社の石膏系仮封材や酸化亜鉛ユージノールなどへの代替を検討する。
最後に、仮封以外の用途には使えない点を確認しておきたい。先述のように、クラウンやブリッジの仮着用途には不適であり、逆に仮封以外への応用は基本的にない。稀に「ハイシールが余っているから仮歯の裏装に使えないか」などの発想が浮かぶかもしれないが、物性や硬化特性が目的外使用に合っていないため推奨できない。それぞれの製品は本来の適応範囲内で使うことが何より重要である。
歯科医院のタイプ別・ハイシール導入の判断ポイント
どんな優れた材料でも、医院の方針や診療内容との相性がある。ここでは、歯科医院のタイプ別にハイシール導入の向き不向きを考えてみよう。
保険診療中心で効率重視の医院の場合
保険診療を主体とし、多くの患者を回転させる診療スタイルの医院では、治療効率とコストのバランスを常に意識する必要がある。仮封材に関しても、材料費を極力抑えるために伝統的なストッピングや安価なZOE系セメントのみで凌いでいるケースが見受けられる。このような医院にとってハイシールへの切り替えは、一見「贅沢」な投資に映るかもしれない。しかし前述した通り、ハイシール1回分のコストは数十円程度であり、その投入によって得られる時間短縮やトラブル減少のメリットは計り知れない。頻繁に仮封処置を行う保険診療型医院だからこそ、仮封の信頼性向上が日々の業務効率に直結しやすいのである。仮封の失敗による再処置や患者クレームが減れば、その分だけ他の患者に時間を充てられ収益機会が増える。薄利多売の経営モデルこそ品質リスクの影響が大きいことを踏まえれば、ハイシールは効率重視医院にとってむしろコスト以上の価値を提供する道具となる。唯一、初期硬化に時間がかかる点だけは注意が必要だが、多忙な医院では待合滞在時間が多少延びても患者理解が得られるケースが多く、それよりも「仮詰めがしっかりしている安心感」を提供する方が患者満足度は高まるだろう。
自費診療に注力する高付加価値志向の医院の場合
審美歯科やインプラントなど高付加価値の自費診療を中心とする医院では、使用する材料もクオリティ最優先で選ぶ傾向がある。このような医院にとって、ハイシールの導入は患者サービス向上の観点から大いに意義がある。まず、自費診療の患者は治療に対する期待が高く、細部にまで配慮した丁寧な処置を評価する。ハイシールによって仮封期間中の不快感やトラブルが減れば、患者は「終わるまで快適だった」という満足感を抱きやすい。たとえ患者自身が仮封材の違いに気付かなくとも、何事もなく順調に通院できる体験そのものが医院の評価につながる。
また、自費診療は治療間隔が長めになるケースもある。技工物の精密製作や複雑な治療計画により、仮封状態で過ごす期間が保険診療より長期化しがちだ。そうした場面でも、ハイシールなら適度な耐久性を示し、次回来院まで状態を維持しやすい。仮に2〜3週間程度であれば大きな劣化もなく耐えるだろう。万一外れてしまっても、自費診療の患者であれば連絡すればすぐ来院してくれることが多く、迅速にリカバリーできる。高額治療に見合ったリスクマネジメントとして、初めから質の高い仮封材を選ぶことは理にかなっている。
むしろ「治療中の仮詰めにも高品質な材料を使用している」という姿勢をアピールすることで差別化につなげ、患者への訴求材料とすることも可能である。実際にそこまで謳うかは別としても、医院としては自費診療の価値提供の一環としてハイシールを選択する意義は十分にある。
口腔外科・インプラント中心の医院の場合
親知らず抜歯やインプラント手術など外科処置中心のクリニックでは、一見すると仮封材は縁遠い存在かもしれない。これらの医院では保存修復や補綴処置をあまり行わないため、仮封の出番自体が少ないだろう。しかし、完全に無関係かと言えばそうでもない。例えば、インプラント埋入後のヒーリングアバットメントのネジ穴を一時的に封鎖する場合や、外科的処置と保存処置を並行して行うケース(抜歯即時治療で隣在歯を仮封しておく等)では、やはり信頼できる仮封材があると安心である。使用頻度が低いからこそ、いざという時に即座に使える手軽な材料であることは重要だ。ハイシールであれば混ぜる手間もなく棚から取り出してすぐ使えるため、オペに集中したい場面でも邪魔にならない。
経営的視点では、外科中心の医院にとって仮封材はメイン収益に寄与するものではない。しかし、トラブル防止や患者ケアの質向上のための保険として用意しておく意義はある。むしろ使用頻度が少ない分、ストッピングのように年月を経て劣化する素材よりもハイシールのように保存性が高く安定した製品の方が無駄になりにくい。1ジャー買っておけば長期間もつので、コスト負担もごくわずかである。外科系処置の合間に保存処置が必要になった場合に備え、院内に常備する仮封材としてハイシールは適任と言える。
よくある質問(FAQ)
ハイシールはどれくらいの期間、仮封として持続するか?
通常のケースでは次回予約までの1〜2週間程度は問題なく封鎖状態を維持できる。唾液中で徐々に溶解・摩耗する性質上、目安として数週間以内の使用に適すると考えられる。1ヶ月以上の長期にわたる場合、表面が軟化してくる可能性があるため、途中で仮封をやり直すか他材への切り替えを検討すべきである。短期間であれば、適切に詰めておけば咀嚼により脱落することは少ない。
ハイシールにユージノールは含まれているか?レジン接着への影響は?
ハイシールはユージノール無配合であるため、レジン系接着剤やレジンセメントの硬化を阻害しない。仮封除去後の歯面に残留物がある場合も、アルコール綿で清拭すればきれいに除去でき、接着操作へすぐ移行できる。ユージノール系の仮封材(いわゆるZOE)は接着阻害や軟組織刺激の懸念があるが、ハイシールではそれらの心配は基本的にない。ただし除去残渣が大量に残っていては物理的な妨げになるため、必ず完全に清掃してから接着処置に入るべきである。
ハイシールをクラウンの仮着に使ってもよいか?
推奨できない。 ハイシールは窩洞や根管孔の封鎖用に設計された材料であり、クラウンやブリッジの一時固定には専用の仮着用セメントを使うべきである。ハイシールを仮着代わりに使用すると、硬化膨張によって補綴物が浮いたり、辺縁部から漏れて歯肉に刺激を与える可能性がある。また、硬化後も弾性が残るため、クラウン保持力も不十分で外れやすい。必ず用途に適した材料を選択していただきたい。
誤って患者がハイシールを飲み込んでしまった場合、安全か?
ハイシールの主成分は石膏(硫酸カルシウム)であり、体内で有害な化学反応を起こす成分は含まれていない。少量であれば経口摂取しても基本的に無害で、そのまま消化管を通過して排泄される。ただし大きな塊を誤嚥すると窒息の危険があるため、特に小児や高齢者では注意が必要だ。患者が飲み込んだ疑いがある場合は速やかに歯科医師に相談し、必要に応じて医科受診を検討する。幸い仮封材が外れて飲み込まれるケースは稀だが、普段から術後指導で注意を促すことが最善の予防策である。
「HY材」とは何か?ハイシールにおける役割は?
HY材とは、松風が開発・採用しているタンニン酸とフッ化物の複合成分のことである。かつて本間・山田両博士によって考案された歯科用材料添加物で、タンニン酸の収斂作用とフッ化物の抗う蝕効果を組み合わせ、歯髄や歯質を保護する目的がある。ハイシールにもHY材が配合されており、仮封期間中の歯に優しい処置となるよう配慮されている。ただし、HY材配合によって劇的に予後が変わるわけではなく、あくまで補助的な効果である。重要なのは材料そのものの封鎖性と適切な取り扱いであり、HY材はその一助となっていると理解すればよい。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う「ハイシール」とは?使い方や特徴を分かりやすく解説