- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科の仮封材「キャビトン」のすべて。添付文書や成分、注意点等を網羅的に解説
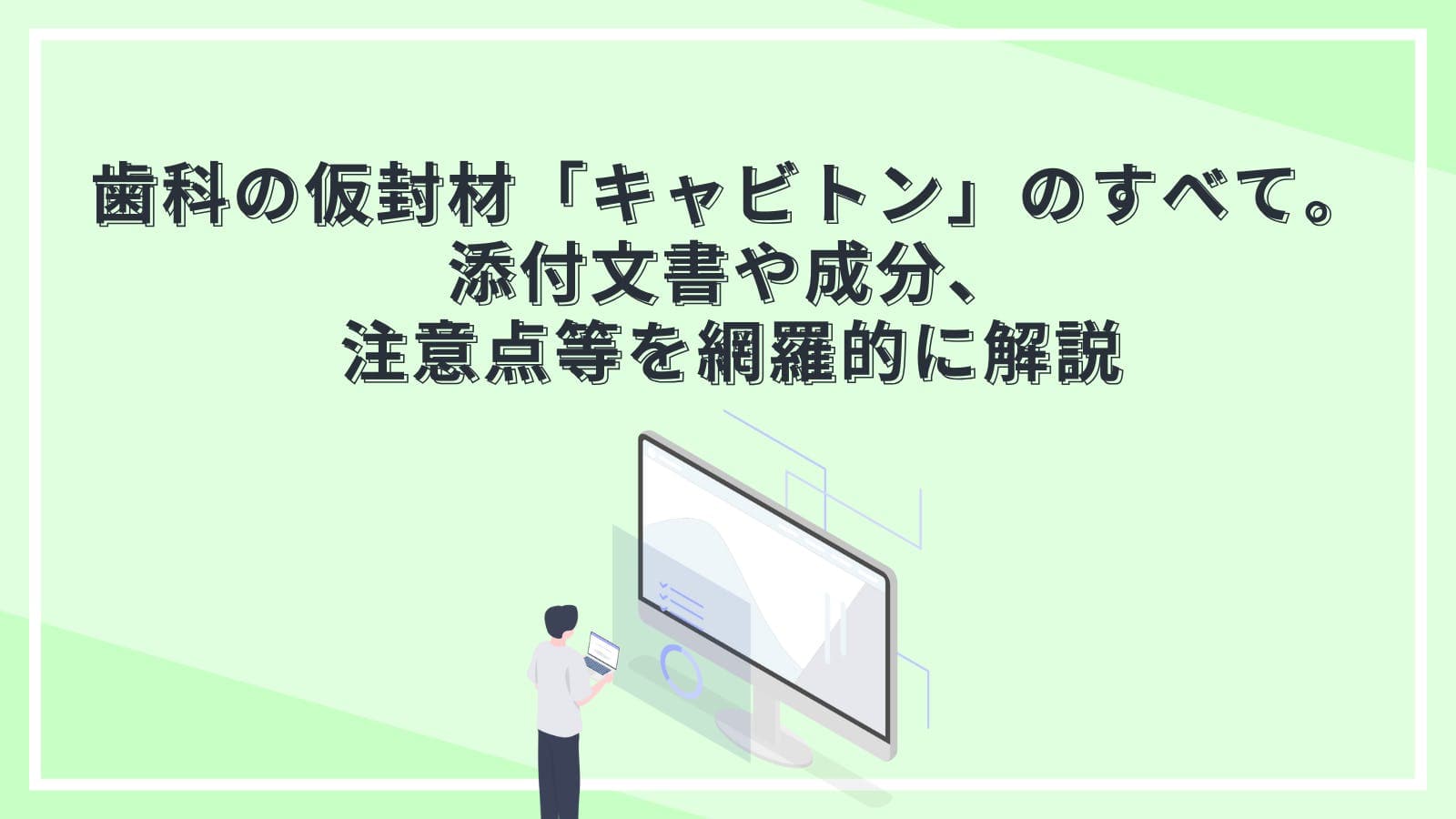
歯科の仮封材「キャビトン」のすべて。添付文書や成分、注意点等を網羅的に解説
根管治療の仮封が外れてしまい、患者が予約外で駆け込んできた――そんな経験を持つ歯科医師は少なくないだろう。仮封材が途中で脱離したり封鎖が不十分だと、唾液による細菌漏洩で再感染のリスクが高まり、治療工程のやり直しにつながりかねない。多忙な診療の合間に予定外の処置が入り、医院のスケジュールが乱れること自体、経営面でも痛手である。
こうしたトラブルを未然に防ぐ鍵の1つが、適切な仮封材の選択と使いこなしである。本稿では、水硬性仮封材として古くから用いられている「キャビトン」に焦点を当て、添付文書に基づく基本情報から臨床テクニック上の注意、さらには医院経営への影響まで網羅的に解説する。小さな仮封の工夫が治療予後と医院の信頼度に大きく寄与することを、臨床経験と経営の両面から考察していきたい。
製品の概要(キャビトンの基本情報)
キャビトンは株式会社ジーシー(GC)が製造販売する歯科用仮封材である。正式な区分は「歯科用仮封材 ジーシー キャビトン」で、医療機器としてはクラスIIの管理医療機器に分類される(認証番号: 221AABZX00194000)。水硬性仮封材に属し、唾液など口腔内の水分と反応して硬化するペーストタイプの材料である。
キャビトンの主な用途は治療中の一時的な穴の封鎖(仮封)である。具体的には、根管治療の各セッション間での仮封や、インレー形成後から次回セットまでの一時的な窩洞の封鎖などに用いられる。あくまで最終補綴物や永久充填までの間、歯内を唾液や細菌から保護するための暫間材料であり、治療完了後には除去される前提の素材である。
キャビトンは数十年前から臨床で使われてきたロングセラー製品であり、その間に改良版も登場している。2000年代末には「キャビトンEX」が発売され、ペーストの操作性と硬化後の耐久性が向上した【※】。さらに近年では「キャビトン ファスト」がラインナップに加わり、初期硬化時間を大幅に短縮する改良がなされている【※】。いずれも基本的な適応範囲は同じで、根管治療やう蝕処置の仮封用途に使用できる。包装は各製品とも30g入りの容器1本で提供されており、色調は従来のピンク・ホワイトに加え、EX以降はアイボリーも選択可能になっている。いずれも練和不要の単一ペーストであり、チューブやジャーから直接必要量を取り出して使用する手軽さが特徴である。
【※】キャビトンEX(2009年発売)は従来品のメリットを維持しつつ、ペーストのベタつきを軽減し硬化後の耐摩耗性を高めた改良版である。キャビトンファスト(発売時期: 2021年頃)は初期硬化時間の短縮と操作性向上を実現した最新モデル。
主要スペックと臨床的特徴
キャビトンの主成分は、公表されている情報によれば酸化亜鉛、硫酸カルシウム(石こう)、および酢酸ビニル樹脂である。これらの組成がキャビトンの物性を規定している。硫酸カルシウムは唾液中の水分と接触することで結晶化し、硬化体を形成する。硬化の際にわずかな吸水膨張が起こるため、窩洞内部に密着してすき間を埋める作用がある。このため辺縁封鎖性(微小漏洩の防止能力)に優れることが臨床上の大きな利点である。事実、従来から水硬性仮封材は一時的封鎖の封漏防止効果が高いことが報告されており、根管治療における短期間の仮封材として広く選択されてきた。
一方で、酸化亜鉛主体の硬化物は機械的強度において永久充填材ほど高くない。キャビトンが硬化したあとの硬さは、いわゆるセメント充填物より柔らかく、爪で強く押すとわずかに跡がつく程度である。これは意図的な設計で、仮封中に過度に硬くなりすぎず、除去が容易にできるようにするためである。硬すぎないおかげで、次回の治療時に削り取る際に歯質を傷つけにくく、一塊で除去しやすい。ただし強度が低い分、厚みが不十分だったり長期間経過すると咬合圧で摩耗・脱落しやすい点には注意が必要である。
硬化時間は臨床操作上重要なスペックである。キャビトンは空気中では硬化せず、水分に反応して徐々に固まるため、硬化開始から一定時間は圧力に弱い。従来型やEXでは、強い咬合力に耐えるまで約60分を要するとされ、患者には仮封後1時間程度は硬い物を噛まないよう指示するのが通例であった。最新のキャビトンファストでは組成粒子の微細化などにより初期硬化が早まり、約30分で咬合可能な強度に達するとされている。これは患者の食事制限時間を短縮でき、仮封直後に誤って咬合してしまった場合の脱離リスクも低減できる改良点である。
キャビトンペーストの操作性もスペック上見逃せないポイントである。従来品ではペーストが器具に付きやすく、充填時にべたつきを感じることがあった。キャビトンEX以降ではこのインスツルメント離れが改善され、粘調度が扱いやすく調整されている。ペーストは指で押せば変形する柔らかさで、スパチュラや充填器で容易にすくい取って窩洞内に充填できる。硬化が始まる前であれば過不足を追加したり除去したりの操作も容易で、形態修正もしやすい。色はピンク・ホワイト(およびEX/ファストではアイボリー)があり、ケースによって使い分けられる。ピンクはコントラストが高く除去忘れを防ぎやすいため主に臨床で好まれる。一方、前歯部や患者の審美的配慮が必要な場合には歯に近い白色や象牙色を選択し、目立たない仮封とすることもできる。
生物学的な特徴としては、キャビトンは非ユージノール系の仮封材であり歯髄への刺激が少ない点が挙げられる。従来から一時的封鎖に使われるもう一つの代表的材料に酸化亜鉛ユージノール系セメント(いわゆるIRMなど)があるが、ユージノールは歯髄鎮静効果がある一方で露髄面には刺激となり得る。キャビトンはユージノールを含まず中性に近い組成のため、間接的に歯髄近くへ使用しても有害作用が少ない。またユージノールはレジン系接着の重合阻害を起こすことで知られるが、キャビトンにはそれがない。このため後続処置でコンポジットレジンやレジンセメントを使う場合でも、接着阻害のリスクが低い点は臨床上メリットである(※後述の互換性の項も参照)。
最後にX線不透過性について触れると、キャビトン自体に金属成分はないが酸化亜鉛由来の亜鉛元素を含むため、硬化物はエックス線写真上で周囲歯質よりわずかに白く写る。完全な造影性はないものの、仮封材の残留確認は肉眼と触知で行う前提ではあるが、万一の取り残しもX線である程度判別可能である。いずれにせよ除去性が良く取り残しが生じにくい製品ではあるが、術後チェックでは視認性・造影性が一定ある色調・組成であることが手助けとなる。
使い方と運用上のポイント(互換性・手順など)
基本的な使用方法: キャビトンは練和不要の単一ペーストなので、容器から直接適量を取り出し窩洞に充填するだけである。一般には金属製またはプラスチック製のスパチュラや充填器(へら状または球状の器具)を用い、ペーストをすくい取って窩壁に圧接するように詰めていく。根管治療のような深い穴では、あらかじめ根管内に綿糸やコットンペレットを入れておき、その上からキャビトンを詰めるのが標準的手技である。こうすることで根管内への押し込みすぎを防止し、後日の除去も容易になる。また綿を入れることで適切な厚みのキャビトン層を確保でき、封鎖性を高める狙いもある。
充填時には唾液や血液による汚染状況に注意する。キャビトンは水分で硬化するため完全乾燥下で使う必要はないが、あまりに唾液や出血で湿潤しすぎている環境ではペーストが流出したり緩くなりすぎる恐れがある。術野は可能な限りラバーダムやロールワッテで湿度コントロールし、過剰な水分は軽く乾綿子で吸収してから充填すると良い。逆に全く唾液の届かない深い部位では、表面にごく微量の水を綿棒で与えると硬化が促進される場合もある。充填後は器具で軽く圧接し、縁を滑らかに整える。適正な操作で入れば、キャビトンは窩洞内で自己保持し、通常は接着材を使わなくても脱落せず安定する。
他材料との互換・併用: 前述の通りキャビトンはユージノールを含まず、硬化後も残渣が歯面に残りにくいため、後続の接着処置に与える影響は極めて少ない。ただしレジン接着を行う際は、仮封材を完全に除去し、アルコール綿などで歯面を清拭しておくことが望ましい(微細な粉残りなどを除くため)。どうしても仮封材の一部が残置する状況では、ユージノール系に比べ接着阻害の心配は少ないが、可能な限り健全歯質を露出させるようにする。なおグラスアイオノマーセメント系の仮封材(例: ファストセットのもの)や光重合型レジン仮封材と比べても、キャビトンは除去時に歯面へ強固には付着しないため、撤去後の歯面処理は比較的容易である。
必要に応じて、キャビトンと他の暫間材料を組み合わせて二重仮封とするケースもある。例えば長期間(数週間〜数か月)仮封せざるを得ない場合、キャビトン単独では不安なときには、キャビトンで密封した上に更に強度のある仮封材を覆罩することがある。実際の手順としては、まず窩底付近にキャビトンを詰めてしっかり封鎖し、その上から硬化後にIRM(酸化亜鉛ユージノールセメント)や仮着用レジンなどを詰め足して表層を補強する。こうすることで封鎖性と耐久性の両立を図るわけである。ただし二重仮封は除去時に手間がかかるため、あくまで必要最小限の期間に留め、定期的にやり直す前提で使う方が安全である。
院内運用と保管: キャビトンは1本の容器を複数患者で繰り返し使用するため、取り扱いには清潔操作が求められる。直接容器先端を患者の口に触れさせることは避け、必ず清潔な器具で必要量を容器から採取する。万一容器内に唾液が逆流すると中身が部分硬化し劣化する恐れがある。使用後は容器の蓋を速やかにしっかり閉め、直射日光や高温多湿を避けて保管する。キャビトンファストでは密閉性の高い新容器が採用され、開封後の乾燥硬化を防ぎやすくなっているが、それでも保管環境によっては徐々にペーストが硬くなる可能性がある。適切に保管すれば未開封で数年、開封後でも最後まで柔らかい状態を保てるが、明らかに硬化が始まり塊状になった場合は新品に交換した方がよい。
また、スタッフへの教育という観点では、キャビトンは操作手順がシンプルでミスが起こりにくい素材である。練板や計量が不要なため新人でも扱いやすく、一定の封鎖効果が得られる。ただし、例えば綿栓を入れ忘れて根管内に深く押し込んでしまう等のミスが起これば逆効果なので、基本手順は院内で統一して共有しておく必要がある。仮封材の扱いは地味ではあるが、院内マニュアルできちんと定めておくことで、スタッフ間のばらつきを減らし安定した治療品質につながる。
導入による経営インパクト(コストとROI)
キャビトンのコストは歯科材料の中でも微々たるものである。メーカー希望価格は30g入り1本あたり約1,000円程度(実勢販売価格は800〜900円台)であり、1症例で使用する量はごくわずかだ。例えば根管治療1回の仮封に0.3g使用した場合、材料費は十数円程度に過ぎない計算である。当然ながら保険診療報酬の中で充分吸収できるコストであり、導入の金銭的ハードルはほとんど無いと言える。
むしろ経営面で重要なのは、その間接的な費用対効果(ROI)である。仮封材の性能や使い方ひとつで、治療のやり直しや無駄な診療時間が発生するかどうかが左右される。例えばキャビトンの封鎖が甘く細菌漏洩を許せば、次回来院時に再消毒や根管洗浄を余儀なくされ、本来不要だった処置に時間を取られる。また最悪の場合、仮封不良で根管内が汚染され根尖病変が悪化すれば、治療計画自体が延長・複雑化し、追加の費用と時間が発生する。これらは患者満足度の低下にも直結し、医院にとってマイナス要因である。
キャビトンを適切に用いて仮封成功率を高めることは、再処置の削減=余計なコスト削減につながる。例えば仮封脱離による緊急再来院が1件減れば、その時間に別の有償処置を行うこともできる。また緊急対応では通常、再仮封に追加料金を請求しにくいため(サービス対応になりがち)、施術者側の持ち出し作業となるケースも多い。それを防ぐこと自体が機会損失の防止であり、小さな材料費で大きなリターンを得ていることになる。
さらにチェアタイムの効率化という観点では、キャビトンファストの登場は注目に値する。患者への注意指導(「○○時間は食事を控えてください」)の負担軽減や、仮封後に院内で少し待機してもらう必要がある場合の待機時間短縮など、細かな点で診療フローの無駄を削減できる可能性がある。患者にとっても治療当日に早く普段の生活に戻れる安心感があり、結果的に治療満足度向上に寄与する。患者満足度が上がれば口コミやリピートにも好影響を及ぼし、これは経営的なプラスと言える。
また仮封が確実であれば治療ステップ間の間隔を柔軟に取れるようになる。例えば忙しい患者で次回予約が先になっても、仮封が信頼できれば無理に短期間で来てもらわずに済む。患者本位の予約スケジュールが組みやすくなることは、医院の評判向上や通院継続率アップにつながり、ひいては経営改善につながるだろう。
まとめれば、キャビトン導入自体の費用は些細だが、適切に活用することで得られる利益は大きい。安全確実な仮封による治療成功率の向上、不測のトラブル対応削減による生産性向上、患者満足度の向上による増患効果など、目に見えにくい効果が積み重なる。ROIという視点では、キャビトンは「投資」というより診療の質を底上げする必要経費に近いが、その僅かな経費で大きなリスク低減と信頼獲得を得ていると考えれば、極めてコストパフォーマンスの高いアイテムと言える。
キャビトンを使いこなすポイント(臨床テクニック編)
キャビトンの性能を最大限発揮するには、いくつか臨床上のコツがある。まず十分な厚みを確保することが重要だ。一般に仮封材は厚みが薄いと強度・封鎖性が低下する傾向がある。キャビトンも例外ではなく、可能な限り3〜4mm程度の層厚を持たせることで、咬合圧に耐え漏洩もしにくい安定した仮封となる。窩洞が浅すぎて厚みが取れない場合は、綿を敷かずに底までキャビトンを充填したり、他の材料と併用して強度を補完するなどの工夫が必要になる。
咬合調整もポイントだ。仮封箇所が噛み合わせの当たる面にある場合、そのままだと柔らかい硬化途中に強い力がかかり脱離する恐れがある。充填後、軽く咬合させてみて高点があれば器具で平坦に削ぎ落としておく。理想的には、仮封箇所は僅かに咬合面より陥没させ、周囲の歯質に咬合がかかるよう調整しておくと安心である。ただし削りすぎて薄くなっては元も子もないため、厚みと咬合のバランスを見極める必要がある。特に大きな咬合力が予想される臼歯部では、患者にも「反対側でなるべく咀嚼してください」と一声かけ、負荷を分散する配慮が望ましい。
硬化初期の取り扱いにも注意する。キャビトンは詰めてから数分で表面がゴム硬さに固まり始めるが、完全硬化までは力に弱い。充填直後に患者が強く舌で触れたり吸引のチューブで引っ掛けたりすると剥がれてしまうことがある。充填後しばらくは患者に口唇を閉じてもらい静かにしてもらうか、必要に応じて綿球を軽く咬ませて保護する。仮封操作が終わったら「これから◯◯分ほどでしっかり固まりますので、それまで強い力を加えないようにしてください」と具体的な時間を伝えて注意喚起する。キャビトンファスト使用時は「30分程度」、従来品なら「1時間程度」が目安となる。
患者説明と啓蒙も仮封成功の鍵である。患者には仮封が「一時的なふた」であり壊れ得るものだと理解してもらう必要がある。具体的には、粘着性の食べ物(ガム、餅など)は避ける、硬い物を反対側で噛む、歯磨きは優しく行うことなどを指導する。特に食後にデンタルフロスを使う患者には、仮封部位ではフロスを通した後に引き抜く方向に気を付けるよう伝える(上から引っ張ると仮封を引き出してしまうため、横からスッと抜くようにする)。これらの指示を徹底することで、患者自身に仮封を長持ちさせる協力をしてもらうわけである。
万一仮封が取れてしまった場合の対応策も事前に伝えておくと親切だ。例えば「外れて穴が開いたら来院前でも歯ブラシで清潔にしておいてください」「詰め物が外れたまま放置すると痛みや感染の原因になるので、できるだけ早めに連絡ください」といったアドバイスである。患者にとっては小さな仮封が外れただけでも不安になるものだ。それを見越して適切な対応法を示しておくことで、医院への信頼感も増すだろう。
テクニック上の細かなコツとしては、キャビトンは一度で大量に入れようとせず少しずつ分割充填すると隅々まで密着しやすい。また器具への付着が気になる場合、器具先端をあらかじめ水で湿らせておくとペーストが付きにくくなる(ただし水滴が多すぎるとペーストが緩むので注意)。硬化不全を防ぐため、充填後にペースト表面を唾液に触れさせるようにするのもポイントだ。具体的には、最後表面をならしたら患者に軽く舌で触れてもらうか、唾液を行き渡らせるようにすることで、表層の硬化を確実に開始させる。長時間唾液が届かないままだと表面だけ軟らかいまま残る可能性がある。
以上のように、キャビトンの使いこなしは決して難しくはないが、基本を怠らないことが肝心である。仮封は派手さのない処置だが、丁寧に行えばトラブルを減らし、雑に扱えば思わぬ再治療を招く。経験20年を超える筆者自身も、若手の頃に仮封の軽視から痛い目を見たことがある。例えば根管治療中に仮封が漏洩し、次回来院時に根管内が排膿だらけになって愕然とした体験だ。それ以来、仮封材選びと扱い方を見直し、スタッフにも徹底するようになった。キャビトンはそうした失敗を教訓に、きちんと使えば確かな安心感をもたらしてくれる道具だと実感している。
適応症と適さないケース
キャビトンの適応症は、一言で言えば「短期間歯を封鎖したい全ての場面」である。典型的なのは根管治療の仮封であり、これはほぼ標準的適応と言える。またう蝕除去後の仮充填にも用いられる。たとえば深い齲窩の一時的保存療法として水酸化カルシウム製剤を貼薬し、その上をキャビトンで封鎖して経過を観察する、といった用途である。さらに、補綴治療の分野でもインレーやアンレー形成後、技工物装着までの間に窩洞を塞ぐのに使われる。いずれも期間にして数日から数週間程度の短期が想定されたシチュエーションである。
一方、キャビトンが適さないケースも把握しておく必要がある。まず長期間の仮封には不向きである。目安として数か月以上にわたる封鎖が必要な場合、キャビトンでは徐々に摩耗・脱落・漏洩のリスクが高まる。そのようなケースでは、グラスアイオノマーや一時的なレジン充填、またはテンポラリークラウン等、より長期安定性のある方法を検討すべきである。
また大きな欠損の仮修復にも適さない。例えば歯冠部の大部分が失われているような歯を数週間保たせたい場合、キャビトンでその形を作り上げるのは現実的でない。キャビトンはあくまで穴を塞ぐ材料であり、形態を構築して咬合力を支える用途には弱い。そうした場合にはレジンによる簡易的なコア築造や仮歯の装着が必要となる。また隣接面に及ぶような広範な窩洞も、キャビトン単独では保持が難しい。隣接面に穴が抜けるケースでは、フロスの使用で引っかかり簡単に外れてしまうため、この場合もレジンなどで補強するか他材を使うのが望ましい。
湿潤がひどく制御できない状況もキャビトンには不利である。例えば歯肉縁下まで及ぶ深い窩洞で出血が止まらないようなケースでは、キャビトンを入れても血液で流出して固まらない可能性がある。そのような場合、一時的に圧排や電気メスで出血を抑えたり、血餅が固まるのを待ってから仮封する工夫が必要だ。あるいは一旦酸化亜鉛ユージノールセメントで蓋をして止血し、後日キャビトンに置き換えるという方法もとられる。
アレルギーの懸念も一応考慮しておく。キャビトンは重篤なアレルゲンを含むわけではないが、酢酸ビニル系樹脂に対するアレルギーが皆無とは言い切れない。患者に樹脂類でアレルギー既往がある場合は注意深く経過を見るか、別の材料を検討すべきだろう。ただ、一般的な臨床ではキャビトン使用でアレルギー反応が問題になった報告はほとんどない。
最後に用途外使用の注意として、キャビトンは補綴物の仮着材には使えない。例えば仮歯を装着する際に内面へキャビトンを塗って接着するような使い方は想定されていない。粘着力が低く接着剤の代用にはならないため、仮着用には専用の仮着セメントを用いるべきである。同様に、義歯の一時固定や支台装置としても適応外であり、想定用途以外に流用しないことが安全面から重要である。
導入判断の指針(診療スタイル別に見る適性)
キャビトンの導入は、多くの場合それほど迷うような大きな投資判断ではない。しかし歯科医院の診療スタイルによっては重視すべきポイントや代替策の検討が異なるだろう。いくつか代表的なタイプ別に、キャビトンがどの程度マッチするか考察する。
保険診療が中心で効率重視のクリニックの場合
日常的に多数の根管治療や齲蝕処置をこなす保険診療主体の医院では、キャビトンは必須の実用品と言える。低コストで手早く仮封できるため、チェアタイム短縮と回転率向上に寄与する。練和の手間がなくスタッフ負担も軽減できるので、短時間で必要十分な処置を提供するという効率第一の診療に合致する。
また患者層的にも、保険診療中心のケースでは仮封期間中に強く噛んでしまったりといったアクシデント率もそれなりに高いと考えられる。その点、キャビトンファストのように短時間で硬化が安定する素材を使えば、そうした患者さんにも対応しやすい。万一外れてしまっても材料費が安価なので、無料で付け直すような場合でも経済的ダメージは軽微で済む。
効率重視の院長にとっては「仮封なんて何でも同じ」と思う向きもあるかもしれない。しかし上述のように、仮封の善し悪しが結果的に無駄なやり直し処置を増やすか減らすかに関わってくる。数分の手間と数十円の材料費で後日の余分な30分処置を防げるなら、こんなに割の良い話はないだろう。実際、多くの保険診療中心の先生方がキャビトンを常備し、信頼して使い続けているのはそのためである。コスト意識の高い医院こそ、安定した仮封によるトラブル回避が経営の助けになることを認識するとよい。
自費診療・高度治療を重視するクリニックの場合
審美やインプラントなど自費治療中心でクオリティ重視の医院では、可能な限り一回で治療を完結させ、仮封自体避ける戦略を取ることも多い。それでも根管治療や複数回に及ぶ処置が必要な場合、やはり仮封材の出番はある。その際に重視されるのは、やはり確実な封鎖性と後工程への悪影響の無さだろう。
キャビトンは封鎖効果が高く接着阻害も起こしにくいため、高品質な治療を追求する場面でも安心して使える。例えばオールセラミックインレーのセット前にキャビトン仮封していても、残渣を除去すればボンディングに支障をきたすことはない。また術中の写真映えを気にするような審美治療においても、ホワイトやアイボリーを選べば患者に仮の詰め物だと気付かれにくい利点もある(実際には術後説明で伝えるにせよ、見た目の印象は大切である)。
自費中心の医院では費用より効果が最優先となるため、もし他にキャビトン以上に封鎖性・耐久性の良い材料があればそちらを使うかもしれない。しかし現在のところ、水硬性仮封材としての実績やエビデンスではキャビトン(や同等品)がスタンダードとなっている。逆に言えば、変にマニアックな材料を使うより実績のある定番品で確実に封鎖する方がリスク管理上賢明だろう。
もっとも、高度な治療志向の先生方は仮封にも独自のこだわりを持つことがある。中にはキャビトンの上に光重合レジンをラミネートして完璧を期すという方法を実践する例もある。それも一つの工夫だが、前述のように除去がやや厄介になるため、手間とのバランスを考えたいところだ。総じて言えば、自費中心の診療においてもキャビトンは「なくてはならない黒子役」として治療を支えてくれる。目立ちはしないが縁の下で治療成功を支援する存在として、確実に押さえておきたい。
外科・インプラント中心で補綴をあまり行わない場合
口腔外科処置やインプラント治療が主体で、保存修復や根管治療はほとんど行わないクリニックもあるだろう。そのような場合、キャビトンの重要度は相対的に下がる。抜歯や外科では仮封材を使う場面自体が少なく、インプラント治療でも一次手術ではフラップを縫合するだけで仮封は不要だ。強いて言えば、インプラント上部構造のスクリューリテイン固定でアクセスホールを一時的に埋める際に仮封材を使う程度である。ただしその場合、通常は綿栓の上にコンポジットやワックスで蓋をすることが多く、キャビトンを使うことは稀である。
したがって外科系メインの医院では、キャビトンの使用頻度は低く在庫の優先順位も高くはないかもしれない。使うとしても年に数回でチューブ1本がなかなか減らない、という状況も考えられる。その場合でも、製品寿命が切れて硬化してしまっては肝心な時に使えないため、期限管理には注意したい。逆に言えば使用頻度が低いなら、必要なときに確実に使えるよう管理しておくことが大事だ。古くなったら買い替える程度のコストなので、定期的にチェックしておくとよい。
もっとも、完全に保存処置をしない歯科というのも珍しいため、ほとんどの医院では結局キャビトンの出番がゼロということはないだろう。外科中心でも、抜歯後の一時的な窩洞保護や、隣接歯の露髄処置など急なトラブル対応は起こり得る。その際に手元に適切な仮封材が無いと困るのはどの歯科医師も同じだ。したがって診療スタイルを問わず、「いざという時の安心材料」としてキャビトンを常備しておく意義は十分にある。
よくある質問(FAQ)
Q. キャビトンの仮封はどのくらいの期間もちますか?長期使用しても大丈夫でしょうか?
A. キャビトンによる仮封は短期間(一連の治療期間内)での使用を想定しています。おおむね数日から2〜3週間程度であれば適切に封鎖効果を保つとされています。ただし期間が長くなるほど咬合による摩耗やわずかな隙の発生で封鎖力が低下する可能性があります。特に1か月以上の放置は推奨されません。長期に渡る場合は途中で仮封をやり直すか、より耐久性の高い他の暫間充填材への切り替えを検討してください。仮封期間中でも、もし違和感(噛み合わせが急に低くなった等)や痛みが出た場合は、仮封が劣化・漏洩している可能性があるので早めに再来院いただくよう患者さんに案内しておくことが望ましいです。
Q. キャビトンにはユージノールが含まれていますか?レジンの接着に影響ありませんか?
A. キャビトンは非ユージノール系の仮封材であり、成分にクローブ由来のユージノールは含まれていません。主成分は酸化亜鉛・硫酸カルシウム・酢酸ビニル樹脂で、硬化後も表面に遊離成分が残りにくいため、後続のレジン接着処置への影響は極めて少ないとされています。実際、根管治療後のレジンコア築造や接着修復において広く問題なく併用されています。ただし接着操作を行う際は、キャビトンを完全に除去し、歯面を清潔にすることが前提です。わずかな残留でも気になる場合はアルコールガーゼで清拭するなどすれば万全でしょう。なおユージノールによる鎮痛効果はキャビトンには期待できませんが、歯髄への刺激が少なく安全に使用できる点で優れています。稀に酢酸ビニル樹脂などへのアレルギーを懸念される場合もありますが、臨床的には報告はほとんど無く、安心して使用できる材料と言えます。
Q. 仮封したキャビトンが取れてしまった患者にはどう対処・指示すべきですか?
A. 仮封が万一外れてしまった場合、患者さんには早めの再来院をお願いするのが基本です。まず電話等で連絡があった時点で、「穴が開いた状態で放置すると中が汚染されてしまう恐れがあるので、できるだけ早く来院してください」と伝えましょう。それまでの応急処置としては、「外れた所を清潔に保つように」と指示します。具体的には食後に軽くうがいをしてもらい、歯ブラシで強く突っ込まず周囲を清掃する程度で十分です。市販のガムや綿で自分で穴を塞ごうとする方もいますが、異物混入のリスクがあるので推奨しません。また痛みが出ている場合は市販鎮痛剤の服用でしのいでもらい、とにかく穴を清潔に維持してもらうことです。
患者には仮封材が外れること自体は時折起こり得ることで、外れたらすぐ対処すれば問題ない旨を説明し、不安を和らげます。再来院時には状況に応じて消毒・洗浄を行い、新しいキャビトンで仮封をやり直します。もし短期間で何度も外れる場合、噛み合わせの調整不足や厚み不足が考えられるため、その点を改善して封鎖し直します。患者さんへの事前指導(硬い物を避ける等)も再確認し、協力してもらうことが大切です。
Q. 「テンポラリーストッピング」との違いや使い分けは何ですか?
A. テンポラリーストッピング(一般に「ストッピング」と呼ばれることもあります)は、歴史的に仮封に用いられてきた蝋やガッタパーチャ系の仮封材です。細長い棒状(長さ約9cmの棒)になっており、使う際に小片に切って温めて柔らかくし、窩洞に押し込んで蓋をするという方法をとります。ストッピングの利点は、冷えると比較的硬くなり物理的に隙間を埋めること、X線造影性がある程度あること、一塊でスポッと除去しやすいことなどが挙げられます。特に根管内に綿栓がなくても塊で抜けやすい点は一部で評価されています。
一方、キャビトンのような水硬性の仮封材は、ペースト状で隅々まで行き渡り封鎖性が高いことが最大のメリットです。ストッピングは機械的封鎖に頼るため、壁との間に微小な隙間が残りやすく、長期間放置すると漏洩リスクが高まるとされています。またストッピングは加熱軟化の手間があり、操作にコツが要りますが、キャビトンは練和も加熱も不要で即座に充填できる手軽さがあります。
使い分けとしては、現在の臨床ではキャビトン等の水硬性仮封材が主流であり、ストッピングは特殊な場合に限定的に使われる程度です。例えば根管充填直後のごく短期間だけ仮封する間に、ストッピングを蓋代わりに乗せてすぐ外す、といった場面では有用かもしれません。しかし総合的には、封鎖効果と扱いやすさの観点でキャビトンに軍配が上がります。実際、古くからストッピングを使用してきた歯科医も、現在はキャビトンに切り替えていることが多いです。ただし診療スタイルによっては両方常備し、短期(ストッピング)と中期(キャビトン)で使い分けている例もあります。要は好みとケースバイケースですが、迷った場合はまずキャビトンを使っておけば間違いないでしょう。
Q. キャビトンEXやキャビトンファストなど複数種類ありますが、どれを選ぶべきでしょうか?
A. 現在、市場には従来型のキャビトンに加え、改良版のキャビトンEX、最新のキャビトンファストが流通しています。基本的な封鎖性能や適応症はどれも共通ですが、それぞれ使い勝手と硬化スピードに違いがあります。キャビトンEXは従来品よりペーストの粘つきが少なく扱いやすい点と、硬化後の耐摩耗性がやや向上している点が特徴です。キャビトンファストはさらに初期硬化が早まり、充填後30分で咬合できる速硬化が最大のメリットです。従来は仮封後1時間待つよう指導していたものが半分の時間で済むため、患者の負担軽減につながります。またファストでは保存容器の密閉性も高くなり、ペーストが乾燥しにくい工夫もされています。
どれを選ぶかは医院のニーズによります。スピード重視で患者さんの咬合制限時間を短縮したい、あるいは仮封後すぐに激しい咬合が予想される(あるいは患者が注意を守らない傾向がある)場合にはキャビトンファストが適しています。価格は従来品と大きく変わらないため、特段の理由がなければファストを採用して問題ないでしょう。既に従来品を使い慣れており、特に不満が無い場合は在庫品をそのまま使い続けても構いませんが、一度ファストを試してみて操作感や硬化時間の差を確認してみることをおすすめします。多くのユーザーは「もう元には戻れない」というほど快適さを実感しています。
なお製品ごとの色調バリエーションも若干異なります。アイボリー色が必要な場合はEXかファストを選ぶ必要があります(従来品はピンクとホワイトのみ)。総じて、新しい製品ほど改良されているのは確かですので、特別な理由がなければ最新モデルに移行する方がメリットは大きいでしょう。ただ在庫管理上、一度に複数種類を置く必要はないため、自院の用途に合致する1種類に絞っておけば十分です。どのタイプを使うにせよ、適切に扱えばキャビトンシリーズは期待に応えてくれるはずです。患者さんへの注意事項などは共通ですので、医院内でルールを決めて運用しましょう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科の仮封材「キャビトン」のすべて。添付文書や成分、注意点等を網羅的に解説