- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う「PRGプロテクトシール」とは?デュラシールとの違いや用途、注意事項
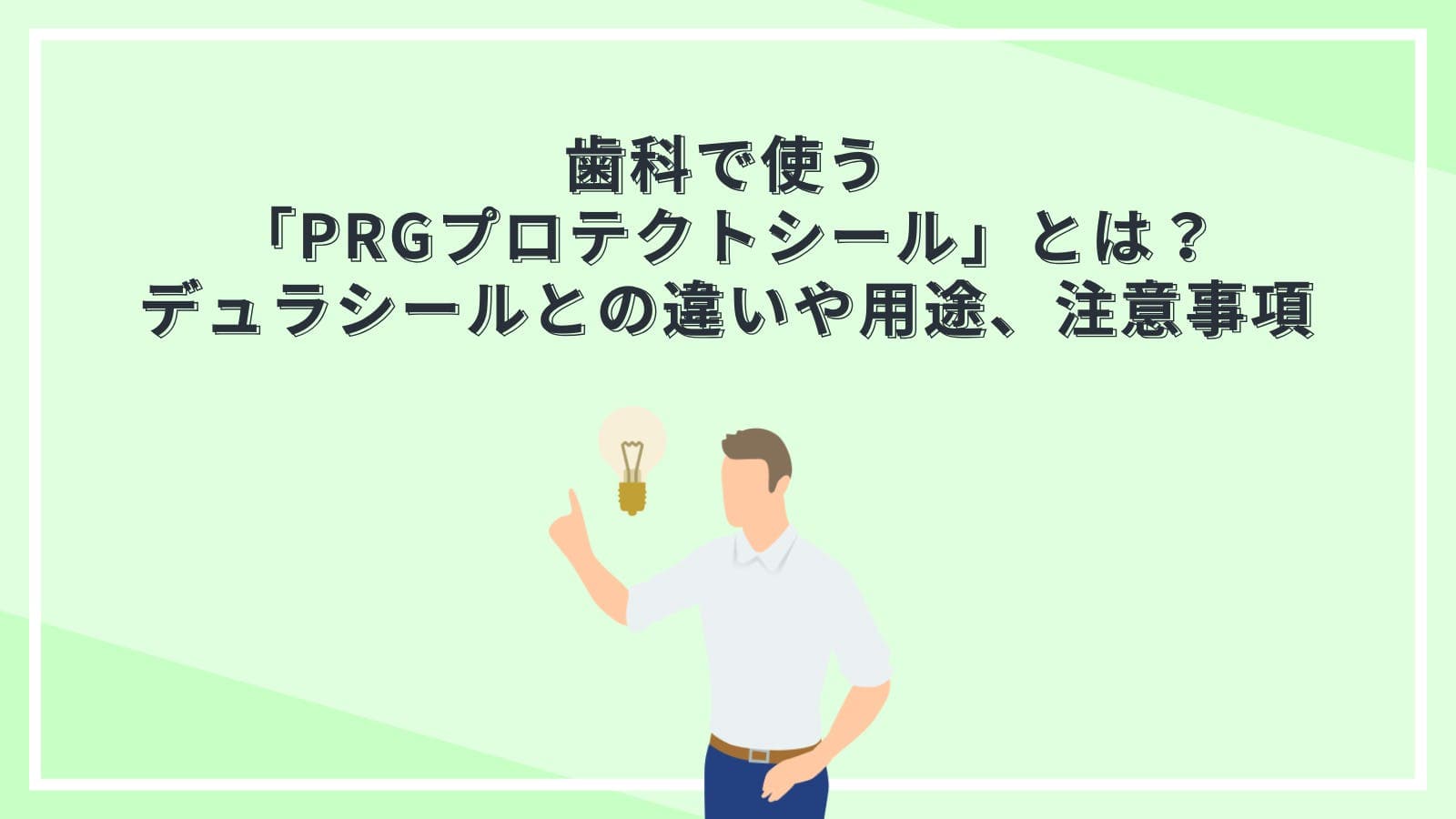
歯科で使う「PRGプロテクトシール」とは?デュラシールとの違いや用途、注意事項
一般歯科診療で日常的に行われるインレーやクラウン形成後の仮封処置は、地味ながら診療効率や患者満足度に影響する重要なステップである。例えば、保険診療でのインレー形成後に一時的なフタをしたところ、次回来院時に仮封が外れて患歯がしみてしまった経験や、仮封材が硬くなりすぎて撤去に苦労し探針を曲げてしまった経験はないだろうか。仮封材選びを疎かにすると、思わぬ再処置や患者からの急患連絡につながり、チェアタイムの浪費や患者の信頼低下を招く。臨床現場では「簡単に外れすぎず、しかし除去は容易」という一見矛盾する条件を満たす材料が求められてきた。また経営の視点では、仮封に余計な時間を取られずスムーズに本処置へ移行できることや、仮封中のトラブルを減らすことが医院全体の生産性向上につながる。こうした背景の中、近年登場したPRGプロテクトシールという仮封材が注目されている。本稿では、従来から使われてきたデュラシールとの違いを軸に、このPRGプロテクトシールの特徴・用途・注意点を臨床と経営の両面から解説する。長年の臨床経験に基づく現場目線と経営的考察を交え、読者が自院の診療スタイルに適した仮封材を選択する一助としたい。
PRGプロテクトシールの製品概要
PRGプロテクトシールは、株式会社松風が2014年に発売したレジン系の仮封用材料である。粉末と液を混ぜて用いる常温重合型(自己硬化型)の樹脂材料で、歯科用高分子系仮封材に分類される管理医療機器(クラスII)である。適応は、う蝕治療後から最終修復物装着までの間の一時的な窩洞封鎖であり、具体的にはインレーやクラウン、ラミネートベニアなどの形成後に削合部位を一時的にふさぐ用途に用いる。製品名の「PRG」は松風独自のS-PRGフィラー(表面処理プリレジンガラスフィラー)の技術に由来し、この仮封材にもS-PRGフィラーが配合されている。S-PRGフィラーはフッ化物イオンを含む6種類のイオンを持続放出するガラス粒子で、歯科用コンポジットレジン(ジオマー)などに応用されてきた。PRGプロテクトシールもその一製品であり、仮封中の歯質を守ることを意図してフィラーが組み込まれている点が大きな特徴である。粉末はアイボリー(象牙色)とピンクの2色展開で、液は無色透明の単一タイプである。1キット相当として、小分けサイズの粉35gと液50mL(各アイボリー色の場合)が用意されており、希望小売価格は粉・液各1本あたり約2,900円(税抜)である。大容量の粉250g・液250mLも販売されており、こちらは小容量品に比べて割安な価格設定となっている。液剤の容器にはスポイト不要のノズルが採用されており、従来の仮封材で見られたような専用スポイトの管理や液だれの煩わしさを軽減している。仮封材単独では保険点数に直接影響しないものの、治療全体の円滑さや患者の安心感に寄与するクリティカルな裏方アイテムと言えるだろう。
対するデュラシールは、Reliance社製(日本国内では茂久田商会が流通)のレジン系仮封材である。発売以来長年にわたり広く用いられてきた定番製品で、PRGプロテクトシールと同様に粉と液を混ぜて使う即時硬化型の仮封材である。医療機器承認番号から推測するとクラスII相当の管理医療機器であり、適応もほぼ同じく窩洞の一時封鎖に用いる。デュラシールは2000年代から使われている実績があり、多くの歯科医師がインレー形成後の仮封といえばまずこの製品を思い浮かべるほど浸透している。色調はレギュラーシェード(やや透明感のある白色)とライトシェード(低透明度の淡色)が用意され、症例に応じて選択できる。粉・液は2オンス(約56g程度)のボトルが標準キットとして販売され、さらにお得用の8オンスボトルも存在する。標準キットには粉・液のほか小型スポイトや滴下用プラグが付属しており、従来はスポイトで液を滴下して調合するスタイルであった。なお、デュラシールという名称はそのまま「耐久性のあるシール材」を意味しており、強度と除去性を両立した仮封材として位置付けられている。
主な特徴とスペックの比較(PRGプロテクトシール vs デュラシール)
仮封材として要求される性能は、封鎖中の安定性と撤去時の容易さのバランスである。PRGプロテクトシールとデュラシールはいずれもレジン系材料で、この点で従来の酸化亜鉛ユージノール系セメント(IRMやスーパーEBAなど)とは異なる性質を持つ。以下、主なスペックとその臨床的意味について両製品を比較しつつ述べる。
硬化後の弾性と硬度
PRGプロテクトシールはメーカーの命名が示す通り適度な弾力性(ゴム弾性)を備えるよう調整されている。硬化後に完全な剛体とはならず適度にしなやかで、時間が経過しても極端に硬化が進みすぎない性質である。このゴム状の弾性により、深いアンダーカット部まで入り込んでも、後の除去操作でパキパキと割れたり欠片が残ったりしにくい。一方、デュラシールも硬化後はゴム状の弾性を示すが、使用経験者の声では「時間が経つとやや硬く感じる」傾向が指摘されている。GDS(スタディグループ)の評価では、「PRGプロテクトシールは時間が経っても硬くなりすぎず、当院で以前使用していたデュラシールより除去しやすい」との報告がある。ただし両者ともゴム質で完全に軟らかいわけではないため、咬合力にはある程度耐える強度を持つ。実際、奥歯の臼歯部でテンポラリークラウン(TEK)を装着せず仮封材のみで経過を見たケースでも、両材とも咬合に耐えて疼痛も出さないとの臨床報告がある。この適度な硬さと弾性のバランスにより、仮封中に容易に割れたり脱落したりしない一方、除去時には塊のまま外しやすいという両立が図られている。
操作性(筆積み法による充填挙動)
両製品とも筆積み法と呼ばれる独特の操作で窩洞に充填する。専用の筆(ラウンドブラシのチップ)を使い、筆先に液を含ませてから粉末に浸し、筆先で小さな団子状のペーストを練るようにして窩洞へ盛り付けていく。この操作性に関して、PRGプロテクトシールは「ダレにくく付形しやすい適度な粘性」を特徴とする。筆先で練った際にペーストが流れすぎず、クルクルと丸めると自立する程度の粘度があるため、特にクラスII窩洞の近心遠心壁などにも垂れずに盛り上げられる。一方で適度に流動性もあるため、筆で軽く押さえれば窩壁にしっかり馴染む。デュラシールも筆積みに対応した材料で、従来から「扱いやすい」と評価されてきた。使用者の意見では「操作性はPRGプロテクトシールはデュラシールに近い」とされ、両者に大きな隔たりはない。ただし細かな違いとして、デュラシールの方がやや硬化時間が短めで早くゴム状に固まり始める傾向がある。PRGプロテクトシールは逆に作業時間に少し余裕がある印象で、余計な所に流れにくい反面、硬化完了まで若干ゆっくりである。実際、「操作時間が長めで形態付与しやすいが、硬化がやや遅い」との評価もある。両者とも常温重合で口腔内では概ね3分前後で硬化するため、極端に待たされることはない。適切なタイミングで咬合調整と余剰除去を行えば、いずれの材でもほぼ問題なく操作できるだろう。
辺縁封鎖性と湿潤性
仮封材の密閉性も重要な指標である。PRGプロテクトシールは製品資料にて「歯質への濡れ性を高め、高い辺縁封鎖性を実現」とうたわれている。実験としてフクシン染色液の浸漏試験において低い漏洩スコアが示されており、樹脂材料として歯質との適合が良好で微漏洩が少ないことが示唆されている。これにはS-PRGフィラーの効果もある可能性がある。フィラーから放出されるフッ素やストロンチウムイオンはう蝕抑制や象牙質の耐酸性向上に寄与し、仮封期間中の歯質劣化を防ぐことで長期的な封鎖性を担保する狙いがある。一方のデュラシールも臨床的には十分な封鎖性を示し、通常2〜3週間程度の仮封期間で二次う蝕を誘発するような不適合は報告されていない。ただしデュラシール自体には予防効果を持つ成分は含まれないため、長期的な観点ではPRGプロテクトシールの予防歯科的メリットが評価ポイントとなるだろう。いずれの場合も、材料の性能を活かすには適切な術式(窩洞の十分な清掃乾燥、必要に応じた裏層処置)が前提となる。
色調と視認性
PRGプロテクトシールはアイボリー(白色)とピンクの2色を展開する。アイボリーは歯に近い色調で審美的に目立ちにくく、前歯部の仮封でも過度に目立たない。一方ピンク色は一見すると派手だが、除去残渣を視認しやすいメリットがある。実際、仮封材が歯質に残っているかどうかは白い粉末状だと判別しづらい場合があり、ピンクは取り残し防止に役立つ。デュラシールは国内ではレギュラー(やや透明白)とライト(不透明淡色)の2種が一般的だが、海外仕様などではホワイトやイエローなど計4色程度のラインナップも存在する。日本では実質半透明か不透明かの選択肢と考えてよい。審美性重視ならレギュラーシェードで目立たなくし、治療部位を隠したい場合(例えば深い着色象牙質を患者に見せたくないとき)はライトシェードを使うといった使い分けがされてきた。色に関してはどちらも十分なバリエーションがあり、大きな差異とは言えないが、ピンク色の存在はPRGプロテクトシール特有の利点である。仮封材の残留に気を遣う歯科医師には、この派手な色がむしろ安心感を与えるだろう。
その他のスペック
両製品とも粉液混和型であり、混合比は明確な指定がない(適量を混和)が、経験的には液1滴に対し粉少々を筆先にまとわせることで適切な粘度になる。寒天印象材のような練和器具や加熱は不要で、常温で即座に使える手軽さは共通する。硬化収縮や熱発生も最小限で、窩洞内で使って歯にひび割れが入るようなことは基本的に起こらない。また、樹脂系仮封材はユージノール系と異なり刺激臭が少なく、硬化後は無味無臭である。デュラシールは液の主成分がメチルメタクリレートであり、混和時にツンとしたモノマー臭が感じられる。しかし硬化すれば臭いは消えるため患者に不快感は残らない。PRGプロテクトシールの液も同様のモノマー系溶剤(安息香酸ベンジルなど)を含むため、混和中は多少の臭気があるが、可塑剤の配合バランスにより刺激臭は抑えられている印象である。いずれにせよ、臭いの点では従来の仮封用セメント(クローブ油臭)より患者への訴えは少ないだろう。なお、両者とも医療機器認証を取得しており品質管理はなされている。PRGプロテクトシールの認証番号は225AKBZX00087000、デュラシールの承認番号は15300BZY1836号である。医療事故やクレームの大きな報告はなく、安全性に関しては同等レベルと考えて差し支えない。
既存材料との互換性と運用上の注意点
PRGプロテクトシールおよびデュラシールの使用にあたっては、他の歯科材料や手技との相性に注意する必要がある。まず窩洞内の湿度管理が重要である。どちらのレジン系仮封材も水分に弱く、乾燥が不十分だと脱離しやすいことが知られている。使用前にはエアーブローなどで窩洞を十分乾燥させることが推奨される。ただし乾燥させすぎて象牙質が痛むほどエアーを強く当てる必要はなく、表面の水分を飛ばす程度でよい。また、う蝕が深く象牙質が露出している場合には、直接仮封材を触れさせる前に水硬性の裏層材(水酸化カルシウムライナーやグラスアイオノマーセメントなど)で覆覆を行うべきである。これは患者の疼痛予防と細菌封鎖の観点から基本的な手順であり、仮封材固有の注意点というより一般的な配慮である。
次に他材との直接接触についての注意である。レジン系仮封材はモノマー重合によって固まるため、周囲に重合を阻害する物質があると硬化不良を起こす恐れがある。代表的なのがユージノール系材料で、仮封直前に根管貼薬などで酸化亜鉛ユージノールペーストを使った場合などが該当する。PRGプロテクトシールの添付文書でも「ユージノール系材料の上に使用する場合はワセリンを塗布すること。直接充填すると硬化不良の原因となる」と明記されている。これはデュラシールでも同様で、ユージノール残渣がある場合は一層取り除くか、表面にワセリンやセパレーターを塗ってから仮封するのが望ましい。またレジン含有の材料上への仮封にも注意が必要である。近年の支台築造(コア)やボンディング処置ではレジン系の材料を多用するため、それらが窩底や周囲に露出した状態で仮封材を充填すると、重合過程で半重合の層どうしが接着し合い、仮封材が貼り付いて除去困難になるケースがある。これも添付文書に注意喚起があり、レジンコア材や接着材が露出している場合は事前にワセリンを塗布しておくべきである。マトリックスバンドを用いる部位(隣接面が開放されたクラスIIなど)でも、バンド表面に薄くワセリンを塗ってから仮封材を盛ると硬化後にバンドがスムーズに外れる。
感染対策と器材管理の面でも留意点がある。PRGプロテクトシールには別売りで専用の「ユニバーサル筆」が設定されており、柄と使い捨て交換式の筆先チップからなる。デュラシールでも筆積み法を行う際はナイロン製のラウンドブラシなどを使用する。これらの筆は患者ごとに新しいものを使うか、少なくとも滅菌または十分な清拭消毒を行う必要がある。レジン仮封材は軟質とはいえ口腔内で固まるため、筆先に硬化残渣が付着すると清掃が難しい。経済的理由で筆先を使い回す医院もあるが、清潔な状態で材料を練らないと汚染が混入し封鎖不良の原因となりかねない。松風のユニバーサル筆チップは1セットに複数本入りで安価に提供されているため、使い捨て感覚で交換することが推奨される。また、仮封材の粉・液は可燃性の化学物質(特に液はモノマー)を含むため、取り扱いは換気の良い場所で火気厳禁である。使用後は速やかに容器のフタを閉め、揮発による濃度上昇や酸素接触を最小限にする。保存は室温1〜30℃の暗所が望ましく、在庫を大量に抱えすぎないよう注意する。特に液剤のメタクリル酸モノマーは経時で重合したり揮発したりして劣化するため、開封後はなるべく半年〜1年以内に使い切る方が良い。
最後に患者への指示についても触れておく。仮封材はあくまで一時的な封鎖材であり、過度な咬合力や粘着力には耐えられない。デュラシールについて患者向けに説明する場合、「ゴムのような仮のフタをしています。ガムやキャラメルなどネバネバした物は避けてください」と指導することが多い。PRGプロテクトシールでも基本は同様であり、粘着性の食品や硬すぎる食品は治療完了まで控えてもらう。仮封が取れてしまった場合はすぐ来院してもらうよう伝え、痛みや沁みが出たら放置せず対応する旨も周知する。患者にとって仮封は治療途中の不安材料になりやすいが、「次回までの間、この材料が歯を守ってくれる」という安心感を与えられるよう丁寧な説明を心がけたい。特にPRGプロテクトシールの場合、フッ素徐放性があることから「虫歯を再び防ぐ効果も期待できる材料で蓋をしています」と付け加えると、患者の納得度やセルフケア意識向上にもつながるだろう。
経営面から見た導入メリットとコスト試算
仮封材そのものは1症例あたり数十円程度のコストにすぎないが、その間接的な経営インパクトは軽視できない。まず材料費について簡単に触れると、PRGプロテクトシールの小ボトルセット(粉35g+液50mL、計約5,800円)からは数十〜数百症例分の仮封が可能であり、1症例あたりに換算すればごく僅かな出費である。同様にデュラシールも標準ボトルキットで数百円台/10症例程度のランニングコストと言われ、大きな負担ではない。従って、価格だけを理由にどちらかを諦める必要は基本的に無い。一方で、仮封材の性能差が医院経営に与える影響は主に時間と信頼の面で現れる。
チェアタイムの効率化は重要な指標である。仮封の操作に手間取ったり、硬化に無駄に時間がかかったり、除去に手こずったりすると、わずか1〜2分のロスでも積もれば診療スケジュールに響く。例えば、デュラシール使用時に硬化が早すぎて形態修正に手間取り、やり直しに1分ロスした経験がある場合、それが週に何度も起これば月間で数十分の損失となる。PRGプロテクトシールは前述の通り作業時間にゆとりがあり、形態調整を落ち着いて行えるため、せわしなく焦る場面が減るだろう。また除去時に一括でスルリと外れると、探針でガリガリ掻き出したり、残留片をバーで削ったりする時間が節約できる。仮に撤去作業が毎回30秒短縮されるとしても、1日に10症例あれば5分の短縮、1年では数百分(数時間)の診療時間創出となる。1症例数十円の材料費で時間を買う効果が得られると考えれば、投資対効果(ROI)は決して小さくない。特に保険診療中心で回転率が求められる医院では、この時短効果がそのまま増患や残業削減につながる。
次に再処置リスク低減によるコスト削減がある。仮封材が外れてしまい急患対応をした場合、本来予定していた診療枠を圧迫し他患者の待ち時間増大を招く。また無償対応するケースも多く、その分の人件費がロスとなる。デュラシールは適切に使えば滅多に外れないが、やはり粘着物で外れる事故はゼロではない。PRGプロテクトシールはメーカーの調査でも縁漏れの少なさが示唆されており、歯質への付着性が高い分だけ脱離しにくい可能性がある。加えてフィラーの効果で二次カリエス抑制が期待できるため、仮封期間が延びてもリスクを最小化できる(※長期仮封自体は推奨されないが、患者の事情で治療間隔が延びた場合などの保険となる)。これらは患者満足度の向上にも寄与する。仮封が安定していれば患者は治療途中でも安心して過ごせ、医院への信頼も増す。患者からの信頼は口コミやリピートに繋がり、長期的には収益性の向上要因となる。
さらに、PRGプロテクトシールの持つ付加価値サービスをマーケティングに活かす視点もある。例えば予防歯科に力を入れるクリニックなら「治療中もフッ素パワーで歯を守る仮封材を使っています」とアピールできる。患者には細かい違いは分からなくとも、「最新の良い材料を使って丁寧に処置してくれる医院」というブランディングに繋がる。このように、仮封材の選択一つでも医院の姿勢を示すことができ、それが他院との差別化や自費治療の付加価値説明にも利用できる。
最後に耐用性と在庫管理についての経営視点を述べる。粉液タイプの仮封材は開封後も比較的長期間保管できるが、経年で劣化する可能性がある。大量購入して使い切れず廃棄するのはコスト浪費となるため、自院の症例数に見合ったサイズを選ぶことが大切である。保険診療中心で日々多数のインレーを行う医院なら、大容量のPRGプロテクトシール250gセットを導入し単価を抑えるメリットがある。一方、自費中心で仮封の出番が少ない医院では、小容量を購入して使い切り頻度を上げる方が品質劣化を防げ結果的に無駄がない。デュラシールについても同様である。在庫品の使用期限の管理も忘れずに行い、古い材料による硬化不良などを防ぐことが肝要である。
使いこなしのポイントと導入初期の注意
新たにPRGプロテクトシールを導入する場合、その使いこなしのコツを習得することで効果を最大限引き出せる。まず導入初期には、スタッフ全員で筆積み法の練習をしておくとよい。特に歯科衛生士や助手が仮封充填をアシストする場合、粉と液の扱い方や混合比の目安を共有する必要がある。練習では実際に模型の窩洞に筆積み操作で充填し、適切なペースト状になる粉液比を体感する。液を付けすぎるとサラサラに流れて窩底に溜まり、粉が多すぎるとボソボソで筆から離れない。「筆に液を含ませすぎず、粉も筆先の半分程度まで付着させ、くるくると回して団子状にまとめる」という基本手順を身につけると、本番でも失敗しにくい。また、遠心側やコンタクト部など見づらい部位から盛り始めると良いというポイントもある。窩洞全体にまんべんなく伸ばし、特に辺縁部(マージン)に段差が生じないよう筆でしっかり押さえ込むことが重要である。盛り過ぎて咬合が高くならないよう、最後に噛ませてから余剰を除去するプロセスも徹底したい。
硬化が始まるタイミングの見極めもポイントである。PRGプロテクトシールの場合、口腔内で約3分ほどで完全硬化するが、1分前後経過した時点で一度咬合確認し、高い部分を削ぎ取るのがコツである。硬化直後はまだわずかに柔軟性が残るので、スケーラーや探針で余剰をカットしやすい。これを逃すとカチカチになってから調整する羽目になり、せっかくの除去性の良さが半減する。デュラシールでも同様の手順が推奨されており、硬化しすぎないうちに形を整えるのが仮封材全般に通じるコツと言える。
除去時のテクニックもマスターしておきたい。PRGプロテクトシールは適切に使えば一塊で外れるが、それには除去の起点を作ることが必要である。具体的には探針の先や細めのエキスプローラーを、仮封材と歯との境目に差し込む。辺縁がはっきりしていればそのまま引き上げれば外れるが、引っかかりが弱い場合は探針を前後左右に小さく動かして隙間を作り、空気を入れるようにする。するとパコンと塊状に剥離する感覚がある。無理に力を入れず、テコの原理で軽く浮かすイメージが大切である。デュラシールでも基本は同じだが、こちらはやや硬めのため、深いアンダーカットでは一部がちぎれて残ることもある。その場合でもピンセットで摘まめる大きさに残すことがコツで、小さく粉砕してしまわないよう注意する。PRGプロテクトシールのピンク色を使用していれば、残留片は色で判断できるので取り残し予防になる。逆にアイボリーを使った場合は、取り残しが象牙質と同化して見逃しやすいので、ルーペや探針でよく確認する習慣をつけよう。
院内体制としては、誰が仮封処置を担当しても質が一定になるようオペレーションを整備することが望ましい。例えば、歯科医師が形成後すぐ席を外して技工所連絡や他の患者対応を行い、その間に歯科衛生士が仮封をしておく、といった時間効率的な流れを組む医院もある。そのためには衛生士もPRGプロテクトシールの扱いを習熟している必要がある。メーカーのデモ依頼やセミナー参加も検討し、スタッフ研修の機会を設けるのも良いだろう。松風は営業担当による医院内デモを行ってくれることがあるので、新規導入時には問い合わせてみる価値がある。また、最初のうちはデュラシールと併用し、症例によって使い比べてみるのも勉強になる。そうすることで自院にとって本当に使いやすいのはどちらか、使用感や患者の反応から判断できる。
患者説明のポイントとしては、前述のように食事指導や万一外れた際の対処を丁寧に伝えること。そして「本日は仮の蓋をしていますが、次回しっかり本物をつけますので安心してください」と声掛けし、治療途中であることを理解してもらう。PRGプロテクトシールを使った場合は「仮蓋にフッ素が入っていて歯を守ります」と一言添えると、患者の安心感はより高まるだろう。些細な違いかもしれないが、患者とのコミュニケーションにおいてこうした先進材料の活用をアピールすること自体が医院の信頼獲得に繋がる。導入当初はスタッフ間で声掛けの内容も共有し、統一した説明を心がけたい。
適応症と使用を避けるべきケース
PRGプロテクトシールとデュラシールが力を発揮する適応症は、おおむね共通している。両者ともインレー・アンレー、3/4クラウンやジャケットクラウンといった部分的な歯冠修復の仮封に最適である。こうしたケースでは形成窩洞が比較的小さく、仮封材のみで蓋を作ることで充分対応できる。また短期間(次回まで1〜2週間程度)の一時封鎖には両製品とも良好な密封性を示す。う蝕除去後に即日修復せず経過を見る場合や、インレーセットまで技工期間が必要な場合、さらにはダイレクトボンディングの合間(ラバーダム下で数日後に持ち越す等)にも利用できる。
適応が難しいケースとしてまず挙げられるのは、長期に及ぶ仮封である。PRGプロテクトシールの添付文書では「1ヶ月以上に渡る仮封には使用しないこと」と明記されている。デュラシール自体にも公式な期間制限はないものの、経験上長期間放置すると硬化が進みすぎて除去しにくくなったり、周囲からの微少漏洩で辺縁部に着色や二次う蝕リスクが生じたりする可能性がある。従って、長期仮封が見込まれる場合(例えば患者の事情で治療再開が大幅に遅れる場合など)は、より耐久性の高い仮封法に切り替える方が良い。具体的にはテンポラリークラウンの装着や、グラスアイオノマーセメントによる封鎖、場合によっては裏層材と軟質レジン仮封材の併用などを検討する。
また、歯内療法(根管治療)中の仮封にもレジン系仮封材は基本的に向かない。根管治療では薬剤の効果や封鎖力から、酸化亜鉛ユージノール系の軟鋳セメント(例えばハイボンド)や、吸水膨張による密閉が得られるキャビトン(水硬性仮封材)が使われることが多い。PRGプロテクトシールは「歯内療法処置後の仮封には使用しないこと」と禁忌事項に明記されている。これは上記の理由に加え、根管内の湿潤環境ではレジン仮封材が十分硬化しない可能性や、ユージノールの影響を受けやすいことが考えられる。従って根管充填間の仮封や鎮痛剤貼薬時の封鎖には、従来通り適材(IRMやワンペーストタイプの軟封鎖材)を用いるのが無難である。
さらに大きな欠損への仮封にも限界がある。例えば全周的なクラウン形成を行った支台歯に、仮封材だけで蓋をするのは非現実的である。この場合は仮歯(TEC)を作製して被せる必要がある。同様に、ブリッジの仮封や咬頭全体が欠損した大臼歯の仮封なども、レジン仮封材単独では保持が難しいか咬合に耐えられない可能性がある。PRGプロテクトシールやデュラシールは基本的に単一歯の窩洞封鎖を目的としており、形態の再現が難しい広範囲には適さない。極端に深い窩洞やフロアが大きく開いた洞形態では、あらかじめ綿栓や遮蔽材で底を埋めてから仮封材を充填するなどの工夫が必要になる。
アレルギーリスクも一応挙げておきたい。成分的に、両製品ともメタクリル酸系モノマーを含むため、レジンアレルギー既往のある患者には使用しないのが原則である。もっとも患者レベルで重度のレジンアレルギーは稀で、多くは術者側(長年レジンに触れてきた歯科医師・衛生士)の接触皮膚炎という形で問題化することが多い。手袋や防湿で直接触れないようにする対策と、万一体調不良や発疹が出た場合は使用中止し医療機関を受診する、といった一般的注意で足りるが、頭の片隅に入れておくべきポイントである。患者に関しては、過去にプラスチック製仮歯で腫れた経験がある等の情報があれば避けるか様子を見る程度で、過度に心配しすぎる必要はない。
最後に、代替アプローチとして考えられるケースを述べる。もし仮封材自体を使わずに済ませられるならそれに越したことはないという考えもある。例えば小さなコンポジットレジン修復であれば、その日のうちに充填してしまえば仮封不要である。またデジタル技工の普及により、即日補綴物装着(ワンデイトリートメント)が可能なら仮封は不要になる。極端な例では、ラバーダム防湿下で接着操作を翌日に持ち越す場合、窩洞をテフロンテープなどで封入してそのまま仮封材なしで維持する術式も報告されている。ただし一般的にはリスクが高く推奨はできない。結局のところ、安心確実に歯を保護する仮封は依然不可欠であり、その中でより扱いやすく安心な材料を選ぶことが求められる。PRGプロテクトシールとデュラシールはいずれも信頼できる選択肢だが、前述のような得意不得意を踏まえてケースバイケースで使い分けるのが賢明である。
歯科医院のタイプ別に本製品は誰に向いているかを解説
仮封材選びは、歯科医師それぞれの診療スタイルや医院方針によって重視ポイントが異なる。ここでは典型的な医院タイプ別に、PRGプロテクトシール導入の向き不向きやメリットを考察する。
1. 保険診療中心で効率最優先の医院
一日に多数の患者を回し、インレー・クラウンなどの修復処置もスピーディに行うクリニックでは、仮封材に求めるのはとにかく安定して早いことである。デュラシールは長年の実績があり、多くの歯科医師が手慣れている点で安心感がある。操作も硬化も素早く、除去も概ね簡単で、大きな不満は少ないだろう。ただ、PRGプロテクトシールに切り替えることで得られる僅かな時短効果や除去の確実性は、効率重視の医院ほど恩恵が大きい。特に複数チェアをアシスタント付きで回すような場合、スタッフが扱いやすい材料はミスを減らし全体の流れを滑らかにする。PRGプロテクトシールはピンク色の利用で「取り残しゼロ運動」を展開することもでき、院内標準化に役立つだろう。一方、コスト意識が強い保険中心医院では、新材料導入にシビアな面もある。とはいえ前述のように材料単価の違いは些細であり、トラブルによる機会損失防止という観点からは導入価値は十分にある。
2. 高付加価値の自費診療を重視する医院
審美歯科や予防歯科など、患者への付加価値提供を重視するクリニックでは、細部にこだわった材料選択がブランドイメージにつながる。PRGプロテクトシールはS-PRGフィラーによる予防効果や先進性をアピールできるため、このような医院にはマッチする。例えばオールセラミックの高額治療中に、「仮歯(仮封)にも歯を守る材料を使っています」と説明すれば、患者は「自分は良い治療を受けている」と感じやすい。院内のこだわりとしてブログやSNSで発信すれば、他院との差別化にも役立つだろう。加えて、自費治療では仮封期間が長引くケースもある(技工精度を上げるため複数回試適を行う等)。その際にPRGプロテクトシールの封鎖性やフッ素放出性は歯の健康を守る上で心強い。デュラシールも安定はしているが、特筆すべき付加価値はないため、高付加価値路線の医院ならPRGプロテクトシールの方が医院の提供価値と哲学に合致するだろう。ただし一つ注意として、審美領域でピンク色の仮封は目立ちすぎて患者が驚く可能性がある。前歯部ではアイボリーを選択し、説明時に「ピンクも選べるがあえて歯と近い色にしている」と一言触れるなど配慮しても良い。
3. 外科・インプラント中心で一般治療は少なめの医院
口腔外科やインプラント専門に近いクリニックでは、そもそも小さなインレー修復の機会が少ないかもしれない。仮封材の使用頻度が低い場合、デュラシールの大きなボトルを買っても持て余す可能性がある。その点、PRGプロテクトシールは少量セットがあり、必要な時に無駄なく使える利点がある。インプラント手術の際の仮封(例えば二次オペまでのヒーリングアバットメント周囲封鎖等)には通常仮封材は用いないが、残根保存や補綴前提の外科処置で一時的に穴を塞ぐ場面では有用だ。例えば抜歯即時インプラントまでの間、隣接するカリエス部位を仮封しておく、などの応用が考えられる。外科系のドクターはレジン練和に不慣れな場合も多いが、PRGプロテクトシールはダレにくいため多少不器用でも扱いやすいだろう。逆に根管治療など保存分野は積極的に行わない医院であれば、前述したように本製品を使うべきでない症例(根管仮封など)はそもそも生じにくい。よって自院の診療範囲内で安全に使えるという点で、導入リスクも低いと考えられる。ただ、使用頻度が低すぎると粉末が湿気たり液が劣化したりする恐れがあるため、購入時は最小単位に留め定期的に買い替える方が結果的に経済的である。
4. 経験豊富で道具にこだわりのある歯科医師
例えば長年デュラシールを愛用し「これで困ったことはない」というベテラン開業医も多い。そのような方にとって、新製品への乗り換えは煩わしく映るかもしれない。慣れ親しんだ材料でルーティンが確立しているなら、無理に変える必要はないとも言える。ただし、PRGプロテクトシールは決して操作を難しくするものではなく、従来テクニックの延長で使える点が強みである。デュラシールで築いた筆積みテクニックやタイミングの掴み方はそのまま活かせるため、リスクの少ない乗り換えが可能だろう。むしろベテランであればあるほど、細かな違いによるメリットを享受できる。探針を曲げた経験があるならば、次からは曲げずに済むという安心感は何物にも代えがたい。経営コンサルタントの視点では、新材料導入はスタッフのモチベーション向上にも繋がる。長年同じ道具ばかりだと惰性になりがちな現場に、新風を入れることで知的刺激となる。結果的に院内勉強会が開かれたり、スタッフから改善提案が出たりと良い波及効果も期待できる。従ってベテラン歯科医にも、ツールのアップデートは定期的に検討する価値がある。デュラシールをベンチマークとしてPRGプロテクトシールを試用し、「やはり旧来品で十分」と判断するのも一つの結論だが、その評価作業自体が医院の知見を深めるはずだ。
よくある質問(FAQ)
Q. PRGプロテクトシールはどのくらいの期間まで仮封に使えるのか?
A. 製品の添付文書では長期(1ヶ月以上)に及ぶ仮封には使用しないよう明記されている。通常は次回予約までの1〜2週間程度の短期間で使用し、もし治療間隔が延びる場合は途中で仮封材を交換するか、より長期安定性のある方法(仮歯装着など)に切り替える方が良い。長期間放置すると硬化が進みすぎたり封鎖力が低下したりする可能性があるため注意が必要である。
Q. PRGプロテクトシールに含まれるS-PRGフィラーの効果は具体的に何か?
A. S-PRGフィラーは松風独自のバイオアクティブフィラーで、フッ化物イオンを含む6種類のイオンを徐放する。これにより歯質の再石灰化や抗菌効果、酸の中和などが期待できる。仮封期間中、周囲の歯質を強化し二次う蝕を抑制するサポートとなる。ただし、劇的な効果ではなくあくまで補助的な作用であることに留意する。日常のフッ化物応用や口腔清掃が主体であり、フィラーはあくまで治療中の環境を健全に保つ一助と考えられる。
Q. デュラシールとの価格差はどの程度あるのか?コスト面で有利不利は?
A. 両者の標準キット価格には大きな差はない。デュラシールは発売が古いためディスカウント価格で流通している場合もあるが、PRGプロテクトシールも医院向け価格ではさほど高価ではない。仮封1症例あたりに換算すると数十円程度であり、むしろ余剰在庫や使い切り易さの方がコストに影響する。PRGプロテクトシールは小分けサイズがあるため、少量ずつ購入して鮮度を保てる利点がある。経済的には、材料単価よりも削減できるチェアタイムや防げるトラブルによるメリットの方が大きく、総合的に見てコストパフォーマンスは高い。
Q. 仮封材を除去する際、歯や器具を傷める心配はないか?
A. 適切に操作すれば心配はほとんどない。PRGプロテクトシールは適度な弾力のおかげで、探針を差し込んでも強い力をかけずに外すことができる。これにより探針やエキスプローラーが曲がったり折れたりするリスクが低減される。デュラシールでも基本的には容易に外れるが、長期間経過した場合などは少し硬くなるため慎重な操作が必要となる。コツとしては、除去時に無理にこじらず隙間に器具を入れて空気を通すイメージで外すこと。歯面に残った微細片は必ず取り除く必要があるが、ピンク色の仮封材を使っていれば確認しやすい。バーで削って外す場合も、軟質なので歯質を傷めにくい。総じて、両製品とも除去時に器具や歯を損傷させにくい設計になっている。
Q. 研磨・仕上げは必要か?仮封材をしたまま何か処置すべきことはある?
A. 仮封材自体の研磨は基本的に不要である。咬合調整後、表面がざらついている場合でも患者が舌で触れて極端な不快を訴えることは少ない。ただ、非常に鋭利な尖りが残った場合は軟化しきらないうちに表面を綿球でなでるか、硬化後に軽くバーで滑沢にすることもある。多くの場合は唾液中で表面がなじんで滑らかになるので問題ない。また、仮封期間中に特別な処置は必要ないが、患者には歯磨きの際に仮封が取れないよう優しく磨くよう指導しておく。もし仮封中に痛みや外れが起きたらすぐ連絡してもらうよう再度周知すると良い。特にPRGプロテクトシールはフィラー効果で表面にプラークが付きにくいとも言われているが、だからといって清掃を怠ってよいわけではない。通常の歯磨きを続けてもらうことで、仮封期間中の口腔衛生も問題なく維持できる。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う「PRGプロテクトシール」とは?デュラシールとの違いや用途、注意事項