- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科の「カッパーシールセメント」とは?使い方や特徴・成分、効果時間を解説
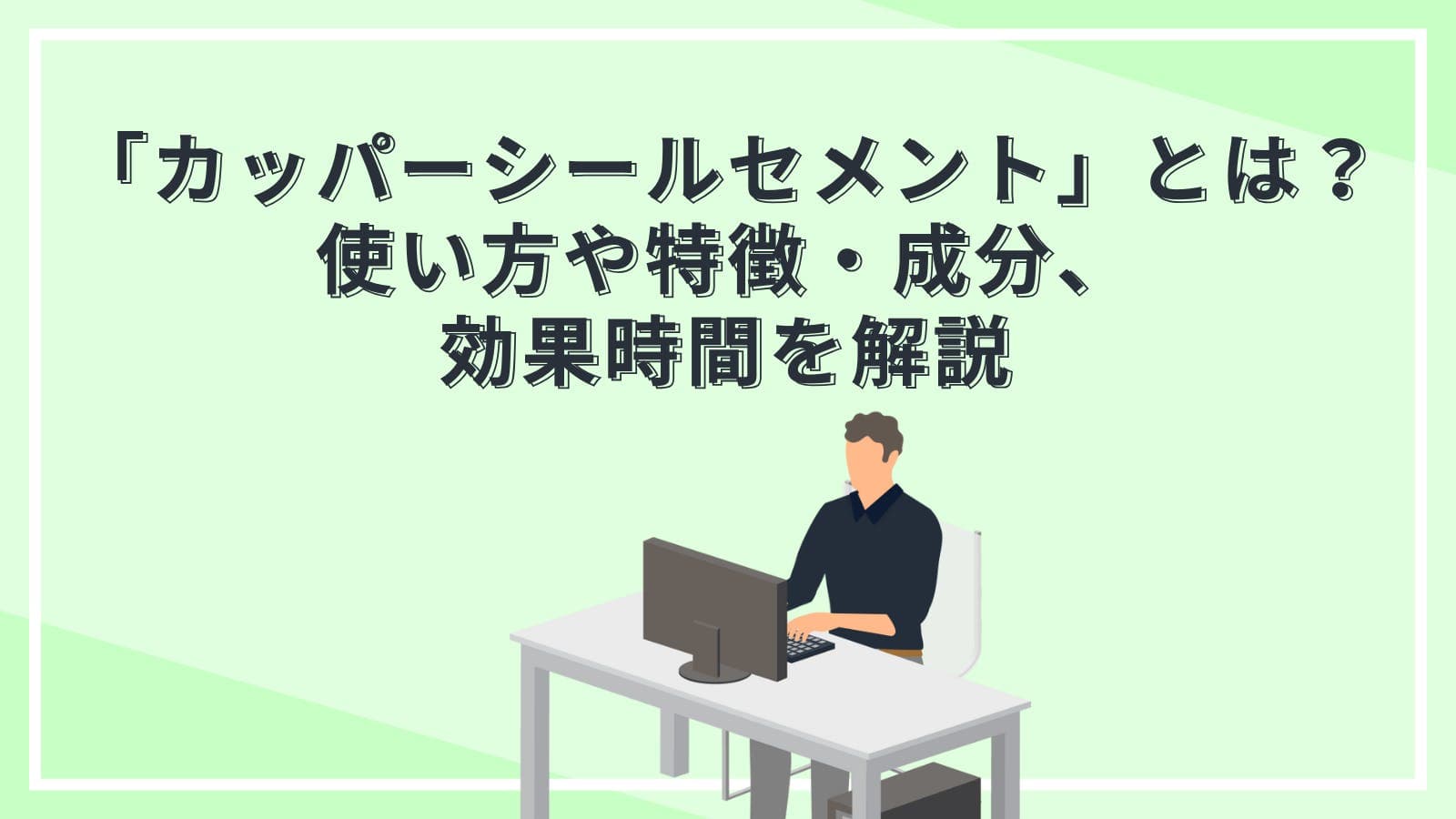
歯科の「カッパーシールセメント」とは?使い方や特徴・成分、効果時間を解説
ある夕方、根管治療中の患者が「仮詰めが取れてしまった」と急患来院した経験はないだろうか。忙しい診療の合間に仮封のやり直しを迫られる状況は、臨床家にとって避けたいトラブルである。仮封材の選択は地味ながら重要であり、適切な材料を使えばこうしたトラブルや患者の不安を減らすことができる。歯科で伝統的に用いられてきた「ユージダイン」(酸化亜鉛ユージノール系の仮封用セメント)に対し、近年はカッパーシールセメントという製品名を耳にすることが増えた。本稿では、カッパーシールセメントとは何か、その使い方・特徴・成分・効果時間などを臨床と経営の両面から詳しく解説する。忙しい保険診療中心の先生から高品質な自費治療を志向する先生まで、それぞれの診療スタイルに合わせた仮封材選択のヒントを提供したい。
製品の概要
カッパーシールセメントは、株式会社ジーシー(GC)が提供する歯科用の仮封材である。正式には「ジーシー カッパーシールセメント」という管理医療機器(クラスII)で、一般的名称は歯科用リン酸亜鉛セメント(仮封用)に分類される。粉末と液を練り合わせて使用する化学硬化型のセメントであり、一時的な充填(仮封)を目的として開発された製品である。想定される適応症は、う蝕処置や根管治療の合間における暫間的な窩洞の封鎖である。特に無髄歯(失活歯)のように歯髄のない歯では自発痛の懸念が少ない一方で、咬合圧に耐える仮封の強度が求められる。カッパーシールセメントはそうした状況で威力を発揮するよう設計されている。製品の色調はピンクとホワイトの2色が用意されており、処置部位や用途に応じて使い分けが可能である。包装内容は粉末125gと液58mL(90g)が基本セットで、医療機器承認番号は「12400BZZ02971000」と登録されている。なお本製品は仮封専用であり、クラウンやインレーの仮着(一時的装着)用には設計されていない点に注意が必要である。
主要スペックと臨床的特徴
カッパーシールセメントの主要スペックを紐解くと、その臨床的メリットが見えてくる。本製品はリン酸亜鉛セメント系であり、粉末の主成分は酸化亜鉛(ZnO)、液はリン酸を主成分とする溶液である。特徴的なのは硬化の速さと高い機械的強度である。練和開始から約6分で硬化が完了し(23℃環境下、標準粉液比での測定値)、一般的な酸化亜鉛ユージノールセメント(例えばユージダイン等)の硬化時間5分程度と比較しても遜色ないスピードである。操作可能時間(ワーキングタイム)は練和後2〜3分程度と短めであるが、これは裏を返せばチェアサイドで患者を待たせる時間が少なくて済むことを意味する。忙しい診療中でも硬化を待つストレスが少なく、仮封後すぐに次の処置へ移行しやすい。
また、カッパーシールセメントは操作性の良さもセールスポイントである。粉液を適切な比率で練った際にべたつきが少なく扱いやすいペースト状になるよう調整されている。これは細部まで緊密に充填しやすい反面、練和器具や指に極端に付着して困ることが少ないということでもある。実際、メーカーによる改良で従来品より約1.5倍の耐離脱性(脱落のしにくさ)を実現しつつ、過度な粘着による扱い難さを抑制している。硬化後は高い圧縮強さを示し、咬合圧がかかる部位でも割れたり崩れたりしにくい。この強度面の信頼性が、長めの次回予約間隔でも患者の仮封が保たれる安心感につながる。色調に関しては、ピンク色は仮封材がどこに入っているかを明確に視認できる利点があり、ホワイト色は歯と調和して目立ちにくい利点がある。審美性を求める前歯部にはホワイト、除去時に識別しやすい方がよいケース(奥深い窩洞や根管内など)ではピンク、といった使い分けも可能である。
さらに着目すべき成分上の特徴として、本製品はユージノール(丁香油成分)を含まない。したがってレジン系材料の硬化阻害が起きない点は重要である。仮封後にコンポジットレジン修復やレジン系接着材料を使用する予定がある場合、ユージノール系の仮封材では残留した油分が接着に悪影響を及ぼす可能性がある。しかしリン酸亜鉛セメントであるカッパーシールセメントならその懸念がない。また、ユージノールによる独特の香りや歯髄鎮静効果は本製品にはないが、逆に歯髄への刺激が少ない非ユージノール系仮封材として、歯質や歯肉への影響を最小限に抑える処方となっている。名前に「カッパー(銅)」とある点については、歴史的に歯科領域で銅イオンは殺菌効果を期待してセメントに添加された経緯がある。本製品でも一部に銅由来の成分が配合されている可能性が示唆されるが、詳細な組成は公表されていない。しかしピンク色の色調から推測するに、微量の銅化合物の添加によって抗菌性や材質強化が図られているのだろう。いずれにせよ、従来型リン酸亜鉛セメントを仮封用途に最適化したスペックがカッパーシールセメントの核であり、それが臨床現場での安心感につながっている。
互換性や運用方法
カッパーシールセメントは粉末と液をその都度練り合わせて使う手練用材料である。練和には紙製のパレットやガラス板、金属製スパチュラなど一般的なセメント練和器具を用いる。計量スプーンが付属しており、メーカー推奨の粉液比(例: 粉末1.3gに対し液0.5mLなど)が示されているため、まずその比率で少量ずつ練り、季節や湿度による粘度の違いは微調整してゆくとよい。適切に練ったペーストは流動性がありすぎず程良い硬さになるため、シリンジ等は不要で、スパチュラ先端やエキスカベーターで直接窩洞へ運び込める。既存の器具立てや練和スペースがあれば新たな設備投資は不要であり、日常の保存修復や歯内療法のフローにすぐに組み込める互換性の高い材料である。
他材料との併用についても述べておこう。根管治療中の仮封では、しばしば綿巻き(コットンペレット)を根管口に入れ、その上から本材を充填するテクニックが推奨される。こうすることで後日の除去時にコットンまで掘れば根管に到達でき、誤って根管内に仮封材を押し込むリスクを避けられる。また深い窩洞で仮封材の厚みが大きくなる場合、二層封鎖も有効である。例えば窩底近くには水硬性の仮封材(石膏系やグラスアイオノマー系)を薄く詰めて封鎖性を高め、その上をカッパーシールセメントで蓋をする方法である。内部に柔らかい層を作ることで、外層に硬い本材を使用しても除去時に割りやすくなる利点がある。このように他の仮封材や裏層材との組み合わせ使用にも柔軟性が高い。
感染対策や運用上の留意点としては、粉末と液を容器から取り出す際にクロスコンタミネーションを防ぐことが挙げられる。ディスポーザブルの計量スプーンや単回使用の練和紙を用い、一度患者に使用したらその都度捨てるのが望ましい。また練和に使用した金属スパチュラやガラス板に本材が付着した場合、硬化しきる前にアルコール綿やガーゼで素早く拭き取ることが重要である。硬化後のリン酸亜鉛セメントは器具に固着すると除去が困難になるため、使用直後の器具清掃を徹底したい。保管に関しては、粉末容器は湿気を避けてしっかり蓋を閉め、液は揮発しやすい成分を含むため気密に保つ。直射日光や高温多湿を避けた場所で保管すれば、未開封の状態で有効期限内は安定した性能を発揮する。
データ互換性やデジタルとの連携という点では、本製品自体はアナログな充填材であり直接の関係はない。しかし院内マニュアルという意味で運用ルールを統一しておくことは大切である。例えば、どの症例でカッパーシールセメントを使い、どの症例ではユージノール系を使うか、といった判断基準をスタッフ間で共有しておくと良い。新人歯科医師やスタッフに対しては、実習用抜去歯などで一度練和・充填・除去までの手順を練習させ、硬化時間や扱い感覚を体験させるのも運用上の工夫である。総じてカッパーシールセメントは、特別なデバイスを必要とせず既存の診療フローに乗せやすい点で導入のハードルが低い製品である。
経営インパクト
仮封材の選択は患者の術後経過に影響するだけでなく、医院経営にも密接に関わっている。一見低価格な消耗材料であるが、その性能如何で無駄な時間やコストを省ける可能性がある。まず直接的なコストを見てみると、カッパーシールセメントの価格は市場実勢で粉末125gあたり約3,000円前後、液58mLあたり1,000〜1,500円程度である(販売ルートや会員価格により変動)。セット購入しても合計5,000円程度であり、1回の使用量は粉末0.3〜0.5g、液0.05〜0.1mL程度に過ぎない。単純計算で1症例あたりの材料費はせいぜい十数円から数十円という極めて小さな負担である。経営上、このコストはほぼ無視できるレベルであり、仮封材をけちって使いどきを誤る方が却って高くつくと言える。
重要なのは仮封の信頼性がもたらす間接的な経営効果である。例えば仮封が外れて患者が再来院した場合、その対応にチェアタイムを割かなければならない。これは本来予定していた別の有料処置を行う時間を圧迫し、人件費的にもロスになる。カッパーシールセメントのように脱離しにくく咬合にも耐える仮封であれば、次回予約日まで安定して持つ可能性が高まり、緊急対応のリスクが減少する。1件のトラブル対応に15分の時間とスタッフリソースを費やすと仮定すれば、仮封材の性能向上でそれが月に数件でも減れば年間で数時間〜数十時間の診療時間を有効活用できる計算になる。これは実質的な収入機会の増加につながる。
また、硬化が早く扱いやすいことは診療効率の向上にも寄与する。仮封にかかる時間が短縮されれば、その分だけ1日に対応できる患者数を増やすことも可能だ。特に保険診療で回転率を上げたい医院にとって、1患者あたり数分の短縮でも積み重なれば残業削減やスタッフの業務負担軽減にもつながるだろう。さらに患者満足度の観点では、仮封が安定して外れなければ患者の不安や不信感を減らせる。患者が安心して次回まで過ごせればキャンセル率も下がり、結果として継続来院による収益確保にも寄与する。自費治療前提の精密治療においても、仮封中に問題が起きなければ患者からの信頼感が維持され、高額治療への同意を得やすくなるという側面もある。つまり、仮封材への適切な投資(と言ってもごく少額だが)は、ROI(投資対効果)が非常に高い施策のひとつと言える。
耐用年数という概念は材料そのものにはないが、粉末125gと液58mLで一般的な症例なら数百回分の仮封が可能である。仮に300症例に使用できたとすれば、1症例あたりの材料費十数円で患者満足とトラブル防止が買える計算になる。経営者視点で見れば、これほど費用対効果の高い支出は少ない。高額な医療機器の導入と違い、数千円の材料投資で確実な診療品質の底上げが図れる点は見逃せない。唯一考慮すべきは、在庫管理とロスの問題である。大量購入しても使用期限を過ぎて廃棄しては意味がないため、医院の症例数に見合った適量を仕入れることが肝要だ。もっとも、カッパーシールセメントは常に出番のある汎用材料であり、在庫が腐る心配は小さいだろう。まとめれば、本製品の導入は低コストで高リターンをもたらす可能性があり、経営の観点からも合理的な選択肢である。
使いこなしのポイント
カッパーシールセメントを真価発揮させるには、いくつかのコツや留意点がある。まず導入初期の注意点としては、メーカー指定の粉液比を守ることが挙げられる。リン酸亜鉛セメントは粉液比によって硬化時間や強度が左右されるため、初めは説明書通りに計量し、適切な練和時間(目安として1分以内)で練り上げる習慣を付けたい。粉が多過ぎれば練和中に急激に固くなり操作時間が短くなってしまうし、液が多すぎれば硬化不良や強度低下の原因となる。適正練和は技術というより注意深さでカバーできる部分なので、忙しい中でもここは丁寧に行うべきである。
充填の際のポイントとしては、窩壁にしっかり圧接することが重要である。練和直後のペーストをスパチュラでそっと置くだけでなく、アルコール綿球や平滑なプラガーなどで軽く圧接しながら表面を平滑に整えると、適合が高まり封鎖性が向上する。圧接することで余剰な材料や気泡も排出され、辺縁からのマイクロリーケージ(唾液漏洩)も起きにくくなる。ここで強く擦りすぎると未硬化の材料が擦り取られてしまうので、軽圧で押さえる程度がコツである。特にマージン部は丁寧に押さえ、舌や頬側から撫でるように整形しておくと、硬化後の飛び出しや咬合干渉が少なくなる。
患者説明のポイントも押さえておこう。仮封材はあくまで一時的なものであり、ガムやキャラメルのような粘着性食品や極端に硬い物は避けるよう伝える必要がある。カッパーシールセメントは強度が高いとはいえ、所詮は仮の詰め物なので過度な負荷がかかれば欠けたり外れたりする可能性はある。「普通に食事して問題ないが、糸切り歯で噛み切るような硬い食品は避けてください」「もし取れてしまったら無理に戻そうとせず早めに連絡してください」といった具体的な指示を与えると患者も安心する。また、ピンク色で入れた場合は患者自身が鏡で仮詰めを確認しやすい。逆にホワイトで入れた場合は一見歯と見分けがつきにくいため、「ここに白い仮の物が入っています」と一言添えておくと良いだろう。患者が仮封材の存在と大切さを認識していれば、自宅で不用意に爪楊枝などで触ってしまう事故も減る。
除去時のコツも習得しておきたい。カッパーシールセメントは硬化後に脆性があるため、エキスカベーターやラウンドバーで一部に溝を付けてやれば割りやすく崩しやすい。ユージノール系の仮封材ではエキスカベーターを加熱して軟化させる方法が有効だったが、本材は加熱で軟らかくなる性質はない。しかし、その分ポロポロと塊で取れる感じがあるので、無理に全部一括で外そうとせず少しずつ破砕しながら除去すると安全である。特に隣接面や深部に残った小片は見逃しやすいので、吸引やエアブローで取り残しがないか確認しながら進める。ホワイト色の場合、歯質との識別がつきにくく残留片が見落とされるリスクがあるため、う蝕検知液を軽く塗布して白いセメントだけ染め出すテクニックも有用である(リン酸亜鉛セメントは多孔質なので染色液が染み込みやすい)。外す際に歯が欠けないか心配になるかもしれないが、本材は接着性はなく機械的嵌合で留まっているだけなので、適切に破壊すれば支台歯や窩洞へのダメージはほとんどない。むしろ封鎖性の高いレジン系仮封材を無理にこじる方が歯に負荷がかかることもある。適材適所で使いこなせば、カッパーシールセメントは除去まで含めてストレスの少ない材料である。
適応と適さないケース
カッパーシールセメントの適応症は、基本的には短期〜中期の窩洞封鎖全般である。その中でも特に得意とするのは無髄歯や大きな窩洞の仮封である。例えば、根管治療中の歯(歯髄が除去された歯)は痛覚がないためユージノールによる鎮静効果は不要であり、むしろ物理的強度の高い封鎖が求められる。こうしたケースで本材は仮封材の脱離や破折を防ぎ、治療ステップ間の歯内環境を安定に保つのに有用である。また、大きなMOD窩洞など咬合面積が広い仮封でも、本材なら咬合圧に耐え割れにくい。加えて、レジンへの影響がないので、仮封期間終了後にコンポジットレジン修復や接着性レジンセメントを用いる場合にも安心して使える。たとえば隣接面カリエスで一時的に仮封し後日CR充填する際、ユージノール系で仮封するとレジン充填時に接着阻害のリスクがあるが、カッパーシールセメントならそうした心配は不要だ。
一方で適さないケースも存在する。第一に、歯髄の保護や鎮痛を優先すべき症例では本材は向いていない。露髄のリスクが高いう蝕や、生活歯で深い窩洞を一時的に封鎖する場合、ユージノール系仮封材や水酸化カルシウム製剤の併用が望ましいことがある。リン酸亜鉛セメントは硬化時にリン酸による初期酸性を示すため、極端に深い象牙質面では刺激となる可能性がある。そのため、歯髄炎症状がある歯や、仮封中に鎮静を図りたいケースでは、酸化亜鉛ユージノールセメント(例: ユージダイン)などの方が適している場合もある。また長期仮封(1ヶ月以上)には本材単独では不向きである。数週間程度であれば問題ないが、患者の都合で処置再開まで何ヶ月も空くような場合、唾液中での溶解や摩耗、隙間からの二次う蝕リスクが懸念される。そうした場合は仮封材というよりも、一時的な充填物としてグラスアイオノマーセメントやレジンを用いることが望ましい。
さらに審美が強く求められる場面では代替を検討したい。ホワイト色は用意されているものの、色調は単一で透明感もないため、前歯部に長期間入れるとやはり目立ってしまう。特に患者が美意識の高い場合、仮の詰め物とはいえ見た目への不満が出ることがある。このようなケースではレジン仮封材(レジン系テンポラリー)や、あらかじめ色調を合わせて作製する仮着冠などの方が患者満足度は高いだろう。カッパーシールセメントは機能性重視の材料であり、審美性においては樹脂材料に一歩譲る点は押さえておく必要がある。
最後に禁止事項・注意事項として、製品添付文書上も「本材の成分に対し過敏症の既往歴がある患者には使用しないこと」と規定されている。具体的には本材に含まれるリン酸や金属成分(亜鉛・マグネシウム等)で過去にアレルギー反応を示した患者には使用すべきでない。また仮封目的以外(例: 仮着やベースライナー用途)には使用しない。特に仮着用途(暫間的な冠の装着)に本材を流用することは推奨されない。リン酸亜鉛セメントは硬化後に薄い被膜でも高い強度を持つため、クラウン内部に塗布すると外そうとした際にクラウンが壊れたり除去困難になる恐れがある。仮着には専用の仮着用セメント(非ユージノール系レジンセメントやユージノール系セメントなど)があるため、用途を混同しないよう注意したい。
導入判断の指針(読者タイプ別)
歯科医師にも様々な診療スタイルや価値観がある。本製品がどのようなタイプのクリニックに向いているか、いくつかの典型像を通じて考察してみよう。
1. 保険診療中心で効率最優先の先生へ
保険治療をメインに日々多数の患者を捌いている医院では、とにかくチェアタイムの短縮とトラブル再来の防止が重要課題である。そうした環境では、カッパーシールセメントの硬化の早さと安定した封鎖力が大いに貢献する。仮封に時間を取られず次の処置に進めるため診療の回転率が上がり、仮封外れによる予期せぬ再来院対応も減れば無駄なコストも減るだろう。材料費もごく僅かで済むため、コスト意識の高い保険診療型クリニックでも採用しやすい。あえて注意点を挙げるなら、生活歯のう蝕処置で仮詰めに使う際には歯髄保護に留意することくらいだ。総じて「安価で効率アップ」に直結する本材は、効率重視の先生にとって理にかなった選択となる。
2. 高付加価値の自費診療を追求する先生へ
自費の根管治療や補綴治療などクオリティ最優先の診療を提供している医院では、治療の精度と患者満足度が肝となる。このタイプの先生には、カッパーシールセメントは裏方として治療成功を支える材料と言える。例えば精密根管治療では治療中の感染予防が極めて重要だが、本材の高い封鎖性は細菌漏洩を防ぎ予後を良好にする一助となる。また非ユージノールなので、次回の接着操作やレジン充填に悪影響を及ぼさない点もハイエンドな治療との相性が良い。ただし、審美領域では仮封中も見た目への配慮が求められる。審美歯科に力を入れる先生であれば、前歯部など目立つ部位では本材ではなく光重合型の樹脂仮封材を選択するかもしれない。それでも、咬合力が強くかかる臼歯部や長期間安定が必要な仮封ではカッパーシールセメントの信頼性は捨て難い魅力である。要は症例に応じて審美材と機能材を使い分ければよく、質の高い治療を陰で支えるパートナーとして、本材は自費志向の医院にも十分価値を提供できるだろう。
3. 外科・インプラント中心で補綴前処置を多く扱う先生へ
インプラントや歯周外科など外科処置をメインにしている医院では、一見仮封材は縁遠いように思われるかもしれない。しかし実際には、外科と補綴はセットであり、術後の一時的な補綴処置が必要な場面が少なくない。例えばインプラント埋入後の治癒期間中、隣在歯のう蝕治療を仮封のまま経過観察したり、骨造成の間仮義歯のクラスプ設置のための窩洞を封鎖する等、特殊なシチュエーションが起こりうる。これらは通常より長期の仮封や強固な仮封が要求されるケースと言える。カッパーシールセメントは高強度で脱落しにくいため、数週間から数ヶ月単位の仮封にも耐える(ただし1ヶ月を超える場合は定期的に状態をチェックし、必要に応じて補綴的フォローをすべきである)。外科処置中心の先生にとっては主役級の材料ではないが、いざという時に頼れる存在として備えておく価値は高い。逆に言えば、外科系処置ばかりで保存修復やエンド治療を全く行わないのであれば、本材の出番は限られるかもしれない。その場合でも、提携先の保存専門医や補綴担当医に情報提供し、院内で本材を共有しておくとスムーズだろう。総じて、外科系の先生にとっても縁の下の力持ち的な役割で、本材は診療の質と患者ケアの向上に寄与しうる。
以上のように、診療スタイルによって本材の活きる場面は多少異なる。だが共通して言えるのは、「仮封を確実にする」ことは全ての歯科医療に通じるベーシックであり、そこを支える材料選びを軽視すべきではないという点である。カッパーシールセメントは、効率と品質の両立を目指す現代の歯科臨床にマッチした選択肢となり得る。
よくある質問(FAQ)
Q. カッパーシールセメントはどれくらいの期間、仮封したまま維持できますか?
A. 一般的なケースでは次回診療までの1〜2週間程度の仮封に問題なく耐えるよう設計されている。メーカーも仮封後1〜2週間を目安に撤去・本処置へ移行することを推奨している。実際には数週間から1ヶ月程度持たせられた例もあるが、1ヶ月以上の長期仮封には向かない。長期間放置すると周囲からの唾液浸透や摩耗で封鎖性が低下する恐れがあるため、定期的なチェックと必要に応じた仮封材の交換が望ましい。
Q. ユージノール(丁香油)が入っていますか?レジンの硬化阻害は起きませんか?
A. ユージノールは含まれていない。 したがってユージノール系に見られるようなレジン硬化阻害作用は起こらない。レジン充填や接着を行う前にも、本材による影響でボンディング不良になる心配はない。ただし、仮封材の取り残しがレジン接着面にあるとそれ自体が界面弱点となる可能性があるため、除去は完全に行う必要がある点は他材と同様である。
Q. 「ユージダイン」とは何ですか?カッパーシールセメントとの違いは?
A. ユージダインは、酸化亜鉛ユージノール系の代表的な仮封用セメントである。ジーシー昭和薬品から販売されていた製品名で、粉末に酸化亜鉛、液にユージノール(丁香油)を主成分とする。歯髄鎮静効果や封鎖性に優れる一方、硬化後の強度やレジンへの影響に課題があった。カッパーシールセメントはユージノールを含まずリン酸亜鉛系に属し、強度と操作性を高めた仮封材である点が異なる。簡潔に言えば、ユージダインが「しみないよう歯髄を労る伝統派」だとすれば、カッパーシールセメントは「強度重視でトラブルを防ぐ実務派」と言える。それぞれ得意分野が違うため、症例に応じて使い分けるのが望ましい。
Q. 仮着用のセメントとして使っても大丈夫でしょうか?
A. お勧めできない。本材は仮封専用と考えるべきである。仮着(例えばテンポラリークラウンの一時装着)には、着脱しやすいよう粘着力や強度を調整した専用セメントがある。カッパーシールセメントを仮着目的に使用すると、硬化後の強度が高いためにクラウンの除去が困難になったり、無理に外そうとして補綴物や歯質を破損するリスクがある。仮着には非ユージノール系の樹脂仮着材や、ユージノール系でも流動性と強度を抑えた製品(例: ネオダイン系統)を用いる方が安全である。用途に応じて適材適所の材料を選ぶことが肝要だ。
Q. 使用する上での注意点やリスクはありますか?
A. 大きなリスクはないが、いくつか注意点がある。1つ目は歯髄への配慮で、深い窩洞では直接本材を厚盛りしないか、必要に応じて裏層材を併用すること。2つ目は混ぜ過ぎないことで、長時間練和すると操作時間が短くなり不十分な充填につながるため、手早く練る習慣が必要である。3つ目はアレルギー確認で、亜鉛やリン酸にアレルギーがある患者には使用禁止である。最後に保管について、粉末が湿気を吸うと性能が落ちるため蓋はしっかり閉め、高温多湿を避けて保管する。これらの点を守れば、本材は非常に安全かつ有用に使用できる。万一硬化不良や脱離が発生した場合は、粉液比や使用期限を見直し、適切な条件で再挑戦すれば大抵の問題は解決する。総じて取扱説明書を遵守し基本に忠実に扱えば、リスクは最小限であると言える。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科の「カッパーシールセメント」とは?使い方や特徴・成分、効果時間を解説