- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う仮封材「ユージダイン」とは?特徴や成分を分かりやすく解説
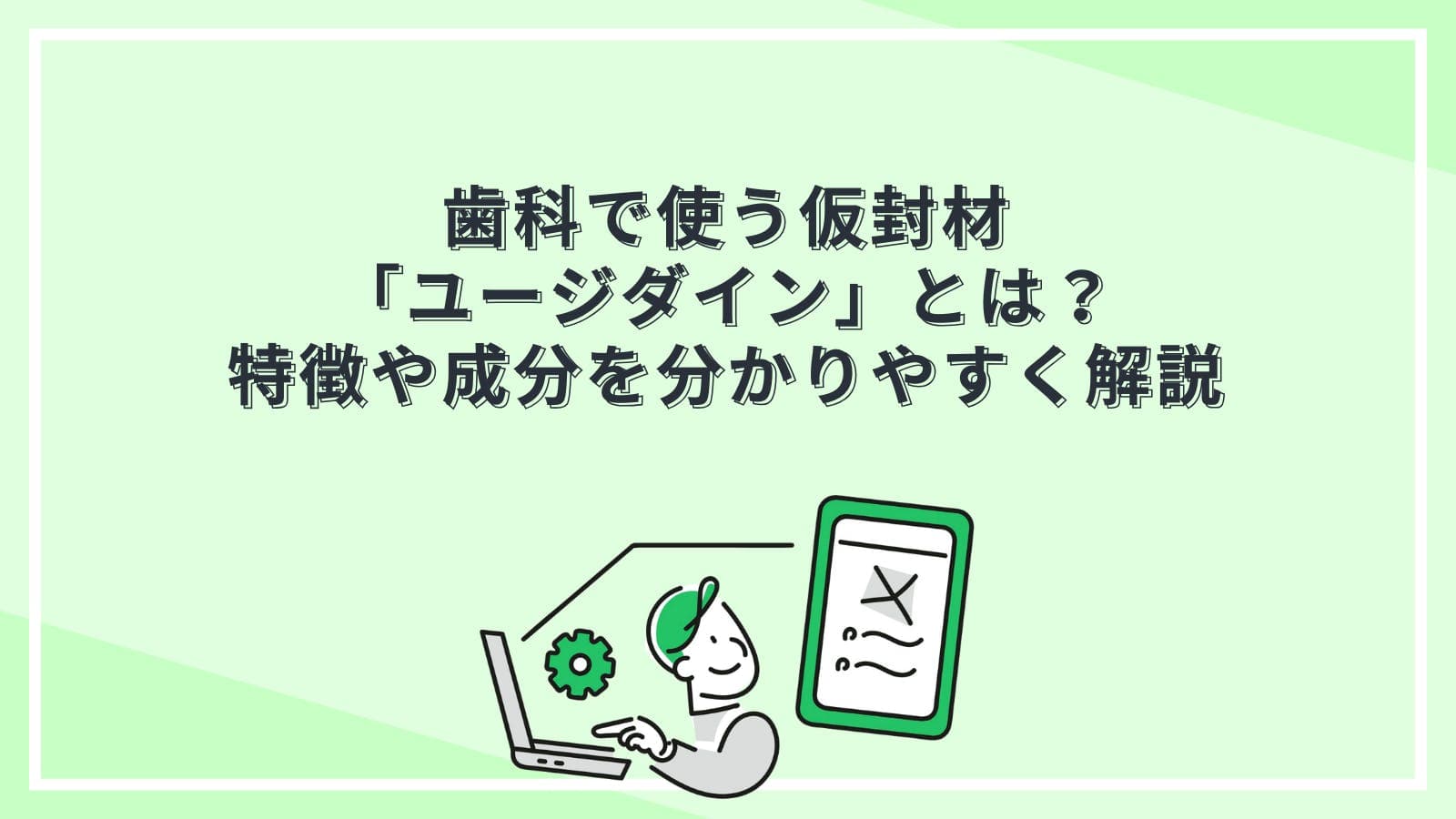
歯科で使う仮封材「ユージダイン」とは?特徴や成分を分かりやすく解説
日々の診療で、処置と処置の合間に行う仮封(仮の詰め物)の重要性を痛感する場面は多い。例えば、根管治療の途中で詰めた仮封材が次回来院前に脱落し、患者に急患来院してもらった経験はないだろうか。あるいは、仮封をしっかりしすぎた結果、次の処置で除去に手間取り治療時間が延びてしまったこともあるかもしれない。また、ユージノール(丁香油)の独特な香りに触れると、学生実習で使った酸化亜鉛ユージノールセメントを思い出す歯科医師も多いだろう。仮封や仮着に昔から用いられてきたこの材料だが、近年は各社から操作性や性能を改良した製品、さらにはユージノールを含まないタイプまで登場している。
本稿では、歯科用仮封材として代表的な「ユージダイン」に焦点を当て、その特徴や成分を臨床面と経営面の両方から詳しく解説する。長年の臨床経験に基づく知見を交え、仮封材選びの判断基準を明確にし、自院の診療スタイルに最適な製品かどうかを検討する一助となれば幸いである。ユージダインを使いこなすことで得られる臨床上のメリットだけでなく、チェアタイム短縮や患者満足度向上による経営的な効果についても考察する。読者自身が投資対効果(ROI)を最大化できる戦略的な製品導入のヒントを見出せるはずである。
ユージダインの概要
ユージダインは、株式会社ジーシー昭和薬品が製造販売する歯科用の仮封材である。正式には「歯科用酸化亜鉛ユージノール仮封向け材料」に分類され、管理医療機器(クラスII)として承認を受けた製品である。一般的な粉液混合型の仮封用セメントで、粉末(散剤)には酸化亜鉛を主成分とし、液剤は丁香油由来のユージノールを主成分とする。いわゆる酸化亜鉛ユージノールセメント(ZOEセメント)の一種であり、古くから歯科臨床で用いられてきた鎮静効果のある仮封材料を現代向けに改良したものである。
適応となる主な用途は、処置間の一時的な封鎖である。具体的には、う蝕除去後やインレー形成後に次回まで穴を塞いでおく仮充填、根管治療中の仮封、あるいは補綴物装着までの間に仮歯を固定する仮着にも応用可能である。ユージダインは仮封専用に開発された経緯もあり、高い封鎖性と扱いやすさを持つことが特徴である。ただし恒久的な修復材料ではなく、あくまで短期的な一時封鎖に用いる材料である点は認識しておく必要がある。歯科医療用の製品であるため、ユージダインの成分に対しアレルギー(過敏症)のある患者には使用できない。
主要スペックと臨床での意味
ユージダインの成分構成とそれに由来する物性について理解しておこう。粉末成分は酸化亜鉛に加え、製品独自の特殊フィラーが配合されている。液剤はユージノール(丁香油)で、混ぜ合わせることで酸化亜鉛とユージノールの反応により硬化する仕組みである。粉液を練和したペーストは室温(20〜25℃)で約2〜3分の操作時間を確保でき、硬化時間はおよそ5分程度である。手動で練るタイプだが作業時間に大きな制約はなく、落ち着いて充填操作を行えるだろう。
硬化後のユージダインは、中程度の硬さと強度を持つ。従来の純粋な酸化亜鉛ユージノールセメントは硬化後に非常に硬く脆い性質があったが、本製品では適度な強度を保ちつつ、特殊フィラーの効果で微細な隙間まで密着し、高い封鎖性が得られるよう調整されている。実際、酸化亜鉛主体の細かな粉体が象牙質面に良く適合し、長年の臨床使用からもう蝕や細菌の侵入を防ぐ十分な封鎖効果が実証されている。一方で、硬化物は完全に剛直ではなく若干の脆さを残すため、後で除去する際に器具で割りやすい性質も兼ね備えている。これは仮封材としては望ましいバランスであり、封鎖中はしっかり機能しつつ、撤去時には比較的容易に取り除けるという臨床的なメリットにつながる。
ユージノールによる生体作用も重要なスペックである。ユージノールは歯髄鎮静効果(鎮痛・鎮静作用)および抗菌作用を持つことが知られている。深い象牙質まで達するう蝕を除去した後、本材で仮封しておけば、次回来院までの間に歯髄の炎症が沈静化しやすくなる傾向がある。いわば暫間的な歯髄保護の役割も果たしてくれるため、処置間隔が空く症例や深い象牙質が露出した症例でも患者の術後疼痛を和らげる効果が期待できる。ただし、この鎮静効果は一時的なものであり、露髄がある場合は別途適切な覆髄材を用いる必要がある点には留意すべきである。
互換性や運用方法
ユージダインを使用するにあたり、他の材料との相互作用や日常の取り扱いにも目を向けよう。まず、レジン系材料との互換性について重要な注意点がある。酸化亜鉛ユージノールセメント一般に言えることだが、ユージノール成分はレジン(合成樹脂)の重化反応を阻害する性質がある。したがって、仮封後にレジン系の接着操作やコンポジットレジン修復を行う予定がある場合、ユージダインの残留がそれらの接着強度に悪影響を及ぼす可能性がある。実際、ユージダインに限らずユージノール含有の仮封材全般で、後のレジンセメント接着が弱まったり、コンポジット修復物がうまく重化しないケースが報告されている。このため、最終的な修復にレジンを用いる症例では、仮封材の除去残渣を徹底的に清掃することが不可欠である。場合によっては、初めからユージノールを含まない仮封材(ノンユージノール系セメント)に切り替えることも検討すべきであろう。例えば、次回セットでレジン接着性のセメントを使うと分かっているインレー仮着では、あえてユージダインを避けGCのフリージノールのような製品を使う判断も一つの賢明な策となる。
日常の運用面では、粉液混合型ならではの取り扱いに留意する。ユージダインは粉と液をその都度練り合わせて使用するため、専用の紙製練和紙かガラス板、へら(スパチュラ)を用意する必要がある。適量の液(製品指示では標準として液2滴、約0.06mL)に対し、粉末0.3〜0.4gを少しずつ加えながら約1分かけて練る。粉液比は用途に応じて微調整でき、仮封用途では練和直後に柔らかいペースト状になる比率が推奨されている。練和操作自体は難しくなく、粉液比さえ守れば均質なセメントが得られる。練り上がった材料はスパチュラで窩洞に填塞し、アルコール綿で軽く圧接しながら形態を整える。アルコール含浸綿で押さえると余分な粉末や表面の粗れが取れ、適合が向上する。硬化が始まる前に操作を完了し、使用後の器具に付着した残材は硬化しないうちにアルコール綿などで速やかに拭き取っておく。硬化後のセメントが器具に固着すると除去が困難になるため、この清掃工程はスタッフへの周知も含め徹底したい。
保管やメンテナンスに関しては、他の粉液セメントと同様である。粉末は湿気を避けて蓋をしっかり締めて保存し、液剤(ユージノール)は揮発しやすいので使用後すぐ容器を密閉する。適切に保管すれば長期間にわたり品質を保てるが、稀に液が劣化して黄色く変色したり粘度が上がることがある。その際は新品への交換を検討すべきである。なお、ユージダインは他社の酸化亜鉛ユージノール系粉・液と混用しないほうがよい。各製品で添加物の組成が異なる可能性があり、想定外の硬化不良や物性低下を招くリスクがあるためである。
経営面のインパクトとコスト分析
仮封材選びは臨床性能だけでなく、医院経営への影響も考慮すべきである。ユージダインの導入によるコストとメリットを定量的・定性的に見てみよう。
まず材料コストと一症例あたりの単価について見ると、ユージダインは粉末50gと液20mLのセットで提供されている(50g/20mLセット)。市場価格はセット1つあたりおよそ4,000〜5,000円程度で、粉1gあたりでは約80〜100円、液1mLあたりでも同程度の計算になる。1症例で使用する量は微量であり、例えばう蝕処置後の1歯の仮封に粉約0.3g・液0.06mLを用いたとすると、1回の仮封にかかる材料費は20〜30円程度にすぎない計算である。たとえ多少多めに盛り足したとしても数十円レベルであり、材料費の負担は極めて小さい。言い換えれば、ユージダイン自体のコストは診療報酬や自費治療費用から見れば無視できるほど微々たるものである。
むしろ注目すべきは、ユージダインを用いることで得られるトラブル防止効果が医院経営にもたらす恩恵である。仮封が外れてしまった場合、患者から急患連絡が入り、予定外の再来院対応に追われることになる。この追加処置は保険診療では再診料程度しか算定できず、大半はサービス対応になりがちである。そればかりか、本来予約されていた診療枠を圧迫し、他の患者の治療スケジュールにも影響を及ぼしかねない。つまり、仮封材の脱落は医院にとって金銭的・時間的な損失となる。ユージダインは前述のとおり封鎖性と安定性に優れており、適切に使用すれば治療間隔中に外れてしまうリスクを低減できる。仮封の信頼性向上は、こうした隠れたコストを防ぐ意味で経営的な価値が大きい。
次に、仮封材の除去にかかる時間も経営視点では見逃せないポイントである。もし仮封した材料が除去しにくく硬固に残ってしまった場合、次回来院時に本格処置へ移る前に、除去に数分以上かかってしまうことがある。場合によっては切削器具で削り取る必要が生じ、歯や補綴物を傷つけないよう慎重な作業が求められる。これは術者にとってストレスであると同時に、チェアタイムのロスでもある。ユージダインは硬化後に適度に脆く崩れる性質を持つため、加熱したエキスカベーターや探針で引っ掛ければ容易に塊で除去できる。その結果、仮封除去にかかる時間が最小限に抑えられ、治療本編にすぐ移行できる。1症例あたり数分の短縮であっても、積み重なれば1日の診療効率に差が出る。空いた時間で他の処置を行ったり、患者への説明時間を確保したりと、有効活用が可能になる。これはすなわち医院の生産性向上につながり、長期的には収益にもプラスとなるだろう。
経営的視点でもう一つ考慮すべきは、患者満足度への寄与である。仮封がしっかり機能していることで患者は処置間を快適に過ごせる。術後の痛みが少なく、仮の詰め物が外れて困る心配もなければ、医院への信頼感は高まる。逆に仮封の不備で痛みや不都合が生じれば、患者満足度は低下し、最悪の場合治療継続の意思にも影響しかねない。ユージダインの鎮痛効果と高い封鎖性は、患者に「きちんと処置してもらった」という安心感を与える。満足した患者は治療への協力度も上がり、紹介やリピートにもつながりやすい。直接的な数値には表れにくいが、こうした間接的な経営効果も含めると、ユージダイン導入のROIは決して小さくないと言える。
使いこなしのポイント
ユージダインの性能を最大限に引き出し、失敗なく運用するための実践的なポイントをまとめる。
適切な練和と稠度調整
ユージダインは粉液比の調整によりペーストの稠度(ねばり気)を加減できる。例えば、仮歯の装着用(仮着用途)に使う場合には、粉の量をやや減らし液を多めにすると軟らかく流動性のあるセメントになり、薄く塗布しやすくなる。一方、深い窩洞の仮封では標準比もしくはやや粉多めで練り、しっかりしたペースト状にすることで圧接時に隙間なく詰められる。粉を入れすぎると硬化が早まる反面、脆さが増して欠けやすくなるため極端な調整は禁物だが、症例に応じて若干の比率変更ができることは手動練和型ならではの利点である。なお、練和時の環境にも注意したい。気温が高いとセメントの硬化が早まる傾向があるため、夏場はエアコン下で練る、またはガラス板を使用して練和温度を下げるといった工夫が有効である。逆に寒すぎる環境では硬化が遅延することがあるため、冬場は室温を適切に保つよう留意する。
充填時のコツ
ユージダインを窩洞に詰める際は、一度に大量のセメントを乗せるのではなく、適量を少しずつ圧接していくと良い。特に根管治療などで根管口まで封鎖する場合、無理に一塊で入れようとすると根管内に押し込んでしまう恐れがあるため、段階的に詰めていく。窩洞の形態によっては、セメントが機械的にしっかり固着しすぎて除去困難になることもある。深いアンダーカットが避けられない窩洞では、あらかじめワセリンを窩壁の一部に塗布しておくと、完全にロックせず除去しやすくなる場合がある。ただし塗りすぎは封鎖不良につながるため注意が必要だ。詰め終わった後、表面をアルコール綿で圧接・摩擦するのはぜひ実践したいテクニックである。これによって表面が滑沢になり、辺縁からの微漏洩を防ぐだけでなく、適度にセメント中の油分が除去され硬化も安定する。
除去と次工程への準備
ユージダインは硬化後、適切な除去手順を踏めば概ね一塊で取り除ける。メーカーも推奨するように、エキスカベーターの先端をバーナーやアルコールランプで軽く温めてから、仮封材に当ててこじると、熱で軟化したセメントが剥離しやすくなる。熱源が無い場合でも、探針やスプーンエキスカで縁から少しずつ起こせばパキパキと割れて外れてくれる。除去後は、残った微細な破片や被膜をエアブローや吸引で完全に除去することが大切である。特に後続の接着処置を控えている場合、仮封材の残留は致命的な障害となり得るため、根気よく清掃したい。必要であればラバーカップやブラシで軽く研磨して、ユージノール成分の皮膜を取り除く配慮も有効だ。
患者への説明とフォロー
仮封材を装着した状態で患者が過ごす期間についても、適切な指導とフォローが肝心である。ユージダインは通常の食事や生活で問題なく機能するが、極端に粘着性の高い食品(ガムやキャラメルなど)を頻繁に摂取すると、仮封材が一部剥がれてしまう可能性がある。治療中である旨とともに、硬すぎる飴や粘着性食品は控えるよう伝えておくと良い。また、ユージノールの香りや味について患者から質問を受けることもある。クローブ(丁子)のような薬草様の匂いであると説明しておけば、患者は驚かずに済む。万一仮封が取れてしまった場合の応急措置(ティッシュを詰めて早めに連絡をもらう等)についても簡単に伝えておけば、患者の不安を和らげトラブル時も落ち着いて対処してもらえるだろう。こうした配慮が患者満足度の向上につながり、ひいては医院の信頼性向上にも寄与する。
適応症例と使用を避けるべきケース
ユージダインが威力を発揮するケースと、逆に注意が必要なケースを整理する。
適応が推奨されるケース
代表的なのは根管治療中の仮封である。根管充填まで数回の治療が必要な間、しっかりと感染経路を遮断しつつ、疼痛を抑えて歯髄や根尖部組織の安静を保つ必要がある。ユージダインは密閉性が高く、さらに残存歯髄や周囲組織に対する鎮静効果も期待できるため、まさにうってつけである。また、深い齲蝕の一時的な充填にも適している。軟化象牙質を段階的に除去するようなケース(暫間的封鎖療法)では、最初の来院で本材を仮封しておくことで歯髄の反応を見ながら次回の再介入まで歯を保護できる。その他、支台歯形成後の仮封や仮歯の仮着においても、有効な場面がある。支台歯が露出した状態では知覚過敏や歯髄炎症が起こりやすいが、ユージダインでカバーしておけば疼痛を抑えつつ次回まで維持できる。仮歯(プロビジョナルクラウン)の固定に使う場合も、適度な保持力で仮歯を安定させながら、外したい時には割って除去できるという性質が便利である。
使用を避けるべきケース
大きく分けて2つの観点がある。1つは材料学的な相性の問題で、既に述べたようにレジンを用いた最終補綴を予定している場合である。例えばコンポジットインレーや接着ブリッジなど、レジンセメントで本付けする症例では、仮封材にユージダインを用いることは推奨できない。完全に除去したつもりでもユージノール成分が象牙質表面に残留し、接着阻害となるリスクがあるためだ。このようなケースでは初めからノンユージノール系の仮封材を選択する方が安全策である。2つ目は長期仮封・仮着が見込まれる場合である。ユージダインは数日から数週間程度の使用を前提としており、それ以上の長期間にわたって機能させる用途には向かない。長期留置すると徐々に材料が劣化し、辺縁からの漏洩や脱離のリスクが高まる。また、ユージノールは長期間歯肉と接しているとごく稀に刺激となり、歯肉炎や歯肉退縮を引き起こす可能性が報告されている。したがって、例えば患者の事情で仮歯のまま数ヶ月過ごす必要があるような場合、初めからより強度と耐久性の高い仮着セメント(レジン強化型など)を用いる方が良いだろう。さらに、患者要因の注意点として、ユージノールアレルギーの既往がある人には使用禁止である。まれではあるが丁香油に対してアレルギー反応を示す患者が存在するため、問診や既往歴の確認を怠らないことが肝要だ。加えて、ユージノールの香りに強い不快感を示す患者も稀にいる。そのような場合は無理に本材を使わず、臭気の少ない他材に切り替える配慮も患者対応としては重要である。
歯科医院のタイプ別・導入検討ポイント
ユージダインがもたらす価値は、歯科医院の診療方針や重視するポイントによって評価が異なるだろう。いくつかのタイプ別に、本製品の導入判断について考えてみる。
保険診療中心で効率重視のクリニック
日々多数の患者を回しながら保険診療をメインに行っているクリニックでは、「安価で信頼性が高く、手間が少ない」器材が求められる。ユージダインは材料費がごくわずかであるうえ、1回の練和で複数歯の仮封も十分行える経済性が魅力である。仮封脱落による臨時対応が減れば、その分本来の診療に集中でき、院全体の回転率が向上する。また、除去しやすさによるチェアタイム短縮効果も、日々の積み重ねで無視できないメリットとなる。粉液練和の手間は確かにあるものの、1症例あたり1分程度の作業であり、アシスタント訓練次第で診療の流れに組み込める。むしろペーストタイプで硬化を待つ間に他の作業が止まってしまうより、術者やスタッフの裁量でタイミングを調整できる粉液型の方が流れを妨げないという面もある。特に根管治療件数が多く仮封の頻度が高い保険診療主体の医院ほど、ユージダインのコストパフォーマンスと確実性による恩恵は大きいだろう。
自費診療中心でクオリティ重視のクリニック
セラミック修復や高度な接着治療など、自費診療を主とするクリニックでは、最終補綴物のクオリティ確保が最優先となる。その観点からは、ユージダインの使用には慎重な判断が必要である。というのも、前述のとおりユージノールがレジン接着に与える影響があるためだ。高価なセラミックインレーを接着する直前までユージダインで仮封していたがために、いざ本接着で接着不良を起こすような事態は絶対に避けなければならない。したがって、自費診療中心の医院では、基本的に仮封材もレジン系やノンユージノール系のものを用いておき、ユージダインは緊急時の疼痛管理用としてスポット的に使うのが望ましいだろう。例えば、深い齲蝕で突然の疼痛に見舞われた患者に対し、その場で応急的にう蝕を一部除去して鎮痛を図るようなシーンでは、ユージダインの鎮静効果が威力を発揮する。また、自費診療の患者は治療に対する期待値も高く、痛みや不快感への敏感度も高い傾向がある。短期間であればユージダインの封鎖性と鎮痛効果によって快適に過ごしてもらえるため、「痛みに最大限配慮してくれる医院」という印象を与えることができる。ただし長期化する仮封には用いない、接着が絡むケースには用いない、といったルールを院内で決め、質の高い最終結果に影響が出ない範囲で使うことが肝要である。
外科・インプラント中心のクリニック
インプラントや歯周外科など外科処置に力を入れている医院では、仮封材が主役となる場面は多くないかもしれない。インプラント治療では基本的に神経の無いインプラント体相手の処置になるため、歯髄鎮静効果といったユージダイン本来のメリットは発揮されない。その一方で、外科治療後に一時的に欠損を埋める処置や、インプラント埋入後の仮歯の固定など、仮着セメントとして性能が求められるシーンはある。外科・インプラント中心のクリニックでは、むしろ仮歯や仮補綴の長期安定性や歯肉への優しさが重視される傾向にある。そうした局面では、ユージダインよりもレジン系で高強度の仮着材や、非ユージノール系で歯肉刺激の少ない材料が選ばれることが多いだろう。ユージダインを敢えて活用するとすれば、外科処置とは別に一般歯科治療も併設している場合における根管治療や保存修復処置である。外科を専門にしていても、急患で痛みのある虫歯患者が飛び込んでくることはある。そのような際に応急処置としてユージダインを使い、痛みを抑えてあげることは、患者満足の観点から有用である。総じて、外科・インプラント主体の医院にとってユージダインは主力ツールではないが、「いざという時に患者の痛みを和らげる一手」として常備しておく価値はあると言える。
結論
仮封材「ユージダイン」は、古典的な酸化亜鉛ユージノールセメントに現代的な改良を施した信頼性の高い製品である。適切に用いることで、治療の合間の脆弱な期間に高い封鎖性と歯髄の保護を提供し、患者の不快症状を抑えてくれる。その結果、術者にとっては予定調和の治療計画が立てやすくなり、患者にとっては「安心して次回を待てる」快適な治療体験につながる。経営的にも、トラブル対応の減少や効率アップ、患者満足度向上を通じて収益と信頼性の向上を後押しするだろう。ただし、ユージダインは万能ではない。レジンとの相性問題や長期安定性の限界など、弱点も理解した上で使い分けることが重要である。本稿で述べたポイントを踏まえ、自院のケースに照らして導入を検討してみてはいかがだろうか。
明日からできる次の一手
ユージダインに興味を持ったなら、まずは身近な歯科商店やディーラーに問い合わせ、製品の在庫や価格、サンプル提供の有無を確認してみよう。幸いユージダインは比較的低価格な材料であり、初期投資のハードルは高くない。少量からでも取り寄せて、現在使用中の仮封材と比較試用してみる価値は十分にある。院内でスタッフ向けに練和や取扱いの勉強会を開き、皆で使いこなしのコツを共有しておけば、導入後もスムーズに運用できるだろう。仮封材ひとつ変えるだけで、明日の診療がより安心で効率的なものになるかもしれない。
よくある質問
Q. ユージダインを使用した後にレジンで接着する処置を行う場合、接着阻害はどの程度起こるか?
A. ユージダインを含むユージノール系の仮封材は、レジン系接着に対して少なからず負の影響を及ぼす。ユージノールが象牙質に染み込むと、後のボンディング剤やレジンセメントの重合反応を妨げ、接着強度の低下やコンポジット修復物の辺縁不適合を招く恐れがある。その程度は残留状況によって異なるが、細部に残った微量のユージノールでも影響はゼロではない。したがって、仮封除去後は切削や清掃により可能な限り痕跡を除去することが肝要である。それでも不安が残る場合や、症例的に接着成功率を最優先すべき場合には、最初からノンユージノールタイプの仮封材を用いてリスクヘッジするのが無難である。
Q. ユージダインの仮封は最長どのくらいの期間もつか?長期放置するとどうなるか?
A. ユージダインは短期間(数週間程度)の仮封を前提に設計されている。1〜2週間程度であれば適切な封鎖能力を維持するが、1ヶ月以上の長期に及ぶと徐々に材料が劣化し、周囲との境界から隙間が生じたり、硬度が低下して崩れやすくなる可能性がある。また、長期放置するとユージノール成分が揮発・溶出していき封鎖効果が減退する恐れもある。さらに稀なケースだが、仮封が長期にわたり歯肉に触れていると、ユージノールの刺激で炎症や退縮を起こすことが報告されている。したがって、基本的には次回来院までの短期間に留め、もし患者の事情で予定より仮封期間が延びる場合には、一度外して詰め直すか、より耐久性の高い材料への置換を検討すべきである。
Q. ユージダインは露髄した歯の直接覆髄(直接的な歯髄保護)に使えるか?
A. 結論から言えば、ユージダインを直接覆髄剤として使うことは推奨されない。ユージノールには鎮静作用があるとはいえ、濃度の高い状態で歯髄に触れると毒性を示す可能性がある。そのため、歯髄が露出した場合は水酸化カルシウム製剤やMTAセメントなど、歯髄保護に適した材料をまず適用し、その上から二次的封鎖としてユージダインを用いるのが望ましい手順となる。ユージダイン自体はあくまで仮封材であり、直接歯髄組織に接触させる用途には承認されていない。しかし、間接覆髄(ごくわずかに象牙質を残して露髄を避けたケース)において、本材で密閉することで歯髄が安定する効果は期待できる。その場合でも次回までの暫間的処置と割り切り、後日に最終的な適切な覆髄処置と修復を行うことが肝要である。
Q. 仮封したユージダインが一部欠けてしまいました。患者から連絡があった場合、どのように対処すべきか?
A. ユージダインが欠けたり脱落した場合、放置すると細菌の侵入や二次う蝕、痛みの再発につながる可能性があるため、早めの対処が必要である。患者に対しては、まず欠けた部分に食べかすなどが入らないよう清潔に保つよう指示を出す。具体的には、うがいで口腔内を清潔にし、可能であれば市販の一時的な詰め物(歯科用ワックスなど)があれば詰めてもらう。または清潔な綿を小さく丸めて穴に軽く詰めておいてもらう方法もある。そして、できるだけ早い時期に来院してもらい、仮封のやり直しや本処置への移行を検討する。患者には「仮の蓋が外れて中が空いている状態なので、早めに受診を促す」と不安を煽らないよう配慮しつつ伝えることが大切だ。適切にフォローすれば、大事に至らず信頼関係も維持できる。
Q. 他社の仮封材(例えば水硬性のCavitなど)と比べて、ユージダインを選ぶメリットは何か?
A. 水硬性仮封材の代表であるCavit(カルボキシレート系の自己硬化型仮封材)は、練和不要で直接詰め込むだけという手軽さが利点である。一方で、硬化に水分を利用するため長期間置くと唾液で徐々に軟化・溶出しやすい傾向があり、強度もユージダインほど高くはない。また、鎮痛効果は持たないため深い齲蝕後の疼痛管理には寄与しない。ユージダインは練和の手間こそあるものの、硬化後のしっかりとした強度と封鎖性、そして歯髄鎮静効果が大きなメリットである。特に根管治療や深い虫歯の症例で患者の痛みを抑えつつ確実に歯内を保護できる点は、水硬性材料にはない強みと言える。ただし、短期間での簡便さ重視ならCavitのような材料も有用であり、一概にどちらが優れるかではなくケースバイケースである。臨床現場では、ユージダインとCavit等を使い分けている先生も多い。それぞれの特徴を踏まえ、患者の症状や治療期間に応じて最適な仮封材を選択することが重要である。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う仮封材「ユージダイン」とは?特徴や成分を分かりやすく解説