- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う仮封材「ネオダイン」とは?特徴や成分を分かりやすく解説
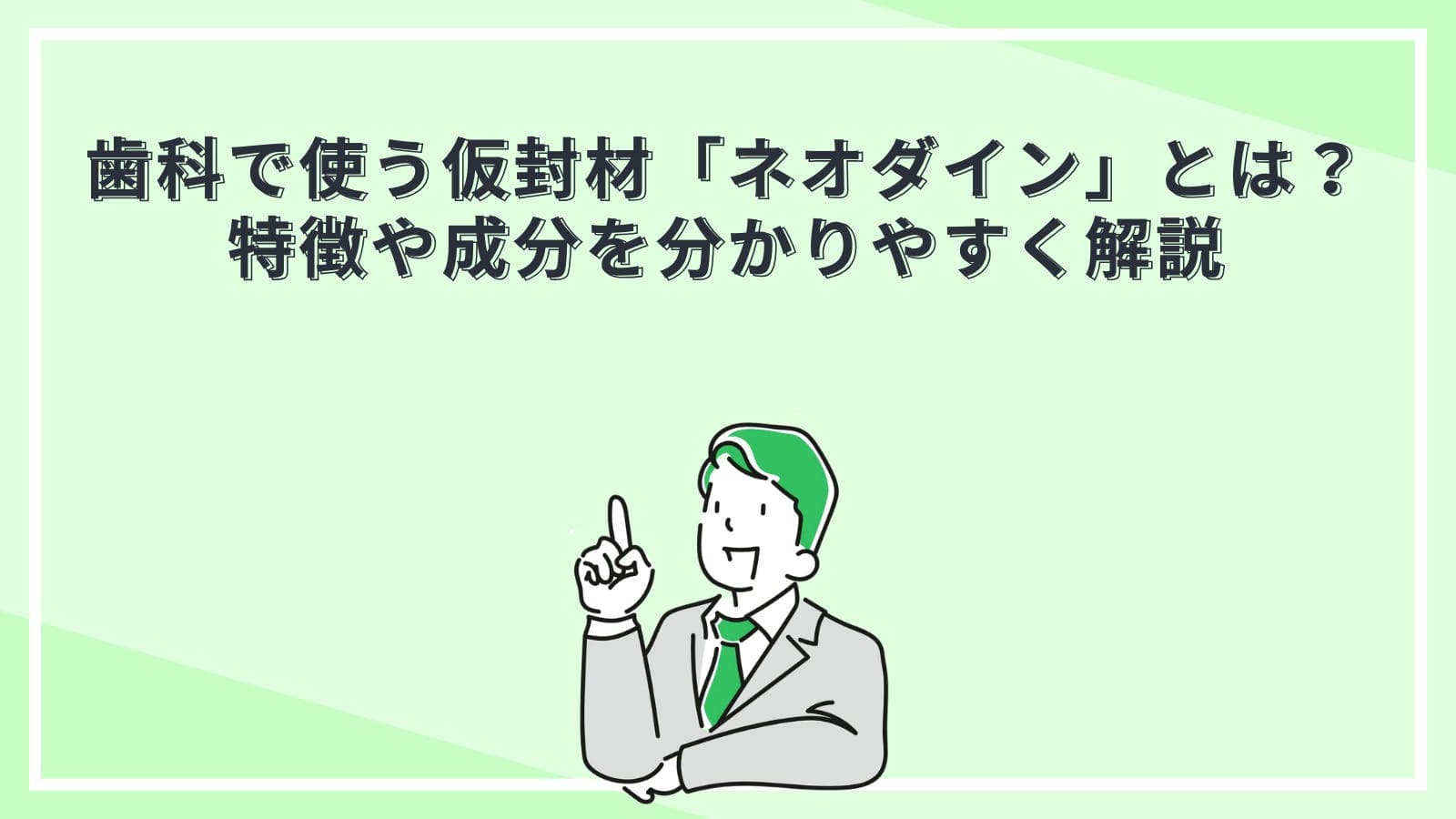
歯科で使う仮封材「ネオダイン」とは?特徴や成分を分かりやすく解説
日々の歯科診療において、根管治療途中の仮封やう蝕除去後の一時的な充填が思わぬトラブルにつながった経験はないだろうか。仮封材が外れて患者が痛みを訴えて来院したり、仮封後も歯髄痛が治まらず夜間に連絡が入ったりすると、診療スケジュールが乱れるだけでなく患者の信頼にも関わる。仮封材ひとつで治療間隔の安定や痛みの軽減が左右されることもあり、その選択と使いこなしは軽視できない問題である。
「ネオダイン」という仮封材は、日本の歯科医なら一度は耳にしたことがある代表的な存在である。本記事では、このネオダインにスポットを当て、その特徴や成分を臨床的価値と医院経営的価値の両面から詳しく解説する。長年の臨床経験と経営コンサルの視点を踏まえ、仮封材選びに悩む先生方が自院の診療スタイルに最適な選択をできるよう、具体的な使用シーンや効果を検証していく。
ネオダインとはどんな仮封材か
ネオダイン(現在の正式製品名はネオダイン-α)は、歯科用酸化亜鉛ユージノールセメントというカテゴリに属する仮封材である。メーカーはネオ製薬工業株式会社で、医療機器としての区分はクラスIIの管理医療機器に該当する。古くから「酸化亜鉛ユージノールセメントと言えばネオダイン」とまで言われ、仮封だけでなく歯髄鎮静効果や象牙質の消毒効果を兼ね備えた応用範囲の広い製品として知られてきた。
ネオダインは粉末と液を練り合わせて使用するタイプで、用途としてう蝕除去後の仮封(一時的な充填)や歯髄覆罩・裏層(間接法的パルプキャップやベース)に用いられる。特に露髄のリスクがある深い象牙質の窩洞で、一時的に歯髄を保護・鎮静しながら最終的な修復まで歯を封鎖する用途に適している。仮蓋として根管治療の間に歯内を密閉したり、一時的な詰め物として次回来院まで歯をカバーしたりと汎用性が高い。ただし、永久的なセメント固定や長期に渡る修復には使用できない仮封専用の材料であり、最終充填には別の接着材料を用いる必要がある。
なお、「ネオダインα」という名称から推察できる通り、本製品はオリジナルの「ネオダイン」を改良して発売されたものである。従来品から硬化時間の安定化や練和時・除去時の操作性向上が図られており、環境温度や湿度に左右されにくく扱いやすい点が特長である。古いネオダインを愛用していた歯科医も、現在はネオダイン-αへと移行しているため、市場では事実上ネオダイン-αが標準となっている(一部の小包装サイズは販売中止となったが、通常セットは継続入手可能である)。また、ネオダインブランドには派生製品も存在する(後述)が、本稿では主に粉末・液タイプのネオダイン-αを中心に説明する。
ネオダインの成分と硬化メカニズム
ネオダイン-αの成分を紐解くと、粉末成分は酸化亜鉛(ZnO)を主体に、少量のロジン(松ヤニ由来の樹脂)や水酸化カルシウム(Ca(OH)2)などが含まれている。液成分はユージノール(オイゲノール)という精油成分で、クローブ(丁子)由来の芳香を持つ淡黄色の液体である。使用直前にこの粉末と液を練り合わせることで、酸化亜鉛とユージノールのキレート反応が起こり硬化が進行する仕組みである。
硬化反応の主役であるユージノールは、歯科では古くから鎮痛鎮静効果で知られる成分で、いわゆる「鎮静材」として歯髄炎の痛みを和らげる作用が期待できる。一方の酸化亜鉛は不溶性の粉末で、ユージノールとの反応で徐々に硬化し不溶性の固まりとなる。これに加えて、粉末中の水酸化カルシウムがわずかに溶出して象牙質に触れることで、歯髄に対して緩やかなアルカリ性刺激を与え、硬組織形成(第2象牙質の生成)を促す効果も狙っている。すなわちネオダインは、鎮痛効果(ユージノール)と抗菌・硬組織誘導効果(水酸化カルシウム)を組み合わせた、療法的要素のある仮封材と言える。
ロジン(松ヤニ)は練和後のペーストの粘性調整剤として含まれており、硬化過程での収縮を抑えたり、硬化物の堅さや付着性を適度に調整する役割がある。こうした添加物により、ネオダインは単なる伝統的ZOE(酸化亜鉛ユージノール)セメントの域を超えて実用上ちょうど良い操作感と硬さを実現している。
主要な物性と臨床での意味
仮封材として性能を語る上で重要な指標に、硬化時間と強度(硬度)、そして封鎖性が挙げられる。ネオダイン-αは室温23℃・湿度50%程度の標準環境下で、約3分前後で硬化し始める。練和後の操作可能時間(ワーキングタイム)はおよそ2分程度で、環境条件によって若干変動する。従来の酸化亜鉛ユージノール系材料は湿度や温度に敏感で、真夏の多湿な診療室では急激に硬化が進んで慌てる…という経験もあった。改良型のネオダイン-αではこの点が改善されており、環境変化に左右されにくい安定した硬化時間が確保されている。とはいえ、湿度が極端に高いと操作時間が短縮するのは避けられないため、真夏や雨季にはエアコンで除湿する、一度に練る量を少なくする等の配慮が望ましい。
硬化後の圧縮強さは、規格上5MPa以上という最低基準を大きく上回り、測定値では40MPa前後の値が報告されている。これは仮封材として十分な強度であり、咀嚼圧に耐えて窩洞内から脱落しにくい硬さを意味する。ただし、必要以上に硬すぎないことも肝要で、ネオダインの硬化物は適度に脆性を持つため次回の除去時にスムーズに破砕できる。金属のエキスプローラーやスプーンエキスカベータでこじれば、硬化物は塊ごと剥がれ落ちやすく、歯面にこびり付いて除去に難儀することは少ない。封鎖性(辺縁封鎖の良さ)についても、練和ペーストには適度な粘度と流動性があるため窩壁に良く適合し、微小な隙間を埋めて唾液や細菌の侵入を防ぐ性能を持つ。
ネオダインは練和比の調整によって稠度(ペーストの固さ)を変えられる特徴もある。粉末を多めに練り込めば硬めでしっかりしたペーストになり、硬化後はより高強度で硬い仮封となる。一方、液を多めにすれば軟らかく流れやすいペーストとなり、細かい隙間にも行き渡る反面、強度や粘着力は低下する。臨床では、窩洞の大きさや位置に応じて硬さを調節できる柔軟性は大きな利点である。例えば、小さな窩洞や根管の開口部だけを覆う場合にはあまり粉厚が取れないため、やや硬めに練って強度を確保する。一方、深い窩洞全体を覆う場合や複雑な形態では、軟らかめに練って確実に行き渡らせるなどの工夫が可能である。経験を積んだ術者は、この粉液比のコントロールによって「外れにくく除去しやすい絶妙な固さ」を作り出している。
練和方法と使用時のポイント
ネオダインの練り方にはいくつかのコツがある。基本は付属のセメント練和紙(パレット)上に、粉末約0.5gに対し液0.1mLという標準比で混ぜる。これは粉:液重量比でおおよそ5:1にあたり、メーカー推奨の割合である。まず練和紙上に粉末と液を計量し、ステンレス製の金属スパチュラでゆっくりと練り混ぜる。金属製の練和スパチュラを使うのは、酸化亜鉛粉末をしっかりと液に擦り合わせてダマなく混ぜるためである(プラスチック製では撓みが大きく十分にすり潰せないことがある)。最初に液体の上に粉を少量ずつ混ぜ込み、ペースト状に練り広げながら残りの粉末も合わせていくと良い。全量が均一に混ざり、ツヤのあるクリーム状からマットな艶消し状態に質感が変わったら練和完了の目安である。標準的な練和時間は1分以内で、悠長に混ぜすぎると作業時間が減ってしまうので注意する。
練和に使用する練板は、付属の使い捨て練和紙でも、ガラス製の練和板でも構わない。ガラス練板は表面が硬く平滑なため練りやすく、必要に応じて冷却しておけば硬化を遅らせる効果も期待できる。ただし、ガラス板を用いる場合は清潔なものを使用し、直前に水分が付いていないか確認する。水滴や高湿度環境はユージノールセメントの硬化を早めてしまうからである。練和器具(スパチュラや練板)は完全に乾燥した状態で使用するのが鉄則で、少しでも湿っていると操作時間が極端に短くなる場合がある。
混ぜ上がったネオダインペーストは練和後すぐは軟らかく糸を引くような粘性がある。このタイミングで窩洞に置くと器具にまとわりつき扱いにくいので、10〜15秒程度待って適度に粘性が増すのを待つと操作しやすい。ペーストを窩洞に運ぶ際は、金属製の充填器(スパチュラの反対側やワックススパチュラ、平滑充填器など)で一塊を取り、目的部位に押し込むように充填する。窩洞の形に合わせて指で軽く圧接することもあるが、直接指で触れるとユージノールが皮膚に付着しやすいので避けたい。おおまかに充填できたら、硬化が始まる前に余剰分を器具で除去して形態を整える。尖ったエキスプローラーで縁をなぞると、はみ出した部分をきれいにカットできる。硬化開始から約2〜3分で初期硬化に至り、それ以降は触れても形が崩れなくなる。
使用後の器具や練板にはネオダインが付着しているため、硬化する前にアルコール綿でよく拭き取ることが重要だ。硬化後は固着して落としにくくなるが、その場合はメーカー純正のネオダインソルベント(柑橘系溶剤)やアルコールに浸したガーゼでふやかすと除去しやすい。診療後に器具に付いたまま放置してカチカチになってしまうと清掃が大変なので、アシスタントも含めて使用直後の片付けを徹底する。清掃時に口腔や皮膚に付着した場合もアルコール綿で速やかに拭き取り、その後水で十分洗い流すよう指導されている(万一目に入った場合は大量の流水で洗眼し眼科受診)。
なお、ネオダインは金属製スパチュラとの相性が良い一方、プラスチックやゴム製のボウルで練らないよう注意したい。ユージノールはプラスチックを劣化させたり、ラバーボウルの素材を硬化不良に陥らせる可能性がある。同様に、シリコーン印象材やレジン材料とも相性が悪く、ネオダインを使用した歯に対して直後にシリコン印象を採ると硬化不良を起こす例が知られている。これはユージノール成分が残留しているためで、レジン系仮封材や印象材の重合反応を阻害するからである。したがってネオダインで仮封した後にレジン充填や接着処置を行う場合は、仮封材を完全に除去し象牙質表面をアルコールやエタノールで清拭することが望ましい。可能であればユージノール非含有の仮封材に切り替えるか、どうしても必要な場合は数日おいてユージノールの影響が減弱してから接着操作を行うといった配慮が必要である。
経営面から見た仮封材選択のインパクト
仮封材の選択は、一見すると臨床上の品質やテクニックの問題と思われがちだが、医院経営にも無視できない影響を与える。まずコスト面を考えると、ネオダイン-αのような粉末・液タイプの材料は単価が非常に安価である。例えばネオダイン-αの1セット(粉末30g+液10mL)で数十〜百回程度の症例に使用でき、1症例あたり数十円程度の材料費に過ぎない計算になる。これは歯科診療報酬の中でごくわずかな割合であり、経営上の負担は軽微である。低コストでありながら患者の疼痛緩和や治療間隔中のトラブル防止といった効果を発揮する点で、費用対効果に優れた材料と言える。
むしろ経営上注目すべきは、仮封材の選択が診療効率や患者満足度に与える間接的な効果である。例えば、質の悪い仮封材や不適切な使用によって仮封が外れてしまうと、患者から急患連絡が入り、予定外の再来院対応に追われる可能性がある。このイレギュラー対応は本来予定していた他の患者の時間を圧迫し、ひいては一日の売上やスタッフの労務効率にもマイナスとなる。また、仮封が原因で感染が再発し治療のやり直しが生じれば、材料費や技術料以上にクリニックの機会損失が大きい。
ネオダインは封鎖性と持続性に優れており、適切に使えば次回予約日まで外れずに保たれる可能性が高い。特に根管治療や深い齲蝕の治療途中では、仮封がしっかり機能することで細菌の侵入や唾液漏洩を防ぎ、治療ステップを順調に進められる。結果として再治療や追加処置の必要が減り、患者の治癒までの来院回数も最小限に抑えられるだろう。これは患者満足度の向上に直結し、ひいては紹介患者の増加や自費治療への移行率アップにもつながり得る。患者からすれば、仮詰め期間中に問題が起きず安心して過ごせることは信頼感につながり、「この医院は処置が丁寧で痛みへの配慮もある」と良い評価を抱いてくれる。
チェアタイムの短縮という観点でも、適切な仮封材は貢献する。例えば次回来院時に仮封材が硬すぎて除去に時間がかかったり、逆に外れていて再清掃や再消毒に余計な手間を取られたりすると、その日の治療時間が延びてしまう。ネオダインであれば除去は容易で、たいていエキスプローラーで引っ掛ければポロッと取れるため、除去作業が短時間で済む。また歯髄鎮静効果によって次回までに痛みや炎症が和らいでいるケースも多く、たとえば急性症状で一旦仮封した歯が、次回には落ち着いて麻酔や抜髄処置がスムーズに行えるといった利点もある。こうした見えにくい時間短縮やリスク回避の積み重ねが、一日の診療ユニット稼働効率に少なからず影響する。
さらに、スタッフ教育コストにも触れておきたい。ネオダインは歴史が長く汎用性が高いため、多くの歯科助手・衛生士が取扱いに習熟している材料でもある。新人スタッフであっても、教育用の動画や先輩からの指導を通じて比較的早く練和のコツを掴むことができる。製品によっては専用機器や高度な手技を要するものもあるが、ネオダインは手作業でシンプルに扱えるため、人件費的な教育コストやトレーニング時間も抑えられる。また、万一練和比のミスなどがあっても材料単価が安いため経済的な無駄も小さく、安心して練習できる点も見逃せない。
以上のように、ネオダインを適切に選択・活用することは、コストパフォーマンスと診療効率の向上につながり、ひいては医院全体のROI(投資対効果)を高めることに寄与する。大がかりな設備投資ではないものの、こうした細やかな材料選択の積み重ねが経営の安定と患者満足の向上を支えていると言えよう。
ネオダインを使いこなすためのポイント
ネオダインは古典的な材料とはいえ、適切に使いこなすことで最大の効果を発揮する。まず導入初期には、歯科医本人だけでなくアシスタントや衛生士にも練和法と取り扱いをしっかりトレーニングしておくことが重要である。前述の基本手順に加え、各医院でルールを決めておくと良い点としては以下が挙げられる。
練和環境の管理
診療室の温度・湿度によって硬化速度が変わるため、極端な高温多湿にならないようエアコンなどで環境を整える。また、事前に計量する粉・液の量は症例に応じて的確に判断する。大きな窩洞であれば多め、小さな修復なら少なめに用意し、混ぜる時間も含め硬化開始までの余裕を調節する。無駄な練り直しを防ぐためにも経験を元に必要量を見極める勘を養いたい。
粉液比の応用
標準比から意図的にずらす応用編として、仮着用途に近い使い方も可能である。例えば仮着専用の「ネオダインT」が手元になくとも、ネオダイン-αを柔らかめに練ることで一時的なクラウン仮着に流用するケースがある。この場合は弱く付着させて外れやすくするために液多め(粉少なめ)で練和する。ただし強度は落ちるため、代用は応急的に留め、本来は専用品を用いるのが望ましい。
綿花の活用
臨床現場の知恵として、綿球(コットンペレット)を併用するテクニックも挙げられる。急性の歯髄炎で麻酔が効かないような症例では、鎮痛剤を浸した綿球やドライな綿球をネオダインペーストと一緒に窩洞に詰めて仮封すると良い。ユージノールが浸みた綿が歯髄をじんわり鎮静化し、次回来院時には炎症が落ち着いて抜髄処置が円滑に行えることがある。さらに綿球を練り込むことで仮封材全体が塊状になり脱離しにくくなる効果もある。ただし、綿を入れすぎると密封が不十分になるため、適量を守り歯冠外に飛び出さないよう配慮する。
保管と品質管理
ネオダインの液剤(ユージノール)は経時で揮発・酸化しやすいため、使用後はボトルの蓋をしっかり閉め、直射日光を避け室温で保管する。長期間放置すると液が濃黄色〜褐色に変色し劣化することがあるので、使用期限を確認しつつ適切にローテーションする。粉末も吸湿を避けるため蓋を密閉し、湿気の多い場所に置かない。万一、液が切れた際に他社製ユージノール液で代用することも可能だが、メーカー純正の組み合わせで試験されているので基本は同社の粉・液をセットで使うのが安全である。
患者への説明
仮封処置を行った患者には、「本日仮詰めした箇所は一時的なものなので硬い物はできるだけ避けてください」「仮封材から丁子のような香りがすることがありますが、鎮静効果のある薬剤ですのでご安心ください」など、一言添えておくと良い。ユージノールの独特な香りは患者によって好き嫌いが分かれるが、「薬の香り」であると説明すれば概ね理解してもらえる。ネオダインの色は淡いクリーム色で金属修復物のように目立つわけではないが、前歯部など審美領域では気にする患者もいるため、場合によっては目立たない仮封材(白色のレジン系材料など)を選ぶことも検討する。
以上のポイントを押さえて運用すれば、ネオダインはクリニックにとって信頼できる縁の下の力持ちとなるだろう。導入当初はスタッフ間で情報共有し、混ぜ残りや硬化不良がないかチェックし合うと安心である。特に新人スタッフが多い場合、院内マニュアルに練和手順や注意点を明文化しておくことを薦めたい。一度習得してしまえば難しい材料ではないので、定期的な勉強会などで症例報告を交えつつ使いこなしのコツを共有することで、スタッフ全員が安心して扱えるようになる。
適応症と適さないケース
ネオダインが真価を発揮するのは、一時的に歯を封鎖しつつ歯髄や象牙質を保護したいケースである。具体的には、大きなう蝕を除去して最終充填まで時間を置く場合や、根管治療で複数回来院が前提のケース、露髄の恐れがあり歯髄の経過を見たい場合などが挙げられる。こうした場面ではネオダインの鎮静・封鎖効果によって、治療と治療の間の期間を安全に乗り切ることが期待できる。痛みが強い急性症状では、前述のように鎮痛効果を活かした仮封が奏功しやすい。逆に、痛みがなく単純な歯冠部の仮封であれば、鎮静効果のない別の仮封材(例: 非ユージノール系のレジン仮封材)でも事足りるため、ネオダインのメリットは相対的に小さくなる。
一方、ネオダインが適さない状況も存在する。第一に、将来的にレジン接着修復を予定している歯では要注意である。ユージノール成分が象牙質に残留すると、後日のコンポジットレジン充填やレジンセメント接着に悪影響を及ぼす可能性がある。このため、たとえばインレーの接着やダイレクトボンディング修復を控えている場合、仮封材としてネオダインを使うのは避け、ユージノールフリーの仮封材(水硬性仮封材や樹脂系仮封材)を選ぶ方が望ましい。もしネオダインを使用した場合でも、最終接着前には十分な除去と歯面清掃を怠らないようにする。
第二に、長期間にわたる仮封には不向きである。ネオダインは比較的溶解しにくい材料ではあるが、所詮仮封用であり半年・一年といったスパンで口腔内に留めておく想定はない。長期放置すると辺縁から徐々に溶出・摩耗して隙間が生じ、二次的な齲蝕や感染のリスクが高まる。もし患者の事情で治療再開が大幅に遅れる場合には、途中で状態を確認し仮封のやり直しを検討すべきである。長期仮封が避けられないケースでは、グラスアイオノマーセメントやレジンなどより長期安定性の高い材料への変更も視野に入れる。
また、深いアンダーカットや欠損が大きすぎるケースも注意が必要だ。ネオダインは硬化後に機械的嵌合で留まるが、あまりに支えが無いと硬化物自体が大きく動揺してしまう。例えば歯冠部がほとんど崩壊しているような場合、ネオダインだけで形を作るのは現実的ではなく、あらかじめ簡易的な型をとってレジン仮歯を作製するか、削合してでも形成を整えテンポラリークラウンで覆う方が安全である。無理にネオダインを盛り上げて形を作ろうとしても強度不足で割れてしまったり、硬化時の収縮で外れたりする可能性がある。
禁忌事項として明確に挙げられるのは、ユージノールや亜鉛化合物に対するアレルギーがある患者である。稀ではあるが、ユージノールで接触性皮膚炎を起こした例なども報告されている。このような患者にはネオダインを使用しないことが製品添付文書でも指示されている。また、過去に問題がなくても、仮封中に異常な痛みや粘膜のただれ等の過敏症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、患者を適切に処置する必要がある。ユージノールの香りが強いため、患者によっては刺激感や辛味を訴えることがあり、その点でも不快感の強い患者では他の無味無臭の材料が無難かもしれない。
最後に、ネオダインと代替アプローチについて触れると、現在の歯科臨床では他にも様々な仮封手段が存在する。水硬性仮封材(例: 石膏系のCavit等)は練らずに充填できるペースト状で操作性が良く、短期間であれば良好な封鎖性を示す。ただし鎮静効果は期待できず、深い窩では硬化膨張が痛みを誘発することもある。レジン系の仮封材(光重合型や二重硬化型)は審美性が高く強度もあるが、仮封除去時にバーで削り取る必要があり歯質にダメージを与えかねない。グラスアイオノマー系は接着性があり長期仮封に向くが、やはり除去に切削が伴う。こうした選択肢と比べても、ネオダインの総合バランスの良さ(封鎖性・鎮静効果・除去の簡便さ・低コスト)は依然として光るものがあり、症例に応じて使い分ける価値が十分にある。
どんな歯科医に適しているか(タイプ別の導入指針)
仮封材の価値観は、歯科医院ごとの診療方針や主な患者層によっても異なる。ここでは医院のタイプ別に、ネオダインの向き・不向きや導入時の指針を考えてみる。
保険診療が中心で効率最優先の先生の場合
毎日多くの患者を回し、う蝕処置や根管治療も数多くこなすような保険診療中心の医院では、スピーディーかつ確実に処置を進めることが求められる。こうした先生にとってネオダイン-αは、低コストで手早く扱え、患者の痛みも軽減できる頼れる相棒となるだろう。多少混雑したスケジュールでも、仮封後に痛みで急患対応…というリスクが減れば安心して治療計画を組める。スタッフが手際よく練和・充填できるよう教育すれば、チェアタイムへの影響も僅かで済む。もし混ぜる手間すら惜しみたい場合、同系統のネオダインEZペースト(ペースト状2剤タイプ)を検討する手もある。EZペーストはチューブから等量押し出して混和するだけで常に均一なペーストが得られ、練和時間の短縮につながる。ただし作業時間が極めて短いため慣れが必要なのと、強度が粉液タイプよりやや低いため、大臼歯部の仮封では粉液タイプに軍配が上がることも頭に入れておきたい。総じて、回転率を重視する医院ではネオダインの信頼性と操作性のバランスがメリットとなり、導入価値は高い。
自費診療・審美治療が多くクオリティ重視の先生の場合
セラミック修復やダイレクトボンディングなど自費の精密治療を中心とする医院では、仮封材にもまた別の視点が求められる。治療の質を最優先するあまり、仮封期間を置かず即日で最終補綴まで完了させるケースも多いかもしれない。そのような場合は仮封材の出番自体が少なく、ネオダインが登場する機会は限定的である。ただ、実際にはラボ作業を伴う補綴治療の間や、難症例で経過観察が必要な際に仮封は不可避である。審美治療志向の先生にとって懸念となるのはユージノールによる接着阻害であろう。この点には十分注意が必要で、ファイバーポストやレジンコア築造を予定する根管にはネオダインを使わず、ノンユージノールの仮封材に切り替える判断も重要だ。審美領域の仮封では色調も無視できない。ネオダインは淡黄色ゆえ長期間置くと若干着色することもあり、前歯部の仮封では患者から見た目の指摘を受ける可能性がある。そのため、自費中心の医院ではケースに応じてレジン仮封材や仮歯を使い分け、ネオダインは主に歯髄保護や痛みの管理が必要なケースに限定して使うのが賢明である。言い換えれば、緊急対応や疼痛管理の切り札としてネオダインを用意しておくイメージである。高付加価値治療を掲げる医院であっても、患者の痛みが出れば信頼は一瞬で揺らぐ。そのリスク管理の観点から、ネオダインは縁の下でハイエンド診療を支える役割を果たすだろう。
外科処置・インプラント中心で根管治療が少ない先生の場合
口腔外科的アプローチやインプラント治療が主な医院では、通常の保存修復や歯内療法の頻度が少ないかもしれない。それでも、急患対応やインプラント前処置としてのう蝕治療などで仮封材が必要になる場面は訪れる。外科メインの先生にとって仮封材選びのポイントは、確実な封鎖で感染を防ぐことであろう。ネオダインはその点で優れており、細菌漏洩を抑える仮封として根管治療専門医からの信頼も厚い。インプラントオペ前に感染源を減らすため一時的に齲蝕処置を行う際など、ネオダインでしっかり封鎖しておけば術後感染のリスク低減に寄与する。ただし、外科中心の医院では接着阻害云々よりも術後の診療連携を考慮する必要がある。インプラント埋入前に仮封した歯を、その後他院の保存専門医が治療再開するケースでは、ユージノール仮封が使われていることが事前に共有されていないと混乱を招く可能性がある。したがって、他の歯科医との連携症例では使用材料を共有する配慮が望ましい。インプラント仮着用セメントについてはノンユージノールが一般的だが、天然歯の仮着(例えばプロビジョナルクラウン装着期間)に限っては、ネオダインTなどユージノール系を用いる方が有髄歯に優しく外しやすい場合もある。外科・補綴を跨ぐ診療を行う先生ほど、症例に応じた材料の選択肢としてネオダインシリーズを押さえておく価値があると言える。
よくある質問(FAQ)
Q. ネオダインとネオダイン-αは何が違うのか。古いネオダインはもう使えないのか。
A. ネオダイン-αは従来のネオダインを改良した現行製品であり、硬化時間の安定性や扱いやすさが向上している。基本的な成分(酸化亜鉛ユージノール)や用途は同じだが、αでは環境による硬化時間のブレが少なく、除去のしやすさなど操作性も改善されている。古いネオダインそのものは現在市販されておらず、実質的にネオダイン-αに置き換わっている。ただし、多くの歯科医は慣習的に「ネオダイン」と呼んでおり、それが現行のネオダイン-αを指すことに注意が必要である。基本性能に大差はないため、古いユーザーも違和感なく移行できるだろう。
Q. ユージノール系の仮封材を使うと、その後のレジン接着に影響が出ると聞いたが本当か。
A. 一定の注意が必要である。ユージノールはレジンの重合反応(ラジカル重合)を阻害する性質があるため、ネオダイン仮封後に直接コンポジットレジン修復や接着性レジンセメントを用いると、接着強度の低下や硬化不良が起こるリスクが知られている。ただしこれは仮封材を歯面から十分除去しなかった場合や、直後に処置を行った場合に顕著である。適切に仮封材を除去し、アルコールなどで歯面を清拭すれば影響は最小限に抑えられる。また、仮封から最終接着まで数日以上間隔が空けばユージノールの残留も減るとされる。それでも不安な場合は、最初からノンユージノールの仮封材(例えば石膏系ペースト)を使う選択もあり、症例に応じて使い分けるのが安全策である。
Q. ネオダインで仮封したら患者さんが「少しスースーする味がする」と言っていた。これは異常か。
A. それはネオダインの主成分ユージノール(丁子油由来)の風味や揮発による感覚であり、基本的には異常ではない。ユージノールにはスパイスのような独特の香りと微かな刺激感があるため、仮封直後に患者が「スースーする」「薬の匂いがする」と感じることがある。むしろその感覚こそが薬効の裏付けであり、歯髄鎮静作用が働いている証拠とも言える。ただし、口腔内軟組織に付着するとヒリヒリする場合があるので、余剰が歯肉に付かないよう注意して充填する必要がある。香りが長引くのを嫌がる患者には、うがいをしてもらうと多少和らぐことを伝えても良い。時間とともに匂いや刺激は減少していくので心配いらない旨を説明し、どうしても気になる場合は次回から別の仮封材に変更することも検討すると案内すると丁寧である。
Q. ネオダインインプレッションペーストとは何か。仮封材のネオダインとは違うものか。
A. ネオダインインプレッションペーストは、同じネオ製薬工業から出ている無歯顎用の印象材である。成分的には酸化亜鉛ユージノール系でネオダインと類似しているが、あくまで総義歯(フルデンチャー)の精密印象採得に使う材料で、用途が全く異なる。ペースト状のベース材と触媒材を混ぜ合わせ、粘膜や可動組織の細部まで記録できるよう適度な流動性と粘性を持たせてある。硬化後の寸法安定性が高く、変形が少ないため、無歯顎顎堤の形態を正確に模型に写し取れるのが特長である。仮封材としてのネオダインとは目的も物性最適化も異なるため、代用はできない。例えば仮封にインプレッションペーストを使っても強度が不足し、逆に仮封材を義歯印象に用いても精度が出ない。混同しないよう注意し、それぞれ専用の用途で使用することが肝要である。
Q. 最近「ネオダインが販売中止になった」という話を聞いたが、本当か。
A. ネオダイン-αそのものが市場から姿を消したわけではない。ただ、一部のディーラーから流れた情報として、小容量のパッケージ(ネオダイン粉末10gなど)の供給終了が「ネオダイン販売中止」と誤解されて伝わった可能性がある。ネオダイン-αの標準セット(粉末30g+液10mL)や補充用の粉末60g・液10mLは、現在も製造・販売が継続されている。メーカーも明確に製品継続の方針を示しており、愛用してきた歯科医が急に入手できなくなる状況ではないので安心して良い。もし流通在庫の問題等で一時的に入手困難な場合でも、同種の酸化亜鉛ユージノール系仮封材(他社製品)で代替は可能である。購入に不安があれば、取引先の歯科商店に在庫状況を確認したり、必要に応じてメーカーに問い合わせて最新情報を得ることをおすすめする。今後もネオダインシリーズは根強い需要があると考えられるため、突然消滅する心配は現時点ではないと考えてよいだろう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う仮封材「ネオダイン」とは?特徴や成分を分かりやすく解説