- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 酸化亜鉛・ユージノール・弾性ポリマーのハイブリッド仮封材「ユージマー」とは?
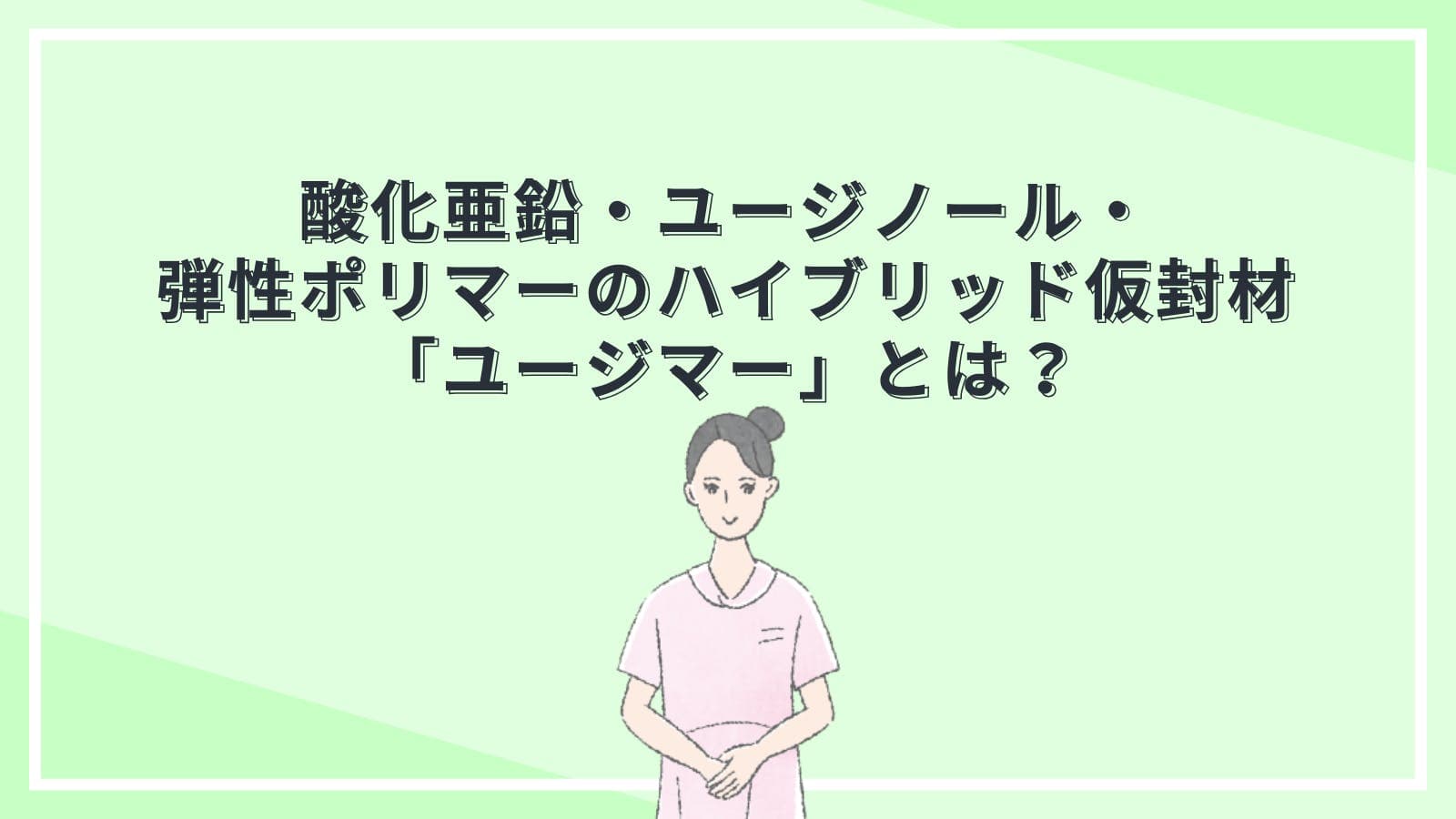
酸化亜鉛・ユージノール・弾性ポリマーのハイブリッド仮封材「ユージマー」とは?
歯科臨床では、治療の合間に詰める仮の材料がしばしば頭痛の種になることがある。たとえば深いう蝕を一時的に封鎖した仮封材が硬化後に脆く砕けてしまい、次回来院時に窩洞内へ細かな破片が残って除去に手間取った経験はないだろうか。また、仮歯を装着していたはずが数日で脱落し、患者に再来院してもらう羽目になったり、逆に仮着した仮歯が強固にくっつきすぎて本番の補綴物の適合に支障をきたしたこともあるかもしれない。さらに、混和時に漂うクローブ(丁香)の香りは、多くの歯科医師に学生実習で使った古典的な酸化亜鉛ユージノールセメントを思い起こさせる。しかし時代は進み、こうした仮封・仮着の不満を解決すべく各社から改良型の材料が登場している。本稿では、その代表例である酸化亜鉛・ユージノール・弾性ポリマーからなるハイブリッド仮封材「ユージマー」に焦点を当てる。臨床の現場目線と医院経営の視点を交え、この製品の特徴を紐解き、自院の診療スタイルに合った価値を見極めるヒントを提供したい。
ユージマーの製品概要
ユージマー(海外名: Eugemer)は、日本歯科薬品株式会社(ニシカ)が製造販売する粉液混合タイプの歯科用仮封材である。一般的名称は「歯科用酸化亜鉛ユージノール仮封向け材料」に分類され、医療機器としてはクラスIIの管理医療機器にあたる。化学組成は粉末成分に酸化亜鉛と独自の弾性ポリマーを含み、液はユージノール(丁香油)を主成分とする。古くからある酸化亜鉛ユージノールセメントをベースに改良を重ねた製品で、初代発売から半世紀以上にわたり改良され続けてきたロングセラーである。現在はメーカー直販のほか松風など歯科材料大手からも発売されており、全国の歯科ディーラーで入手可能である。セット内容は粉末50gと液12mL(計量スプーン・すり切り板付き)で、標準価格は1セットあたり税別約5,600円とされる(粉末・液の補充用も個別に販売)。適応は数日~1週間程度の短期間における窩洞の仮封および仮歯の一時的な装着(仮着)である。長期にわたる仮封・仮着用途には設計されておらず、後述するように必要に応じて他の材料との使い分けが推奨される。
主要スペックと臨床的な意味
ユージマー最大の特徴は、その硬化後の性質にある。従来の酸化亜鉛ユージノール系セメントは硬化後に非常に硬く脆くなる傾向があったが、ユージマーでは粉末に配合された弾性ポリマーの作用により硬化後も適度なしなやかさ(弾性)を保持する。これによって、例えば仮封した窩洞に探針を入れて縁から持ち上げると、セメントがゴムのようにしなって塊ごとペロンと剥がれ落ちる独特の除去性を実現している。この一塊除去が可能な性質は、仮封材として大きな利点である。細かな残留片が窩壁や支台歯表面にこびり付くリスクが低く、次の処置(支台歯の形成修正や最終補綴物の装着準備など)において歯面清掃がスムーズに行える。結果として、余分なチェアタイムを取られず臨床ステップの効率化につながる。
物性面では、封鎖性の高さと歯髄への優しさが挙げられる。粉末の粒子径が最適化されているため、エナメル質・象牙質双方で微小な隙間までよく流れ込み、辺縁部のシール効果が高い。メーカーの社内試験では、硬化後2時間時点での色素浸透を極めて小さく抑えられたとの報告もあり、微漏洩の少ない仮封が期待できる。また液成分のユージノールは古くから鎮静効果と抗菌作用が知られており、露髄を伴わない深い齲窩を一時的に封鎖する場合に歯髄の炎症を和らげてくれる。筆者自身の経験でも、う蝕除去後に本製品で仮封しておくと次回来院まで患者の術後疼痛が生じにくい印象がある。これは直接覆髄材の代わりになるものではないが、歯髄を落ち着かせる仮封という意味で非常に心強い。硬化時間は口腔内で概ね4~5分程度と標準的で、粉と液の比率によって多少前後する。手動練和による操作も特に難しい点はなく、付属スプーンで計量して所定の比率を守れば滑らかなペーストが短時間で調整できる。混和中から固まり始めるまでの作業時間も2分程度は確保でき、チェアサイドで落ち着いて操作できる範囲である。
一方で、強度・保持力に関してはメリットとデメリットが表裏一体で存在する。ユージマーは弾性を残すため、完全に硬化した後の硬度(硬さ)は従来型より低めである。つまり「適度に軟らかい」という性質は、強固に固まらないことの裏返しでもある。仮封材として窩洞内に詰める用途では多少軟らかい方が除去が容易で好都合だが、クラウンやブリッジの仮着(仮歯の固定)用途では維持力の弱さにつながり得る。単独歯のクラウン程度であれば十分保持できるが、長期間にわたるブリッジの仮歯をユージマー単独で固定し続けるのは不安が残るケースもある。この点は製品コンセプト上想定された制約であり、ユージマー自身も「仮封材(temporary filling material)」という位置付けであることを踏まえる必要がある。
他製品との互換性と運用上のポイント
ユージマーは粉液を練り混ぜて使用するクラシックなタイプの材料であるが、その運用は現代の臨床にも十分マッチするよう工夫されている。接続機器やデジタルデータといった概念は該当せず、人の手による練和と適用が基本である。適切な混和比は液1滴に対して付属スプーン山盛り1杯弱の粉末が目安となる。練和は紙パレット上で金属またはプラスチック製のスパチュラを用いて行い、約30秒ほどで均一なペースト状になる。ペーストの硬さ(粘度)は練和時の粉液比で調節可能であり、例えば深い窩洞へ詰める仮封ではやや粉多めで練ると粘調度の高いペーストとなり、盛り上げても沈み込みにくい。一方、仮歯を装着する仮着用途では少し軟らかめ(粉を控えめ)に練ることで薄い被膜厚で全体に行き渡る低粘度ペーストとなり、クラウンを完全に圧接しやすくなる。ただし軟らかいほど保持力も低下するため、症例に応じた加減が必要である。
他材料との化学的な互換性で注意すべき点としては、ユージノール成分がレジン系材料の重合を阻害する可能性が挙げられる。ユージマーを含むユージノール配合の仮封・仮着材は、隣接するコンポジットレジンの硬化や、後続の接着処置に影響を及ぼすことが知られている。そのため、たとえば次回にレジン充填やレジンセメント接着を控えている症例では、ユージマーの残渣を完全に除去することが重要である。幸いユージマーは前述の通り一塊で除去でき残りカスが少ないため、注意深く清掃すれば実質的に重合阻害のリスクはかなり減らせる。また、念入りを期すなら、レジン系接着操作の前にレジンクリーナー(レジン残渣や油分を溶解する専用洗浄剤)で支台歯面や仮歯内面を処理する方法も有効である。実際、仮歯内側に付着したユージノール系セメントをクリーナーで容易に溶解除去できる製品も市販されている。こうした追加ステップには多少コストや手間がかかるが、最終補綴物の接着不良による再製作リスクを防げることを考えれば安い投資と言えるだろう。
日常の清掃・保守については特段難しい点はない。粉末は吸湿しないよう容器の蓋をしっかり閉め、直射日光や高温を避けて保管する。液剤のユージノールも揮発性があるため使用後はすぐにキャップを締める習慣が望ましい。いずれも通常は数年単位の安定した保存性を持つが、長期間経過して粉が固まり始めたり液が濁るような場合は交換時期である。院内感染対策の面では、混和に使うパレットは使い捨てのものを用いると後片付けが楽だ。スパチュラも使用後はすぐにアルコール綿などで拭き取れば匂いも残りにくい。ユージノールの独特な香りは診療空間に広がりやすいので、こぼしたり放置したりしないことも細かなポイントである。
ユージマー導入による経営インパクト
仮封材の選択ひとつで医院経営に大きな差が出るようには思えないかもしれない。しかし、診療現場の効率や患者満足度の積み重ねが経営に与える影響を考えると、ユージマー導入による恩恵は決して見過ごせない。まずコスト面から見ると、ユージマーの材料費は1セットあたり5千円台半ばであるが、1回の処置で使用する粉と液はごく微量である。仮に粉末0.5g・液0.1mL程度を1症例に用いたとすれば、50g/12mLのセットで少なくとも100症例分程度は賄える計算になる。単純計算で1症例あたり数十円程度という低コストであり、従来の安価な仮封材と比較しても患者1人あたりの追加負担は数十円~せいぜい百円程度に過ぎない。これだけを見ると「コスト削減効果は小さい」と思われるかもしれないが、真の経営インパクトはその先の効率化にある。
例えばユージマーを用いることでチェアタイムの短縮が期待できる。硬化後に一塊で除去できるため、次回来院時の仮封除去にかかる時間が従来よりも1~2分ほど短縮できるケースは珍しくない。補綴物の試適・装着の際にも、支台歯や窩洞内に残った仮封材の微細片を探し回る必要がほとんどなく、スムーズに本番処置へ移行できる。仮に1症例あたり2分の時短効果が得られ、こうしたケースが週に10件あれば週20分、年間換算で約16時間もの診療時間が創出される計算になる。この時間を新たな患者対応に充てれば売上増加につながるし、既存のスケジュール圧迫を緩和してスタッフの残業削減や休憩確保に回すこともできる。
さらに、想定外のトラブル減少も見逃せない。ユージマーは適切な短期用途であれば封鎖性と安定性が高く、仮封脱離や術後疼痛の緊急対応が減る可能性がある。もし仮封材の選択ミスで患者が予定外の再来院を要すれば、その都度30分前後の枠が埋まり他の予約にしわ寄せが生じる。患者にとっても負担であり医院の信頼低下にもつながりかねない。ユージマーを使って防げるトラブルがあるなら、その予防効果は一件あたり数千円以上の価値があるとも言えるだろう。実際、深い齲窩の仮封後に痛みが出ず本格治療まで安定して経過すれば、その患者は安心して治療継続してくれる。治療結果だけでなくプロセスの快適さも患者満足度に直結し、紹介やリピートにも好影響を及ぼす。長期視点でROI(投資対効果)を捉えれば、僅かな材料費の差で得られる診療効率と患者信頼の向上は十分に元が取れる投資と言える。
使いこなしのポイントと注意事項
ユージマーを真価発揮させるには、いくつかのポイントを押さえておくとよい。まず導入初期の注意点として、スタッフを含めて適切な練和手順に慣れることが重要である。最近はペーストタイプの即時硬化材料(例:ワンペーストの仮封材など)に慣れた若手歯科医師も多いが、粉液混合型も手順自体は難しくない。付属の計量スプーンやスポイト瓶を活用し、取扱説明書に沿った比率で混ぜれば誰でも短時間で良好なペーストを得られる。焦って一度に大量の粉を加えるとダマになりやすいので、最初は液1滴に対し粉1/2スプーン程度から少しずつ練り込むとムラなく混ざる。その後、必要に応じて少量ずつ粉を追加し希望する硬さに調節すると失敗しにくい。練和中は時間経過とともにペーストが重くなっていく(徐々に硬化が始まる)ため、手早く練り上げて指で触れてみて適度な粘度になったらすぐ使用に移るのがコツである。
窩洞への充填では、あらかじめ唾液や湿気をきちんと除去し乾燥気味の環境で操作する。ペーストは練和直後が一番流動性が高いので、手早く窩洞に填入して表面をならしきることがポイントだ。ある程度盛り上げておいても完全硬化後も弾性があるため、咬合圧で押されれば多少は圧潰して適合する余地がある。しかし噛み合わせが強く当たると脱離につながる恐れがあるため、可能なら対合歯と干渉しないよう形態を整える。適度に硬化したら綿球等で圧接し表面を滑沢にしておくと、唾液との境界が滑らかになり二次う蝕や着色の防止に役立つ。
仮歯の装着にユージマーを用いる際は、必ず外れることを想定した工夫を凝らすと良い。例えば複数歯ブリッジの仮歯でユージマーのみを使う場合、長期間放置するとやはり維持力が心許ない。そのため重要な部位には別の強固な仮着材を併用するなどテクニックで補うことも考えられる。具体的には、大臼歯部など咬合力の大きい支台歯には一部だけユージマーを使わず、脱脂綿を介在させるか他の硬化型セメントを点付けする方法もある。また仮歯装着後の清掃でユージマー余剰セメントを放置しないよう注意したい。軟らかいので細部に入り込みやすいため、フロスや探針で辺縁部の残留物を確実に除去しておく。幸い硬化後もしなやかで除去しやすいので、過不足なく取りきることで後の仕上がりが美しくなる。
患者説明の面では、「仮封材が入っている間の注意事項」を伝えることが肝要である。ユージマー自体のユージノール臭や味は独特だが、多くの患者は「歯医者さんの薬の味」として受け入れる傾向にある。ただ、まれに香料に敏感な患者は不快に感じることもあるため、「一時的に少しスパイシーな香りがする薬を入れていますが心配ありません」と一言添えると安心するだろう。そして何より、仮封中は過度な咀嚼力や粘着性の高い食品を避けるよう指導する。ユージマーは短期間であれば十分な封鎖力を発揮するが、ガムやキャラメルなどはどんな仮封材でも脱落の原因となり得る。もし仮封が取れてしまったり痛みが出たりした場合はすぐ連絡いただくよう説明し、仮封材を入れている間のセルフケア(強いうがいや刺激を与えすぎない等)についても指導しておくと良い。こうした丁寧なフォローにより、患者は安心して次回まで過ごせる上、医院への信頼感も高まるはずである。
適応症と適さないケースの見極め
ユージマーの適応症は、まとめると「短期間の仮封・仮着」で「歯に優しく経過を安定させたい場合」である。具体的には、深い齲窩の一時的封鎖や支台歯形成後から次回補綴処置まで数日〜1週間程度あける場合の仮封に最適だ。例えば大きなう蝕を除去し、本来であれば根管治療に移行するか微妙なケースで、ひとまず歯髄の経過観察をしたい時などにユージマーで密封しておけば、封鎖性が高く細菌漏洩を防ぎつつユージノールで痛みも出にくくできる。同様に、支台歯形成直後に痛みやしみが強い症例で、最終印象採得まで歯髄を沈静化させたいような場合にも有用である。実際、支台歯形成後にユージマーで仮封して数日置くと、次回には刺激痛が治まっていることが多く、その後の形成修正や接着処理を安心して行える。仮歯を一時的に外して支台歯だけ仮封しておく必要がある際(例えば患者の都合で補綴装着を延期する場合)にも、ユージマーなら歯髄保護効果を期待しつつ短期間の支台保護ができるため重宝する。
適さないケースとしては、まず長期に及ぶ仮歯の固定が挙げられる。ユージマーは軟性重視のため、1週間以上の安定保持や強い咬合力への耐久には向かない。インプラント治療中のプロビジョナルクラウンや、大きなブリッジの仮着を数ヶ月維持するようなケースでは、より高強度の仮着専用品を使うのが現実的である。例えばユージノールを含まない樹脂系の仮着セメント(例:フリージノール、テンポラリーセメントハード等)は長期安定性に優れるため、そういった材料との使い分けが望ましい。また、レジン接着が控えている症例も注意が必要だ。ユージマー自体は完全除去しやすいとはいえ、直後にコンポジットレジン充填やレジンセメント接着を行う場合には、わずかな残留成分が接着強度に影響する可能性がゼロではない。特に審美補綴などでレジンによる接着性を最大限発揮させたい症例では、初めからユージノールフリーの仮封材(例:樹脂系仮封材や光重合型の仮封材)を選択するほうが無難な場合もある。同様に、ユージノールアレルギーの患者や、匂いに強い不快感を示す患者には使用すべきでない。幸いそうしたケースは稀だが、既往歴でクローブ系の薬剤に反応したことが分かっている場合は他の材料を検討する。総じてユージマーは万能ではないものの、「短期間」「仮封主体(必要なら単独歯の仮着まで)」という範囲であれば非常にバランスの取れた性能を発揮する。
なお、古典的な水硬性仮封材(商品名キャビトンなど)との比較では、そうした材料は混和不要ですぐ使える利点がある一方、長く置くと溶解・摩耗しやすく深い部位では封鎖不良を起こしやすい傾向がある。また硬化後は脆性が高く除去の際に崩れやすい。ユージマーは混和の手間こそあるものの、封鎖性・安定性・除去性の三拍子で勝り、特に精密な処置の合間や歯髄への刺激を極力避けたい仮封にはうってつけである。一方で、どうしても必要以上の強度を求められる仮着用途では他材に譲るという割り切りも大事だ。適材適所で使い分けることで、材料の長所を最大限に生かした臨床が実現する。
臨床スタイル別・導入判断の指針
歯科医院ごとに診療のスタイルや重視する価値は異なる。ここではいくつかのタイプ別に、ユージマー導入の向き不向きを考察する。
1. 保険診療中心で効率優先の医院
保険診療メインで日々多くの患者を回すクリニックでは、1件あたりの材料コストを抑えつつ手早く確実な処置を行うことが最重要だ。このような医院では昔から馴染みのある安価な仮封材(例えば水硬性仮封材や安価な粉液セメント)が使われることが多い。しかし効率を追求するのであれば、ユージマーがもたらすトラブル減少と再処置削減の効果は見逃せない。仮封の脱離や術後痛による緊急来院が減れば、それだけ無駄な時間を省ける。また来院毎に仮封除去が短時間で終われば、その数分の積み重ねで予約にゆとりが生まれる。材料費の差は1症例数十円ほどであり、患者1人が余計に再来院する事態を防げればすぐに元が取れる計算だ。多忙で回転率重視の現場こそ、ユージマーによる効率アップの恩恵を享受しやすいと言えるだろう。混和のひと手間は必要だが、アシスタントに練和を任せればドクターの手は止まらない。スタッフ教育を含め導入初期の工夫はいるものの、運用に乗れば「安定感による安心」と「時短効果」によって却って診療がスムーズになったと感じられるはずである。
2. 自費診療中心でクオリティ重視の医院
高付加価値の自費診療をメインとするクリニックでは、患者満足度と最終的な治療クオリティが最優先だ。その意味で、ユージマーの歯髄への優しさや仮封中の安定性は、質の高い診療プロセスを支える一助となる。特に審美領域では最終補綴物の適合・接着成功が命題であり、仮封段階で歯が痛んだり仮歯が外れて患者の不安を招くことは絶対に避けたい。ユージマーであれば、深い象牙質まで達した支台歯でも鎮静効果で患者の違和感を抑えつつ、次回来院まで安定した状態を保てる。また除去残渣が少ないため、本番の接着操作前に余計なストレスが無いのもメリットだ。ただし自費補綴では最終的にレジン接着するケースが多いため、前述のようにユージマー使用後の接着操作には細心の注意を払う必要がある。高品質志向の先生であれば、仮封材を選ぶ際も「レジン干渉のリスク vs 歯髄保護メリット」を天秤にかけて判断すると良いだろう。例えば短期で最終セットまで進める見込みなら、あえてユージノールフリーの仮封材を使って接着リスクを皆無にする選択もある。一方で歯髄炎症のリスクが高い症例ではユージマーを使い、接着前にクリーニングを徹底することで両立を図る、といった戦略が考えられる。総じて、自費中心の医院にとってユージマーは「患者に優しくトラブルを減らす保険」のような存在である。治療結果だけでなくプロセスの安心感まで提供したいという価値観を持つ医院にはマッチしやすいと言える。
3. 外科・インプラント中心の医院
主に口腔外科処置やインプラント治療に注力する医院では、日常的に仮封材が活躍する場面は多くないかもしれない。インプラントの一次手術・二次手術自体には仮封の出番はなく、仮歯の装着も特殊なケースを除けばインプラント用の専用仮着材(長期安定性や超薄被膜厚を特徴とする製品)を用いることが一般的だ。そのため、そういった専門領域ではユージマーの必要性は相対的に低いだろう。しかし、インプラント専門とはいえ一部一般診療も行う医院や、口腔外科処置後に隣在歯を保護するような場面では、ユージマーが有用なケースもある。例えばインプラント埋入前に隣の大きな齲蝕を暫間的に封鎖しておく場合、術後感染を避けるためにも密封性が高く歯髄鎮静効果のあるユージマーは理に適っている。また、抜歯即時インプラントなどで隣接歯に余計な刺激を与えたくないとき、一時的にその歯をユージマーで仮封カバーしておくことで侵襲を減らすといった工夫も可能だ。外科処置中心の医院ではユージマーの出番は限定的かもしれないが、「いざという時に頼れる仮封材」として備えておく価値はある。むしろ普段あまり仮封材を使わないからこそ、いざという時に扱いやすく信頼できる製品を選んでおくことが望ましい。インプラント仮歯自体には別途専用品を使うにしても、天然歯の管理やトラブル対応用としてユージマーを常備しておけば、診療の守備範囲をしっかりカバーできるだろう。
よくある質問(FAQ)
ユージマーで仮封したまま、どのくらいの期間維持できますか?
ユージマーでの仮封は数日から1週間程度が目安である。製品としても短期仮封用に位置付けられており、この範囲内であれば封鎖性と安定性が十分発揮される。1週間を超えても直ちに劣化するわけではないが、唾液中で徐々に軟化・溶解する可能性があるため、長期間放置しないことが望ましい。もし治療の都合で仮封期間が延びる場合は、一度仮封を外して状態を確認し、新しいユージマーで仮封のやり直しを行うと安全である。長期にわたる仮封が必要なケースでは、必要に応じて他の材料(例えばレジン系の仮封材や仮着材)への切り替えも検討すべきだ。
ユージノール成分が後のレジン接着に悪影響を及ぼしませんか?
ユージマーに含まれるユージノールは、一般にレジン系材料の重合を阻害する可能性が指摘されている。ただしそれは仮封材の残留成分が歯面や補綴物内面に残ったままの場合に問題となる。ユージマーは硬化後も塊で除去しやすいため、適切に除去すれば残留物はごく微量である。臨床的にも、ユージマー除去後にしっかり研磨・洗浄を行えばレジンセメントの接着不良はほとんど経験しない。ただ、万全を期すならレジンクリーナーでの洗浄やエタノールでの拭掃など、歯面処理を追加することでリスクを最小化できる。どうしても不安な場合や極めて重要なレジン接着ケースでは、初めからユージノールを含まない仮封材を選択する方法もある。要は残留ユージノールをゼロに近づけることが肝心であり、その点さえ押さえればユージマー使用後でも問題なく接着が行える。
ユージマーだけで仮歯の固定(仮着)に使っても大丈夫でしょうか?
単独のクラウンの仮着であれば、多くの場合ユージマーで問題なく固定できる。実際に支台歯1本に対する仮歯装着では、適切にユージマーを塗布・圧接すれば数日~1週間は安定して維持されることが多い。ただし複数歯にまたがるブリッジや長期間外せない仮歯では、ユージマー単独では外れやすいケースがある。そのような場合には、ユージマーを仮封部分に使いながら、別の強固な仮着材(例:グラスアイオノマー系や樹脂系の仮着用セメント)を併用するのが安全策である。実際にはユージマーの他に、高硬度タイプの仮着専用品(過去には「ネオダインT」等)がラインナップされており、仮封用(軟らかめ)と仮着用(硬め)を使い分けることが推奨されてきた経緯がある。まとめると、ユージマーは仮封材メインと考え、短期の単冠仮着までが適応範囲だと捉えるのが無難だ。長期の仮歯維持が必要なら他の材料との併用や置き換えを検討しよう。
他の仮封材(例えば水硬性仮封材やIRM)と比べて何が違いますか?
従来の代表的な仮封材である水硬性仮封材(商品名キャビトンなど)や、強化型の酸化亜鉛ユージノールセメント(IRM等)との違いを整理すると次の通りである。水硬性仮封材はペースト状ですぐ使える手軽さと、唾液で膨潤して窩洞に適合する封鎖性が特長だが、長期間になると溶け出したり摩耗してしまう欠点がある。また硬化後は脆いため取り除く際にボロボロと崩れ、取り残しが生じやすい。一方IRMに代表される従来型のユージノールセメントは、粉に樹脂を混ぜて強度を高めたものの、やはり硬化後は硬く脆い性質で、一度割れると細片が残りやすい。これに対しユージマーは硬化後の適度な弾性により、一塊で除去できて残渣が少なく、封鎖性も高く維持される点が大きなアドバンテージだ。またユージノールによる鎮静効果が得られる点はIRMと共通だが、IRMよりもしなやかで扱いやすく改良されていると言える。簡便さでは水硬性ペーストに軍配が上がるものの、総合的な臨床性能(封鎖性・鎮静効果・除去の容易さ)でユージマーは従来材より一歩秀でた存在だろう。
ユージノールによるアレルギーや刺激の心配はありますか?
ユージノール(丁香油)は比較的安全性の高い薬剤であり、通常の使用で歯髄や歯肉に著しい刺激を与えることは少ない。むしろ歯髄鎮静効果で知られるように、深い齲窩の仮封でも患者の痛みや不快感は出にくい傾向がある。ただし、ごくまれにユージノールやクローブの成分に対しアレルギー反応を示す患者が存在する。また高濃度のユージノールが粘膜に長時間触れると、弱い刺激や灼熱感を訴える場合もゼロではない。臨床上は頻度こそ低いが、既往歴で化粧品や香辛料アレルギーがある患者には留意したい。対策として、心配な場合は事前に口腔内でごく少量試してみて刺激症状が出ないか確認すると安心である。万一ユージノールに過敏な患者であれば、ユージマーの使用は避けて非ユージノール系の仮封材(樹脂系や一時的封鎖用の他製品)を用いるのが無難だ。幸いユージノールアレルギーは極めて稀なので、通常は過度に心配する必要はないが、患者ごとに体質や嗜好を踏まえて材料選択できるよう複数のオプションを用意しておくと安心である。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 酸化亜鉛・ユージノール・弾性ポリマーのハイブリッド仮封材「ユージマー」とは?