- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使うデュラシールと即時重合レジン(即重)の違いとは?
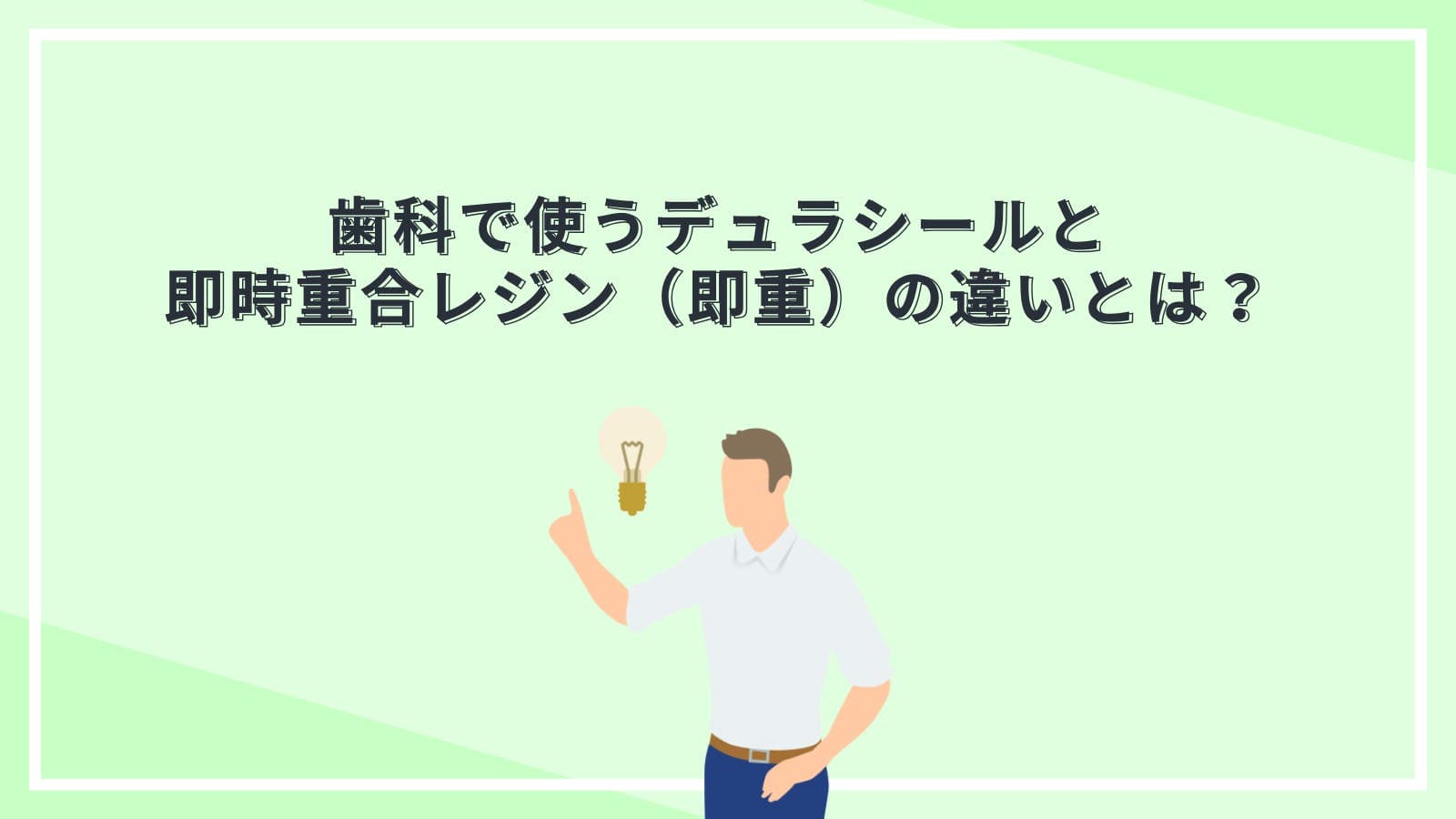
歯科で使うデュラシールと即時重合レジン(即重)の違いとは?
夕方の診療で、奥歯のクラウン(土台の形成と印象採得)を終えたあと、仮封処置に入ったところアシスタントが材料を取り違えた。デュラシールの粉に即時重合レジン用の液を混ぜてしまい、硬化後に「外れなくなるのでは」と冷や汗をかいた経験がある。また、別の日には前歯の大きな形成歯に安易にデュラシールのみで仮蓋したところ、翌日には外れて患者が再来院する事態になった。忙しい診療の中でデュラシールと即時重合レジン(即重)の使い分けに迷う場面は意外と多い。本記事では両者の違いを臨床面と経営面から解説し、適材適所の選択によって患者満足と診療効率を高め、不要なトラブルを防ぐポイントを探る。
要点の早見表
| 比較項目 | デュラシール(仮封用レジン) | 即時重合レジン(Tek用レジン) |
|---|---|---|
| 性質・硬化 | 粉液混合型レジン系仮封材。数分で初期硬化し、完全硬化まで約30分。硬化後はやや弾性を持つゴム状 | 粉液混合型自己重合レジン材。数分で硬化(発熱あり)。硬化後は硬質で剛性が高く弾性なし |
| 主な用途 | インレー形成窩洞等の短期仮封。生活歯の露出面保護と窩洞封鎖 | クラウン・ブリッジの仮歯(テンポラリークラウン/Tek)。大きな欠損の審美・機能回復、数週〜数ヶ月の暫間補綴 |
| 操作方法 | 液と粉を練和し軟らかくなったら筆やスパチュラで窩洞へ充填。口腔内で硬化させる。隔壁や下処理要らず簡便 | 印象やマトリックスを用いて歯型を再現し、レジンを流し込んで成形。直接法ではワセリン塗布や一旦取り外す操作が必要。硬化後に研削・調整して仮着 |
| 硬化後の強度 | 弾性に富み、一塊で除去可能。強度は中程度で噛み合わせの大きな力には不向き | 極めて硬く高強度。咬合や機能を十分支えるが、下方向の力で変形せず引っかかる恐れあり |
| 審美性 | 低い。白色〜乳白色だが形態再現せず穴埋め程度。前歯部には不向き | 高い。歯の形と色(レジンの色調次第)を再現でき、前歯でも目立たない仮歯が作製可能 |
| 患者への注意 | 硬化後30分は飲食禁止。粘着性の食品(ガム、餅等)や硬い物は避ける。フロスは通しにくい場合が多い | 極端に硬い物や粘着物は避ける(通常の食事は可)。フロスは仮歯を押し上げないよう横に引き抜いて使用 |
| 保険診療上の扱い | カリエス処置や補綴処置に含まれる消耗材料(単独算定不可)。材料単価は低コスト | クラウンやブリッジの一環(通常別算定なし)。材料費は僅かだが作製に手間と時間を要する(場合により技工料金が発生) |
| 利点 | 操作が簡便で除去も容易。歯質保護と密封性に優れ、生活歯の疼痛予防に寄与 | 強度と精度が高く、隣接面・咬合を保持。審美的で患者受容性が高い。長期仮歯として安心 |
| 留意点 | 長期間や大きな欠損では脱離・変形リスク。モノマー臭あり。接着面にはレジン分離材が必要な場合あり | 技術・手間が必要。直接法では歯にロックしない注意が必要。装着には仮着セメント使用。過度な放置で二次カリエスの恐れ |
デュラシールと即重、それぞれの臨床的役割と経営上の視点
臨床で求められる役割の違い
デュラシールと即時重合レジンは、どちらも補綴物装着までの一時的な処置だが、その担う役割は異なる。デュラシールは「仮封材」として削った窩洞を封鎖し歯髄や象牙質を保護することが主目的である。冷温刺激によるしみる痛みを防ぎ、削合後の脆弱な歯質が欠けないよう物理的に支えるクッションの役割を果たす。一方、即時重合レジン(以下、即重)は「仮歯(テンポラリークラウン等)」の材料であり、欠損した歯の形態と機能を一時的に回復させることを目的とする。例えば前歯の大きな欠損やクラウンブリッジの支台歯には、審美性と咬合機能を担保する仮歯が必要となる。それに対し、小さなインレー修復待ちであれば形態再現までは求められず、穴を塞ぐ仮封で十分である。臨床的には、デュラシールは「仮詰め」、即重レジンは「仮歯」とイメージすると分かりやすい。
こうした役割の違いから、材料特性もそれぞれ最適化されている。デュラシールは硬化後に適度な弾性を保つよう設計されている。ゴム状の弾力が残ることで、次回処置時に探針などで引っ掛ければ一塊でスポッと除去できる。窩壁のアンダーカットに多少入り込んでいても材料がたわんで外れるため、歯質を傷つけず安全に撤去できる仕組みである。それに対し即重レジンは硬化するとほとんど弾性を示さずカチカチに硬い。仮歯が使用中に歪んだりたわんだりすると、接着した仮着セメントが破折したり咬合が狂ったりする恐れがあるためである。強い力が加わっても変形しない剛性が、咬合圧を受ける仮歯には求められる。一方、この硬さは仮封材用途には不利に働く。例えばインレー窩洞を即重レジンで埋めてしまうと、下方に広がる形で硬化してしまい、弾性がないため除去の際に割れたり歯に引っかかったりする可能性が高まる。実際、デュラシールの粉に誤って即重レジンの液を混ぜて使用したケースでは、通常より硬くなりすぎて外しづらくなる懸念が指摘されている。つまりデュラシールは除去性重視、即重レジンは強度維持重視と、臨床ニーズに合わせた性質になっている。
医院運営への影響の違い
両材料の選択は、医院のオペレーションや収益にも影響を及ぼす。デュラシールは粉液を少量混和するだけで即座に仮封が完了するため、チェアタイムの短縮につながる簡便さが魅力である。1歯あたりの材料コストも数十円程度と僅少であり、頻繁に使用しても経済的負担は小さい。一方、即重レジンを用いた仮歯作製は、印象採得やレジン盛り上げ、硬化後の研磨・調整、仮着といった工程が必要なため、1歯あたり数十分の時間を要することもある。その分、歯科医師やスタッフの労力がかかり、忙しい診療では負担となる。材料自体の費用はデュラシール同様に安価だが、場合によっては技工士による仮歯制作を依頼するケースもあり(特に複数歯や高い審美要求がある場合)、その際は技工料が発生し院内コストとなる。
しかし、仮歯作製に時間とコストを割くことは決して無駄ではない。特に自費治療や前歯部の治療では、仮歯の出来が患者満足度に直結する。美しく違和感のない仮歯を提供すれば、治療中の患者の社会生活への支障を減らし、医院への信頼感向上につながる。また保険診療であっても、適切な仮歯により治療中のトラブルを防止できる。例えば仮歯がない状態で放置すれば隣接歯が移動して型取りや補綴物適合に支障をきたす恐れがあるし、仮封だけで噛ませずにいると対合歯が伸長したり咬合が変化するリスクもある。結果的に補綴物の調整や再製作に時間を取られれば、医院にとって大きな損失となる。初めに適切な暫間処置を行うことが、後工程のスムーズさと患者満足、ひいては経営効率につながることを意識したい。
加えて、スタッフ教育の観点も重要である。デュラシールの扱いは比較的容易で新人アシスタントでも数回で習得できるが、即重レジンを用いた仮歯作製は一定の技術習熟が求められる。医院として仮歯製作のプロトコルを標準化し、スタッフが効率よく質の高い仮歯を作れるようトレーニングしておけば、院長の手が塞がる時間を減らしつつ患者サービスの質を上げることができるだろう。逆に、仮歯作りに不慣れなままでは時間がかかりすぎたり粗悪な仮歯となり、患者の不満や補綴物の不適合につながりかねない。材料の使い分けルールや手順書を整備し、ミス(例えば粉液の取り違えなど)を防ぐ工夫も医院経営のリスクマネジメントの一環である。
適応症と使用を避けるべき場面の整理
デュラシールと即重レジンの代表的な適応は、それぞれ前述の通りだが改めて整理する。デュラシールはインレー修復や小さなMOD修復の待機期間、あるいは根管治療中のアクセスホールの封鎖などに有用である。歯髄が生きている場合には、仮封期間中に刺激や細菌感染から歯髄を守ることが重要であり、デュラシールは密閉性と遮断性に優れるため適している。また短期間(おおむね2〜3週間以内)で次回処置が予定されているケースに向いており、その間に外れてしまっても比較的容易に付け直しができる。ただし大きな咬合力がかかる部位(咬頭が欠けたまま等)では噛むたびにデュラシールがたわんで負荷を受けるため、割れたり外れたりしやすい。このようなケースでは初めから仮歯を装着して噛ませる方が安全である。また前歯部の広範囲な欠損にデュラシールのみで対応するのは避けるべきである。審美的に患者の同意が得られないだけでなく、形態が再現されず舌感や発音にも支障が出る。前歯の場合、たとえ1週間程度でも仮歯を入れておくのが基本である。
即重レジン(Tek材料)の適応は、クラウン・ブリッジ、ラミネートベニア、インプラント上部構造待ちなど、多様な補綴ケースに及ぶ。特に技工物完成まで2週間以上かかるような場合や、複数歯にわたる補綴では仮歯は必須と言える。仮歯は咬合関係と歯列の安定を維持し、歯肉の形態を整える役割も果たすため、長期間仮歯なしで放置することは補綴の成功率を下げる。また抜歯即時埋入インプラント等で隣接歯や対合歯の関係維持が必要な場合にも、仮歯で固定しておくことが多い。逆に適応外もしくは注意すべき場面としては、短期間で済む小さな修復への過剰な仮歯作製が挙げられる。例えば1週間後にセット予定の小臼歯インレーに立派な仮歯を作るのは非効率であり、デュラシールで十分と言える。また深い虫歯で直接法レジンコーティング(象牙質へのボンディング処置)を行ったケースでは、レジン系の仮封材を使うとコーティング面に強く付着して剥がす際に困難を伴う可能性がある。そのような場合はあえてデュラシールを避け、水硬性の仮封材(キャビトン等)や柔らかいストッピング材を用いる選択肢もある。症例ごとに仮封の目的(歯髄保護、咬合維持、審美など)を考慮し、両材料を適材適所で使い分けることが重要である。
ワークフローと品質確保のポイント
デュラシールのワークフロー
あらかじめ処置した窩洞内を清掃・乾燥し、必要に応じて隔壁や覆髄処置を行った上で使用する。粉と液をメーカー指示の比率で練和すると数十秒で次第に粘稠度が上がり「餅状」のペーストになる。まだ流動性が高い初期に入れてしまうと垂れたり咬合面で沈下して低くなる恐れがあるため、適切な硬さになるタイミングを見計らって充填するのがコツである。ペーストを専用の筆やスパチュラで窩洞に押し込め、表面を歯の形に沿って成形する。咬合面では対合歯とあたりが強く出ないようやや凹ませるか、咬ませてから除去する方法もとられる。隣接面まで広い欠損では、隣在歯との間にあえてフロスを通しておき、はみ出した材料が固まる前にフロスを引き抜いて接着しないよう工夫することもある。硬化開始後は数分で触れても圧痕がつかなくなる程度に固まるが、完全硬化までは30分ほど要する。術者は咬合と封鎖状態を確認し、患者には30分間は飲食しないよう伝える。なお、強く噛み締めると未硬化の仮封が沈んで薄くなってしまうため、処置後すぐは軽く噛んでもらい、過度な咬合力がかからないよう注意喚起すると良い。デュラシールは術者にとって扱いやすい材料だが、硬化前後の性状変化が速いため新人スタッフには練習が必要だ。タイミングが早すぎるとベタついて扱いにくく、遅すぎると硬化が進みすぎて盛りにくい。適切なタイミングで充填することで、窩縁までしっかり行き渡りながら表面は滑沢に仕上げることができる。最後に周囲に余剰が残っていれば除去し、患者が違和感無く過ごせる状態に整える。
即重レジンのワークフロー
仮歯の作製法はいくつかあるが、一般的なのは事前に採得した印象を利用する間接法である。補綴物の作製前にあらかじめ患者の歯列の印象(アルジネートなど)を取り、石膏模型やシリコンキーを用意しておく。支台歯形成後、その印象内の欠損部(形成歯に相当する部分)に即重レジンを適量盛り、口腔内に位置合わせして数十秒間あてがう。レジンが自己発熱し始めたら一度口腔内から除去し、印象から仮歯を外して手指で持ちながら硬化を待つ(直接口腔内で最後まで硬化させると発熱や収縮で支台歯に張り付いて外れなくなる恐れがあるため)。硬化が完了したら仮歯のバリを除去し、模型上や口腔内で適合を確認しつつ形態修正を行う。高すぎる隣接接触点や咬合接触を調整し、外観も可能な範囲で滑沢にトリミング・研磨する。必要に応じてレジンを追加重合して細部を補修することもできる(即重レジン同士は新旧でもある程度接着する)。最終的に完成した仮歯を支台歯に装着する際は、通常仮着用セメント(ノンユージノール系またはユージノール系のテンポラリーセメント)を用いる。仮歯内部に適量の仮着材を塗布し、所定の位置に押し込んで余剰セメントを除去すれば完成である。直後に強い咬合力をかけると仮着材が完全硬化する前に脱離することがあるため、数時間は硬い物を避けるよう患者に伝えると良い。なお直接法として、事前印象を取らずに透明なセルロイドクラウンフォームやシリコンキーを活用して仮歯を作る方法もある。この場合も支台歯にレジンがロックしないよう、あらかじめ支台歯表面にワセリンを塗布したり、硬化直前に一度外すステップは共通して必要である。仮歯は出来上がった後に形態調整・研磨を行う点で、仮封材のような「入れたら終わり」の処置とは異なる。そのため精度の高い仮歯を手早く作るには経験が物を言う。スタッフ間で効率的な手順を共有し、器具(小筆、バキューム成形したテンポラリーシェルなど)を工夫することで品質とスピードの両立が可能になる。
品質管理の要点
いずれの材料でも、目的を果たすための品質確保が重要である。デュラシールの場合、密閉性と適合性が品質の鍵となる。きちんと窩洞の隅々まで行き渡り、表面が滑らかであれば唾液漏洩や食片圧入を防げる。もし練和不良で硬化不良が起これば、ベタついて封鎖効果が損なわれるため注意する。また薄く延ばしすぎると弾力が落ちて途中でちぎれるように外れてしまうこともあるので、最低限2mm程度の厚みは確保する。即重レジンの場合、適合精度と強度バランスが品質を左右する。適合が悪いと仮歯が外れやすくなる上、歯肉に不適切な圧迫を与えて炎症や歯肉退縮を招くこともある。強すぎる隣接接触は装着時に支台歯に過大な力をかけ、痛みや歯の移動を引き起こす可能性がある。一方、接触が緩すぎると仮歯装着中に隣接歯が動いてしまい、本番の補綴物が入らなくなる恐れがあるため絶妙な調整が必要だ。咬合も高すぎれば痛みや破折につながり、低すぎれば対合歯の伸長を許す。仮歯は小さな補綴物と同じく精度が要求されることを念頭に、手早くとも手を抜かず調整すべきである。また仮歯表面の滑沢さも見逃せないポイントだ。粗造な表面は細菌プラークの温床となりやすく、仮歯装着期間中に歯肉炎を起こしたり口臭の原因となったりする。前述のように患者が仮歯のまま長期間過ごすケースも現実にあるため、可能な限り研磨し滑沢にしておくことが望ましい。
安全管理と患者説明の実務
一時的な処置とはいえ、仮封・仮歯にも安全管理上の留意点がある。まず、材料の刺激やアレルギーへの配慮である。デュラシールの液成分にはメチルメタクリレート単量体(MMA)など揮発性の強い成分が含まれるため、装着時にツンとした刺激臭を患者が感じることがある。実際「仮蓋から薬品のような味や匂いがする」と不安を訴える患者もいるが、硬化が進めば臭いは消えること、決して有害なものではないことを事前に説明して安心させると良い。もし装着後も刺激が強いようなら、一度取り外し水洗して付け直すといった対応も考えられる(通常は硬化すれば無臭無害となる)。また、稀にアクリルレジン系材料にアレルギーのある患者も存在する。この場合デュラシールや即重レジンの使用で接触皮膚炎や口内炎を起こす可能性があるため、患者のアレルギー歴は確認しておくことが望ましい。代替としてグラスアイオノマー系やシリコーン仮封材の検討もあり得る。
次に誤飲・誤嚥のリスクである。仮封材や仮歯はいずれも外れる可能性がゼロではなく、外れたものを患者が気づかず飲み込んでしまう事故が起こりうる。特に仮歯は歯冠の形をしているため誤飲サイズとしては大きめであり、最悪気道に入れば窒息の危険もある。従って仮歯の装着が不十分でぐらつきがあると判断した場合はその場で付け直し、安定するまで仮着材を追加するなどの処置をすべきである。患者にも「もし仮歯が取れたら飲み込まないよう口から出して保管し、早めに連絡をください」と伝えておく。仮封材に関しても、稀に外れて睡眠中に誤飲する可能性はあるため、「脱落したら舌で穴があいているのが分かるので、その際は無理に詰め直そうとせず連絡ください」と説明しておくと良い。また仮封中・仮歯装着中の生活上の注意は必ず指導する。デュラシールの場合は硬化直後の30分禁飲食は鉄則だ。それ以降も、非常に粘着力の強い食品(ガム、キャラメル)や歯に挟まるようなもの(お餅、トフィーなど)は避けてもらう。硬いナッツ類や氷を噛むような行為もしないように言い含める。仮歯の場合も、基本的に同様である。強い力が加われば仮着セメントごと外れるし、薄い部分は破折する可能性もある。また前歯部の仮歯では、りんごを丸かじりするなど前歯に大きな負荷がかかる動作は破損リスクが高いので控えるよう助言する。清掃指導も重要だ。仮封中の歯はデンタルフロスや歯間ブラシが通らないことが多いが、その間放置すると仮封周囲の歯肉が炎症を起こす場合がある(実際、2週間仮封部だけフロスせずにいた患者で軽度の出血性歯肉炎が起きた例がある)。可能なら仮封材装着後に隣接部を研磨してフロスが通るようにしておくか、困難であれば仮封期間をできるだけ短く設定することが望ましい。仮歯では通常フロスが通るが、力任せに通すと仮歯を外してしまうため、「フロスは一旦通したら横からスッと引き抜いて下さい」と具体的に指導する。これら注意事項は口頭だけでなくカードや紙に書いて渡すと、患者の遵守率が上がりトラブル予防につながる。
最後に万一トラブルが起きた場合の対応も心得ておく。仮封が外れた、仮歯が取れた・割れたといった際には、患者から連絡があればできるだけ早急に対応するのが基本である。痛みや不快症状が出ていれば応急処置として再仮封・再装着を行い、必要なら鎮痛剤の処方も検討する。仮歯が外れて支台歯がしみる場合、仮着材に残ったオイル成分を洗浄除去し、新しい仮着材でつけ直すだけで症状が治まることが多い。逆に仮封が取れて放置されたケースでは、唾液汚染で暫間的に貼薬していた薬剤が流出したり、最悪の場合治療中の歯が再感染して痛みが増す可能性もある。そうなる前に早めに処置し直すことが肝要だ。また、仮歯が外れないケースも問題となる。仮着材が想定以上に強固に固まったり、仮歯の形態が隣在歯に深く引っかかって抜去できなくなると、本番の補綴物装着前に除去するのが難渋する。こうした場合には無理に引き剥がそうとせず、タービンで仮歯を分割切除するのが安全である。特にレジンコーティングをした支台歯に仮歯を長期間つけていた場合、接着界面が強固になっていることがあるため注意が必要だ。除去の際に支台歯表面を傷つけないようダイヤモンドポイントの選択や切削方向にも配慮し、必要に応じてマトリックスバンドなどで歯肉をガードすると良い。仮の処置とはいえ、その後の本処置にスムーズに移行するために安全最優先で管理することが大切である。
費用対効果と導入判断のポイント
デュラシールと即重レジンに関する費用と収益構造は、冒頭で触れたとおり基本的に保険診療内では包括されている。したがって、これら材料を使用したからといって直接収益が上がるわけではない。しかし間接的な費用対効果は無視できない。正しい材料選択によって再治療や時間ロスを防げること自体が、医院経営に貢献する面である。仮封が甘く二次カリエスが生じて補綴がやり直しになれば利益どころか赤字になりうるし、仮歯が外れて患者が何度も来院すれば他の有償処置の時間が削られてしまう。そう考えると、数十分かけて質の高い仮歯を提供し患者の不安とトラブルの種を除いておくことは、長期的に見ればROI(投資対効果)の高い行為と言えよう。
設備投資のように大きな判断を要するテーマではないものの、院長が現場で迷わないための判断基準を持っておくことも重要だ。簡単なロードマップとしては、まずケースの種類と期間で材料を選別することが第一段階である。補綴修復の種類(インレーかクラウンか、前歯か臼歯か、自費か保険か)や次回セットまでの期間によって、大まかにデュラシールか仮歯かの方向性が決まる。次に歯の状態を見る。生活歯で象牙質が露出しているなら遮断性の高い材料で密封する必要があり、場合によっては仮封の下に象牙質の細菌漏洩を防ぐライナーやベースを併用する。無髄歯であれば多少仮封が取れてもしみることはないが、だからといって粗雑にして良いわけではなく、やはり感染予防のため密閉は必要である。力のコントロールも判断材料だ。噛み合わせの力が強い患者や、欠損部位が咬合に大きく関与する場合(たとえば大臼歯部全部被覆)には、デュラシール単独ではもたない可能性が高い。仮歯+強固な仮着材で固定し、それでも食いしばりがあるならナイトガードを併用するなどの対策も考慮する。逆にご高齢で軟食中心の患者なら、簡易な仮封でも意外と問題なく過ごせることもあるので、患者の習癖や全身状態も踏まえる。近隣の歯科技工所やコラボレーションも判断に入れてよい。もし院内で十分な仮歯を提供できない事情(人手不足・技術不足)があるなら、技工所に短期で仮歯製作を依頼することも可能だ。最近は即日で高精度な仮歯を作ってくれるラボや、CAD/CAMで仮歯を設計・切削するシステムも存在する。費用はかかるが、患者満足とのバランスで検討する価値はある。最後に患者への説明だ。どちらの方法を取るにせよ、その理由とメリット・デメリットを患者に理解してもらうことが望ましい。奥歯の場合には「見た目よりもしみないことが大事である」旨を伝えて仮封処置の意図を説明し、前歯では「審美性にも配慮して仮歯を作製する」方針を示すなど、適切に説明すれば多くの患者は安心して協力してくれる。仮封のみで審美性に不安を抱く患者には、それがあくまで簡易な仮蓋であり次回には本物の補綴物が入る予定であることを説明し安心してもらう。仮歯の作製に時間がかかる場合も、現在精密な仮歯を作製している旨を伝え、患者にその価値を理解して待ってもらうよう努める。こうしたコミュニケーションも含め、材料選択と提供のプロセス全体が医院のサービス品質と捉えて判断・実施していくと良いだろう。
参考情報・出典
- 歯科オンライン1D記事「デュラシールとは?目的や仕組みを解説」(2022年8月13日) – デュラシールの用途と硬化機序、患者注意事項について解説
- Yahoo知恵袋「ユニファストとデュラシールの違い」ベストアンサー (2010年1月) – 両者の硬化後の弾性差と用途上の使い分けに関する現場回答
- 歯科助手向け記事「Tek(仮歯)とは?デュラシールやキャビトンとの違い」Wovie (2023年) – 仮歯と仮封材の使い分けやハードレジン/即重レジンの説明
- いけだ歯科 公式ブログ「仮封いろいろ」(2024年9月) – 仮封材・仮歯の種類と特徴、患者への説明事項についての歯科医院からの発信
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使うデュラシールと即時重合レジン(即重)の違いとは?