- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う「仮着材」とは?商品名の種類や特徴、成分を徹底比較
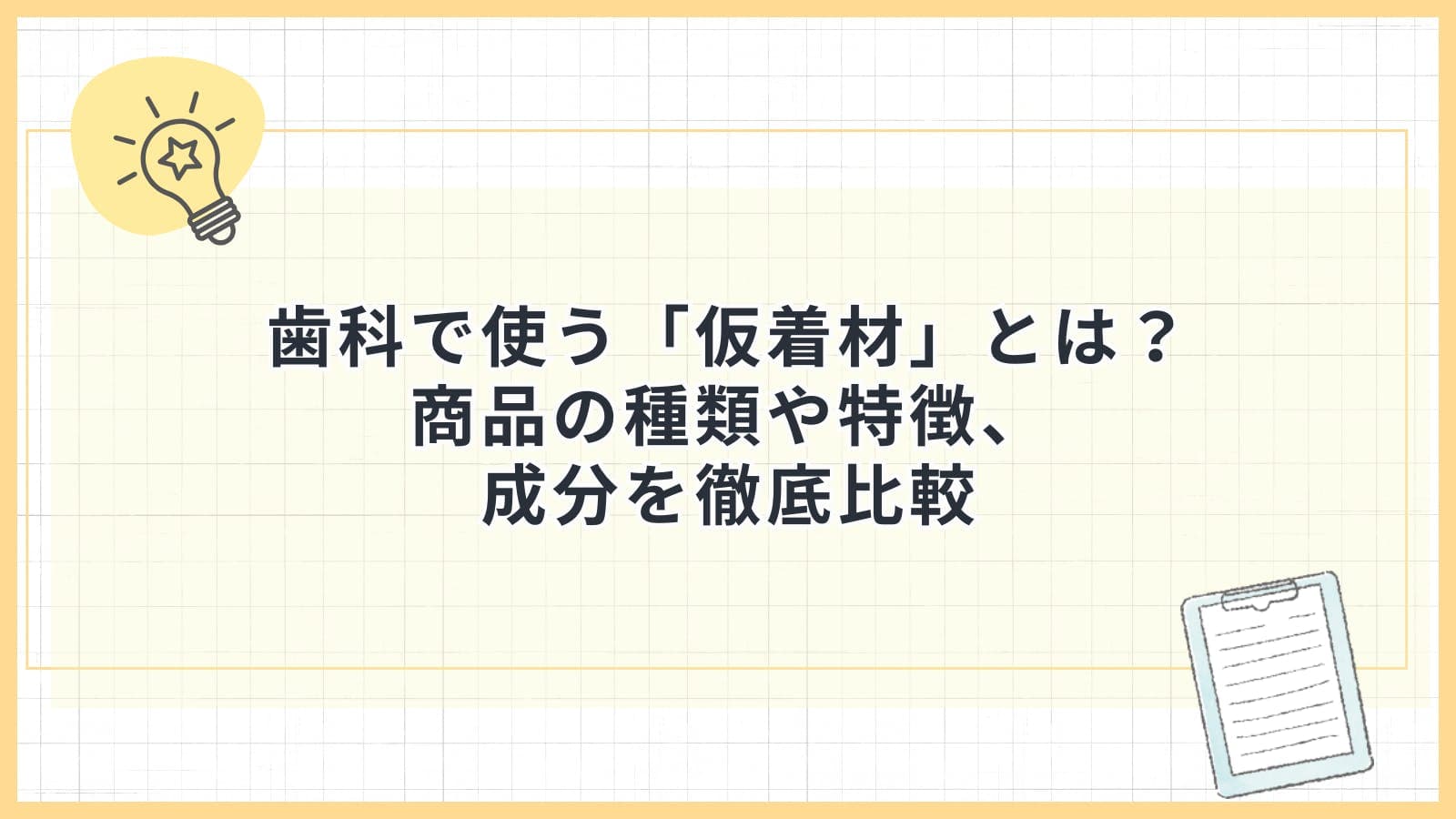
歯科で使う「仮着材」とは?商品名の種類や特徴、成分を徹底比較
歯冠補綴物の仮付けで悩んだ経験はないだろうか。例えば、暫間クラウンを仮着材で装着した直後に簡単に外れてしまい、再装着に追われたことはないだろうか。あるいは逆に、仮着した補綴物が外れず除去に苦労し、本番のセメント接着に支障をきたしそうになったケースも思い当たるかもしれない。仮着材選びは地味ながら臨床の成否を左右する重要な要素である。
仮着材とは、その名の通り補綴物を一時的に装着するためのセメントである。補綴物の適合や咬合を確認する試適期間や、根管治療中・治癒待ちの間に暫間クラウンを固定する際に用いる。短期間だけ固定でき、外すときは容易に除去できることが求められるが、一方で外れるべき時まで勝手に脱離しない充分な保持力も必要だ。このバランスを実現するため、歯科用仮着材にはさまざまな材料系統が存在し、それぞれ臨床的なメリット・デメリットがある。
本記事では、臨床経験豊富な歯科医の視点から主要な仮着材の種類と製品を比較し、その臨床的ヒントと医院経営の観点を整理する。仮着材ごとの物性や操作性の違いを分析し、「なぜその差が生まれるのか」「それが臨床結果と医院収益にどう影響するのか」を掘り下げる。読者自身の診療スタイルに合った最適な仮着材を見極め、患者満足度と投資対効果(ROI)の両立を図る一助となれば幸いである。
比較サマリー表(主要仮着材の早見表)
| 製品名(メーカー) | 主な系統・成分 | ユージノールの有無 | 硬化方式 | 標準的な仮着期間の目安 | 特徴(臨床面) | 特徴(経営面) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイ-ボンド テンポラリーセメント ソフト(松風) | ポリカルボキシレート系(粉液) | 含まない(非ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 〜1週間程度(短期仮着向け) | 軟質で取り外しやすく、裏層・仮封にも利用可 | 低コスト/汎用性◎(1症例あたり数十円程度)粉液手混ぜで手間だが一箱で長期間使用可能 |
| ハイ-ボンド テンポラリーセメント ハード(松風) | ポリカルボキシレート系(粉液) | 含まない(非ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 〜3週間程度(長期仮着対応) | 硬質で高い保持力を発揮。脱離しやすい症例に適する | 低コスト/汎用性◎(ソフト同様)仮着安定により再装着の手間削減 |
| 松風ハイ-ユージノールセメント(松風) | 酸化亜鉛ユージノール系(粉液) | 含む(ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 1〜2週間程度(短期仮着向け) | 鎮痛・消炎効果あり。封鎖性良好だが樹脂硬化阻害に注意 | 低コスト(粉液)歯髄保護効果で患者の不快感軽減、緊急時の応用範囲広い |
| IPテンプセメント(松風) | S-PRG配合セメント(粉液) | 含まない(非ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 〜数ヶ月も可(インプラント暫間など) | 薄膜(約10µm)で高い密着性。水洗で除去可能。インプラント仮歯用に開発 | コスト中(特殊粉液)長期安定により再装着回数を減らし、患者来院回数削減 |
| フリージノール テンポラリーパック(GC) | 酸化亜鉛非ユージノール系(粉液) | 含まない(非ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 〜2週間程度(中期仮着向け) | ユージノール無配合でレジンに優しい。適度な硬さで扱いやすい | 低コスト(粉液)ユージノールアレルギー患者にも使用可。将来の接着トラブル低減 |
| フジTEMP(GC) | グラスアイオノマー系(ペースト) | 含まない(非ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 〜1ヶ月以上(長期仮着対応) | 薄膜(約6µm)で長期仮着でも変色少。フッ素徐放で歯質を保護 | 中コスト(ペーストカプセル)長期症例での再治療リスク軽減。要カプセルミキサー |
| テンプボンドNE(Kerr/Envista) | 酸化亜鉛非ユージノール系(ペースト2材) | 含まない(非ユージノール系) | 化学硬化(常温重合)※自動練和可 | 〜2週間程度(汎用仮着) | 世界的定番ノンユージノール。オートミックスで均一混和 | 中コスト(ペースト式)混和時間短縮で効率アップ。訪問診療でも手早く使用可 |
| テンプボンド(ユージノール)(Kerr/Envista) | 酸化亜鉛ユージノール系(ペースト2材) | 含む(ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 〜2週間程度(汎用仮着) | 古典的ZOEセメント。信頼性高いがレジン硬化阻害あり | 中コスト(ペースト式)鎮静効果で患者の疼痛減少。最終接着にレジン使わない場合に安心 |
| リライエックス テンプNE(3M) | 酸化亜鉛非ユージノール系(ペースト2材) | 含まない(非ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 〜2週間程度(汎用仮着) | 3Mのノンユージノール製品。滑沢なペーストで練和しやすい | 中コスト(ペースト式)大手ブランドの信頼性。多院経営でも統一しやすい |
| ネオダインα・Tシリーズ(ネオ製薬) | 酸化亜鉛ユージノール系(粉液 等) | 含む(ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 〜1週間程度(短期仮着) | 古くからのロングセラー。硬さ調整可能で封鎖性良好 | 低コスト(粉液)長年の臨床実績で安心感。使い慣れた医師多数 |
| テンポリンク クリアー(デタックス) | レジン系デュアルキュア(ペースト) | 含まない(非ユージノール系) | デュアル硬化(光+常温) | 〜数週間(審美仮着向け) | 無色透明の仮着材。光照射併用で硬化時間調整可 | 高コスト(自動練和)審美症例での満足度向上。材料費増も自費治療の価値アップに寄与 |
| インプラントリンク セミ(デタックス) | レジン系セメント(ペースト) | 含まない(非ユージノール系) | 化学硬化(常温重合) | 長期留置可(半永久固定も可) | 非常に高い保持力。定期メンテ時に除去可能な半永久的接着 | 高コスト(特殊レジン)インプラント補綴の維持管理に有用。再来院リスク低減 |
※上記は各メーカーの公表値や標準的な使われ方に基づく比較である。実際の操作条件や症例によって性能は変動するため、あくまで目安として参照されたい。
仮着材を比較するためのポイント
仮着材にはユージノール系と非ユージノール系、さらにはレジン系やグラスアイオノマー系など複数の種類があり、それぞれ物性や操作感が異なる。ここでは臨床と経営の両面から、仮着材選択時に考慮すべき主要な比較ポイントを解説する。
材質による保持力と歯への優しさ
まず注目すべきは材質ごとの保持力(仮着力)と歯質・歯髄への影響である。古典的なユージノール系仮着材(酸化亜鉛ユージノールセメント)は、適度な強度で暫間固定に十分な保持力を示しつつ、ユージノールによる鎮痛・鎮静効果で象牙質を保護する利点がある。ただし硬化後は脆性が高く、長期間の使用には向かない。またユージノールの存在がレジン系接着の重合反応を阻害する点にも留意が必要だ。一方、非ユージノール系仮着材はユージノールを含まないため、レジン系最終接着の邪魔をしない。このタイプには酸化亜鉛をベースに脂肪酸誘導体を液としたもの(例:フリージノール)や、ポリカルボン酸亜鉛系(例:松風ハイボンドソフト/ハード)のように歯質に対する化学的接着性を持つものも含まれる。一般に非ユージノール系はユージノール系より硬化後の強度がやや高めで、長めの仮着期間にも耐えるものが多い。例えばグラスアイオノマー系のフジTEMPは3週間以上の長期仮着でも保持力が持続する。一方でユージノールによる鎮静効果が無い分、深い象牙質に対しては防御が弱くなる点も考慮する必要がある。症例によって「歯髄の敏感さを抑えるか」「レジン接着への影響を避けるか」の判断が求められる。
また、レジン系仮着材(コンポジットレジンセメントを一時固定用に調整したもの)は最も高い保持力を示す。デュアルキュアタイプでは必要に応じ光照射で一部硬化させ、残留セメントをゴム状のうちに除去するテクニックも使える。レジン系は長期安定性が高く、インプラントの上部構造を半永久的に装着する用途(例:デタックス社インプラントリンク セミ)にも用いられる。ただし歯質接着力もあるため、支台歯からの除去時に大きな力を要する場合があり、天然歯の仮着には慎重な適応判断が必要である。
仮着時の操作性と除去の容易さ
仮着材選択では操作性と撤去時の容易さも重要な軸である。粉と液を練る従来型のセメントは、自院のスタッフが混練に熟達していれば問題ないが、混ぜ加減によって粘度や硬化時間が微妙に変化することがある。適切な練和比を保つことが肝要だ。ペーストタイプの2剤を等量混和するタイプ(例:テンプボンド)は、一定の練和比で比較的安定した粘調度が得られるため扱いやすい。さらに近年はシリンジ式のオートミックス製品(例:テンプボンドNEオートミックス)が登場し、ボタン一つで適量のペーストが自動混和されるためヒューマンエラーが減少する。特に訪問診療や人手の少ない場面でも片手で素早く操作できるメリットがあり、院内のワークフロー効率向上に貢献する。ただしオートミックスは専用チップを都度消費するため廃棄コストも発生する点に注意が必要だ。
一方、除去のしやすさは患者の負担と治療効率に直結する。軟質系の仮着材(例:松風ハイボンドソフト)は硬化後もやや弾性を保ち、探針やエキスカベーターで一塊に剥離させやすい。これは仮着物除去時のチェアタイム短縮につながる。逆に硬質な仮着材(例:ポリカルボキシレート系ハードやレジン系)は細片に割れて残留しやすいため、除去残渣の清掃に時間を要する場合がある。残ったセメントは歯肉炎や二次齲蝕の原因にもなりかねないため、レントゲン造影性のある材料(例:IPテンプセメントやフジTEMPなど)であれば術後のX線チェックで見逃しを防止できる。臨床現場では「必要十分な保持力」と「容易な撤去性」はトレードオフになることが多く、症例に応じてバランスを見極めることが重要である。例えば「すぐ外れるのは困るが、次回外せないともっと困る」という単純な真理を念頭に、必要以上に強力すぎない材質を選ぶことが無難だ。また、仮着前に支台歯や補綴物内面にセパレーター(隔離材)を塗布して保持力を調節する方法も実践されている。ワセリンの塗布が古典的手法だが、市販のウォッシャブルセップ(サンメディカル)のように水で洗い流せる隔離材を使えば、仮着力を落としすぎずに除去時だけ接着を弱めることも可能である。
審美性と応用範囲
仮着材は通常白色や淡黄色のペーストだが、審美症例では色調の影響も無視できないポイントとなる。前歯部のオールセラミックスクラウンやラミネートベニアでは、仮着期間中であっても透明感や色調が患者の目に触れる。従来の酸化亜鉛系セメントは不透明な白色のため、審美仮歯に用いると補綴物の色を一時的に変えてしまう恐れがある。こうした問題に応えるため登場したのが透明なレジン系仮着材である。デタックス社のテンポリンク クリアーは代表例で、硬化後に無色透明のフィルム状になるため、下層からの光の透過や色調の乱れがほとんどない。審美歯科において患者に暫間修復の段階から満足感を与えられるため、自費治療のクオリティ向上に直結するだろう。
また、仮着材の応用範囲も考慮したい。多くの仮着材は仮封材(テンポラリーの充填材)としても併用可能である。例えば松風ハイボンドソフト/ハードやハイ-ユージノールセメントは、エンド治療中の仮封や、窩洞の一時的な裏層(ライナー)としても利用できる。ひとつの製品で複数の用途を賄えることは在庫管理の簡素化につながり、小規模医院ではコスト削減とスタッフ習熟のメリットが大きい。一方で、インプラント治療を多く手掛ける医院であれば、インプラント専用の仮着材の有無もポイントになる。例えば松風のIPテンプセメントはインプラントの暫間補綴に特化して開発されており、硬化プロセスにおいて任意のタイミングで補綴物を圧接しても一定の薄い被膜厚さ(約10μm)に収まるという特徴がある。これはインプラントアバットメントと上部構造の間に過厚のセメント層が介在せず、安定した適合を得やすいことを意味する。また硬化後でも水を噴射するとセメント層が容易に崩壊・洗い流しできる設計となっており、スクリュー固定式のインプラント仮歯でも後日清掃や撤去がスムーズに行えるよう配慮されている。このように診療の専門性に応じた仮着材を選べば、自院の強みを最大限に活かした効率的かつ安全な診療を提供できる。
コストと経営効率
最後に、医院経営の視点からコストパフォーマンスを考察する。仮着材は一症例あたり数十円〜数百円程度の材料費であり、歯科医院全体の経費から見れば微々たるものに思えるかもしれない。しかし、その間接的な影響を見逃してはならない。まず、安価な粉液タイプの仮着材(例:伝統的なZOE系やポリカルボキシレート系)は、一瓶数千円程度で数十〜百症例分以上に対応できるため単価は極めて低い。経営上は在庫費用を抑えられる利点がある。ただし手混ぜに時間がかかり硬化もゆっくりなものが多いため、チェアタイムの効率という点ではやや不利だ。特に保険診療中心で短時間に多くの患者を回転させたいクリニックでは、毎回の練和に数分取られることが積み重なると無視できない時間損失となる。
一方、オートミックス式やデュアルキュアレジン式の仮着材は、1キットあたりの価格が高め(数千〜1万円以上)であり、使い切りのチップも消耗品コストとなる。しかし混和ミスによるやり直しが減り、確実に時短できる点を考慮すれば、トータルでのROI(投資対効果)は必ずしも低くない。例えば仮着のたびに毎回2分短縮できれば、1日20件の補綴を行う医院では40分の節約である。節約した時間で追加の診療をこなせれば収益拡大につながるし、スタッフの負担軽減でミス防止や離職防止にも寄与するだろう。また、患者側から見ても待ち時間や無駄な来院が減るメリットは大きい。仮着のやり直しが発生すればその都度患者の不信感や不満足にも直結し、医院の評判低下や機会損失を招きうる。逆に、適切な仮着材選択で暫間期間をトラブルなく乗り切れれば、患者の治療満足度が上がり紹介やリピートにもつながる。特に自費治療の高額症例では、仮歯段階の快適さもサービスの一部と言える。高価な仮着材であっても、それが患者満足を高め最終補綴物の受注や継続通院を確保できるのであれば、経営的には十分に元が取れる投資となる。
主な歯科用仮着材の製品別レビュー
ここからは、日本国内で入手可能な代表的仮着材について、臨床的特徴と経営的視点を織り交ぜながら一つずつ解説する。各製品の強み・弱みを踏まえ、どういった診療スタイルの歯科医師に適しているかを考察する。
ハイ-ボンド テンポラリーセメント ソフト/短期間の仮着と汎用性に優れた軟質タイプ
松風の「ハイ-ボンド テンポラリーセメント ソフト」は、1週間程度までの短期仮着に適した粉液タイプの仮着材である。主成分は酸化亜鉛とポリカルボン酸系の液体で、硬化するとポリカルボキシレートセメントに分類される。硬化物はやや弾性を持つ軟質で、細かく砕けずに一塊で剥がれやすいのが特徴だ。そのため仮着物撤去の際に支台歯や歯肉を傷つけにくく、安全に除去できる。適度な軟らかさは封鎖性にも寄与し、歯内療法中の仮封材や、修復物下の裏層(一時的なライナー)としても利用可能である。実際、本製品は用途欄に「仮着・仮封・裏装」と明記されており、一つ備えておけば応用範囲の広い万能選手と言える。
一方、保持力は長期には向かないよう調整されている。数日の試適期間では十分だが、2週間以上放置すると唾液中で次第に軟化・溶解し、補綴物のゆるみや脱離につながりうる。そのため長期症例には後述のハードタイプへの切り替えが推奨される。また粉と液の手混ぜであるため、忙しい診療中に適量計測・練和する手間はある。とはいえ大きなスパチュラで練る必要があるリン酸亜鉛セメント等と異なり、小さな付属スパチュラで少量を練れるので廃棄ロスは少ない。価格も1セット(粉125g・液60mL)で数百回分に相当し経済的である。保険診療主体でコストを抑えつつ効率良く回したい開業医にとって、ソフトタイプは仮着材の基本アイテムとして信頼できる存在だ。もし仮歯が外れやすい場合でも、本製品ならすぐ気付いて対処しやすく、患者が気付かぬうちに飲み込んでしまうリスクも低減できる。総じて「必要最低限の保持力で安全に外せること」を重視する歯科医師にマッチした仮着材である。
ハイ-ボンド テンポラリーセメント ハード/長期仮着に対応する高強度タイプ
同じ松風の「ハイ-ボンド テンポラリーセメント ハード」は、上記ソフトの姉妹品でより硬化後の強度・硬さを高めたタイプである。粉液の組成はソフト同様にポリカルボキシレート系だが、硬化物は硬質で耐久性に優れ、最大3週間程度の長期仮着にも耐えるよう調整されている。補綴物の維持が難しい症例(例えば支台歯が短い、テーパーがきついなど)の仮着でも脱離を起こしにくく、強い咬合力がかかる臼歯部ブリッジ等にも安心して使用できる。
ハードタイプのメリットは、その名の通り仮着中の安定性である。患者が硬い物をうっかり噛んでも外れにくく、仮歯が取れたことで来院を余儀なくされる緊急対応の頻度を減らせる。これは患者満足のみならず、医院側のアポイント枠の圧迫軽減にも繋がる重要な利点だ。特に自費診療で長めのプロビジョナル期間を設定するケースでは、ハードタイプでしっかり固定しておくことで最終補綴までの経過がスムーズになる。一方でデメリットとして、硬化物がソフトよりも歯面に残留しやすい点が挙げられる。除去時には薄いスケーラーや超音波スケーラーで丁寧に清掃しないと細片が残る可能性がある。支台歯表面に薄く皮膜が残ったままだと、後の本接着に影響を及ぼす恐れがあるため、除去後の清掃ステップに時間を確保することが望ましい。また、ソフトに比べれば歯髄への優しさ(軟化による衝撃吸収)は劣るため、深いう蝕を伴う場合には仮封材やライナーでの歯髄保護を併用すると安心だ。
経営的観点では、ハードとソフトで価格はほぼ同等なので、用途に合わせて両方を備えておく戦略が有効である。実際に両者をミックスして中間的な硬さで使う熟練歯科医も存在するが、薬機法上は混合変調は推奨されないため自己責任となる。安全策として、普段はソフトで対処しつつ脱離リスク例にハードを使い分けるのが合理的だろう。「ハード=強力で安心」というイメージから全例ハードを使いたくなるかもしれないが、何度も述べたように強すぎる仮着は諸刃の剣である。「仮歯の頻繁な脱離で患者に迷惑を掛けたくない」という先生にはハードタイプが心強い味方になるが、一方で「最終装着前には確実に外したい」という当然の目的を忘れず、過信せずに使うことが肝要である。
松風ハイ-ユージノールセメント/歯髄鎮静効果を備えた伝統的仮着材
「松風ハイ-ユージノールセメント」は、その名の通りユージノール(Eugenol)を含有した古典的仮着用セメントである。酸化亜鉛とユージノール液を主成分とする粉液タイプで、歯科領域で長年用いられてきたZOE(酸化亜鉛ユージノール)系セメントを改良した製品だ。ユージノールには鎮痛・鎮静作用があり、本製品でも知覚過敏の緩和や歯髄鎮静が期待できる。う蝕処置後で象牙質が露出した支台歯に仮歯を装着する際など、患者がしみる痛みを訴えそうなケースでは、このユージノール系仮着材が歯髄を落ち着かせてくれる。
本製品のもう一つの特徴は優れた封鎖性である。ペースト状に練和した際の流動性は高すぎず低すぎず、マージン部にしっかり留まる粘度を持つ。硬化後は軟らかめで、辺縁からの微漏洩を防ぎつつ適度に圧力緩衝材の役割も果たす。エンド治療中の仮封材として用いても歯髄鎮静と封鎖を両立できるため、根管充填までの間に細菌侵入を防ぎつつ痛みを抑える効果がある。ただし強度はそれほど高くなく、使用期間の目安は1〜2週間程度に留めるべきである。長期間経過すると徐々に崩壊し、唾液中で溶け出す特性がZOE系にはある。そのため仮着期間が延びる場合や、強固な保持が必要な場合には非ユージノール系への切り替えを検討すべきである。
ユージノール系最大の留意点として、レジン系接着材料への悪影響が挙げられる。ユージノールはレジンの重合を阻害するため、将来的にオールセラミックスクラウンをレジンセメントで装着しようと考えている場合、本製品の使用は避けるか、使った場合でも十分な清掃と時間経過を置く必要がある(ユージノール残留は数日で自然失活するとも言われる)。実際の臨床では「最終補綴にレジンセメントを使わない、もしくは仮着後に一度仮封などで歯面調整期間を設ける」という条件下で本製品を使うのが安全策だ。例えば金属製クラウンをリン酸亜鉛セメントで装着予定の場合や、仮着後にコア築造等を行うため一旦補綴物を外すが接着はさらに後日…というシナリオでは、ユージノール系の恩恵を活かせる。
コスト面では粉液セットで数千円程度と廉価である。松風ハイ-ユージノールは包装容量がやや少なめ(粉40g+液15g)で提供され、頻繁に大量使用するにはやや物足りないかもしれない。しかし「ここぞ」という場面で歯髄保護目的に使うサブ的な位置付けと考えれば、1セット在庫しておく価値は十分ある。特に「支台歯削合後の疼痛トラブルを避けたい」と考える慎重派の先生には心強いアイテムだ。また開業直後で患者獲得に苦心する時期には、仮歯期間中の快適さが患者の安心感につながる。ユージノールの芳香は独特だが患者によっては「歯医者さんの薬の匂い」として安心感を覚えるという声もある。古き良き仮着材として、最新材料にないヒューマンタッチなメリットを提供できる点も見逃せない。
IPテンプセメント/インプラント暫間補綴に特化した高機能仮着材
松風の「IPテンプセメント」は、インプラント・プロビジョナルクラウン(IP:Implant Provisional)用に開発された特殊な仮着材である。粉液タイプだが、独自開発のS-PRGフィラー(表面反応型ガラスイオンomerフィラー)を配合していることが大きな特徴となっている。S-PRGフィラーはフッ素やストロンチウムなど複数の有用イオンを徐放・リチャージ可能な松風独自のフィラー技術で、本製品にもその恩恵が活かされている。すなわち仮着中も継続的にフッ素イオンを放出して支台歯や周囲組織をケアできるのだ。インプラントの場合支台歯(アバットメント)は金属やジルコニアで虫歯にはならないが、隣接天然歯や仮着材周囲の歯肉の健康維持にはプラスに働く。またS-PRGフィラー由来でX線造影性も付与されており、インプラント周囲に残存した仮着材もレントゲンで容易に確認できる。
臨床操作面でもIPテンプセメントは工夫が凝らされている。特筆すべきは、被膜厚さがわずか10µmと極薄で一定に保てる点である。通常、仮着材を塗布して補綴物を圧接する際、圧接のタイミングや力加減でセメント層の厚みが変わり、適合精度に影響することがある。しかし本製品では「硬化が始まるまでどのタイミングで圧接しても一定の被膜厚さが得られる」とされ、臨床家のテクニックによらず安定した適合を実現しやすい。これはインプラント上部構造のみならず、精密な適合が要求される支台歯の仮歯でも有用な特性だ。また硬化後は水で洗浄すると除去可能というユニークな性質を持つ。具体的には、仮着した補綴物を外した後に支台歯上のセメント残渣に水をスプレーし数十秒待つと、セメントが軟化・崩壊してブラシ等で洗い流せる。インプラントのアバットメントは軟組織が緊密に取り囲んでおり、メスシンや超音波チップでの機械的清掃が難しい局面もあるが、水洗除去可能ならデリケートなインプラント周囲組織を傷つけずに済む。これはメインテナンス性の観点からも優れた点と言える。
高機能ゆえに価格は従来品より高めだが、1セットで粉45g・液26mLと十分な量があり、インプラント症例のたびに惜しみなく使える。インプラント補綴を数多く手掛けるクリニックでは、トラブル予防と効率アップの両面でコスト以上のリターンが期待できるだろう。例えば仮歯脱離によるアバットメント露出はインプラント周囲炎のリスクにもなるが、本製品の確実な保持力でそうした事故を防げる。また仮着材残りによる歯肉の炎症や黒ずみが起きにくければ、最終補綴装着時の見た目や治癒も良好となり、患者満足度が高まる。総合すると、IPテンプセメントは「インプラント治療の質にとことんこだわりたい」歯科医師に刺さる製品である。逆に言えば通常の支台歯への仮着にはオーバースペック気味なので、費用対効果を考えて適材適所で使い分けるのが望ましい。
フリージノール テンポラリーパック/樹脂への影響を排除したノンユージノールセメント
GCのフリージノール テンポラリーパック(Freegenol Temporary Pack)は、伝統的なユージノール仮着材の欠点を克服すべく開発された酸化亜鉛非ユージノール系セメントである。名称が示す通り「Freegenol=フリー(ユージノールが無い)」であり、液成分にクローブ油の代替として脂肪酸エステル系の油剤を用いている。これによりレジン材料の硬化阻害や一部患者に見られるユージノールアレルギーの問題を回避している。粉は酸化亜鉛を主体とし、ユージノール系と同様に混練して用いる粉液タイプだ。
臨床的な使い心地は、古典的ユージノールセメントに非常に近い。練和直後は適度な粘性があり、補綴物内面に塗布しやすい。硬化時間も数分程度で扱いやすく、硬化後の硬さ・脆さもZOEとほぼ同等に調整されている。つまり「ユージノール抜きのユージノールセメント」と言える存在で、初めて使う際も違和感なく移行できるだろう。実際、多くのメーカーがこの種のノンユージノールZOE代替品を販売しており、フリージノールはその草分け的な製品だ。仮着期間の目安は1〜2週間程度で、定期チェックや最終補綴までの短いインターバルに適する。力学的保持力は極端に高くはないが、ユージノール系よりわずかに硬く崩れにくい印象があり、仮歯が外れやすい場合の保険的措置としても有用だ。
経営面で注目すべきは、ユージノールの弊害を除去したことによるトラブル低減である。例えば、仮着後に最終補綴をレジンセメントで装着した際、残存ユージノールが原因で接着不良・脱離が起きてしまえば、再製作やクレーム対応で大きなコストと信頼低下を招く。その点、フリージノールならそうしたリスクを初めから排除できる。また患者への説明の際も「こちらは新しいお薬で、将来の接着に影響しないものを使っています」と付加価値を伝えやすく、患者の安心感につながる。価格は粉液セットで比較的安価なので、「ユージノールセメントの使い勝手は好きだが、時代に合わせてアップデートしたい」という歯科医師に最適な選択肢だ。特に最近はセラミック修復の台頭でレジン接着が主流となっており、もはや仮着にユージノールを使わないのはスタンダードとも言える。フリージノールはその過渡期から現在に至るまで支持され続けるロングセラーのノンユージノール仮着材であり、今後もスタンダードとして診療を支えてくれるだろう。
フジTEMP/長期仮着にも安心なグラスアイオノマー系暫間セメント
GCのフジTEMPは、グラスアイオノマーセメント(GIC)の技術を応用して作られたグラスアイオノマー系仮着材である。他の多くの仮着材が酸化亜鉛を基材とするのに対し、フジTEMPはアルミノフルオロケイ酸ガラスとポリアクリル酸を主成分とする。要するに従来は合着用や充填用に使われてきたGICを一時固定用にチューンナップしたものだ。
フジTEMP最大の特徴は、長期安定性と歯質接着性のバランスが優れている点である。化学的にはグラスアイオノマーの酸塩基反応で硬化するため、硬化後は歯質に化学結合的に付着する傾向がある。そのため、他の仮着材では数週間以上で脱離リスクが高まるケースでも、フジTEMPなら3週間以上の仮着期間を安定して維持できるとされる。実際、メーカーの説明では「3週間以上の長期仮着でもフジTEMP自体が変色しにくく、仮着力も持続する」と謳われている。長期症例とは例えば、大幅な咬合再構成で暫間補綴のまま経過観察する場合や、難症例で治療方針検討のため仮歯のまま様子を見る期間が必要な場合などが該当する。こうしたケースでフジTEMPを用いれば、頻繁に仮歯が外れて患者を煩わせることなく、じっくり時間をかけた治療計画が実行できる。
一方、撤去時には多少のコツが要る。グラスアイオノマー系は硬化後にガラス成分が強固にマトリックスを形成するため、ZOEのようにサクサク崩れてはくれない。硬化物は薄いフィルム状に残留しやすいが、これは逆に言えば被膜厚さが非常に薄い(6µm程度)ことの裏返しでもある。補綴物適合への影響が極めて少ないというメリットと紙一重の関係だ。実際の除去では、フジTEMPはゴム状硬化期を見計らって除去するのがコツとなる。余剰セメントが完全硬化する前、指で触れてゴム弾性を示すタイミングで一気に剥ぎ取ると比較的きれいに取れる。逆に硬化完了まで放置するとカチカチに固まり、取り残しが出やすくなるため要注意だ。幸いX線造影性があり、取り残しはレントゲンでチェックしやすい。
経営面では、フジTEMPの活用で新たな自費メニュー創出につながる可能性もある。例えば「長期仮歯プラン」のように、インプラントや歯周治療後の安定待ち期間に特殊な長期仮歯を提供するサービスを考えたとき、通常の仮着材では不安だがフジTEMPなら安心という場合がある。患者にとっても「外れにくい仮歯で快適に過ごせる」とアピールできれば、追加費用を払う価値を感じてもらえるかもしれない。材料自体のコストは一般的なGICのペースト版として中程度だが、カプセル化されており専用ミキサーが必要な点には留意したい。既にGIC充填材などでカプセルミキサーを導入済みの医院なら問題ないが、そうでない場合は初期投資となる。ただしカプセル式は計量・練和の手間が省けミキシングも安定するため、スタッフの負担軽減とミス削減には寄与する。精密補綴や包括的治療に力を入れる歯科医院にとって、フジTEMPは患者ケアの質を底上げし得る一品であり、導入価値は高いと言える。
テンプボンドNE/世界中で使われる自動練和対応の定番ノンユージノール
「テンプボンドNE(テンポラリーセメント)」は、Kerr社(現在はエンビスタ社の一部)の代表的なノンユージノール仮着材である。テンプボンドシリーズ自体は古くからZOE系の代名詞的存在で、NEはそのNon-Eugenol版(ユージノール無し)として位置づけられる。2ペーストタイプで、ベースペーストと触媒ペーストを等量押し出して混和するだけで使用可能だ。特徴的なのはオートミックスシリンジのオプションが用意されている点で、専用カートリッジとミキシングチップを用いれば、手で練る必要すらなくなる。これは訪問診療やユニット外での処置にも適しており、往診先で仮歯が外れた際などにも素早く対処できる。
臨床性能としては保持力と除去性のバランスが優秀で、仮着材の国際標準とも言える存在だ。硬化時間は37℃で約4〜10分程度とされ、口腔内の環境によって多少変動するが概ね扱いやすい範囲である。硬化後の圧縮強さはおよそ35MPa以下に抑えられており、これはわざと恒久的接着には至らないよう低めに設定された値である。フィルム厚も25µm以下と薄く、精密な補綴物でも適合を損なわない。実際、多くの文献でテンプボンドNEは仮着材のリファレンスとして扱われており、その信頼性と安定性は折り紙付きだ。
経営的な観点でテンプボンドNEを捉えると、グローバルスタンダードを採用する安心感が挙げられる。これは特に分院展開している医療法人などで、どの院でも同じ材料・手順を共有したい場合に有用だ。テンプボンドNEなら新人歯科医やスタッフにも馴染みやすく、万一転院してきた患者が「前医でテンプボンドを使っていた」といった場合もスムーズに引き継げる。またオートミックス運用にすれば、練和ムラがなくなることで補綴物のフィット不良やクレームを防ぎ、結果として無駄な調整や再製作のコストを減らす効果が期待できる。もちろんオートミックスチップ代は上乗せになるが、1本のチップから複数歯分を同時に充填できるため実質的な無駄は少ない。例えばフルマウスのプロビジョナルを装着する際、チップ1本で連続的に各支台歯へ塗布でき、テンポライズの時短につながる。
総じてテンプボンドNEは、「迷ったらこれを使っておけば大きな失敗はない」という安定感が光る製品である。ユージノール系を使えない状況でも安心だし、実績豊富でエビデンスも多いので患者説明の裏付けにも困らない。強いて欠点を挙げれば、他社粉液に比べ材料コストがやや高めなことだが、その差額はオートミックスによる効率化やトラブル防止で十分回収できる範囲だろう。最新の設備や材料に積極的な開業医にとって、一歩進んだ標準的仮着材として導入する価値のある一品である。
テンプボンド(ユージノールタイプ)/信頼性の高いオーソドックスなZOE仮着剤
上述のテンプボンドNEと対になる製品が、従来型ユージノール配合の「テンプボンド」である。白と茶色の2ペーストを等量練り混ぜて使う点はNEと同様だが、こちらはユージノールを含むため正真正銘のZOE系仮着材となる。半世紀以上にわたり世界中で使用されてきたロングセラーであり、「テンプボンド」と言えば今でもまずこちらを指すことがあるほど歯科界に浸透した製品だ。
テンプボンド(ユージノールタイプ)の利点は、なんといってもその実績と安心感である。適度な粘度で流れすぎず、仮歯をセットしやすい。硬化後は脆く砕け、除去も比較的容易だ。歯髄鎮静効果も期待でき、深い支台歯でもしみにくい。まさに古典的仮着材の完成形とも言えるバランスの良さがある。高齢の開業医などでは「ずっとテンプボンド一択できた」という方もいるだろう。実際、この製品で大きな問題が起こることは稀で、適応症を守って使えば患者からも信頼を得られる品質を持っている。
しかし現代においては、ユージノール配合ゆえの制約もある。前述したようにレジン系セメントとの相性問題がその筆頭だ。コンポジットレジン接着全盛の昨今では、仮着材にユージノールを使うこと自体が忌避される傾向にある。テンプボンドを使用後にレジンセメントで装着する場合、メーカーも歯面に残留したテンプボンド成分を完全に除去すべきと注意喚起している。具体的にはアルコール綿球等で丁寧に拭い、場合によっては一日仮封期間を設けるなどの対策が取られる。またユージノールは軟組織には刺激となるため、歯肉に触れたまま長期間置くと発赤を招くことがある。こうしたマイナス面を考慮すると、「ユージノール系が必要な場面以外ではNE版を使う」という使い分けが賢明かもしれない。
経営面では、テンプボンド(ユージノール)はコストが比較的低く安定供給されている点で優秀だ。現在でも多くのディーラーで購入でき、一箱用意しておけばかなり長期間使えるだろう。練和もそれほどコツを要さず、歯科衛生士や助手でも扱いやすいのでスタッフ教育の負担も小さい。ただし、もし誤ってユージノール系を使ったせいで最終接着に失敗したような場合、そのフォローにかかるコストは計り知れない。クレーム対応や補綴物再作製になれば数万円〜十数万円の損失もあり得る。したがって、テンプボンド自体の信頼性は高いが時代の要請に合わない局面が増えたというのが正直なところである。まとめると、本製品は「メタルインレーやクラウンをリン酸亜鉛で装着するようなオールドスタイル症例」や「深い窩洞で歯髄鎮静を優先する症例」において真価を発揮する。一方、「オールセラミックスやCAD/CAM冠などレジン接着ありきの治療」を主に行う歯科医であれば、敢えて本製品を選ぶ必然性は薄れつつある。
リライエックス テンプNE/3Mが提供する信頼のノンユージノールセメント
3M社のリライエックス テンプNEも、テンプボンドNEと並ぶ代表的なノンユージノール仮着材である。3Mは歯科用セメント分野で数多くの製品を展開しており、永久固定用のレジンセメントから一時固定用まで幅広いラインナップを持つ。リライエックス テンプNEはその中でZOE系仮着材のユージノールフリー版として位置付けられる。海外では「RelyX Temp NE」として知られ、日本国内でも取り扱いがある。
製品特性としてはテンプボンドNEと大きく差はなく、等量混和のペーストで使いやすい。混和後のペーストはクリーミーで塗布しやすいと評判で、細部まで均一に行き渡るためマージン部の封鎖性も良好である。硬化時間や強度も同等レンジで、互換製品と言って差し支えない。ただ一部ユーザーからは「若干テクスチャーが滑らかで扱いやすい」という声もあり、好みの問題で使い分けているケースもあるようだ。
3M製品を選ぶメリットの一つに、トータルソリューションの一貫性がある。例えば3Mの接着システム(ボンディング材)や最終接着用セメントと組み合わせることで、メーカー推奨の手順を一貫して踏める安心感がある。仮着から本着まで同社製品で揃えることで相性問題の心配が少なく、何かトラブルが起きた際もメーカーサポートに相談しやすいだろう。特に大規模な歯科医院や大学病院では、複数メーカーの材をあれこれ使うより、信頼できるメーカーで標準化する方が管理しやすい面がある。3Mは世界的企業であり、材料の品質保証や入手性も申し分ないので、安心料として多少価格が高めでも導入する価値はある。
開業医の視点では、リライエックス テンプNEはテンプボンドNEと同様に安定したパフォーマンスを提供してくれる。価格帯も近く、どちらか安い方や入手しやすい方を使えば良いという先生も多いだろう。つまり性能面での優劣より、3M派かKerr派かといったブランド選好の問題に近いところもある。患者から見ればどちらを使っているかはわからない部分ではあるが、「うちは信頼の3M製を使用しています」と説明すれば、それだけで一種のブランド訴求にはなるかもしれない。実際、医療機関では材料の質にこだわっているとアピールすることが患者の安心感につながるケースもある。そうした意味で、品質イメージの良い3Mブランドを重視する医院にはマッチした仮着材と言えるだろう。
ネオダインα/ ネオダインTシリーズ/古くから親しまれる国産仮着セメント
国内メーカーであるネオ製薬工業のネオダインシリーズも忘れてはならない。ネオダインは、昭和の時代から歯科医院で広く使われてきた国産酸化亜鉛ユージノール系セメントで、その名は「NEOダイン」の通り新しい時代のZOEを謳って登場した。現在でも改良を重ねながら「ネオダインα」「ネオダインT」「ネオダインEZペースト」などのバリエーションが展開されている。
典型的なネオダインαは粉と液のセットで提供され、練和次第では仮着から仮封、覆髄まで幅広く応用可能な万能製剤として位置付けられている。実際、ネオダインは「酸化亜鉛ユージノールセメントの代名詞」と称されることもあり、歯髄鎮静・消毒効果と高い封鎖性で昔から定評がある。粉液比を加減することで硬化後の硬さや着脱のしやすさをコントロールでき、仮着専用の調整もしやすい。ネオダインTは特に仮着用途向けに調製されたタイプで、より着脱調整がしやすい性状となっている。またEZペーストはペースト状の練和済み製品で、手軽さを求めるユーザーに応える形だ。いずれにせよ、根本の薬効成分は同じであり、「歯に優しい仮封・仮着剤」として長らく臨床を支えてきた。
このシリーズのユーザー層は、比較的ベテランの開業医が多い傾向がある。新人時代からネオダインに馴染んだ歯科医師は、多少新素材が出ても使い慣れた感触を重視してネオダインを使い続けることが多い。実際、材料の手触りや匂い、硬化タイミングの感覚は慣れが物を言う部分であり、下手に冒険してミスするより慣れ親しんだ製品で安定した結果を出す方が理にかなっている場面もある。経営面でもネオダインは安価で入手しやすく、長年の信頼から来る安心感がある。例えばスタッフに仮封を任せる際、「とりあえずネオダインで蓋をしておいて」と指示すれば、ベテラン歯科助手ならすぐ対処できるといった暗黙知が共有されている場合も多い。これは一種の医院文化として根付いた製品と言える。
しかしながら、ユージノール系ゆえの制約はテンプボンド同様に存在する。時代の流れで非ユージノールやレジン系への切り替えが進む中、ネオダインも新製品として非ユージノールの「ネオダインEZペースト」などを投入して対応している。保険診療メインで金属補綴が中心の医院では依然として出番が多いが、審美補綴主体の医院では露出機会が減っているのも事実だ。とはいえネオダインシリーズは今なお国内16社以上が同種製品を供給するマーケットを形成しており、マーケットシェアは侮れない。「昔からの使い心地を大切にしつつ、必要に応じて新技術も取り入れる」という柔軟な歯科医師には、ユージノール系とノンユージノール系をラインナップするネオダインは使い勝手が良い。まさに保険診療の現場を支えてきた縁の下の力持ち的存在であり、今後も根強い支持が続くだろう。
テンポリンク クリアー/前歯部審美仮着に威力を発揮する透明レジンセメント
デタックス社(独)のテンポリンク クリアーは、完全硬化後に無色透明となるレジン系仮着セメントである。前述したように審美領域で仮着材の色が補綴物の見た目に影響を及ぼす問題に対し、明快なソリューションを提供する製品だ。4:1のデュアルキュアペースト(主剤:触媒=4:1)を専用シリンジから押し出しミキシングチップで混和する仕組みになっており、自動練和で操作は簡便だ。
硬化モードがデュアルキュアなのがポイントで、自然硬化でも10分前後でセットするが、必要に応じて光照射することで任意のタイミングで硬化を進められる。例えば、前歯部のラミネートベニアを仮着する際、光を当てずにいれば比較的長い操作時間が確保でき、複数歯を一度に位置決めしてから最後に一括で照射して固定といった芸当も可能だ。逆に素早く初期固化させたい場合は、各歯ごとに短時間光を当てれば即座に仮固定できる。操作時間を自在にコントロールできる柔軟性は、繁忙な診療中に大きな助けとなるだろう。
硬化後はフィルム状の薄層になるため、エッジ部の適合を損なわない。また剥離の際もフィルムのままペリッと剥がせるケースが多く、歯面清掃が容易だ。透明ゆえに仮着中の見た目は極めて良好で、患者が仮歯であることを忘れてしまうほど自然である。特にホワイトニング併用下でのプロビジョナルや、高額な審美治療のトライアル期間では、この自然観は患者の心理的安心に直結する。仮の状態から満足度が高ければ、最終補綴への期待感も高まり、治療継続のモチベーション維持にもつながるはずだ。
難点はコストで、1本5mL程度のシリンジにミキシングチップ付きという構成上、従来粉液より単価が張る。しかし、審美症例は基本的に自費診療なので材料費を適切に治療費に反映させれば問題は少ないだろう。それ以上に患者満足度向上による口コミ効果や追加施術受注といった潜在的リターンが見込める。例えば仮歯が美しいことで患者が周囲に治療中と気づかれず、その安心感から「この歯医者は技術が高い」と評判が広まるかもしれない。そう考えれば、テンポリンク クリアーの導入は単なる材料購入ではなくマーケティング投資とも捉えられる。前歯部審美に力を入れる医院、具体的にはセラミックやラミネートべニアの症例数が多い先生には、ぜひ試してみてほしい製品である。「仮歯なのに全然目立たないですね」と患者から驚きの声が上がったとき、投資の成果を実感できるだろう。
インプラントリンク セミ/半永久固定を可能にする超高保持力セメント
デタックス社のインプラントリンク セミ(Implantlink Semi)は、一見仮着材らしからぬユニークなポジションを占める製品だ。名称に「インプラント」とある通り、インプラント上部構造のセメント固定を念頭に置いて開発されたもので、半永久的な固定すなわち実質的な本付けにも使えるほど高い保持力を備えている。材質的にはレジン系セメントで、除去の際には専用の溶解剤を用いることもできるという特殊な製品である。
従来、インプラントの上部構造はスクリューで固定する方法が一般的だったが、審美性や力学的理由からセメント固定が選択されるケースも増えている。しかし一度セメントで装着してしまうと外すのが難しく、かと言って仮着用だと外れやすくて不安——というジレンマがあった。インプラントリンク セミは、「外れないけれど外そうと思えば外せる」という絶妙なバランスを狙った製品だ。具体的には、硬化後のセメントは非常に高強度で通常使用では脱離しないが、リムーバー(専用溶解スプレー)をマージン部から浸透させることでポロッと外れるよう設計されている。まさに「仮着と本着の中間」ともいえる存在で、海外では「semi-permanent cement」などと呼ばれるカテゴリーである。
臨床応用としては、長期仮着というより「実質本装着だが最悪の事態には撤去可能」という保険をかけたい場合に威力を発揮する。例えばインプラントの予後観察を続ける必要があるが最終補綴を入れておきたい場合、インプラントリンク セミで装着しておけば基本的には外れず安定して機能する一方、もし何か問題が生じれば溶解剤で救済できる。これは患者にとっても術者にとっても精神的安心につながるだろう。ただし、天然歯の仮着には原則用いるべきではない。保持力が高すぎて容易には外せず、支台歯を破折するリスクすらあるからだ。その名の通りインプラント専用と割り切り、通常の仮着用途には使わない方がよい。
経営的には、インプラントリンク セミを導入することでインプラント補綴の自由度が増す点が魅力だ。従来スクリュー固定では難しかった症例(例えば斜め埋入でスクリュー穴位置が不利な場合など)でも、セメント固定+将来の撤去可能性確保という折衷案で対応できる。これにより「インプラントはメンテできないから嫌だ」と敬遠していた患者にも安心して提案できる治療が提供できる。材料費は高価だがインプラント治療自体が高収益メニューであるため、十分吸収可能だろう。それよりも、万一のトラブル時に上部構造を壊さず外せる可能性は、再治療コストの観点で大きな価値を持つ。インプラント再手術や補綴再製作になれば何十万円もの出費になるが、セミで装着していればそれを回避できるかもしれない。そう考えると、これは患者にも医院にも「保険」を提供する製品と言える。
総じて、インプラントリンク セミは最先端のトラブルリスクマネジメント型セメントであり、インプラント治療を積極展開するクリニックには心強い味方だ。逆に通常の仮着材の範疇を超えているので、使用適応とリスクを十分理解した上で導入する必要がある。適切に使えば、将来のメインテナンスや改修を見据えた賢いインプラント治療を患者に提供でき、その信頼がまた次の患者獲得につながっていくだろう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 仮着材が原因で最終接着がうまくいかないことはありますか?
A1. はい、特にユージノール系仮着材の場合は注意が必要である。ユージノール残留がレジンセメントの重合を阻害し、最終補綴物の接着不良を招く可能性がある。そのため、仮着にユージノール系を使った場合は、補綴物撤去後にアルコールなどで歯面を十分清拭し、必要に応じて一日程度仮封して歯面を安静化させると良い。非ユージノール系なら基本的にこうした心配は少ないが、いずれの場合も仮着材の除去残渣を完全に取り除くことが成功の鍵である。
Q2. 仮着期間が長引く場合、途中で仮着材を交換するべきでしょうか?
A2. ケースバイケースである。一般的なZOE系やポリカルボキシレート系仮着材は、2〜3週間を超えて使用すると徐々に劣化して保持力が低下する傾向がある。そのため、治療が延びて1ヶ月以上仮歯で過ごすような場合は、一度補綴物を外して仮着材を入れ直す方が安全だ。ただし、フジTEMPのような長期仮着対応製品や、当初から高強度のレジン系仮着材を用いている場合は、無闇に外さずそのまま経過を見ても問題ない場合も多い。仮着期間が当初計画より延長されそうな時点で、製品の特性を踏まえて判断すると良い。
Q3. 仮着中の仮歯が外れやすく困っています。なにか対策はありますか?
A3. まず仮着材の選択見直しが考えられる。現在軟質系を使っているなら、より高強度のハードタイプやグラスアイオノマー系への変更を検討すると良い。それでも外れる場合、補綴物自体の適合や形態にも問題があるかもしれない。仮歯内面に溝を付けて機械的嵌合を増やす、支台歯に一時的に段差を付ける、などの工夫も考えられる。またセパレーターの使用量を減らすことで仮着材の密着性を高める方法もある(むやみにワセリン等を塗りすぎると保持力が落ちる)。それでもダメな場合は、思い切ってレジン系仮着材を使う最終手段もあるが、外す際の困難さと天秤にかけ慎重に判断してほしい。
Q4. インプラント上部構造を仮着で渡すことはできますか?
A4. 一般的な仮着材でインプラント上部構造を長期間固定するのは推奨されない。なぜなら、仮着材は長期的安定性や咀嚼圧への耐性が限定的で、インプラントでは一旦外れると周囲の骨や軟組織に悪影響が出る可能性があるためだ。しかし、IPテンプセメントやインプラントリンク セミのようにインプラント専用に調整された製品であれば、一定期間の仮着やセミPermanentな固定が可能である。これらを使用する場合でも、定期的に緩みがないかチェックし、問題があればすぐ本付けや再装着に切り替える慎重さが求められる。
Q5. 仮着材による歯の変色や副作用はありますか?
A5. 仮着材自体で歯質が恒久的に変色することは通常ない。ただし、ユージノール系セメントは長期間放置すると成分が茶色く変色し、歯肉や補綴物内面に着色が残る場合がある。またグラスアイオノマー系は環境によっては多少変色することも報告されているが、一時的な使用期間であれば大きな問題にはなりにくい。副作用としては、ごく稀にユージノールアレルギーの患者が接触性の刺激症状を示すことがある。その場合は使用を中止し、非ユージノール系に切り替える必要がある。総じて仮着材は口腔内に長期間留めない前提なので安全性は高いが、患者から違和感や異味が訴えられたら速やかに対応することが大切だ。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 仮封材・仮着材
- 歯科で使う「仮着材」とは?商品名の種類や特徴、成分を徹底比較