- 歯科機材の比較なら1Dモール
- レセコン
- 歯科の電子カルテのメーカーを徹底比較!価格や普及率・シェア、おすすめは?
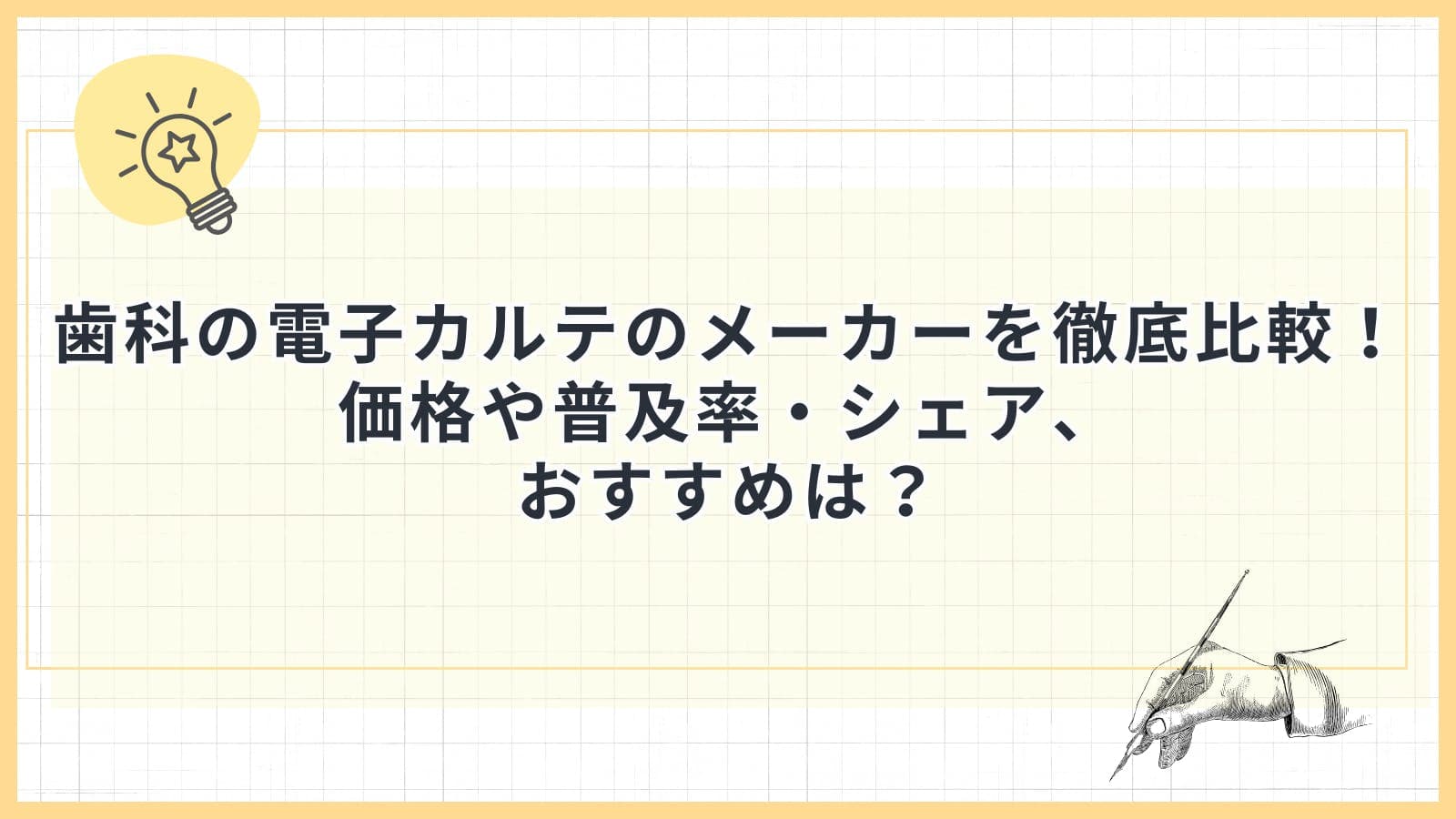
歯科の電子カルテのメーカーを徹底比較!価格や普及率・シェア、おすすめは?
ある患者の診療後、カルテ記載を後回しにして処置に追われ、終業後に慌てて思い出しながら書いた経験はないだろうか。あるいは診療報酬の算定ミスを提出直前に見つけ、冷や汗をかきながら修正したことがあるかもしれない。 歯科医院の経営において、カルテとレセプト業務は車の両輪である。手書きや旧式のレセコンではヒューマンエラーによる返戻リスクや残業が増え、スタッフの疲弊や患者対応の質低下にもつながる2024年9月以降はオンライン請求の原則義務化が迫り、紙やCDでの請求を続けるには特別な届出が必要になるに限界を感じつつも、「どの電子カルテが良いのか」「費用に見合う効果が出るのか」と不安で一歩踏み出せない先生も多いだろう。
本記事では、そうした悩みを持つ先生に向けて歯科用電子カルテ選びの臨床的ヒントと経営的戦略を提供する。
歯科電子カルテ主要製品の比較早見表
まず、国内で導入例の多い歯科電子カルテシステムを代表的な特徴とともに一覧する。臨床面の特徴に加え、導入費用や市場シェアなど経営判断に重要なポイントもまとめた。
| 製品名(メーカー) | タイプ | 初期費用 (概算) | 月額費用 (概算) | 導入シェア | 特徴の概要 |
|---|---|---|---|---|---|
| WiseStaff(ノーザ) | オンプレミス型 | 約190万円(親機) | 保守費用別途 (24時間サポートあり) | 約22%(業界首位) | 豊富な実績と高い安定性。通常入力だけで電子カルテ同時作成 |
| palette(ミック) | オンプレミス型 | 約190万円(エントリープラン) | 月額6,600円~ | 約17%(業界2位) | 40年以上の歴史。機能を自由に選んでカスタマイズ可能 |
| DOC-5 Procyon(モリタ) | オンプレミス型 | 約190万円(推定) | 保守費用別途 | 約10%(業界3位) | 画像・経営分析まで統合管理、豊富な拡張機能 |
| Opt.one3(オプテック) | オンプレミス型 | 約150万円(親機) | 保守費用別途 | 約9%(業界上位) | AIが治療計画を支援、時系列表示に優れる先進型 |
| Power5G(デンタルシステムズ) | クラウド型 | 18.7万円~ | 2.53万円 | 10%(今後拡大) | Power4Gから進化。高速レスポンスと柔軟な操作性 |
| Dentis(メドレー) | クラウド型 | 0~50万円 | 3~4万円 | —(新興) | オンライン診療や予約連携まで備えた次世代クラウド |
| ジュレア(ピクオス) | クラウド型 | 0円 | 1.98万円~ | —(新興) | 月額低価格で端末台数無制限、訪問先からも利用可 |
※初期費用・月額費用は税込目安。実際の価格は構成やオプションにより異なる。シェアは民間調査等による推計。
歯科電子カルテを選ぶ5つの比較ポイント
歯科用電子カルテを比較検討する際、臨床面と経営面の両観点から押さえるべきポイントがある。以下では導入形態の違いからコスト・時間効率まで、5つの軸で各製品の差異とその影響を解説する。それぞれの違いが診療現場の結果や医院収益にどう影響するのか、論理的に見ていこう。
クラウド型 or オンプレミス型とは?
まず検討すべきは、クラウド型かオンプレミス型(院内サーバ設置型)かという点である。クラウド型はメーカー運営のサーバをインターネット経由で利用する形態で、オンプレミス型は院内にサーバを置きシステムを運用する。この違いは導入・運用コストや運用時の柔軟性に大きな影響を及ぼす。
クラウド型のメリットは、初期費用の安さと自動アップデートにある。サーバ機器の購入が不要で、多くのクラウド製品は初期費用ゼロ・月額課金制となっており、導入ハードルが低い。例えばエムスリーデジカル(医科向け製品)では初期0円・月1万円弱という例もあり、歯科用クラウド型でも月額2~4万円程度が一般的だ。ソフトのバージョンアップや診療報酬改定への対応はメーカー側で迅速に行われ、自院で面倒な更新作業をする必要がない。また、データはデータセンターに保管され多重バックアップされるため、院内PCが故障しても情報は守られる。停電等の非常時もクラウド側で冗長化が図られており、業務継続性(BCP)の面でも安心感がある。
一方、クラウド型のデメリットはカスタマイズ性の低さと通信依存である。メーカー共通のプラットフォームを使うため、自院独自の細かな運用に合わせた変更は難しい場合が多い。画面レイアウトや項目を自由に編集することは基本的にできず、機能追加もメーカー任せになる。またネット環境が必須であり、通信障害や回線速度によっては業務に支障を来す恐れもある(特に画像データを大量に扱う場合、回線速度の速いオンプレミス型が有利という指摘もある)。
オンプレミス型のメリットは、院内完結の安心感と自由度の高さである。サーバやデータを院内管理するため、外部への情報流出リスクが極めて低くセキュリティ面で安心できる。また、自院のニーズに合わせて機能を柔軟にカスタマイズ可能な製品が多い。例えばミックの「palette」は60種類もの機能モジュールから必要なものだけを選んで実装でき、医院ごとの運用にぴったり沿ったシステム構築が可能である。紙のカルテ様式に近い画面や、入力手順を自由に設定できる製品もあり、現場の感覚に合わせた使い勝手を追求できる。
ただしオンプレミス型の導入費用は高額になりがちである。サーバ機器やソフトウェアライセンスの購入費用として数百万円規模が必要な場合が多く、初期投資の負担は無視できない。さらに数年ごとのハード更新や保守費用も計上すると、5年間総額ではクラウド型と同程度かそれ以上になるケースもある。また、システム更新は各医院で実施しなければならず、例えば診療報酬改定時に自力でソフト更新パッチを当てる必要があるなどITに強い人材がいないと苦労する場面もある。バックアップも自己責任となり、万一のサーバ故障時に備えた体制(RAID構成や定期外部バックアップ)が求められる。
結論として、初期費用を抑え手軽に最新機能を享受したいならクラウド型、カスタマイズ性やオフライン環境での強みに重きを置くならオンプレ型が適している。ただ近年は、クラウド型でも医科のORCA連携で低コスト化を図る動きや、オンプレミス型でもオンラインアップデートやリモート保守に対応した製品が登場しており、両者のギャップは埋まりつつある。実際、歯科市場では2024年以降クラウド型への移行が年20%ペースで進んでいるというデータもあり、今後はクラウド型の比率が着実に伸びていくだろう。
操作性と入力効率
どんなに高機能なシステムでも、日々の診療で使いこなせなければ宝の持ち腐れである。電子カルテ導入時によく聞かれる不安が、「入力に時間がかかり診療が滞るのではないか」という点だ。しかし最新の歯科用電子カルテは、現場の声を反映した様々な工夫で紙カルテ同等かそれ以上の入力効率を実現している。
例えばミックの「palette」は、テンプレート文章の選択だけでカルテ記入が完了する機能を備えており、忙しい診療中でも素早く正確に記録できる。紙カルテにフリーハンドで書くより入力時間を大幅に短縮でき、患者を待たせずに会計まで進められる。このようなテンプレートや定型文機能は各社が工夫を凝らしており、処置内容や投薬内容をあらかじめ登録してワンクリックで記載するといった使い方が可能だ。筆者の経験では、補綴物装着やブラッシング指導など毎回似た内容になる所見はテンプレ化すると格段に入力が早くなる。カルテ記載がスピーディーになれば診療後の記入漏れ防止にもつながり、ヒヤリハットの削減や残業削減の効果も大きい。
直感的な操作設計も重要なポイントだ。プラネット社の「iQalte」はiPadですべての操作を完結できるよう設計されており、画面は紙のカルテ用紙そのままのレイアウトである。マニュアルを読まなくとも指でのタップ操作とApple Pencilでの手書き入力だけで直感的に記録でき、PC操作が苦手なスタッフでも戸惑いが少ない。紙カルテに近いUIのおかげでベテラン歯科医師でも違和感なく移行しやすいだろう。また、iPadを増やすだけでチェアサイドに端末を追加できるため、ユニット数の多い医院でもスペースを取らず機動的に入力端末を展開できる。アシスタントや歯科衛生士も各自のタブレットで同時に入力・閲覧が可能になり、院内の情報共有と入力分担が円滑になる。
一方、オンプレミス型の多くはキーボードとマウス中心の操作だが、こちらも工夫次第で快適に使える。例えばオプテック社の「Opt.one3」では、対話形式のQ&A画面で問診票やカルテを入力できるようになっている。質問に答えていくだけで所見や診断名が記録される仕組みで、初学者でも迷いにくい。また同製品はSOAP形式(主観・客観・評価・計画の構造化フォーマット)を採用しており、歯科衛生士のメンテナンス記録なども標準化された手順で入力できるのが特徴だ。このような構造化入力は記録内容の抜け漏れを防ぎつつ業務効率を高める利点がある。実際、Opt.one3では入力データからAIが次回治療方法を提案する機能もあり、カルテ記載と同時に治療計画立案までサポートされる。操作面の工夫が診療そのものの質向上につながっている好例といえよう。
応答速度も無視できないポイントだ。処理が遅いシステムでは入力のたびストレスを感じ、現場定着の妨げになる。クラウド型はネット回線に依存するため不安視する声もあるが、例えばデンタルシステムズ社「Power5G」は処理スピード3秒以内を目標に開発されており、実用上ストレスない応答性を実現している。筆者が実際にデモ機で試した際も、患者検索やレセプト算定処理が一瞬で完了し、旧来のレセコンのもたつきは皆無だった。近年のシステムはハードウェア性能向上も相まって大量データでも高速処理が当たり前になりつつあり、この点は大きく心配しすぎる必要はない。
総じて、各製品とも「いかに現場の負担を減らすか」に注力した工夫が見られる。導入初期は誰しも慣れが必要だが、適切な研修と設定を行えば紙運用に劣らぬスピードで記録できるようになる。むしろ自動チェックやテンプレ活用で「紙より速い・正確」という体験を得られれば、スタッフも積極的に電子カルテを使いこなすようになるだろう。
機能と拡張性
電子カルテを選ぶ際、単にカルテ記録やレセプト作成だけでなく、プラスアルファの機能にも目を向けたい。各メーカーとも独自の付加機能を備えており、それが診療効率や患者サービス、ひいては医院の収益向上に寄与するケースがあるからだ。
例えば、予約システムやリコール(定期検診通知)機能の搭載は、患者管理に直結する重要なポイントだ。ピクオス社「ジュレア」は予約管理システム「デンタマッププラス」を標準搭載し、診療台にいながら次回予約を入れるチェアサイド予約や予約データ分析まで可能である。リコールハガキやメール送信も自動化され、プロアクティブに患者をフォローできる仕組みだ。ある導入医院では、リマインド機能で無断キャンセル率を12%から5%に改善し、月商45万円アップ(7ヶ月で投資回収)を達成した例も報告されている。このようにシステムの活用が患者数増加につながることも十分にあり得る。
また訪問診療対応も見逃せない。高齢化が進む中、在宅歯科診療に対応する医院では、介護保険請求や訪問先での記録入力が効率よく行えるシステムが望ましい。モリタのDOC-5プロキオンはオプションで介護請求の伝送や訪問予定管理に対応し、在宅診療の流れを一括管理できる。Opt.one3も医科・歯科の両レセプトに対応しており、医療保険と介護保険をシームレスに扱える。クラウド型なら訪問先にタブレットを持参し記録を入力、即座に院内とデータ共有することも容易だ。実際、ジュレアやDentisは訪問先からのアクセスを前提に設計されており、移動中や自宅でもカルテを確認・編集できるフットワークの軽さが強みである。訪問診療を展開する医院にとって、これらの機能は業務効率とサービス品質の向上=経営メリットに直結する。
医療連携やデータ活用の仕組みも重要だ。例えばモリタのDOC-5はNTTデータとの連携により高度なセキュリティで院内データ一元管理を実現している。また、患者説明支援のために治療計画の自動作成や視覚的プレゼン機能を備えており、治療の見える化で患者満足度向上と自費率アップに貢献するという。オプテックのOpt.one3ではエビデンスに基づく論理的なカルテ記載が特徴で、AIによる治療提案機能と合わせて、インフォームドコンセントの質を高める狙いがある。実際に「患者説明がスムーズになった」との声もあり、患者理解を助け追加治療の成約率が上がる効果も期待できる。
さらに、他システムや医療機器との連携もチェックしたい。デジタルレントゲンや口腔内写真をカルテ画面でスムーズに参照できれば診断効率は上がるが、製品によって対応状況は様々だ。クラウド型では画像ファイル連携に追加費用がかからないものもあれば、オンプレミス型では他社画像ソフトとのブリッジ接続がオプション扱い(費用加算)となる例もある。例えばOpt.one3は画像連携が拡張性豊かな一方で一部有料オプションとなっているので、フル活用するには追加投資が必要だ。逆にモリタのDOC-5は自社のデジタルX線機器や口腔内カメラとの統合を強みにしており、カルテ画面で撮影画像やCT解析結果をワンタッチ表示できる。画像説明の容易さは患者の信頼獲得にも寄与するため、自院の設備状況に応じて適切な製品を選ぶ必要がある。
このように電子カルテは単なる記録ツールではなく、医院運営をトータルに支援するプラットフォームへと進化している。搭載機能の豊富さに目移りしてしまうが、重要なのは「その機能が自院に本当に必要か」「投資回収に寄与するか」を見極めることである。例えば自費率向上を狙うなら患者説明支援機能や経営分析が充実したものを、保険診療メインで回転率重視なら予約・会計連動でチェア稼働を最適化できるものを、といった具合に医院の戦略に沿った機能を重視すると良いだろう。
サポート体制と安全性
電子カルテは導入して終わりではない。長期にわたり日常的に使い続けるものだから、メーカーのサポート品質やシステムの信頼性は極めて重要だ。特に診療中やレセプト請求直前にシステムトラブルが起これば、診療ストップや売上計上不能という最悪の事態にもなりかねない。「困ったときにいつでも頼れるか」は製品選定の大きな判断軸となる。
まず注目すべきはサポート対応時間と手段である。業界随一のサポート力で知られるノーザ社の「WiseStaff」は、24時間365日の電話サポートと遠隔保守を提供している。深夜に予期せぬトラブルが起きても、ワイズスタッフのヘルプデスクに電話すれば技術者が対応してくれる安心感がある。筆者も過去、年末の夜間に受付PCが故障した際、24時間サポートに連絡して代替機へのデータ移行手順を指示してもらい、翌朝の診療に影響を出さずに済んだ経験がある。こうした「いつでも駆け付けてくれる」支援は、医院経営者にとって心強い。クラウド型でも、メドレー社Dentisやエムスリー系システムが24時間ヘルプデスクを掲げており、夜間休日の対応可否は必ず確認したいポイントだ。
次に導入時のサポートも重要だ。新システムへの移行には、スタッフ研修や旧データの移行が伴う。実績豊富なメーカーはこの点のノウハウが蓄積されており、導入前後の手厚い伴走支援を提供している。例えばWiseStaffでは専門スタッフが導入時から立ち会い、運用定着までフォローする体制が整っているという。またデータ移行では、旧レセコンからCSVで患者データを書き出し、メーカー側で新システムにマッピングする作業を代行してくれる場合が多い。数万件のカルテ情報でも数日で移行可能との報告があり、プロに任せれば移行の不安は大幅に軽減する。新規開業であれば初期設定からスタッフトレーニングまで一気通貫でサポートを受けられるか確認するとよいだろう。
災害や障害への備えという観点では、システム自体の堅牢性に加え、非常時の対応策をチェックしたい。オンプレミス型の場合、データ消失リスクに備えたバックアップ体制は必須だ。具体的には外付けHDDやクラウドストレージへの定期バックアップ、自家発電設備や無停電電源装置(UPS)の設置などを検討すべきである。Opt.one3のように自動バックアップ機能を備える製品もあるが、最終的には人為的な確認も欠かせない。一方クラウド型は、データセンター側で複数拠点へのリアルタイム複製(ミラーリング)が行われており、地震や火災時にもデータ保全されやすい強みがある。モリタのDOC-5ではNTTデータ基盤上にデータを集約し、ウイルス監視や改ざん防止まで施している。いざというとき信頼できるインフラがバックにあるかどうかは大きな安心材料だ。
法規制への対応も安全性の一部と考えよう。電子カルテで診療録を保存する場合、日本では厚労省の「電子保存ガイドライン」に沿った運用が求められる。具体的には真実性・見読性・保存性のいわゆる「電子カルテ三原則」を満たすことが必要だ。多くの市販システムはこれらに準拠しており、例えばOpt.one3は電子カルテ三原則に対応と明言している。またオンライン資格確認や電子処方箋など新しい制度との連携も進んでおり、DentisやSunnyシリーズはマイナンバーカード認証端末との接続にも対応済みだ。法改正や制度変更へのアップデート提供が迅速かどうかも、メーカー選定時に確認しておきたい(クラウド型は改定後1~2日で自動更新される一方、オンプレ型は1週間遅れで手動パッチという例が多い)。
総じて、「人」と「技術」の両面で支えてくれるメーカーが安心だ。困ったときはすぐ相談でき、予防策も含め長期的に医院を支援してくれるパートナー選びが重要である。契約前にはサービスレベル契約(SLA)に目を通し、サポート対応時間や代替措置、データの所有権(退去時のデータ返還ルール)などについて十分確認しておこう。電子カルテは長い付き合いになるだけに、信頼できるメーカーとの出会いが医院経営の安心につながる。
コストと経営効率
最後に、経営者である歯科医師にとって避けて通れないコストとROI(投資対効果)の問題を考察しよう。電子カルテ導入には決して安くないコストがかかるが、それを上回る効果が得られるかどうかが重要である。単純な価格比較にとどまらず、1症例あたりのコスト削減効果や業務効率改善による収益増まで含めて多角的に評価する必要がある。
まず初期費用+5年間の総コストでクラウド型とオンプレ型を比較してみる。前述の通りクラウド型は初期ゼロ~数十万円、月額数万円が相場である。仮に月額3万円(年36万円)とすれば5年で約180万円の支出だ。一方オンプレ型は初期導入に200万円前後、さらに年保守料10~20万円が発生するケースが多い。例えばあるオンプレ製品では「親機1台190万円+子機1台10万円、保守年12万円」の価格設定があり、5年合計では約250万円となる。この概算では5年スパンではクラウド型の方が安いが、利用期間が10年20年と長くなればオンプレ型は保守費用程度で済むため結果的にコスト優位になる場合もある。自院でどれくらいの年数使う見込みか、途中で買い替えやリース更新が入るかなどを踏まえ、ライフサイクルコストで判断することが大切だ。
とはいえコスト算出は支出面だけを見ても不十分である。肝心なのはそれによってどれだけ時間と労力を節約できるかというリターンの部分だ。あるモデルケースを考えてみよう。月200件の保険診療を行う歯科医院がクラウド電子カルテを導入し、月額利用料が3万円だとする。この医院で紙レセプト時代には毎月事務スタッフがレセ点検に10時間かけていたとすれば、電子化でチェック業務が自動化され月8時間の削減につながったとしよう(残り2時間は手動確認に充てる)。スタッフ時給を2,000円と見積もると、月あたり16,000円の人件費節約になり5年で約96万円のコスト減となる。月額3万円×60ヶ月=180万円の支出と相殺すると実質84万円のコストで5年間運用できた計算だ。これは単なる一例だが、電子カルテは目に見えにくい隠れコストを削減する効果が大きい。点検作業だけでなく、カルテ記載漏れ防止による返戻削減(取りこぼし収入の減少防止)や、業務効率化による残業代圧縮、紙や印刷代の節約など様々な面で経費カットにつながる。
さらに収益拡大効果も考えてみたい。例えばリコール葉書の送付やリマインドメールをシステムで自動化し患者来院率が上がれば、売上に直結する。前述のようにキャンセル減少で月商が大幅アップした例や、デジタルツールで治療説明を充実させ自費率が向上したケースもあるだろう。筆者のクリニックでも電子カルテ導入後、衛生士によるPMTCリコールの管理が飛躍的に改善し、リコール患者数が前年より20%増加した。結果として予防歯科の売上が伸び、システム費用を十分補填できる利益増となった。電子カルテが患者満足度を高め紹介を呼び込む効果も見逃せない。待ち時間短縮や会計のスムーズさ、カルテを見せながらの丁寧な説明といった体験は、患者の医院評価を確実に上げる。そうした積み重ねが口コミやリピーター増につながれば、計算上のROI以上の価値があると言える。
もちろん、経営効率の改善度合いは医院ごとの工夫と努力次第でもある。新システムを宝の持ち腐れにしないためには、スタッフ教育や運用ルールの整備も欠かせない。導入直後に時間短縮効果が出なくても諦めずにPDCAを回し、使いこなし方を模索してほしい。メーカー提供の活用セミナーやユーザー会に参加し、他院の成功事例を参考にするのも有効だ。単なる費用でなく「投資」と捉え、どう回収するかの戦略を練ることが、電子カルテ導入を成功させる鍵となる。
主な歯科用電子カルテ製品レビュー
以上の比較ポイントを踏まえ、ここからは主要な歯科電子カルテ製品それぞれの特徴を見ていく。客観的なスペックやデータに基づき、各製品の強みと弱みを整理するとともに、「どのような医院・歯科医師に向いているか」を臨床・経営両面の観点から考察する。先生ご自身の価値観に合った製品選びのヒントにしてほしい。
WiseStaff
WiseStaff(ワイズスタッフ)は国内シェアトップを誇る歯科総合システムで、その実績ゆえの信頼性・安定性と手厚いサポートで知られる。現行版の「WiseStaff-9 Plus」では普段のレセコン入力をするだけで同時に電子カルテが自動生成されるため、紙カルテ併用時代と比較して入力の二度手間がない。点数入力ミスの自動チェックやレセプト一括点検機能も備え、返戻率の低さにも定評がある。24時間365日の電話サポートと遠隔保守は業界随一で、夜間や休日でもトラブル対応してもらえる安心感が大きい。また全国規模のサービス網で導入支援から研修まで手厚く、ITに不慣れな医院でも安心して移行できる。
技術面でも古参に留まらない。リモートバックアップやオンラインアップデートに対応し、従来型オンプレミス製品の弱点をカバーしている。さらに訪問診療用のVPN接続機能やiPadビューア、患者向けモバイルアプリ連携など先進機能も取り入れており、クラウドに引けを取らない利便性を実現している。とはいえ初期導入費用は約200万円と高価で月額費用も高め(保守含め数万円)なため、中小規模クリニックには負担感もある。また高機能ゆえに設定項目が多く、使いこなしには習熟が必要だ。「質の高いサポートに価値を感じ、とにかく安心・安定を買いたい」という院長には最適である。事実、大規模医療法人から個人開業医まで幅広く支持されており、市場シェア約22%と2位以下を引き離す導入実績が何よりの信頼材料だ。
palette
ミック社のpalette(パレット)は、40年以上の歴史を持つロングセラーの歯科用コンピュータである。業界第2位のシェアを占め(約17%)、全国で多数のユーザーに使われてきた実績がある。palette最大の特徴は、必要な機能を取捨選択して組み合わせられるカスタマイズ性にある。基本のレセプト請求・会計機能に加え、予約管理・リコール・統計分析・訪問診療・介護連携など実に60種類以上のオプション機能から自院に必要なものだけを選んで導入できる。これにより、例えば自費中心の審美歯科ならリコールやカウンセリング管理を重視、在宅診療に注力する医院なら訪問機能をプラス、といったオーダーメイド感覚のシステム構築が可能だ。
操作画面も昔からの歯科医に親しみやすいUIを踏襲している。カルテ入力欄は紙の1号・2号用紙に準じたレイアウトで、キーボード中心の操作に慣れた先生にも違和感が少ない。初期導入はCD-ROM媒体だが、プログラムのアップデートはオンラインダウンロードに対応しており、時代に合わせた利便性も兼ね備える。さらにミックは全国対応のサポート網を持ち、古くからのユーザーも多いため、同業の先生同士で情報交換がしやすい点もメリットと言える。
反面、高度なカスタマイズは裏を返せば設定の複雑さでもある。機能を盛り込みすぎると画面が煩雑になり操作が難解になる恐れがあるため、本当に使う機能に絞った導入計画が肝要だ。またクラウド全盛の現在ではオンプレミス型が主流のpaletteはやや古さを指摘されることもある。近年は「MIC WEB SERVICE」というインターネット経由サービスも提供されているが、基本は院内サーバ型であり、クラウド製品のような外部アクセスや自動更新の利便性は限定的だ。それでも「細部まで自院仕様に作り込みたい」「長年使われ磨かれた安定システムが欲しい」というニーズには応えられるだろう。実際、ある医院では紙カルテからpaletteに移行する際、頻用する薬剤セットや処置コメントを事前登録し運用したところ、診療の流れにピタリと合ったシステムになったと満足している。自由度の高さをうまく活かせる医院にとって、paletteは強力な相棒となる。
Dentis
メドレー社のDentis(デンティス)は、近年登場したクラウド型歯科電子カルテの中でも先進的なコンセプトで注目されている。単なるカルテ・レセコン機能に留まらず、「歯科医院と患者をオンラインでつなげ、新しい患者体験を提供する」ことを掲げている。具体的には、Web予約システムやオンライン診療機能、キャッシュレス決済との連携など、デジタル技術で患者の利便性を高める機能が統合されている。患者はスマホのアプリ(CLINICSアプリ)を通じて予約~問診~診療~決済までシームレスに体験でき、医院側もアプリ経由の情報発信やリコール通知で新たな関係構築が可能となる。
もちろんカルテ・レセコンとしての基本性能も高い。カルテ記載と同時にレセプト電算処理が裏で走り、内容のエラーチェックもリアルタイムに行われるため入力ミスを防ぎやすい。またクラウドならではの場所を選ばないアクセス性で、院長が自宅から本日分のカルテを確認したり、往診先で入力した内容をクリニックのスタッフが即座に閲覧したりといったことも可能だ。自費のデジタル矯正やインプラントなどで症例写真や動画を用いたオンライン相談を行うといった、新しい診療スタイルにもマッチするだろう。
Dentisの導入費用はクラウド型としては中~高めで、プランによっては初期費用50万円・月額4万円程度になる場合もある(機能絞り込みのライトプランならもっと安価な設定もあり得る)。ただ、IT導入補助金の対象ツールにもなっており補助金活用で実質負担を軽減できる可能性がある点は覚えておきたい。弱みとしては、まだ比較的新しい製品ゆえ歯科特有の細かな運用ノウハウが発展途上な部分があることだ。大手医科向けシステムのノウハウを活かしているとはいえ、歯科ならではの算定や特殊ケース対応でユーザーの声を反映し改良していく余地はあるだろう。
「最新テクノロジーで医院運営を革新したい」と考えるデジタル志向の院長には大いに魅力的な選択肢である。特に都会の若い患者層をターゲットに、自費サービスやリコールを積極展開するようなクリニックでは、Dentisの提供するスマートな患者体験が差別化につながるはずだ。一方でレセコンとしての実績重視や安定稼働を最優先するなら、導入済み医院の事例やサポート体制について慎重な確認が必要だ。「攻め」の経営を志向する医院向けのハイエンド製品と言えるだろう。
Power5G
デンタルシステムズ社のPower5Gは、旧来より普及していた「POWER4G」というレセコンをクラウド化・サブスクリプション化してリリースされた製品である。つまり実績あるオンプレシステムの信頼性とクラウド型の利便性を両立した存在と言える。シンプルで見やすい画面設計と柔軟なカスタマイズ性を受け継ぎつつ、クラウド化によって場所を問わない利用や自動アップデートなどを実現した。特筆すべきは処理レスポンスの速さで、開発段階から応答時間3秒以内を目標に最適化されている。実際、レセプト算定や集計処理のスピードは群を抜いており、ストレスフリーな操作感が得られる。
機能面では、紙カルテ感覚の患者画面や高速なレセプトチェック、さらに訪問診療時の介護保険入力機能など、日常業務に寄り添った痒い所に手が届く便利機能が充実している。例えば訪問先での処置内容を簡単にメモ入力し、帰院後に本格入力する機能なども備え、在宅診療のフットワークを損なわない配慮が見られる。また、Power5Gは他システム連携実績が豊富で、既存のデジタルレントゲンソフトや予約システムと繋いで使っている医院も多い。このあたり、長年使われてきた前身システムからの強みが活きている。
費用は初期約18.7万円、月額2.5万円程度からとクラウド型として標準的だ(利用端末数などで変動)。民間調査によれば旧Power4G時代から一定のシェアがあり、WiseStaff・palette・DOC5に次ぐグループに属する。クラウド移行後はさらに伸長が期待され、今後有力な選択肢の一つとなっていくだろう。
「実績ある国産レセコンをクラウドで使いたい」というニーズにまさに合致する製品であり、レセコンから電子カルテへのステップアップを図りたい場合にも導入しやすい。過去にPOWERシリーズを使っていた医院なら操作体系が大きく変わらないため抵抗感は少ないはずだ。逆にまったく新規に採用する場合、カスタマイズ項目が多いぶん設定に戸惑う可能性もあるので、導入時のサポートをうまく活用すると良い。堅実で使いやすく、それでいてクラウドならではの機動力も備えたバランスの良い製品と言えるだろう。
ジュレア
ピクオス社のジュレアは、何よりリーズナブルな価格設定が光るクラウド型電子カルテ/レセコンである。初期費用0円・月額利用料19,800円(税込)~という低コストが大きな魅力で、これは主要クラウド製品の中でも最安クラスに位置する。さらに台数無制限で同一料金であり、院内PCやタブレットを何台増やしても追加費用が発生しない。これはユニット数やスタッフ数が多い医院にはありがたいポイントだ。メーカー専用端末の購入も不要で、既存のPCやiPadを活用できるため、設備投資も最小限に抑えられる。クラウド型ゆえソフト更新料もなく、法改正時のバージョンアップも全て月額料金に含まれており追加徴収は一切ない。
低コストだからといって機能が貧弱なわけではない。レセプト請求データの点検や各種帳票(領収書・処方箋など)の発行、自費診療管理など、歯科医院の日常業務に必要な機能は一通り網羅されている。特に標準搭載の予約システム「デンタマッププラス」は秀逸で、チェアサイドから次回予約が入れられるほか、予約分析やリコール支援までこなす。これにより受付業務の省力化だけでなく、患者フォローによる増患効果も期待できる。クラウド型なので訪問先や自宅からもアクセス可能で、フットワークの軽さも持ち味だ。
弱点としては、シェアトップ企業と比べて会社規模やサポート拠点が限られる点が挙げられる。サポートはメール・電話対応で、リモート操作支援にも対応しているが、24時間対応ではないようだ。また低価格ゆえに高度なオプションや専門的分析機能などは割り切って省かれており、「とにかく安く基本機能だけ使えれば良い」という割り切りが必要になる。ただ開業間もない医院や、なるべくコストをかけずIT化を進めたい先生にとって、この価格設定は大きな武器になる。実際、IT補助金を使わずとも導入しやすいので、補助金要件に縛られず自由なタイミングで電子カルテ化を図れるメリットもある。
「コスト最優先だが妥協はしたくない」という医院にはジュレアは有力な選択肢だ。クリニックの規模拡大や運用ニーズの変化に応じて上位製品に移行することも視野に入れつつ、まずはジュレアで電子カルテの恩恵を享受してみるのも一つの戦略だろう。低コストで始めて効果を実感できれば、その後の設備投資判断もポジティブに行えるはずである。
With(ウィズ)シリーズ
メディア社のWithシリーズは、「レセコンを超えた歯科診療支援システム」を掲げる意欲的な製品だ。オンプレミス型の「With」と、クラウド型の「Withエポック」が提供されており(双方の機能連携も可能)、医院のニーズに合わせて選択できる。最大の特徴は、正しいカルテ記載をナビゲートし医療事故や指導リスクを減らすというコンセプトに基づく豊富なチェック機能である。問診時から治療処置まで丁寧なガイドメッセージが表示され、カルテ入力時にはリアルタイムで記載内容の矛盾や漏れを検知してアラートを出してくれる。例えばう蝕の部位や処置内容の組み合わせ誤りなども即座に指摘され、提出前に修正できるため、レセプト返戻や個別指導での指摘を回避しやすくなる。
さらに医療安全の支援機能も充実している。たとえば処方入力時には問診票に基づく既往歴や現在の服薬内容を参照し、投薬禁忌や注意事項があればポップアップで警告する。血圧やアレルギー情報といった全身管理データもカルテと連動してチェックされるため、安心して診療を進められる。これは患者の安全はもちろん、万一のトラブル時にも「システム上で確認していた」というエビデンスになり、医療訴訟リスクの低減にも役立つだろう。
Withは多職種の連携や周辺業務統合にも意欲的だ。受付~会計までの効率化、省力化を図る一方、予約管理システムや患者説明ツール、訪問診療クラウドとのデータ連携など、医院内外の様々なシステムと繋がるハブとしても機能する。例えば医院独自に運用しているiPad説明用アプリやWeb予約サイトなどがあれば、連携可能かメーカーに相談してみると良いだろう。
注意点として、Withシリーズは機能が豊富なぶんシステム要件や価格が高めであることが挙げられる。ハードウェアも高性能PCや院内サーバが推奨されるため、小規模医院で導入するにはオーバースペックと感じる向きもあるかもしれない。また操作画面も多機能ゆえ複雑になりがちで、導入初期のトレーニングは不可欠だ。しかし「とことん安全で正確な診療を追求したい」「保険請求のミスで経営リスクを負いたくない」という医院には心強い味方となる。特にスタッフが多くヒューマンエラーが起こりやすい大規模クリニックでは、Withの持つエラー防止ガードレールが経営を下支えするだろう。クラウド版のWithエポックなら初期費用も抑えめで、データセンターもISMS認証取得済みと万全なので、セキュリティ重視の院長にも訴求するはずだ。
iQalte
プラネット社のiQalte(アイカルテ)は、その名が示す通りカルテ作成から会計・レセプト確認まで全てをiPad上で行えるユニークなシステムだ。DentalXというプラネット社の患者情報一元管理プラットフォームと連携し、院内のあらゆる情報をデジタルで統合するコンセプトとなっている。操作はタッチとApple Pencilによるペーパーレス体験に特化しており、画面構成は紙のカルテそのもの。1号用紙・2号用紙がそのまま電子化されているので、ユーザーは紙に書く要領で直感的に入力できる。医療現場でありがちな「システムが変わると紙と操作が違って混乱する」という事態を避け、誰でも違和感なく使い始められる点は大きな強みだ。
iQalteはボーダーレスな運用を可能にする。院内であればWi-Fi経由でどのユニットからでもカルテ入力でき、スタッフの人数に応じてiPadを増やすだけで良い。院外でもインターネット接続があればカルテ閲覧・入力が可能なため、在宅診療先や自宅での事後記録など、場所を選ばない働き方を実現する。例えば夕方の訪問診療後に院長が帰宅し、その夜にiPadでカルテ記載を仕上げておけば、翌朝クリニックでスタッフがすぐ請求チェックに回せるといった具合だ。スペースや時間の制約をデジタルで超えるこのメリットは、忙しい開業医にとって計り知れない価値がある。
加えて、DentalX/R(デンタルアール)やDental Hubとのデータ連携により、院内の他システムとの垣根が低いのも特徴だ。レントゲン画像や口腔内写真の管理、技工所とのやり取り、他院紹介状の作成など、様々な機能モジュールとスムーズに連携する。歯科医院のデジタルトランスフォーメーション(DX)をトータルにサポートする設計であり、単なるカルテソフトの枠を超えている。
デメリットとしては、iPad主体の運用に抵抗を感じる層がまだいる点だ。特にキーボード入力を多用するベテラン事務スタッフなどは最初戸惑うかもしれない。しかしiQalteはペンシル手書きによる所見記入もサポートしており、例えば難しい症例で直接イラストを描き込んだり、デンタルチャートにマーキングしたりすることも可能だ。紙とデジタルの良いとこ取りを目指しており、慣れればキーボードに勝るとも劣らない効率が出せるだろう。費用面では導入実績拡大期ということもあり比較的抑えめとも言われるが、詳細は都度問い合わせになる。いずれにせよ「院内のすべてをタブレットでスマートに運用したい」という医院には理想的な選択肢である。クラウドの柔軟さと紙カルテの親しみやすさを融合したiQalteは、まさにデジタルネイティブ世代の歯科医師にフィットする未来志向の電子カルテと言えよう。
DOC-5 Procyon
DOC-5 Procyon(プロキオン)は歯科大手メーカーのモリタ社が開発する歯科統合システムのフラッグシップである。その位置づけに相応しく、患者受付から会計・経営管理に至るまで医院業務の全てを一元化しようというコンセプトが貫かれている。患者情報はモリタデータセンターで一括管理され、受付~問診~検査~カウンセリング~治療~会計~経営分析までシームレスにデータが連携する様は圧巻だ。電子カルテとしての機能も充実しており、問題志向型診療記録(POMR)の考えを取り入れたカルテ構造や治療計画自動作成機能を備え、視覚的な治療プレゼンテーションにも長ける。患者へ治療内容を分かりやすく提示できるため、説明ツールとしても非常に優秀だ。
セキュリティ面では、信頼のNTTデータと組んでシステムを構築している点が特徴的だ。データセンター側で二重三重のウイルス・不正侵入対策が施され、万一のサイバー攻撃からも患者情報を守る体制となっている。医療情報の安全管理に厳しい病院クラスにも耐えうる設計で、個人開業医にとってはオーバースペックに感じるほどしっかりした作りだ。オンライン請求にも当然対応し、オプションでレセ電送を自動化。介護保険請求や在宅診療スケジュール管理などもアドオンで追加でき、まさに死角のないフルスペックと言える。
反面、その導入コストは最も高額な部類に入る。具体的な価格は規模や構成次第だが、親機・子機合わせて数百万円単位の初期費用が見込まれる。小規模クリニックが容易に手を出せる価格ではないため、導入しているのは中~大規模の歯科医院や病院歯科部門が中心となっているようだ。また機能が膨大であるため、全てを使いこなすには相当のITリテラシーと習熟期間が必要だろう。正直なところ、ユニット数2~3台程度の一般歯科では宝の持ち腐れになりかねない。
しかし「歯科医院の将来像はこうあるべき」という一つの到達点を示す製品であることは間違いない。例えば分院展開を視野に入れている法人なら、DOC-5基盤で本院分院をオンライン連携し一元管理することも可能だろう。あるいは高度な診療科(例えば口腔外科や障害者歯科など)で詳細なデータ管理や院内他職種との連携が求められる場合にも、この統合システムは力を発揮する。「将来を見据えた先行投資」と位置づけて導入できるかどうかがポイントになる製品だ。モリタブランドの安心感と最新テクノロジーを両立したDOC-5 Procyonは、歯科医療のDXをけん引する存在として今後も進化を続けていくだろう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 電子カルテを導入すると紙カルテより入力に時間がかかるのでは?
A1. 慣れの問題はあるが、適切に運用すれば入力時間は紙と同等かそれ以上に短縮できる。多くの電子カルテにはテンプレート機能や自動チェック機能があり、文章を一から書く手間が省ける。例えば定型処置であれば選択肢をクリックするだけで記録が完成し、後から追記修正も容易である。紙では見落としがちな点もエラー表示されるため、むしろ後工程の修正時間が減りトータルでは効率化することが多い。導入初期にしっかり研修し、頻用テンプレートを整備すれば、紙運用と遜色ないスピードで入力できるようになるだろう。
Q2. 今使っているレセコンはそのままに、電子カルテ機能だけ追加導入できるか?
A2. 可能なケースもあるが基本的には一体型システムへの移行がおすすめである。現在のレセコンに電子カルテ連携オプションがあれば追加導入は可能だし、あるいはORCA連動型の独立電子カルテを別PCで併用する手もある。しかし記録と請求が分断されると二重入力や整合性の問題が生じやすい。せっかく電子化しても業務効率が上がらない懸念がある。理想はカルテとレセコンが一体となった製品に統合することだ。最近の主流は一体型であり、予約や会計まで含めデータが一元管理されるため、情報重複や入力漏れが起こりにくい利点がある。一時的な過渡期対応として併用も可能だが、最終的には統合を目指すのが望ましい。
Q3. データの保存やセキュリティが心配。サーバが飛んだらカルテが消えてしまうのでは?
A3. 現在の電子カルテは法規に則った厳格な保存要件を満たしており、適切なバックアップさえ取っていれば紙より安全とすら言える。オンプレミス型の場合、自院でのバックアップが重要だが、多くの製品で自動バックアップ機能が搭載されているほか、外部メディアやクラウドストレージへの複製も推奨されている。クラウド型ならデータセンター側で多重バックアップされるため、ハード故障程度ではデータ消失しない。通信は暗号化され、アクセス制限も厳格に管理されている。万一院内サーバが故障してもバックアップから新サーバへ復元可能だし、クラウドなら他端末からログインするだけで業務を再開できる。大切なのは日頃からのバックアップ確認と災害対策で、紙カルテを倉庫に保管するより確実かつ迅速に復旧できる点で電子カルテの方が安全と言える。
Q4. デジタルレントゲンや口腔内スキャナーなどの機器と電子カルテは連動できるの?
A4. 多くの電子カルテが画像管理ソフトとの連携機能を備えている。例えばカルテ画面からボタン一つで患者のデジタルX線画像ビューアを開いたり、口腔内写真を呼び出したりできる。また撮影と同時にカルテにサムネイル表示される仕組みを持つ製品もある。製品間の組み合わせによってはオプション費用が必要なケースもあるが、主要メーカー同士では相互連携の実績が豊富なので、現在お使いの機器名をメーカーに伝えれば対応可否を教えてくれるだろう。クラウド型では画像データ容量が大きい場合に読み込み速度の課題があるが、高速インターネット回線や院内LANキャッシュを活用することで実用上問題ないレベルに改善されている。院内のデジタル機器を孤立させず、カルテと結びつけて運用することがDX推進のポイントであり、導入時にぜひ連携設定まで行うことをおすすめする。
Q5. 万が一メーカーがサービス終了したらどうなる? データ移行は可能か?
A5. 確かにベンダーの統廃合は起こり得るが、データさえ標準形式で保管しておけば心配しすぎる必要はない。医療情報の互換性を高める取り組みは進んでおり、カルテデータの標準フォーマット(例えばPDF化やCSVエクスポート)での出力機能を持つ製品が多い。契約時に「データの所有権は医院側にあり、サービス終了時には全データを無償提供する」旨を確認しておけば安心だ。また、たとえメーカーが撤退してもすぐ使えなくなるわけではなく、一定期間は既存システムを運用しつつ新システムへの移行猶予が与えられるのが通常だ。実際、過去にもレセコン業界のM&A再編はあったが、ユーザーのカルテデータが消失して困ったという話は聞かない。重要なのは、定期的にデータを外部にエクスポートしておく習慣である。非常時に備え、自院でも読める形でバックアップを確保しておけば、いざというとき他社製品へのスムーズな乗り換えが可能だ。メーカー任せにせず「データは自分でも守る」という意識を持っておけば万全だろう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- レセコン
- 歯科の電子カルテのメーカーを徹底比較!価格や普及率・シェア、おすすめは?