- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 口腔内スキャナー
- ストローマン社のアライナー矯正「クリアコレクト」のセミナーはどこで受講できる?
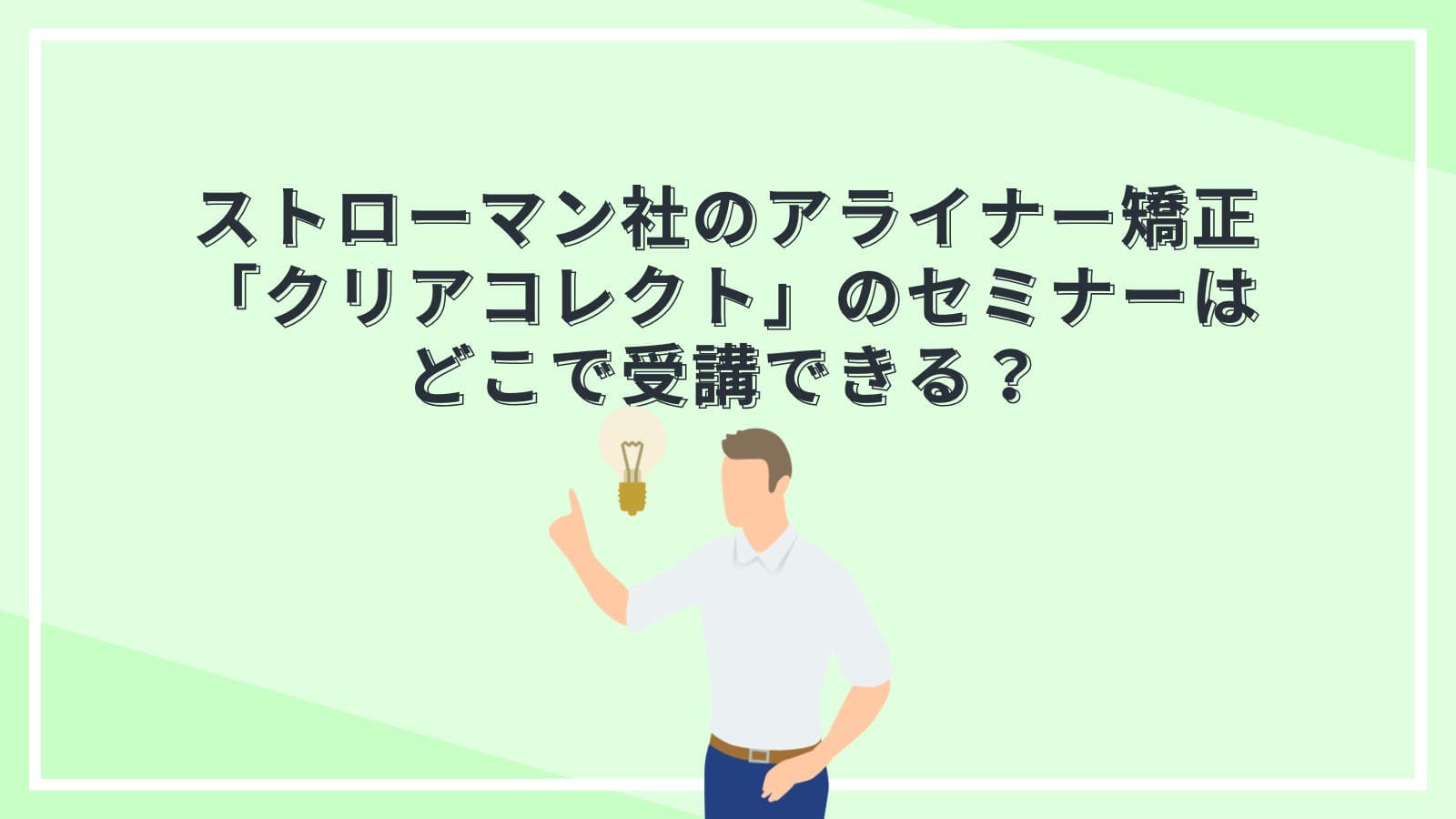
ストローマン社のアライナー矯正「クリアコレクト」のセミナーはどこで受講できる?
ある開業歯科医の先生は、定期検診に訪れた患者から「目立たない矯正はできますか?」と相談を受けた。従来なら大学病院の矯正科や連携する専門医に紹介していたが、最近ストローマン社のマウスピース型矯正装置ClearCorrect(クリアコレクト)の存在を知り、自院で提供できないかと考え始めた。しかし、矯正治療は専門性が高く安易に手を出すことへ不安もある。この先生のようにクリアコレクト導入を検討する歯科医師に向けて、本記事では公式セミナーの受講方法と内容、そして臨床面・経営面の両軸から導入判断に必要な実務ポイントを解説する。
要点の早見表
クリアコレクトを導入するために歯科医師向けに提供されている主なセミナーとその概要を下表にまとめる。各コースは目的や対象に応じて設計されており、オンライン開催と会場開催が用意されている。
| セミナー名(形式) | 概要・目的 | 会場・受講形式 | 受講費用(税込)目安 | 対象・特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Straumann Aligner Starter Course(対面) | アライナー矯正の基礎を一から学ぶ入門コース。矯正歯科学の基本とClearCorrectの治療フローを体系的に習得する。講師は矯正専門医。 | 原則対面(東京都など主要都市)※日程によりオンライン開催もあり | 約10,000〜15,000円 | アライナー矯正未経験の歯科医師(これから導入を検討する方向け) |
| ★Webセミナー★ Introduction to ClearCorrect(オンライン) | 卒後あまり矯正に関わってこなかった一般歯科医向けの入門講義。不正咬合の分類や適応症の見極めなどを概観し、GPによるアライナー治療の第一歩を解説。 | オンライン(Zoomライブ配信)双方向参加型 | 約3,000〜5,000円 | 基礎知識に不安がある歯科医師(矯正知識のリフレッシュ目的) |
| Straumann Aligner Club(オンライン) | 症例検討形式の発展コース。矯正専門医の指導のもと参加者の症例を共有し学ぶ。適応症の判断や治療計画のポイントを議論し、具体症例を通じ実践力を向上させる。 | オンライン(Zoomミーティング) | 約5,000円 | 既にクリアコレクトを開始した歯科医師(さらなる知識習得・症例相談) |
| Straumann Aligner スタッフセミナー(対面) | 歯科医院スタッフ向け研修。患者への効果的なアプローチ法を習得する。カウンセリング手法や院内マーケティング、IOS(口腔内スキャナー)の活用など、医院全体で矯正を推進する体制づくりに焦点。 | 対面(ストローマン研修施設等で開催) | 約10,000〜12,000円 | 歯科衛生士・受付などスタッフ(患者説明・啓発の役割を担う) |
| ClearCorrectベーシックセミナー(対面) | 年間10症例以上の提供を目指す歯科医院向けの実践セミナー。包括的歯科診療におけるアライナー矯正の位置付けや、自費転換の必要性、患者獲得のコンサル術を学ぶ。GPによるマウスピース矯正導入の経営戦略に重点。 | 対面(地域会場例:東京・品川) | 約10,000〜15,000円 | 保険中心から自費矯正に移行を検討する歯科医師(経営的視点も学ぶ) |
※上記以外にも、ストローマン・ジャパン主催のユーザーミーティング(症例発表・共有イベント)やオンデマンド配信のウェビナーが随時開催されている。最新の日程はストローマン社の教育プラットフォーム「SKILL」にて確認可能(要アカウント登録、2025年8月現在)。
理解を深めるための軸
クリニックでクリアコレクトを導入する判断には、臨床的な軸と経営的な軸の両面から検討が必要である。臨床面では、術者自身の矯正に関する専門知識と技術の習得度合いが成否を分ける。マウスピース矯正は一見シンプルに見えても、歯の移動計画や咬合への影響評価など、従来のワイヤー矯正に匹敵する深い理解が求められる。適応症の見極めを誤れば、計画通りに歯が動かず再治療や補綴でのリカバリーが必要になるリスクもある。
一方、経営面の軸では、新たな矯正メニュー導入による投資対効果と医院運営へのインパクトを評価する。セミナー受講料やスターターキット購入費、場合によっては口腔内スキャナー導入費用など初期投資が発生する。またスタッフ教育や患者説明の体制整備にも時間とコストを割く必要がある。しかし、クリアコレクトを導入すれば従来は他院紹介としていた矯正ニーズを自院で収益化でき、新患の増加や患者満足度向上が期待できる。すなわち臨床軸(適切な症例選択と治療遂行)が上手く機能すれば、経営軸(収益拡大と差別化)にも好影響を与える。一方で臨床対応に無理が生じれば、経営的にも患者信用損失や追加コスト発生につながるため、この二軸は表裏一体と言える。
以上を踏まえ、以下ではクリアコレクト導入に関連するトピックを掘り下げ、臨床と経営の観点を交えて解説する。
代表的な適応症と禁忌事項
クリアコレクトを含むマウスピース型矯正装置の適応症は原則として軽度の不正咬合である。日本矯正歯科学会の治療指針によれば、非抜歯で軽度の空隙や叢生があり、歯列のわずかな拡大で改善可能な症例が推奨されている。具体的には前歯部の軽い歯列不正や、矯正後の後戻り症例など、歯の大きな移動を必要としないケースが適している。また金属アレルギーの患者にとって、金属ブラケットを用いないアライナー矯正は有効な選択肢となる。
一方、重度の症例や抜歯を伴う矯正は慎重な対応が求められる。大きな顎骨のずれを伴う骨格性不正咬合や、上下顎前突で抜歯が必要なケース、犬歯の大きな遠心移動や大きな歯の回転・挺出・圧下を要する症例は、アライナー単独ではコントロールが難しい。不適応なケースにクリアコレクトを適用すると、予期せぬ歯の移動や咬合の乱れを招き、結局ワイヤー矯正でのリカバリーが必要になる場合もある。また、小児の混合歯列期は顎の成長や歯の萌出を予測しづらく、マウスピース矯正には不向きである。加えて患者の協力度(装着時間遵守など)が低い場合、計画通りの歯牙移動は望めない。以上のことから、クリアコレクト導入にあたっては適応症の選別基準を明確に持つことが重要である。セミナーでは「最初に選ぶ患者の基準」について具体例を交えて解説しており、初心者が陥りがちな症例選択ミスを避ける指針が得られる。
標準的な治療ワークフローと品質管理
クリアコレクト治療の流れは一般的なアライナー矯正と概ね共通している。まず初診時に口腔内スキャナー(IOS)による光学印象採得やシリコン印象と写真・レントゲン資料を揃え、Doctor Portalを通じてストローマン社のクリアコレクト専用プラットフォームに症例を提出する。提出時には患者の主訴や治療ゴール、歯の移動に関する細かな指示(IPRの有無やアタッチメント〔エンゲージャー〕装着位置など)を送信し、技工側でデジタル治療計画を作成する。医師はクラウド上の3DシミュレーションソフトClearPilotでステージごとの歯列移動を確認・修正し、最終プランを承認する。承認後、工場でアライナーが製造され医院に出荷される。患者へは1〜数週間ごとの間隔で複数ステージ分をまとめて渡し、自宅での装着を指示する。以降、数か月ごとに来院してもらい治療のモニタリングを行い、必要に応じ追加アライナーの発注(追加料金が発生する場合あり)や補助処置(IPR施行、アタッチメント追加等)を行う。最終的な歯列移動が計画通り完了すれば保定装置による保定期間に移行する。
このワークフロー全体で品質を確保するには、適切な計画立案とデータ精度の管理が肝要である。セミナーではClearCorrectの治療フロー習得がカリキュラムに含まれており、写真撮影・スキャン手技の注意点からClearPilot上でのシミュレーション評価方法まで詳しく学ぶことができる。特に光学印象を用いる場合、撮影範囲や咬合の記録精度が不十分だと、作成されるアライナーが適合不良となり再スキャン・再製作を招く。品質管理には院内のデジタル機器の校正や清潔な印象採得も欠かせない。また、症例提出時の指示の出し方ひとつで仕上がりが変わることも多く、講習では「プリファレンス設定」やテクニシャンとの効果的なコミュニケーション方法も共有される。これらを踏まえ、標準的なワークフローの各段階でチェックリストに沿った確認を徹底することが、再製作や治療遅延の防止につながる。
安全管理と患者説明の実務
クリアコレクトを扱う上で患者安全の確保と十分な説明・同意は最優先事項である。まず、日本国内でClearCorrect関連製品(アライナーシート、治療シミュレーターソフト等)は医療機器として承認・認証を取得済みであり(販売名「ストローマン アライナーシートCC」他)、適正に供給される製品である。しかし、実際の診療では装置自体の安全性だけでなく、術者の扱い方によって患者の転帰が左右される点に注意が必要だ。アライナー装置は取り外し可能な利点がある反面、患者自身の協力がなければ効果は得られない。装着時間が不足すると計画より歯の移動が遅れ、治療期間延長や仕上がり不良を招く。そのため事前の説明で「1日20時間以上の装着」を厳守すべきことや、飲食時の着脱・清掃方法を具体的に指導する。装置装着中は唾液による自浄作用が妨げられることから、食後のブラッシング徹底や間食制限についても助言し、う蝕や歯周炎リスクの増加を防ぐ。
また、治療開始前にはインフォームドコンセント(同意取得)を文書で確実に行う。これは日本矯正歯科学会の指針でも強調されている。具体的には、クリアコレクトの治療目的・必要性・有効性だけでなく、他の矯正治療法(ワイヤー矯正等)との比較や、万一アライナーだけでは十分な結果が得られなかった場合にブラケット矯正等の代替治療が必要になる可能性も説明する。患者が治療の利点と限界を正しく理解した上で同意していることが重要である。セミナーでは患者説明のロールプレイや同意書のひな形なども紹介されることがあり、受講後すぐに活用できる実践的な知識が得られる。また、安全管理面では、万一のアライナー紛失や破損時の対処、アタッチメント脱離への対応、顎関節症状への注意など臨床現場で遭遇しうるトラブルへの備えも議論される。加えて、矯正治療には長期のフォローアップが必要なため、カルテ上での経過記録や患者情報の管理も含め院内で統一プロトコルを定めておくことが推奨される。
費用と収益構造の考え方
クリアコレクト導入に係る費用には、初期投資とランニングコストの両方が存在する。初期投資として代表的なのは、ストローマン社のスターターキット購入費用である。スターターキットにはクリニックがClearCorrect症例を開始する上で必要なツール類(アタッチメント設置用テンプレートやIPR用ストリップ、専用ケースなど)が含まれており、定価で数万円程度(例えば約47,000円)で提供されている。セミナー参加者には期間限定で割引価格が適用されるキャンペーンが行われることもある。また、症例提出・管理のためのDoctor Portal利用自体には基本料はかからないが、症例ごとのアライナー製作費(いわゆるラボフィー)が発生する。費用体系は症例の難易度やステージ数によって異なることがあるが、1症例あたり数十万円規模のコストを見込んでおく必要がある。例えば、軽度の矯正でステージ数が少ない場合と、長期に及ぶケースでは費用が異なるプランが設定されている可能性があるため、導入前にストローマン社の営業担当者から詳細な価格表の説明を受けることが望ましい。
一方、収益構造の面では、クリアコレクト導入により新たに得られる自費診療収入が重要となる。日本においてアライナー矯正は公的医療保険の適用外(顎変形症など特定の場合を除き保険算定不可)であり、患者には全額自費負担となる。そのため治療費は相応に高額となるが、適切に提供できれば医院にとっては利益率の高いメニューとなりうる。一般的なマウスピース矯正の患者負担額は症例の程度によって数十万〜百数十万円に及ぶことが多く、その中からラボフィーと診療経費を差し引いた分がクリニックの粗利となる。単純計算すれば、仮に1症例あたり50万円の治療費を設定し、そのうちラボフィー等の変動費が20万円かかる場合、残り30万円が医院側の収入となる。ただしここから診療チェアタイムに応じた人件費や光熱費、減価償却費(機器導入時)も考慮する必要がある。
クリアコレクト導入の投資回収シミュレーションとしては、例えばスターターキット等に初期投資で約50万円(キット・セミナー・周辺機器費用の合算)を要したとして、それを回収するには何症例の矯正治療契約が必要かを試算することになる。前述の粗利30万円/症例のモデルであれば2症例でほぼ回収可能だが、実際には症例獲得までのマーケティングコストや導入初期の非効率もあるため、余裕を持って3〜5症例程度の成約を目標とするとよいだろう。セミナーではこうした収支モデルについても触れられ、既存医院での平均症例数や価格設定の事例紹介、自費率向上のポイントなど経営的視点からの講義が行われる。留意すべきは、矯正治療は施術開始から終了まで長期間にわたるため収入も分割されやすい点である。患者からの治療費支払いは一括前払いだけでなく分割・デンタルローン利用もあり、医院のキャッシュフローに与える影響も考慮した上で価格設定と徴収方法を決定する必要がある。
外注・共同利用・自院導入の選択肢比較
クリアコレクトを自院で導入するか否か判断する際、他の選択肢との比較検討も重要である。まず挙げられるのは、矯正専門医への外部紹介(外注)という選択肢である。従来どおり信頼できる矯正歯科に患者を紹介すれば、自院で矯正治療を行わない分リスクは低く抑えられる。臨床的にも経験豊富な専門医が担当するため患者に高水準の治療を提供できる。しかし、紹介先で治療が完結する場合、自院の収益には直接結びつかず、患者が治療期間中は定期メンテナンス以外来院しなくなることもあり得る。また昨今はマウスピース矯正を前面に打ち出す矯正専門クリニックも増えており、患者が紹介先でそのまま補綴治療やホワイトニング等も受けてしまい、自院に戻って来ないリスクも否定できない。
次に、共同利用や提携という形態も考えられる。例えば非常勤の矯正医に定期的に来院してもらい、自院設備でクリアコレクト治療を実施するケースである。この場合、装置の発注や治療計画は矯正医が担うため、一般歯科側は症例選択や治療方針の判断を専門医に委ねられる利点がある。医院としては診療チェアや設備を提供しつつ、収益の一部を矯正医とレベニューシェアするモデルが考えられる。患者にとっては通い慣れた自院で矯正治療が完結する安心感があり、医院としても一定の収入を得られる。ただし矯正日が限られるなど柔軟性に欠ける点や、結局知識が医院内に蓄積されにくい点はデメリットとなる。
最後に、歯科医師自身が自院でクリアコレクトを本格導入するパターンである。これには今回取り上げているように公式セミナーを受講し、自ら治療計画を立案して症例をこなしていくスタイルが該当する。最大のメリットは矯正治療も自院完結とすることで診療の幅が広がり、新たな収益源になることである。また患者管理も一貫するため他の治療との両立がしやすく、総合的な歯科治療計画に組み込みやすい。さらに症例を重ねることで術者のスキルが向上し、医院の強みとして「マウスピース矯正ができる一般歯科」としての評価を得ることも可能だ。一方、デメリットは術者自身に相応の矯正知識・技術が要求される点である。前述のとおり日本矯正歯科学会は「アライナー矯正を行うには認定医相当の知識・技術・経験が必要」と勧告している。言い換えれば、一般歯科医が安易に手を出せばトラブルが生じかねない領域ということである。このハードルを乗り越えるには、体系立てて知識を学び少ないリスク症例から経験を積むこと、そして難症例は無理せず専門医に委託する判断もできる冷静さが必要だ。クリアコレクトのセミナーで繰り返し強調されるのも「無理な症例は手掛けない」「基本に忠実な治療計画を立てる」といった点であり、自院導入の際には自ずと守備範囲と限界を見極める姿勢が求められる。
よくある失敗と回避策
クリアコレクト導入初期に見られるよくある失敗パターンとして、いくつかの例が知られている。まず一つは症例選択の誤りである。ありがちなのは、患者からの強い希望を断れず難しいケースに手を付けてしまうケースだ。例えば明らかに抜歯が必要なレベルの叢生や、大きな下顎前突を伴う症例に対し、無理にマウスピースだけで治そうとして途中で計画行き詰まるといった事態である。回避策としては、初めのうちは「Social 6」と呼ばれる前歯部の部分矯正的な簡易症例や、咬合に大きな変化を及ぼさない範囲の軽度不正に限定して実施することだ。セミナーでも初診時カウンセリングにおける断り方や、専門医紹介が必要な場合の患者対応について言及がある。患者の希望に応えることと、安全確実な治療を提供することのバランスを取り違えないことが肝要である。
次に治療計画の詰めの甘さも失敗の原因となる。アライナー矯正では歯根の動きが視覚化されにくく、初心者はシミュレーション上で歯冠だけを見て判断しがちだ。しかし実際には歯根の向きや周囲骨の厚みなど不可視の要素が結果を左右する。計画段階でこれらを見落としていると、アライナーが進むにつれ予期せぬ歯の傾斜移動や後戻り現象が発覚し、追加アライナーや最悪ブラケット併用が必要になる。回避するには、事前にセファロ分析や模型診断を併用し、本当にアライナー単独でゴールまで行けるかを検証する習慣を持つことである。ClearCorrectでは必要に応じてシミュレーションを何度でも修正できるため、安易に承認ボタンを押さず複数パターンを比較検討するくらい慎重でちょうど良い。また、治療途中でのモニタリング不足も失敗に繋がる。順調に見えても実はアライナーの適合が悪くなり計画との差異が生じていることがある。各ステージの交換時期に合わせて患者からフィードバックを聞き、予定通り動いているか口腔内を確認するプロセスを省いてはいけない。もし明らかに動きが停滞していれば、早めに追加スキャンして中間リファイン(追加アライナー再作製)を行うべきである。セミナーではこうした途中経過のチェックポイントやトラブル兆候の見極め方も詳説されるので、学んだ内容をもとに院内プロトコルに落とし込むと良い。
さらに患者コミュニケーションの失敗も挙げられる。例えば治療前の説明不足により、患者が「マウスピースだから痛みもなく簡単」と誤解したまま開始してしまうと、実際に加圧痛や話しにくさが生じた際にクレームになりやすい。あるいは装着時間の自己申告を鵜呑みにしてしまい、患者が十分装着していないのに「計画通り進んでいますね」などと伝えてしまうミスもある。これを避けるには、初めからデメリットや起こり得る不便さも率直に説明し、患者の協力が不可欠であることを強調しておく必要がある。また、経過報告時には口腔内写真を見せながら「ここは予定より動きが遅れているので装着時間を再確認しましょう」など、客観的事実に基づいて伝えることで、患者自身も主体的に協力しようという意識が高まる。スタッフと連携し、リコール来院のたびに装着状況や使用状況をヒアリングする仕組みづくりも効果的である。
導入判断のロードマップ
クリアコレクトの導入可否を検討する際には、段階的に意思決定していくことが望ましい。まず潜在需要の推定から始める。自院の患者層を見渡し、成人の矯正ニーズがどれくらい存在するかを把握する。例えば過去に「歯並びを治したい」と相談された件数や、現在補綴治療中で歯列不正が気になる症例の数などを洗い出す。また地域の人口構成や競合医院の矯正提供状況も参考に、マーケット的に見込める症例数を概算する。次に自己のスキル評価である。院長自身(または担当する歯科医師)が矯正治療にどの程度精通しているか、上述した指針で求められる知識・経験に照らし自己評価する。もし卒後研修以来矯正に触れていないようであれば、導入前に基礎から学び直す決意が必要だろう。公式セミナーへの参加はその第一歩となる。
その上で具体的な計画立案に移る。まずはストローマン社のセミナーに登録し、可能であれば院長と担当スタッフがセットで受講することを推奨する。院長がStarter Courseで臨床の基礎を学ぶ一方、スタッフもスタッフセミナー等で患者対応術を学べば、院内に共通言語が生まれスムーズな導入準備が可能だ。次に、導入初期に扱う症例のプロトタイプを決める。例えば「下顎前歯の軽度叢生を主訴とする20〜30代」をターゲットに想定し、そのケースでの診断〜治療フローを頭の中でシミュレーションしてみる。この際、使用する機器や材料のリストアップも行う(デジタルスキャナー有無で手順が変わるため要検討)。さらに施設基準や届出も確認する。現在のところクリアコレクト提供自体に特別な届出は不要だが、院内広告やWebサイトで矯正を新たに謳う場合は医療広告ガイドラインに抵触しない表現に更新する必要がある。例えば「矯正専門医在籍」「マウスピース矯正〇〇件の実績」といった宣伝文は、根拠や資格が伴わなければ使えないため注意が必要だ。
計画の段階では損益予測も欠かせない。前述の費用構造を基に、1年間で何症例取り扱えば黒字転換できるか、またその症例数を集患するために必要な販促策とコストは何か、シミュレーションしてみる。例えば年間10症例を目標とするなら、月に1人ペースで契約が必要となる。この達成に向け、現患者への案内文作成や無料矯正相談の実施、あるいは紹介会社やウェブ広告の利用といった具体策を検討する。あわせて院内オペレーションの調整も行う。マウスピース矯正は診療時間の使い方が従来治療と異なる。初回カウンセリングや診断用資料採得に通常より長めのチェアタイムを要し、その後は装置装着やチェックで短時間の診療が分散する形になる。これらを無理なく既存のアポイント枠に組み込むには、診療アシスタントや受付との役割分担の見直しが必要かもしれない。セミナーで学んだ「業務分担の重要性」も参考に、例えばカウンセリングはトリートメントコーディネーターが担当し、術者は診断と計画立案に専念する、といった体制を整えると効率的である。
最後に試験導入と評価である。準備が整ったら、まずは少数の症例で運用し結果を検証する。できれば最初のケースは無理のない適応症を選び、セミナー講師やストローマンのクリニカルアドバイザーに相談しながら進めると安心である。治療終了まで完遂したら、患者の満足度アンケートやスタッフとの振り返りミーティングを行い、良かった点・改善点を洗い出す。ここで判明した課題(例えば模型管理の手順ミスや患者説明の不足など)はマニュアルに反映させ、次の症例以降に活かす。このPDCAサイクルを通じて医院の提供するクリアコレクト治療の質を高めていくことが重要である。一連のロードマップを経れば、無理なくクリアコレクト導入の是非と具体的手順が見えてくるだろう。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 口腔内スキャナー
- ストローマン社のアライナー矯正「クリアコレクト」のセミナーはどこで受講できる?