- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 口腔内スキャナー
- セレック(CEREC)で使われる口腔内スキャナーを価格や性能でまとめてみた
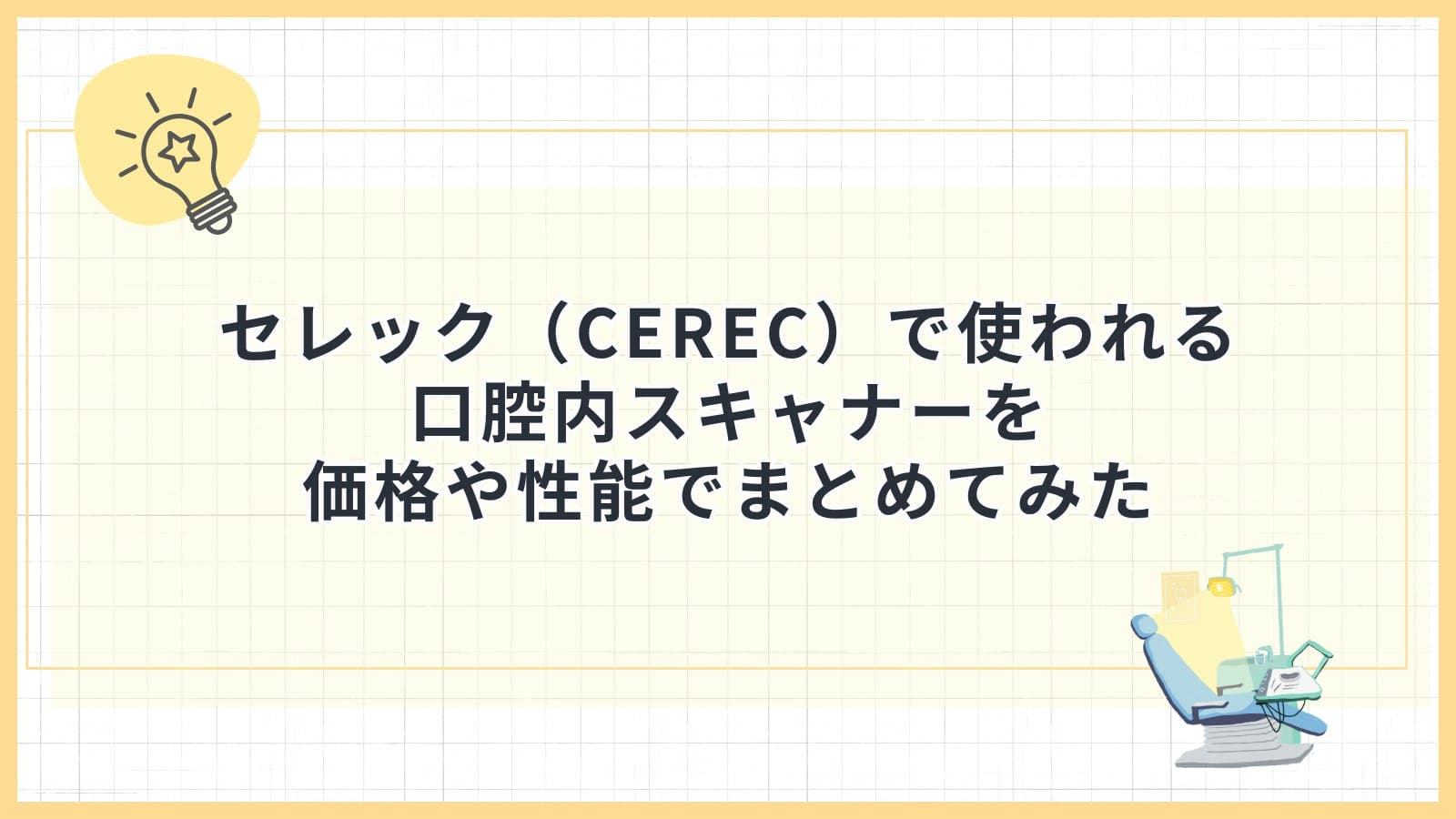
セレック(CEREC)で使われる口腔内スキャナーを価格や性能でまとめてみた
歯科医院にCAD/CAMシステムを導入する際、「どの口腔内スキャナーを選べばいいのか分からない」「高額な投資に見合う効果が本当に得られるのか」と悩んだ経験はないだろうか。例えば、従来の印象採得で嘔吐反射に苦しむ患者に気を遣いながら作業したり、石膏模型の精度や輸送時間に頭を抱えたりしたことがあるかもしれない。あるいは、「セレックで1日で補綴物を提供できれば患者に喜ばれるのに」と感じつつも、機器のコストや操作習熟への不安から導入に踏み切れずにいるケースも多い。
本記事では、そうした臨床現場と経営面双方の課題を解決するヒントを提供したい。セレック(CEREC)システム用の口腔内スキャナー各モデルの特徴と違いを、臨床的価値と経営的価値の両面から客観的にリストアップする。最後まで読み進めれば、セレック用スキャナー各種の強み・弱みがはっきりと掴め、高額な設備投資のROI(投資対効果)を改善する戦略が見えてくるはずである。
主要モデルの早見表
まず、現在セレックワークフローで使用される代表的な口腔内スキャナーを一覧にまとめる。各モデルの主なスペックと費用目安を把握し、全体像を掴んでほしい。
| モデル | 発売時期 | パウダー要否 | カラー取得 | ワイヤレス | スキャン速度 (フルアーチ目安) | ワンド重量 | 標準価格 (税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEREC Bluecam (ブルーカム) | 2009年頃 | 必要(全面塗布) | 非対応(モノクロ) | 非対応(有線) | 数分以上(静止画撮影方式) | 約――※ | 約400万~500万円※ | 足踏みスイッチ操作式 深度10mm程度 |
| CEREC Omnicam (オムニカム) | 2012年発売 | 不要 | 対応(フルカラー) | 非対応(有線) | 約2~3分(動画連続撮影) | 約316g | 約640万円 | タッチ操作カート型 深度15mm |
| CEREC Primescan (プライムスキャン) | 2019年発売 | 不要 | 対応(フルカラー) | 非対応(有線) | ~1分強(高速連続撮影) | 約525g | 約690万~745万円 | タッチ操作カート型 深度20mm |
| CEREC Primescan 2 | 2024年発売 | 不要 | 対応(フルカラー) | 対応(無線) | ~1分未満(高速連続撮影) | 約542g※ | 定価450万円 | ワイヤレスハンドピース クラウド連携 |
※Bluecamの重量は公称値未公開(カメラ一体型ユニット)。Primescan 2の542gはバッテリー・スリーブ装着時の重量。
表より、旧世代から最近のモデルにかけてパウダーレス化とカラー化の達成、スキャン速度の飛躍的向上が読み取れる。加えて、ワイヤレス対応による運用の自由度向上と、クラウド活用によるデータ管理の効率化が図られている点にも注目だ。価格面では、新モデルほど初期導入費用は高額になる傾向だが、一方で運用コスト(ソフトウェア更新料やクラウドサービス料)や付随設備にも違いがある。以下でこれらのポイントを軸に、各モデルの特徴と評価を詳述していこう。
セレック口腔内スキャナーのポイント
同じ「セレック用スキャナー」とはいえ、世代やモデルによって得意不得意や経営効率への影響は様々である。ここでは、臨床面の評価軸と経営面の評価軸を織り交ぜながら、スキャナーポイントを解説する。具体的には、「精度」「スキャン速度」「操作性」「データ連携(オープン性)」「コスト&ROI」の5つの観点から論じていく。
高精度スキャンと補綴適合性への影響
補綴物の適合精度を左右するのは、スキャナーの解像度や精度である。モデル間では、新しい世代ほどセンサー技術と画像処理アルゴリズムが進歩し、精密なスキャンデータを取得できる傾向がある。例えば、Primescanは微細なエッジや線をシャープに描写できる超高精細スキャンが可能で、市場でも口腔内スキャナーのゴールドスタンダードと称されるほど精度が高い。実際、複数の調査で裏付けられているように、Primescanの精度誤差はフルアーチでも50ミクロン以内に収まるとされ、これは従来法のシリコン印象材にも匹敵するレベルである。こうした高精度スキャンは、支台歯のマージン形態を明瞭に記録し、適合の良い補綴物設計につながる。
一方、旧世代のBluecamも発売当時は高精度とされたものの、パウダーを塗布する手間や経時的な粉の厚み変化が精度に影響しうる点は否めない。粉の塗布が不均一だとスキャン結果に誤差が生じ、マージン部の再現性にもムラが出やすかった。Omnicamではパウダーレス化によりこの誤差要因が排除され、歯肉と支台歯形成縁を色調差で明確に区別できるため、肉眼で見えにくいマージンもデータ上でははっきり確認できる。さらにPrimescanになるとダイナミック深度スキャン技術により被写界深度がおよそ20mmに達し、従来は困難だった深いマージン(歯肉縁下)の描出もかなり良好である。こうした精度向上により、クラウンやインレーの適合不良による再調整・再製作率が低減し、臨床現場のストレス軽減と患者満足度向上に寄与する。
経営的観点では、精度の高さは再製作の削減によるコスト節約と直結する。適合精度が低いとやり直し症例が発生し、材料費や技工費の無駄だけでなく追加のチェアタイムも発生する。高精度スキャナーを使えば一発で適合の良い補綴物を提供できる可能性が高まり、無駄なコストと時間を省ける。また、精度への信頼性が高まれば、インプラントの複数ユニット補綴や長いブリッジ症例にもデジタル印象を活用できる範囲が広がる。結果として、自費診療の高度なケースまで院内で完結できるようになり、新たな収益機会を創出することにもつながる。
スキャン速度とチェアタイム短縮の効果
次にスキャン速度である。口腔内全体の撮影に要する時間は、患者の負担感や診療効率に直結する。世代を経るごとにカメラの取り込みスピードや視野の広さが向上し、フルアーチのスキャン時間は飛躍的に短縮されてきた。
Bluecam時代は、1歯ずつ静止画を足踏みスイッチでキャプチャしていく方式で、上下顎と咬合を合わせれば全体で5分以上かかることも珍しくなかった。粉を吹き付けながらの撮影は患者・術者双方にとって時間的にも心理的にも負担で、特に嘔吐反射の強い患者では辛い時間となっていた。Omnicamでは動画による連続撮影(フレームレート約20fps)に変わり、スキャナーを動かし続けるだけで自動的にデータがどんどん取得できるようになった。この結果、経験を積めば片顎1~2分程度でスキャンを完了することも可能となり、従来より大幅なチェアタイム短縮が実現した。
さらにPrimescanになると、視野の広いレンズと高速な画像処理によりフルアーチでも1分強で撮影可能とされるレベルに到達した。実際にPrimescanを使用した臨床家からは「全顎スキャンが1分程度で完了して驚いた」という報告もあり、もはや従来のシリコン印象でトレーを保持する時間より短く口腔内のデジタル記録が完結する。Primescan 2では無線化に伴うハードウェア構成の変化はあれど、基本のスキャン速度・精度は前モデルを踏襲しているため、「1分以内でフルマウスをスキャン可能」という水準を維持している。スキャン中のソフトウェア処理もクラウドで並行して行われるため、大容量データで動作が重くなる心配も少ない。
スキャン時間の短縮は、そのまま患者の拘束時間短縮と直結する。患者は大きく口を開ける負担から早く解放され、診療体験の快適さが増す。一方医院側にとっても、1症例あたり数分でも所要時間が減れば1日の診療枠に余裕が生まれ、追加の患者を受け入れたり別の処置に時間を充てたりすることが可能になる。特に自費診療で1件あたりの収益が大きい場合、わずかな時間短縮が年間の売上増に繋がる潜在力を持つ。また、チェアタイム短縮はスタッフの残業削減や診療後の疲労軽減にも寄与し、長期的には人件費圧縮やスタッフ定着率向上といった経営メリットも期待できる。
さらに、即日治療ワークフローの実現にもスキャン速度は重要だ。セレックシステムで来院当日に補綴物を装着しようとすれば、スキャン後の設計・削り出し・焼成まで含め限られた時間との勝負になる。スキャナー性能が低く何度も取り直しが発生したり遅々として進まなかったりすれば、当日装着は困難になるだろう。高速・高精度なスキャナーは即日治療の成功率を高め、患者への迅速な提供価値=医院の評判向上にもつながるのだ。
操作性・ワークフローとスタッフ活用
スキャナーの操作性や人間工学的な設計も大切なポイントである。臨床で日常的に使う機器だからこそ、扱いやすさは導入後の活用度を左右する。各モデルを振り返ると、まずBluecamはカメラヘッドがやや大きく重量バランスも独特で、撮影毎にフットペダルを踏む必要があったため慣れるまで姿勢や手順に工夫が必要だった。また粉を均一に吹く作業も煩雑で、クリニック全員が使いこなすハードルは高かったと言える。そのため、「数百万円で導入したものの結局持て余してしまい、診療ユニットの片隅で埃をかぶっている」といった失敗談も当時は散見された。
Omnicamではハンドピース部の重量約316gと比較的軽量で、ペン型機器に近い握り心地を実現している。カメラヘッドもコンパクトで小さな開口量でも奥歯にアクセスしやすく、口腔内スキャナー初心者でも取り回しに苦労しにくい設計だ。パウダーフリーとなり撮影前準備が激減したことも相まって、チェアサイドで直感的に扱えるようになった。筆者自身、初めてOmnicamを手にした際はその操作感に感動した記憶がある。まるでハンドピースで歯面をなぞるだけでカラーの3Dモデルがスクリーンに立ち上がっていく様子は衝撃的で、「これなら印象採得が苦手なスタッフでも任せられる」と感じたほどである。
Primescanではカメラ部分が大型化し重量も約524.5gと増加したが、機器バランスの最適化により実使用時の負担は想像より少ない。もちろん長時間連続で保持すればずっしり感は出るものの、多くの症例では1~2分程度の操作で済むため問題になりにくい。またPrimescanにはハンドピース内にヒーターが搭載され、長時間口腔内に入れていてもレンズが曇らない工夫がなされている。Omnicamではスキャンが長引くとカメラ先端が唾液で冷えて曇り、一旦口腔外で拭いてから再開…といった煩わしさがあったが、Primescanではそうした中断が基本的になくスムーズに最後まで取り切れる。これは地味ながら臨床現場では大きな利点で、術者のストレス軽減と時間ロス防止につながっている。
Primescan 2では、さらにワイヤレス化による操作性向上が図られた。煩わしいケーブルが無くなったことで、ユニット周りでの取り回しや体勢の自由度が飛躍的にアップしている。例えば、従来はカートごと移動させにくかったため特定の診療台でしかスキャンできなかったが、Primescan 2ならハンドピース単体を別のユニットに持ち込み、その場のPCやタブレットでスキャンを開始することもできる(DS Core経由)。診療室間で機器を融通しやすいため、1台の投資で複数ユニットをカバーできるメリットもある。またケーブル断線のリスクや取り回し時のアシスタント補助も不要となり、結果としてスタッフ単独でスキャン業務を完結しやすい環境が整った。実際、Primescan 2ではアシスタントや衛生士にスキャニングを委譲する運用も想定されており、診療のタスクシフトが円滑に進むだろう。院長が補綴設計や他の患者対応に専念している間に、スタッフが隣のユニットでデジタル印象を採得しておく、といった効率的なワークフローが現実的となる。
このように操作性の向上は機器活用率を高める鍵であり、結果としてROIにも影響する。使いにくい機器は宝の持ち腐れになりやすく、高額投資が無駄になる可能性がある。逆に扱いやすいスキャナーは院内でフル稼働し、アポイント毎に価値を生み出してくれる。特にスタッフが自主的に使いこなせるようになれば、院長一人に依存せずデジタル診療が回せるようになるため、医院全体の生産性向上につながる。導入にあたっては、スペック表の数値だけでなく実際に試用してみたフィーリングやスタッフの反応も重視すべきなのはこのためである。
データ連携とオープンシステム:ワークフローの柔軟性
デジタルスキャンの活用範囲を広げる上で重要なのが、取得データの連携性(オープン性)である。セレックは元来、院内完結のCAD/CAMシステムとして開発されており、スキャナーも基本的には同社の設計ソフト・加工機とシームレスに繋がる前提になっている。各モデルとも、セレックソフトウェア上でスキャンから設計・削り出しまで一貫して行える点は共通だ。これは同じメーカー内の統合システムゆえの信頼性であり、データ変換の煩雑さや他社機器との非互換に悩まされるリスクが低いというメリットがある。
しかし一方で、「取得したスキャンデータを外部のラボや他社ソフトで活用したい」というニーズも現場では存在する。例えば矯正診断用に他社の解析ソフトへ読み込みたい、自費の精密補綴なので熟練技工士に外注したい…といった場合だ。そこでポイントになるのが、オープンなデータ形式(STLやPLYなど)でエクスポートできるかである。古い世代ではメーカー独自形式に一旦依存する部分もあったが、Omnicam以降、基本的にSTLエクスポート機能が提供されている。ただしOmnicamや初代Primescanではエクスポート機能やラボ送信には専用のConnect Case Centerというクラウドサービスを介する必要があった。このサービスを利用することで、ラボ側も受信ボックスからデータを取得でき便利だが、年額のライセンス費用が発生する点には注意が必要だ(後述)。
Primescan 2ではこのデータ連携がより進化しており、DS Coreクラウドプラットフォームと直結する形となった。スキャン後のデータは自動でクラウド保存され、必要に応じてWebブラウザからSTL/PLY形式でダウンロードしたり、遠隔地の技工所と共有したりできる。加えて、患者説明用のシミュレーション(SureSmileシミュレータによる矯正治療の術前後比較など)にもDS Core上でアクセス可能で、取得データの活用範囲が広がっている。オープンデータの扱いやすさという点では、最新世代ほどフレキシブルと考えてよいだろう。もっとも、こうした高度な連携機能はクラウドサービス利用が前提となるため、院内LAN環境の整備や通信セキュリティ対策もセットで検討しておく必要がある。
データ連携の柔軟性は経営面でも見逃せないポイントだ。オープンなスキャナーであれば、ユーザーは特定メーカーのワークフローに縛られず自由に機器やサービスを組み合わせてROIを改善できる。例えば、スキャンデータを使って自院で3Dプリント模型を出力し技工に活用する、あるいはインビザラインなどマウスピース矯正に提供する、といった新たな収益源の開拓が可能だ。セレック純正ワークフロー以外の用途にもデータを使い回せることで、1台のスキャナー投資から得られるリターンが倍増するイメージである。一方で、もしデータが閉鎖的で特定システム内でしか使えない場合、そのシステムが陳腐化した際に機器ごと価値が下がってしまうリスクもある。昨今、多くのメーカーが自社システムのクローズド戦略を改めつつあり、Dentsply Sironaも例外ではない。「オープンだけれどもシームレス」というバランスを模索し、ユーザーに選択肢を与えながら自社エコシステムの利便性も提供する方向にシフトしている。購入前には、エクスポート可能なファイル形式や追加の利用料が必要かどうか等を販売会社に確認し、自院の活用方針に適合するか見極めることが重要である。
コストパフォーマンスとROI:初期費用と維持費をどう捉えるか
最後に、コストとROI(投資対効果)の視点で見てみよう。導入を検討する歯科医師にとって、機器の価格は避けて通れない要素であり、同時に価格以上の価値を生み出せるかが判断の鍵となる。
上述の早見表に示したように、新しいモデルほど標準価格(定価)は高額だ。BluecamやOmnicamが数百万円台中盤~後半だったのに対し、Primescanはフルセットで700万円超と非常に高価である。ただし留意すべきは、価格体系や含まれるソフトウェアライセンスがモデルによって異なる点だ。例えば、初代Primescanが発売された当初は専用のカートPC・タッチスクリーン込みのセット価格が設定されており、それが700万円近い価格帯となっていた。一方で近年では、医院の既存PCに接続して使う「Primescan Connect」パッケージが登場し、こちらはPC込みでも定価350万円程度(税抜)と大幅に安価である。すなわち、同じPrimescan技術でも運用スタイル次第でコストを抑えた導入が可能になっている。2024年登場のPrimescan 2も、ワイヤレスハンドピース単体で450万円(税別)という定価が示されており、従来のカート型に比べれば低価格に感じられる。ただし、設計ソフトや周辺機器を別途揃える必要がある場合は追加費用が発生するため、見積もり時には総額で比較する必要がある。
維持費についても考慮が必要だ。セレックの場合、ソフトウェア更新やクラウド利用に年間ライセンス費用が設定されている。OmnicamやPrimescanでは、Connect Case Center利用料およびソフト更新料として年間約18万円(税別)が目安となる。これを支払うことで最新バージョンへのアップグレードやクラウド送信機能の継続利用が可能だ。一方、他社スキャナーではソフト更新料が不要なモデルもあり、ランニングコスト面では製品ごとに差がある。Primescan 2については発売間もないため詳細な費用体系は変化し得るが、DS Coreのクラウドストレージ容量によっては有料プラン加入が必要になる可能性もある。加えて、スキャナー用のディスポーザブルスリーブ(カバー)代も症例ごとに発生する。Omnicamはガラススリーブを滅菌再利用できたが、Primescan 2ではシングルユースのプラスチックスリーブが基本となるため、1患者あたり数百円程度の消耗品コストを見込んでおくべきだ。これら維持費も踏まえ、1症例あたりのデジタル印象コストを概算すると、おおよそ数百円~千円程度と言われる。従来のシリコン印象材やトレー代と大差ない水準ではあるが、投資回収の計画を立てる際には初期費用だけでなくこうしたランニングも織り込む必要がある。
ROIを考える上で重要なのは、その機器導入によって何がどれだけ改善・拡大されるかを定量化することだ。単に「最新のほうが良さそう」と高額機を選ぶのではなく、自院の状況に照らしてシナリオを描くことが求められる。例えば、年間〇本の自費クラウンを提供しているクリニックでPrimescanを導入すれば、技工所への外注費が年△円削減でき、患者一人あたりの滞在時間が×分短縮されることで追加の患者対応が年間□人増やせる――といった具合だ。さらに、「即日治療」を新たなメニューとして打ち出すことで患者獲得数が▲%向上するかもしれない。このように多角的にシミュレーションすれば、投資回収に必要な期間(何年で元が取れるか)が見えてくるだろう。実際、ある歯科医院ではセレックシステム一式に約1000万円投資し、自費補綴の内製化によってわずか3年で回収を終えたケースもある。その医院では従来ラボ委託していたセラミッククラウンの利益率が大幅に改善し、患者にも「1日で白い歯が入る」と好評で来院数が伸びたという。もっとも、こうした成功例は医院の患者層やマーケティング戦略にも左右される。地域柄、保険診療中心で補綴の単価アップが見込みにくい場合は、ROI達成に時間がかかる可能性もあるだろう。
幸い、日本では歯科向けの設備投資を後押しする制度も存在する。近年、口腔内スキャナーは国のものづくり補助金の対象品目となっており、条件を満たせば購入費用の1/2ほど(上限1000万円)の補助を受けられるケースもある。さらに2024年の診療報酬改定では一部のCAD/CAMインレーで光学印象が保険算定可能となり、デジタル印象への追い風が吹いている。これらも踏まえ、単に価格の安さだけでなく中長期的な経営計画の中で機器導入が果たす役割を考えてほしい。適切な機種を選び、使い倒すことで、必ずや投資に見合う収益と診療クオリティの向上が得られるはずである。
CEREC対応口腔内スキャナー各モデルの評価
以上のポイントを踏まえ、セレックシステムで使用される主なスキャナーを個別に見ていこう。それぞれの強み・弱みと、どういった診療ニーズにマッチするかをレビューする。自身のクリニックの方針や課題に照らし合わせながら読んでいただきたい。
CEREC Bluecam(ブルーカム)
Bluecamは、セレックACに搭載された旧世代の口腔内スキャナーである。青色LED光を用いた光学印象技術により、解像度・スキャン範囲が向上した。当時としては画期的だったが、特徴(かつ課題)として「スキャン対象へのパウダー塗布」が必須であった点が挙げられる。歯面にチタニウム粉末を均一にコーティングすることで反射率を揃え、カメラが読み取りやすくする仕組みだが、この作業が煩雑でトレーニングを要した。粉の塗り残しやムラがあるとデータ欠損や歪みの原因となるため、精密な印象を得るには術者の経験に依存する部分が大きかった。
Bluecamは基本的に静止画を連続撮影して3次元モデルを構築する方式である。一箇所を撮影するごとにフットペダルを踏んでシャッターを切り、少しずつカメラをずらしながら複数枚の画像を取得していく必要があった。このため、スキャンに要する時間は長めで、特にフルアーチを撮影する際は数百枚もの画像を繋ぎ合わせる関係上5分以上を要することもあった。被写界深度も約10mm程度と浅めで、歯肉縁下の深いマージンなどは物理的に見えない限り記録が難しかった。一方で、カメラ自体の精度は当時高水準であり、適切に粉を塗布しさえすれば単冠レベルでは良好な適合の補綴物を作製できた。事実、Bluecam導入により「印象採得の精度が安定し、クラウン適合が向上した」と報告する臨床家もいた。ただしそれは高度にトレーニングされた場合の話であり、現実にはパウダーや機器操作の難しさから十分に使いこなせなかったケースも少なくない。
経営面でBluecamを見ると、現在ではあえて新規導入すべき機種とは言い難い。発売から十年以上が経過しメーカーサポートも縮小傾向であるため、中古で安価に入手できても将来のメンテナンスに不安が残る。なにより、パウダー必須の煩雑さは診療効率を下げスタッフ受けも悪いため、せっかく導入しても活用されないリスクが高いだろう。当時を知る身としてはノスタルジックな愛着もある機種だが、現在の基準で臨床的・経営的価値を考えるとBluecamを選択するメリットは乏しい。強いて言えば、デジタル印象の基礎を学ぶ教材的な位置づけか、あるいは何らかの理由で粉体スキャン特有のテクスチャが必要な特殊ケースくらいだろう。結論として、現代の歯科医院がわざわざBluecamを導入する場面はほぼ無く、後述のOmnicam以降の機種から選ぶのが現実的である。
CEREC Omnicam(オムニカム)
Omnicamは2012年に登場したセレック用スキャナーで、デジタル印象の実用性を飛躍的に高めたモデルである。革新点は何と言ってもパウダーレス化の実現だった。煩わしい粉の工程が不要になったことで、誰でも直感的に口腔内スキャナーを扱えるようになり、デジタル技術の普及を一気に押し進めた立役者と言える。また、フルカラー撮影が可能になった点も見逃せない。これにより取得データ上で歯と歯肉、充填物などを色で識別でき、マージンラインの視認性も飛躍的に向上した。患者にとっても、自分の口腔内がカラーの立体画像で表示されることで治療内容を理解しやすくなるという副次的なメリットが生まれた。
Omnicamはビデオ式のスキャンを採用しており、カメラを動かすだけで連続的にデータを取得できる。これにより、術者は目視で口腔内を確認しながらスキャナーをペン先のように走らせるだけでよく、手順がシンプルになった。カメラヘッドもBluecamに比べ小型化され、重量も約316gと軽量で、長時間持っても手が疲れにくいエルゴノミクスデザインになっている。さらに、セルフヒーティング(自動曇り止め)機能は無いものの、撮影スピードが速いためカメラが曇る前に完了できるケースが多くなった。こうした改良により、小臼歯部までなら支台歯を隔壁で覆わなくとも十分マージンが映り込むし、ブリッジ程度なら精度良くスキャンできる性能を備えている。発売当初、筆者も実際にOmnicamを用いて数多くの即日補綴を経験したが、臨床的な仕上がりは従来法と遜色なく、むしろ再現性の高さに驚かされた。複数ユニットの同時スキャンも、テクニックさえ習得すれば概ね問題なく行える。
Omnicamの弱点をあえて挙げるなら、フルアーチスキャンにはやや時間を要する点と、解像度が劣る点である。スキャン範囲が広がるにつれてデータ処理が重くなり、全顎を一度に撮ると2~3分程度はかかる。また、カメラの視野が狭く一度に撮れる範囲が限られるため、小刻みに動かして全体をなめらかに覆う必要がある。そのため、多数歯欠損の症例や無歯顎の症例では撮影自体は可能でも微小な誤差累積が起きやすく、完全な精度を求めると難がある場合もあった。また解像度については、やはり粗さを感じる場面がある。具体的には、細かなプリパレーション形態や咬合面の精細さで僅かな差が出る。ただし単冠や3ユニット程度のブリッジであれば臨床上問題ないレベルの精度であり、むしろデータ容量が軽い分だけ扱いやすいという面もある。
経営的に見たOmnicamは、現在において「コスト重視でデジタルを導入したい場合の現実解」になり得る。既に生産終了しているものの、流通在庫や中古市場では比較的安価に手に入る場合がある。新品販売時の標準価格は約640万円だったが、現在ではその半額程度で入手できた例もある。初期費用を抑えてまずデジタル印象を始めてみたい、という開業医にとってOmnicamは一つの妥協点となるだろう。性能面でも、保険の単冠や小規模な自費補綴が中心であれば不足は感じにくい。むしろ、スタッフ教育や運用ルールをこの段階で整備し、収益が上がってきたら後継機にアップグレードするというステップ導入も現実的だ。ただし留意点として、メーカーのソフトウェア更新サポートがいつまで継続するかはチェックしたい。2023年時点ではOmnicamもソフト(CEREC SWなど)の動作対象だが、今後数年でサポート外になる可能性もある。その際は旧バージョンのまま使い続けることもできるが、新しい機能(例えば保険CAD/CAMインレー対応や材料ライブラリなど)が使えなくなる懸念はある。
総じて、Omnicamは「パウダーレス&カラー化でデジタル印象の実用レベルを確立した立役者」と言える。現在では後継が登場し一世代前のモデルとなったが、中堅モデルとしてのバランスの良さは健在だ。特に「保険診療主体で、とにかく効率よく型どりを済ませたい」「セレックの即日修復を導入してみたいが投資は抑えたい」という先生には、Omnicamは必要十分なパフォーマンスを発揮してくれるだろう。
CEREC Primescan(プライムスキャン)
Primescanは2019年に登場したセレック用スキャナーのフラッグシップモデルである。開発段階から「口腔内スキャンの既成概念を打ち破る」ことを謳っていただけあり、Omnicamから多くのブラッシュアップが施された。まず特筆すべきは圧倒的なスキャン精度と処理能力である。Primescanには独自開発のスマートピクセルセンサーとダイナミック深度スキャン技術が搭載され、1秒間に数百万もの3Dポイントを取得できる。その結果、非常にシャープでディテール豊かな3次元画像がリアルタイムに生成される。実際に、Primescanで撮影したデータはエッジがくっきりと描画され、わずかな支台歯のテーパー角や咬合面形態まで鮮明だ。複雑な形態の支台歯やフルクラウン前提の切削歯でも、迷うことなくマージンが読み取れる印象である。この精度の高さは各種研究でも裏付けられている。
スキャン速度もPrimescanの大きな売りである。先に述べたように、熟練すればフルマウスを1分程度でスキャンできるほど高速だ。これはカメラ視野の拡大と並行演算処理の改良によるもので、一度に広範囲を取り込みつつ画像合成の遅延を極限まで減らした成果だ。実際、筆者のクリニックでもPrimescan導入直後に全スタッフで練習したところ、多少の慣れでOmnicam時代の半分以下の時間でスキャンが完了するようになった。患者からも「もう終わったの?」と驚かれるほどで、デジタル印象への抵抗感がさらに下がったように感じる。特に嘔吐反射の強い患者でも短時間で済むため、大きなストレスを与えずに処置を進められるようになった。
Primescanのハードウェア面では、可動式のワイドタッチスクリーンを備えた専用カートが標準構成となっている。操作用のタッチパッドも搭載され、ユニット脇に設置したカート上で直感的な操作が可能だ。画面上でスキャン結果を回転・拡大しながら確認したり、そのまま設計ステップに移行したりと、椅子に座ったまま一連の作業が完結するデザインは秀逸である。またハンドピース先端のセルフヒーティング機能により、長時間のスキャンでもレンズが曇らず鮮明な画像を維持できる。Omnicamで煩わされた細かな中断が無くなったことは、ストレスフリーな使用感につながっている。さらにワンド先端はディスポーザブルスリーブを装着可能で、患者ごとに新品のカバーに付け替えられるため衛生面も安心だ(メタル製のオートクレーブ可能スリーブも選択可能)。
Primescanの弱点としては、まずコストが非常に高いことが挙げられる。発売当初フルパッケージで700万円以上という価格は、他社競合機種と比較しても最高クラスだった。加えて前述のようにConnect Case Center利用料などランニング費用も掛かるため、長期的に見れば相応の投資計画が必要となる。また、ハンドピースが重め(約525g)な点は、人によっては長所にも短所にもなる。重量ゆえの安定感でブレにくいという意見もある一方、手が小さい方や力の弱い方には負担と感じられる可能性がある。幸いスキャン時間自体は短いので深刻ではないが、複数人で使い回す場合は全員が問題なく扱えるか確認したほうがよいだろう。
もう一つ、Primescanはその高性能ゆえにデータサイズが大きく扱いづらい場面がある。取得する点群が緻密なため、STLにエクスポートするとファイルサイズが膨大になり送受信に時間がかかることがある。他社のミドルレンジスキャナーが軽量データでクラウド連携に優れる点と比較すると、Primescanは高精細さと引き換えにデータ量がヘビーというトレードオフがある。ただ、この点もPrimescan 2ではDS Core上でうまく最適化されているようで、必要に応じて解像度を落としたプレビューを使うなどの工夫が施されている。
Primescanが力を発揮するのは、やはり高度な要求のある自費診療領域である。インプラント症例で複数ユニットの同時印象採得をする場合や、全顎的な補綴治療で正確な咬合再現が必要な場合など、精度と再現性が成否を分けるケースでは頼もしい相棒となるだろう。また、患者への「機器に力を入れている」という訴求ポイントにもなる。実際、機器に敏感な患者から「この医院は設備が整っている」という信頼を獲得しやすくなり、差別化に成功した例もある。経営面では初期投資の負担は大きいものの、同時に得られる付加価値(時間短縮・技工費削減・患者満足度向上など)が総合的に見て上回るかが導入判断のポイントだ。もし既にOmnicamを使っていて更なる効率アップや症例拡大を目指したいなら、Primescanへのアップグレードは有力な選択肢となる。逆に、歯科用CAD/CAM初導入でいきなりPrimescanフルセットに投資するのはハードルが高いため、まずはConnectパッケージ等で小さく始め、必要に応じて拡張する方がリスクは少ないだろう。
CEREC Primescan 2
Primescan 2は2024年に発売された最新世代のセレック用スキャナーであり、前モデルPrimescanの長所を継承しつつ現代のニーズに合わせた改良が加えられている。トピックは何と言ってもワイヤレス化である。Primescan 2のハンドピースは従来のカートや有線接続を必要とせず、本体内蔵のバッテリーとWi-Fi通信によってPCやタブレットとリンクする。これにより、診療チェア間の機器移動や配線トラブルから解放され、医院内での運用柔軟性が飛躍的に高まった。例えば、忙しい日はユニットAで院長がPrimescan 2を使ってスキャンし、次の瞬間にはユニットBで衛生士が同じデバイスを使って別患者のスキャンを開始するといった運用が可能になる。1台のスキャナーで複数の診療台をカバーできるため、結果として設備投資額の削減や機器稼働率の向上につながるだろう。
ワイヤレス化に伴い、スキャナー本体のデータ処理はクラウドプラットフォーム(DS Core)に依存する設計となった。Primescan 2はハードウェアに依存しないクラウドネイティブなデバイスとして位置付けられており、インターネット接続されたPCさえあれば専用の高性能ワークステーションが無くともスキャンが行える。実際、診療室のノートPCやタブレットのブラウザ上でDS Coreにログインすれば、そのままPrimescan 2からリアルタイムにスキャンを進めることが可能だ。ソフトウェアのインストールや更新もクラウド側で自動管理されるため、ユーザーは煩雑なアップデート作業から解放される。これは医院のIT管理負荷を下げるとともに、常に最新機能を利用できるメリットがある。また、スキャンデータはプライマリにクラウド保存されるため、院内サーバの容量圧迫を心配する必要も減る(必要に応じてローカルにエクスポートも可能)。
Primescan 2では細部の使い勝手も向上している。ハンドピースデザインは前モデルより一回り大きくなったものの、先端部は細く改良され、大臼歯遠心や智歯部へのアクセスがしやすくなった。実際の臨床では頬や舌の干渉を受けにくくなり、隅々までスムーズに走査できる印象だ。また、新たにタップセンサーが搭載されており、指先で本体をトントンと叩くだけでスキャンの開始・停止やモード切替えが行える。これは院内感染対策にも有効で、グローブ越しでも反応するため余計なボタン操作なしに清潔に作業できる。感染対策といえば、Primescan 2は使い捨てスリーブの採用で衛生面をさらに強化している。Omnicamや旧Primescanでは再利用スリーブの滅菌が必要だったが、Primescan 2では毎回新品スリーブに差し替える運用が推奨され、院内感染リスクを低減できる。ただし前述の通りランニングコスト増には留意が必要だ。なお、オプションでサファイアガラス製の再利用スリーブも発売予定とのことで、コストと利便性のバランスをユーザーが選べるのはありがたい。
性能面に関して、Primescan 2のスキャン精度・速度自体は初代Primescanと同等レベルを維持している。つまり現時点で業界トップクラスの精度とスピードをしっかり備えているということだ。メーカー公式には「フルアーチスキャン1分未満」という触れ込みであり、筆者の体感でも前モデル同様きわめて高速だ。実際の診療では、ワイヤレスゆえに通信状態に左右される部分もあるが、院内Wi-Fiを整備しておけば遅延は感じない。むしろクラウド処理のおかげで、スキャン後のデータポリゴン生成やノイズ除去などの処理がバックグラウンドで素早く完了する印象を受けた。今後ソフトウェアのアップデートでさらなるAI処理(自動マージン検出や不要組織のリアルタイム削除など)が強化されれば、ユーザーの作業はますます簡便になるだろう。
Primescan 2を導入するべき歯科医院像としては、いくつか考えられる。まず複数ユニットでデジタルを活用したい中規模以上のクリニックだ。1台の機器をスタッフ間で融通できるため、院内のデジタル化を効率よく推進できる。次に最新技術をアピールしたい高度自費診療主体の医院。ワイヤレススキャナーは患者向けPRにもなり、差別化につながる。さらに、訪問診療や外来手術室での印象採得ニーズがある場合もPrimescan 2は有用だ。例えば往診先で義歯の光学印象を取る、全身麻酔下で外科と同時進行で補綴印象を取るなど、機動力が要求されるシーンでも真価を発揮するだろう。もっとも、これらは高度な活用例であり、多くの一般開業医にとっては「Primescanのワイヤレス版」という位置づけになる。既にPrimescanを持っている医院が直ちに買い替える必然性は薄いが、新規にセレック導入を検討していて将来を見据えたクラウド環境構築も厭わない先生には、Primescan 2は極めて魅力的な選択肢となる。価格面も従来より抑えられているため、初めてのデジタル投資としても手が届きやすくなった印象だ。ただし注意点として、クラウドサービスに対する院内のITリテラシーは求められる。もしデジタル環境の整備が苦手な場合、導入後の運用に戸惑う場面があるかもしれない。その場合はメーカーや販売店のサポートを仰ぎつつ、スタッフと共に新しいデジタルワークフローへの順応期間をしっかり確保することが重要だ。
よくある質問(FAQ)
Q. セレック用の口腔内スキャナーは、長期的に見てどのくらい使えるものなのか?
A. 一般に歯科機器の耐用年数は7~10年程度と言われるが、口腔内スキャナーもハード的には同様である。実際にはソフトウェアのサポート期限が実用寿命を左右する面が大きい。メーカーがソフト更新を打ち切れば新しい材料や機能に対応できなくなるため、そのタイミングが買い替え時期と考えるべきだ。現在、Omnicam発売(2012年)から10年以上経過しているが、未だソフト対応は続いている。ただPrimescan 2の登場もあり、今後数年でOmnicamのアップデート提供が終了する可能性はある。対してPrimescan 2はクラウド型で常に最新状態が維持されるため、ソフトの陳腐化リスクは低い。ハード故障さえしなければかなり長期間使えるだろう。総じて、5年ごとに各世代の技術革新が起きているため、5~7年スパンでのリプレースを見込んでおくと安心である。
Q. 現在プライムスキャン(初代)を使用中だが、プライムスキャン2に乗り換えるメリットはある?
A. 既存のPrimescanを使いこなせているなら、精度や基本性能の面では乗り換えの必要性は高くない。Primescan 2の利点は主にワイヤレス化とクラウド連携強化によるワークフロー効率アップなので、例えば「院内で複数ユニットにまたがりスキャンを使いたい」「PC管理を簡素化したい」といったニーズが強い場合にはメリットがある。また患者サービスとして最新機のアピールも図れる。しかし投資額との比較では、単に最新だからという理由だけで無理に買い替える必要はないだろう。メーカーも初代Primescanユーザー向けにアップグレードプログラム等を用意している場合があるので、どうしても興味があれば販売店に相談してみるとよい。基本的には現行機を大事に使い倒し、耐用年数やサポート期限が近づいてから次世代機を検討するのが賢明である。
Q. 口腔内スキャナー導入で患者さんからの評判や満足度は本当に上がるのか?
A. 筆者の経験上、間違いなく患者満足度は向上する。まず、嘔吐反射や窮屈感を伴う従来のシリコン印象が不要になるため、患者から「楽だった」「全然苦しくなかった」という声が多く聞かれるようになる。また、スキャン中にリアルタイムで自分の歯が3D表示される様子を見て、興味を示す患者も多いだろう。治療説明の際にもカラーの3D画像を共有することで、自身の口の状況を直感的に理解してもらえる。例えば、「ここに虫歯があり、この部分を削って詰めます」と模型やレントゲンを見せるより、スキャンデータ上で患部を拡大表示したほうが患者の理解度・納得感は高まる。その結果、治療への同意や追加処置の提案もスムーズに進む傾向がある。さらに、「最新の設備を導入している」という事実は医院のブランディングにもプラスであり、口コミや紹介でデジタルに積極的な医院として評価され来院に繋がったケースもある。無論、機器は魔法ではないので、その後の治療結果が伴ってこそ本当の満足に繋がる。しかし少なくとも印象採得の段階で患者の不快を減らし信頼感を高められることは、治療全体の満足度向上に直結する重要なファクターだと言える。
Q. セレックシステムはミリングマシンまで含めて導入すべき? スキャナー単体でも効果はある?
A. これは医院の方針による。スキャナー単体の導入でも十分メリットはあるが、その活かし方が変わってくる。スキャナーのみの場合、取得したデジタルデータを外部技工所に送って補綴物を作製することになる。従来の印象送付より迅速かつ精度高くデータ共有でき、模型レスで技工が進むため、納期短縮や精度向上に寄与する。また、矯正やインプラントガイド製作等にもスキャンデータを活用できる。しかし即日治療(One Day Treatment)の提供はスキャナー単体では不可能であり、患者メリットとしては「印象が楽になった」止まりになる面もある。一方、ミリングマシン・焼成炉まで揃えれば院内完結型のCAD/CAMシステムとなり、その日のうちにセラミック修復物を提供することが可能だ。患者満足度や医院の収益性(技工外注費削減)という意味ではフルセット導入が理想ではある。ただし初期投資・維持コストも跳ね上がるため、まずはスキャナーだけ導入して運用に慣れ、症例数が増えてきたらミリングを追加という段階的な導入も賢い戦略だ。実際、スキャナー導入後に「デジタル印象の快適さから自費補綴が増えた」「もっと即日でやってほしいという患者要望が出た」等の変化を経て、後からミリングマシンを追加購入した医院も多い。まずはスキャナーでデジタルフローの第一歩を踏み出し、自院に見合った範囲で徐々に拡張するというアプローチで問題ないだろう。
Q. 保険診療が多い歯科医院でも口腔内スキャナー導入の経済効果はあるのか?
A. 保険診療中心の医院であっても、経済効果は十分見込める。確かに自費診療に比べ直接的な収益アップは限定的かもしれないが、効率化による利益向上という側面が大きい。例えば、保険のクラウンやブリッジをデジタル印象に切り替えることで、印象材コストが削減できる。1症例あたり数百円かもしれないが、年間数百症例で積み上がればそれなりの額になる。また、型どりや石膏流しにかかっていたスタッフ時間を他業務に振り向けられる点も大きい。熟練の歯科助手が石膏模型製作に費やしていた時間を、チェアサイドアシストや滅菌作業に充てることで人員配置の効率化が図れる。さらに近年では、保険適用のCAD/CAMインレーや小臼歯部CAD/CAM冠などデジタル技工のフィールドが広がっている。これらは口腔内スキャナーとの親和性が高く、印象の省略や適合精度向上による調整時間短縮といったメリットがある。保険診療は点数が決まっているため収入を劇的に増やすのは難しいが、コスト削減と業務効率化を積み重ねることで利益率を改善することは可能である。特に、多数の患者を回す必要がある保険メインのクリニックほど、数分のタイムセーブや些細なコスト削減が年間では大きな差となって現れる。したがって、保険診療主体でもデジタル化のメリットは充分にあり、むしろ早期に取り入れたほうが収益構造の健全化につながると考えられる。
- 歯科機材の比較なら1Dモール
- 口腔内スキャナー
- セレック(CEREC)で使われる口腔内スキャナーを価格や性能でまとめてみた